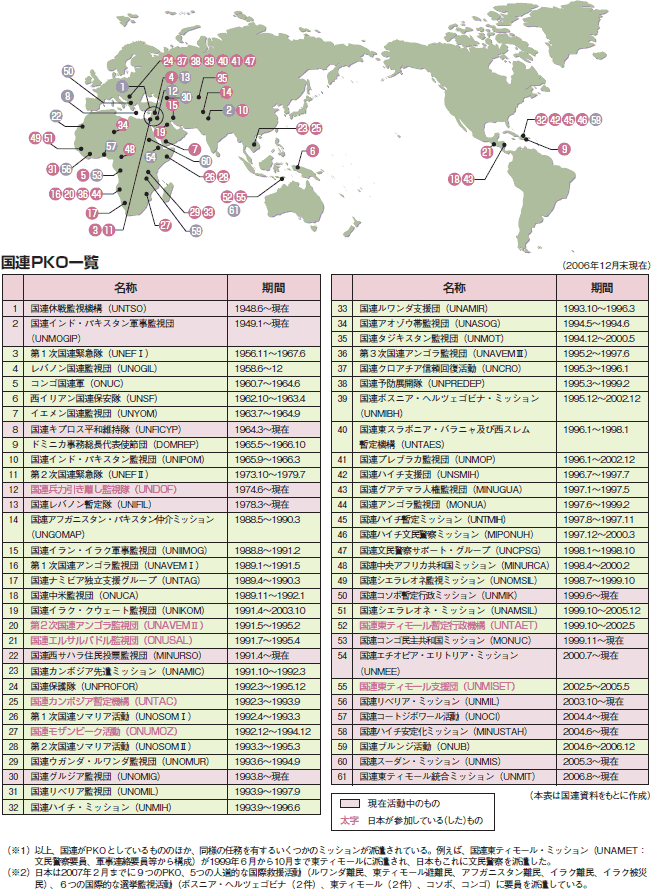(イ)PKO (注18) 等の人的貢献
現在、世界各地では15の国連PKOミッションが活動中である(2007年1月現在)。8月の国連レバノン暫定隊(UNIFIL)の拡大、同月の国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)の設立等の影響を受け、国連史上最大規模の8万人を超えるPKO要員が世界各地で活動している(2006年12月末現在)。
日本は国際平和協力法に基づき、現在国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に45名の自衛隊員を派遣しているほか、7月と10月にはコンゴ民主共和国での国民議会選挙・大統領選挙に選挙監視団を派遣した。また、10月にはスリランカ被災民に対する人道救援活動に取り組む国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の要請に基づき、スリーピングマット等の物資協力を実施するなど、同法に基づく物資協力も行っている。さらに、2007年1月末には、UNMITに警察要員を派遣した。
(ロ)平和構築に向けたODA支援、協力
日本は、ODA大綱で「平和の構築」を重点課題として位置付け、紛争の予防や緊急人道支援とともに、紛争の終結を促進する支援から平和の定着や国づくり支援に至るまで、ODAを通じた国際社会における平和構築支援、さらには日本の繁栄と安全の確保に積極的に取り組んでいる。
イラクについては、2003年10月に表明した最大50億ドルのイラク復興支援のうち、紛争後のイラク国民の生活基盤の再建及び治安の改善に重点を置いた15億ドルの無償資金協力については、既に全使途を決定し、現在、着実に実施に努めている。今後は、最大35億ドルの円借款により、イラクにおける平和の定着や本格的復興に不可欠となる経済社会インフラの整備に取り組む考えであり、2006年末時点で、8案件約16億ドルの支援の意図を表明し、2007年1月にはこのうち4案件について書簡の交換が行われた。さらに、こうした資金協力との一層の連携を図りつつ技術協力によるイラクの人材育成も継続している。
アフガニスタンでは、2002年に発表した「平和の定着」構想に基づき政治プロセス・ガバナンス、治安の維持及び復興の3つの柱を中心に総額10億ドルを超える支援を行っている。1月のアフガニスタン復興会議(ロンドン会議)では当面4億5,000万ドルの追加支援を表明し、7月には「平和の定着」に関する第2回東京会議を開催するなど、選挙支援や元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration)から難民・避難民の定住支援、インフラ整備まで継ぎ目のない包括的な支援を行っている。
スリランカにおいては2002年2月の停戦合意以降、20年間にわたる紛争で疲弊した北・東部地域に対して、人道・復旧分野を中心とする支援を実施している。また、日本は、2003年6月に、米国、ノルウェー、欧州連合(EU)とともに「スリランカ復興開発に関する東京会議」を開催する等、同国の和平プロセスに中心的な役割を果たした。同会議では、和平の進展を十分見極めながら3年間で最大10億ドルの支援を行う用意があることを表明し、このうち2005年度までに約7億5,000万ドルの支援を実施した。
アフリカ地域においても、2月に「TICAD平和の定着会議」を開催し、スーダン、大湖地域、西アフリカを中心に6,000万ドル規模の当面の支援策を発表した。また、スーダンでは、UNHCRや国連世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)等の国際機関を通じ難民・国内避難民に対し、総額5,500万ドルの人道支援を行った。
また、日本は、アジア、アフリカを中心とする紛争被害国において、人道上大きな問題となるのみならず、復興・開発活動を妨げる対人地雷・小型武器の回収・廃棄等を積極的に支援している。アンゴラでは、「アンゴラ共和国における国家地雷除去院能力向上計画」(4億6,400万円)等のプロジェクトを実施しているほか、日本のNGOの地雷・不発弾処理事業や地雷回避教育事業に対して計3億7,000万円の拠出を行った。