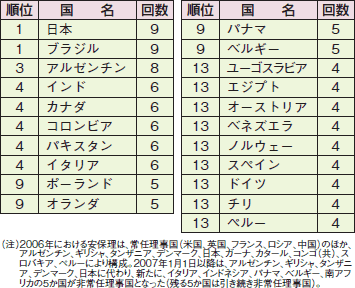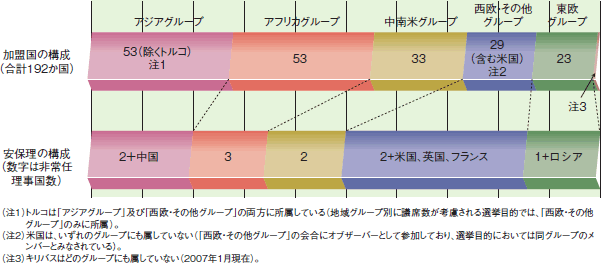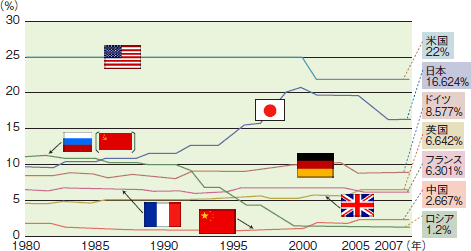冷戦の終結後も世界の様々な地域で紛争が勃発し、国連、とりわけ世界の平和と安全の維持という重責を担う安保理の役割はますます拡大している。その一方で、安保理の構成は国連創設以来根本的には変化していないため、国際社会の変遷に追いついておらず、安保理改革の実現は、今や国際社会の緊急課題である。日本は、従来世界の平和と繁栄について役割を果たしてきているところからも、その経験と知見を最大限に発揮し、21世紀の安保理常任理事国として一層の責任を果たしたいと考えている。日本の常任理事国入りは、日本にとって、(1)日本の安全保障に直結する問題への関与と国益の実現、(2)国際社会への貢献に見合う地位の確保、(3)国際の平和への更なる貢献-等の点で大きな意味を持つ。また、国際社会にとっても、(1)軍縮不拡散等の分野での日本の貢献と指導力の発揮、(2)第2位の経済大国の貢献の確保及び強化、(3)アジアの代表性向上を通じた安保理の信頼性向上-といった点で有意義である。
2005年、日本はドイツ、ブラジル、インドと結成したG4を通じて安保理改革の実現に向けた運動を展開し、具体的な安保理改革案を国連総会に上程したが、最終的に加盟国の3分の2の支持(128か国)を得る見通しが立つまでには至らなかった (注13) 。
2006年の安保理改革の動きは、G4のうち日本を除く3か国による、前年と同内容の決議案の提出をもって幕を開けた。これは、前年12月のアフリカの一部諸国による決議案再提出 (注14) を受けた戦術的な動きであったが、日本は、主要国の態度に変化がない中で採択の見通しがない同決議案を共同提案することは見送り、G4間の連携を維持しつつ、より多くの支持を得られる案を検討するために米国をはじめ他国との協議プロセスに入った。米国は、従来日本の常任理事国入りを力強く支持しており、6月の小泉総理大臣訪米の際の共同文書では、その実現に向けた両国の連携がうたわれた。また、中国との間では、2005年12月に続いて7月に担当局長間の対話が実施され、また10月の安倍総理大臣と温家宝総理との間の首脳会談後の「共同プレス宣言」において、「安保理改革を含む必要かつ合理的な改革を行うことに賛成し、これにつき対話を強化する」ことが表明された。
この間、安保理の議席拡大に加え、安保理の作業方法の改善 (注15) の必要性についての加盟国の認識も高まり、3月、スイス等の中小国5か国が常任理事国の拒否権行使の制限等を求める内容を含む決議案を国連総会に提出した。この決議案は採決に付されずに終わったものの、加盟国にはおおむね好意的に受けとめられた。日本は、このような動きと並行して、安保理非常任理事国としての地位をいかし、安保理内で実際に作業方法の改善を検討する作業部会の議長を務め、議論の成果を安保理議長ノートとして発出した。
2005年9月の国連首脳会合で決定された国連の機構改革のうち、人権理事会及び平和構築委員会が6月に活動を開始したことにより、加盟国は、残る最大の未解決の課題が安保理改革であるとの認識を新たにした。7月に開催された安保理改革に関する国連総会審議では、各国が相次いで安保理議席拡大の必要性について言及し、安保理の現状維持はオプションたり得ないこと、引き続き安保理改革の実現に向けた加盟国の取組が必要であることが確認された。また、9月の第61回総会会期冒頭の一般討論演説においても、安保理改革の重要性に直接・間接的に言及した国の数は、発言した191か国のうちおよそ3分の2に上った。日本からは大島賢三国連大使が、加盟国は創造的かつ説得的な新たな提案を必要としていると訴えた。さらに、12月に開催された安保理改革に関する国連総会審議でも、引き続き多くの国から安保理改革の必要性・緊急性が指摘される中、日本の大島大使は、具体的な提案を積極的に検討しており、しかるべき時に提案したい旨表明した。
安保理改革は、いまだ道半ばである。戦後の国際制度を大きく変革する試みであり、各国の国益に直結する事柄であることから、具体案に対する各国の立場の相違を埋めることは決して容易ではないが、改革実現の緊急性はすべての加盟国の一致するところである。日本としては、これまでの機運の高まりも踏まえ、加盟国の幅広い支持を得て改革努力を現実の成果に早期に結びつけるべく新たな具体案の検討を行っており、今後とも、粘り強く運動を展開していく考えである。