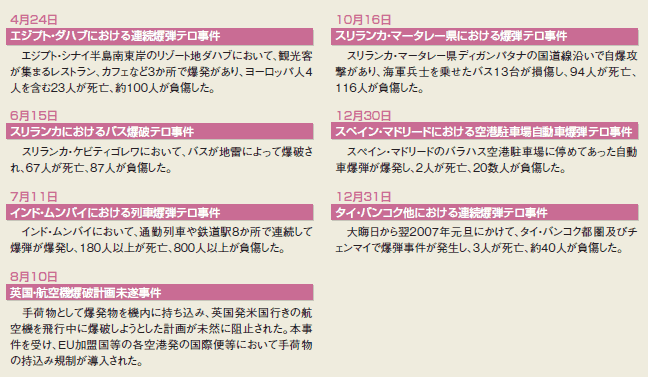2.テロ・国際組織犯罪対策
【総 論】
2001年9月11日の米国同時多発テロ以降、国際社会はテロ対策を最優先課題の一つと位置付け、国連やG8など多国間の枠組み、東南アジア諸国連合(ASEAN)、アジア太平洋経済協力(APEC)、アジア欧州会合(ASEM)など地域的な協力、二国間協力など様々な場において、テロ対策の強化が合意・確認され、テロとの闘いに関する政治的意思の強化と実質的協力が進展している。
国際テロ組織アル・カーイダ及び関連団体の指導部の能力は減退し、戦闘員は減少したものの、いまだにその勢力は軽視し得ない。2006年も、世界各地で多くのテロ事件が発生している。8月にはイギリスでの航空機爆破テロ計画が発覚するなど、日本人旅行者や在留邦人、日本企業に対しても、国際テロの脅威は及んでいる。
テロは国家及び国民の安全の確保の問題のみならず、投資・観光・貿易等に対する影響を通じ、我々の経済生活にも重大な影響を与え得る問題である。いかなる理由をもってしてもテロを正当化することはできず、断じて容認できないとの立場から、日本は、テロ対策を自らの問題ととらえ、他国に対する支援や国際的な法的枠組みの強化をはじめとする多岐にわたる分野で、引き続き国際社会と協力して積極的にテロ対策を強化していく考えである。
また、グローバル化や情報通信の高度化、人の移動の拡大等に伴い、人身取引、薬物犯罪、サイバー犯罪、資金洗浄等の国境を越える組織犯罪(国際組織犯罪)が一層深刻化している。国連、G8、金融活動作業部会(FATF) (注4) 等の国際的な枠組みにおいて、国際組織犯罪に対処するため国際社会が一致してとるべき措置等につき協議・意見交換が行われており、日本もそれらの枠組みの重要なメンバーとして、国際的な取組に積極的に参画している。特に、条約等の国際的なルールづくりが重要であり、日本は、国際組織犯罪対策に関する条約の締結に努めるとともに、必要な国内法整備を進めている。