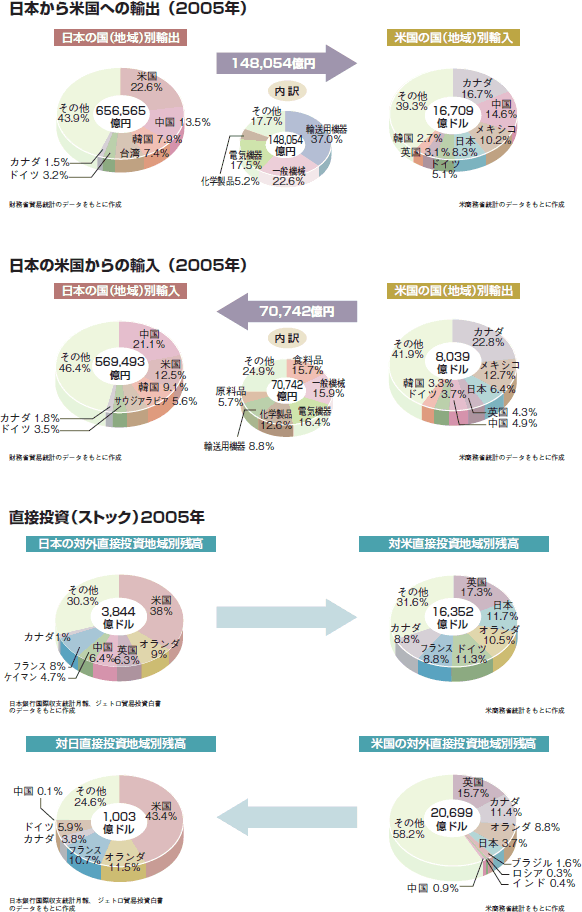このような日米間の緊密な連携は、政治分野同様に、経済分野においても常日ごろから行われている。近年の日米経済関係は、かつての摩擦に象徴される関係から、建設的な対話を通じた協調の関係へと変ぼうを遂げてきた。一方、グローバル化が進展する国際経済における新興国の台頭は、世界経済の更なる繁栄の機会のみならず新たな課題をも提示している。こうした中で、日米両国は、経済分野における法の支配や、WTOをはじめとする地域的・グローバルな経済の課題について協力を深めることを目指している。
6月の日米首脳会談において発出された共同文書「新世紀の日米同盟」で、両首脳は「成長のための日米経済パートナーシップ」 (注1) を基礎として、二国間経済関係を更に深化させ、地域や世界の経済的課題に関する協力を強化する方策を探ることで一致した。同首脳会談及び11月にAPECに際して行われた日米首脳会談を受け、日米協力の具体的方向性を議論するために、12月、日米次官級経済対話 (注2) が開催された。その結果、日米両国は、法の支配の強化とビジネス環境の改善という共通の課題への対処のための協力を強化し、その具体的協力分野として、(1)テロ対策と円滑な貿易の両立、(2)エネルギー安全保障、(3)知的財産権の保護-等における協力を具体化していくことで一致した。また、対途上国援助の在り方、APEC等のアジア太平洋地域の経済枠組みの在り方等においても引き続き協調していくことになった。
また、「成長のための日米経済パートナーシップ」の枠組みの下では、日米両国が双方向の対話の原則を基本として「規制改革及び競争政策イニシアティブ」に取り組んでいる。2006年も各作業部会 (注3) や次官級の上級会合を開催、6月29日の日米首脳会談にあわせて日米両首脳に対する第5回報告書をとりまとめ、公表した。また、12月5日には6年目の対話に関する日米の要望書の交換を行った。
このように協調的・建設的な日米経済関係を維持していく上で、日本は、個別案件についても以下の案件についての取組を行っている。
第一に、米国産牛肉輸入問題については、2005年12月12日に米国産牛肉輸入を再開したが、2006年1月20日、輸入の認められていない特定危険部位(脊柱)の含まれた子牛肉が日本に到着したことから、すべての米国産牛肉の輸入手続きを停止し、政府は日本の消費者の食の安全・安心の確保を大前提に協議を行った。その結果、7月27日、米国産牛肉の輸入手続きを再開するに至った。
第二に、2001年9月の米国同時多発テロ以降のテロ対策の強化に関し、政府は米政府による査証取得・更新手続きの厳格化をはじめとする出入国管理の強化等が日米間の貿易投資に悪影響を与えることのないよう申し入れるとともに、上述の次官級経済対話の下で、日米の先進技術を活用したテロ対策と円滑なモノとヒトの流れの両立を図るべく努力していくこととしている。