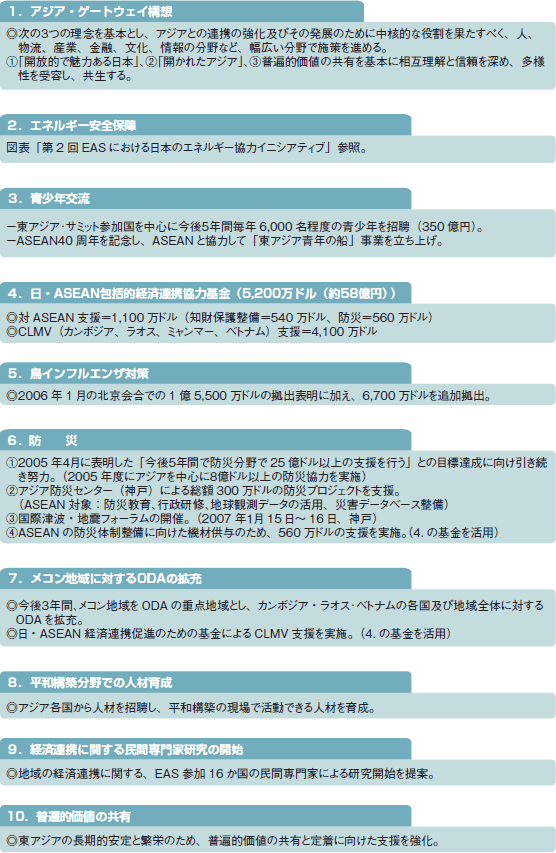(1)東アジア首脳会議(EAS)
2005年12月にクアラルンプールで第1回会議が開催されたEASは、2006年を通じて、着実な発展を遂げた。
日本は、EASが、共同体形成に実際に重要な役割を果たせる枠組みとなるよう、EASの足場固めを着実に進めていくとの基本方針の下、EASの枠組みを通じて地域が共通して直面する課題に対して具体的な効果を上げるような協力事業を進めることで、EASの役割を拡大し、同時に参加国間の一体感を高めることを目指してきた。
こうした日本の考え方が各国に浸透した結果、7月にクアラルンプールで開催された、EAS参加国の外相による会合では、ASEANから、EASの下で取り組むべき5つの重点分野として、(1)エネルギー安全保障、(2)金融、(3)青少年交流を含む教育、(4)鳥インフルエンザ、(5)防災-が提示され、ASEAN以外の国も、これらの課題に重点的に取り組む必要性について、認識を共有した。特に、第2回EASの議長を務めるフィリピンは、エネルギー安全保障に集中的に取り組みたいとの意図を表明した。さらに、これに相前後して、日本のイニシアティブで男女共同参画及び科学技術の分野でEAS参加国の担当閣僚が出席する会合が開催され、さらに経済大臣会合も開催された。
2007年1月15日にフィリピンのセブにおいて開催された第2回EASでは、地域のエネルギー安全保障をはじめとする地域の課題やEASの将来について、各国首脳が大局的に議論した。会議に出席した安倍総理大臣は、エネルギー安全保障に関し、(1)省エネの推進、(2)バイオマスエネルギーの推進、(3)石炭のクリーンな利用、(4)エネルギー貧困の解消-からなる協力イニシアティブを表明した。また、会議終了後、省エネ目標・行動計画の設定、バイオ燃料の利用促進等を内容とする「東アジアのエネルギー安全保障に関するセブ宣言」を採択した。さらに、次回会議までに閣僚級会合や作業部会等を開催し、同宣言に盛り込まれた協力措置をフォローアップしていくこととなった。
エネルギー以外の分野でも、安倍総理大臣は、「アジア・ゲートウェイ」構想や「21世紀東アジア青少年大交流計画」 (注61) をはじめとする、一連の具体的な東アジア協力を表明した。
首脳会議後に発出された議長声明は、日本のエネルギー協力イニシアティブを歓迎し、また5分野すべてにおける具体的協力の開始に言及するなど、EASを具体的協力の場へと育てていく機運を首脳レベルで確認することとなった。また、日本の提案として、経済連携に関するEAS16か国の民間専門家による研究の開始と、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)の設立にも言及した。