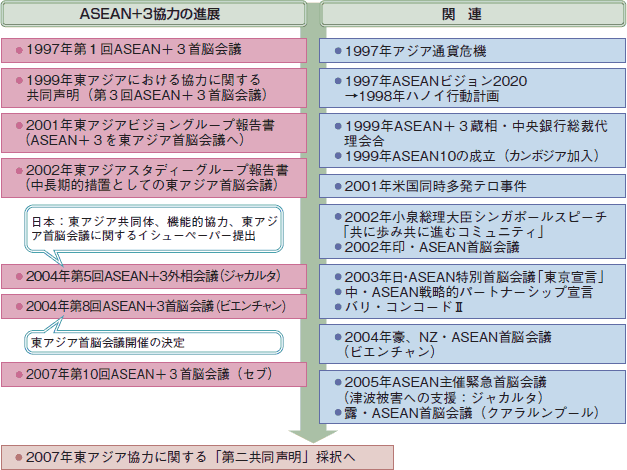アジア通貨危機を直接の契機として誕生したASEAN+3では、9年の歴史の中で、貿易・投資、金融から環境や国境を越える犯罪まで、幅広い協力が進展してきた。2006年には、経済、金融、保健、労働、農業、環境の分野で閣僚会合が開催された。さらに、新たな協力分野として、女性、貧困対策、防災、鉱業の4つが加わった。
また、日本が2005年にASEAN+3外相会議に提出した、東アジア地域協力の包括的なデータベースをもとに、ASEAN事務局自らがとりまとめたデータベースが公表された。さらには、2007年の第11回ASEAN+3首脳会議で採択する「東アジア協力に関する第二共同声明(後出)」作成準備のため、過去の協力実績を包括的にとりまとめる作業を進めることでも合意される等、協力開始10周年となる2007年の節目を前に、これまでの協力実績と問題点を再検討するとともに、より具体的成果を上げるための改善策を考えていく機運が高まった。
2007年1月14日にセブで開催された第10回ASEAN+3首脳会議では、ASEAN+3協力の中長期的方向性、個別分野の協力、同年11月の次回首脳会議で採択する「東アジア協力に関する第二共同声明」の方向性等などについて議論した。会議に出席した安倍総理大臣は、引き続きASEAN+3協力を推進していく意志を示すとともに、特に、地域協力の将来の方向性として、「東アジア協力に関する第二共同声明」の中で、(1)開放性・透明性・普遍的価値を基礎とした協力を推進する意志を共有すること、(2)ASEAN+3、EAS、APEC、ASEAN+1等すべての地域協力を進める意志を確認し、地域内外のすべての協力パートナーの支持を確保していくこと-が重要であるとの基本的考え方を表明した。
▼ASEAN+3協力の進展