(2)国際平和協力
国連自らが国際社会の平和と安全に直接携わる中心的な活動としては、PKO(注22)がある。2005年には、1月のスーダン南北包括和平合意の成立を受け、新しいPKOミッションが活動を開始した。12月現在、世界では16のPKOミッションが展開中であり、合計で約7万人の要員が活動している。地域別に見るとそのうち8つのミッションがアフリカで活動している。
PKOとは本来、安保理決議に基づき、停戦合意の成立後に国連が紛争当事者の間に立って停戦や軍の撤退の監視等を行うことにより、事態の沈静化や紛争の再発防止を図り、紛争当事者による対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、現在のPKOではこれらの伝統的な任務に加え、選挙、文民警察、人権、難民帰還の支援から行政事務や復興開発までも任務とする複合的なPKOが増加しており、任務の多様化、複雑化の傾向が進んでいる。
こうした状況を受け、今日の国際社会においては、平和構築に携わる国々や国際機関等の役割の調整と一貫性ある戦略の立案が大きな課題となっている。これは平和構築委員会設立の前提となった問題意識である。また、PKOの現場における軍事要員と文民要員の協力と役割分担の在り方の統合調整は、PKO以外の平和構築の取組全般にもかかわる問題として、国際社会の注目を集めている(注23)。
日本は1992年の国際平和協力法制定以来、同法に基づき、延べ5,607人(2006年2月時点)の要員を海外に派遣するなど、様々な国際平和協力を行ってきた。2006年1月現在では、ゴラン高原における停戦監視等により中東和平プロセスを下支えする国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に45名の自衛隊員を派遣している(1996年以降、これまでに延べ約900人を派遣)。また、10月には外務省職員が国連スーダン・ミッション(UNMIS)に採用され、現地で情報分析業務に従事している(コラム「スーダンの和平とPKO」参照)。
近年ではこのような人的貢献に加え、国連や人道的な国際救援活動に取り組む国際機関に物資協力を行う物的貢献の比重も高まっている。10月には、国連からの要請に基づき、UNMISに参加するアフリカ諸国部隊(ケニア、ザンビア)の活動に資するため、四輪駆動車27台、地雷探知機60機、大型テント20張を供与した。
また、地域機構が行う平和支援活動(PSO)(注24)に対する支援の重要性が増大していることにかんがみ、日本はスーダン西部のダルフール地方で停戦監視等を行っているAUの活動を支援するため、3月にAUに対して207万ドルを拠出したほか、10月にはAU部隊要員の国際人道法等に関する知識向上のためのトレーニングを実施する目的で、人間の安全保障基金を通じて約281万ドルを支援した。
日本は国際社会の一員としての責任を自覚し、また国際社会の平和と安全が日本の平和と安全に密接にかかわっているとの認識の下、今後も国際貢献のための体制整備に努め、紛争に苦しむ国々に対し積極的な国際平和協力を行っていく考えである。
▼日本が参加中のPKO(2006年1月末現在)
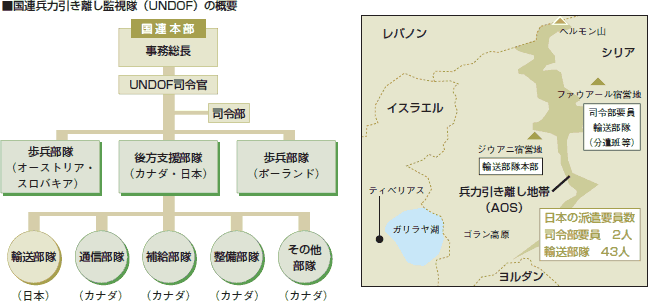
▼PKOの現状
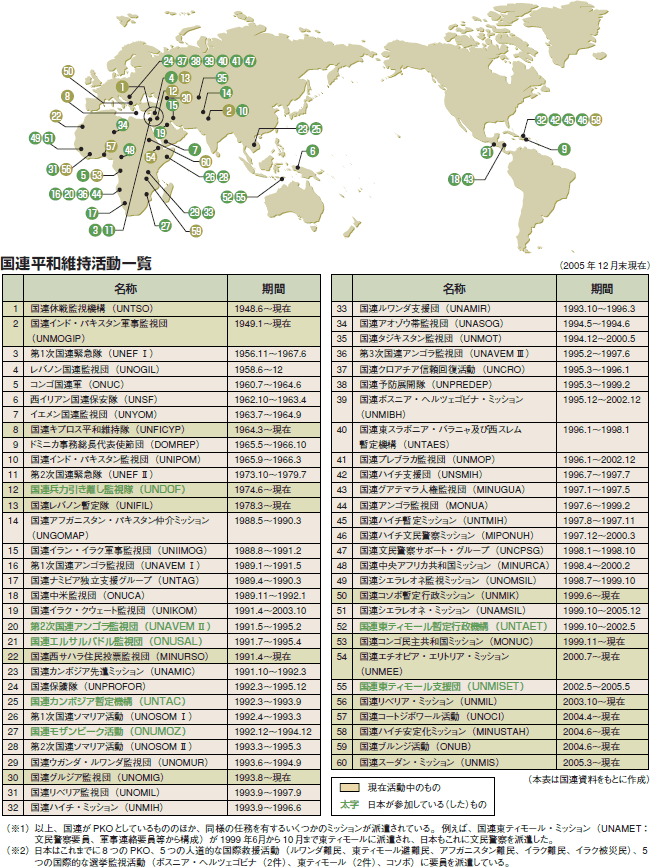
▼国際平和協力法に基づく日本の国際平和協力業務の実績
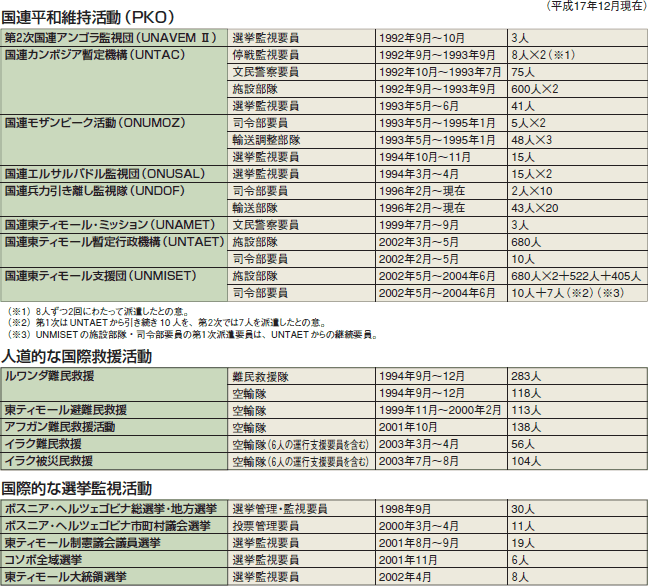
|