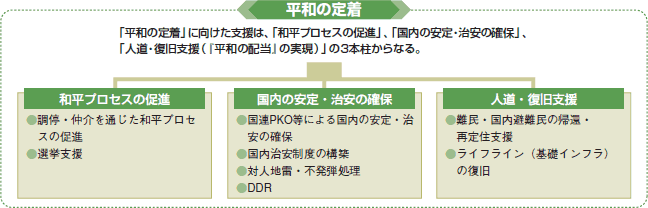5.紛争への包括的取組
【総 論】
冷戦終結後今日まで、世界各地ではいまだに数多くの紛争が続いている。その要因は宗教・民族の相違に基づく対立や、部族間の抗争、天然資源の争奪など多様であり、またその多くは、主権国家の枠組みではとらえきれない内戦や国境を越えた紛争等の形をとっている。紛争は時に大量の難民・国内避難民の発生や大規模虐殺等、悲劇的な結果を招いた。また、紛争に疲弊し統治能力を失ったいわゆる「破綻国家」は、大量破壊兵器拡散やテロの温床の生成を助長するものとして、大きな問題となっている。
国際社会では近年、こうした地域の平和と安定の回復には、紛争の解決から復旧、社会復帰、復興に至る過程を長期的かつ包括的な視点でとらえることが重要であるとの認識が高まっている。国連において12月、平和構築委員会設立の決議が採択されたのは、そのような国際社会の認識の表れであると言える。
日本は、紛争を恒久的に解決し持続的な復興へとつなげていくためには、国際社会が一致して、(1)和平プロセスの促進、(2)国内の安定・治安の確保、(3)人々の平和な生活の回復(人道・復興支援)-の3つの要素にわたる「平和の定着」に向けた努力を推進していくことが必要であると考えている。このような認識に基づき、ODAをはじめとする外交手段を活用して国連等の国際機関、各国、非政府組織(NGO)とともに具体的な取組を行っている。
また、国際社会の平和と安定に向けた取組に効果的な形で貢献できる人材を官民を問わず幅広く育成し、日本の国際貢献の人的基盤を拡大強化することも緊急の課題である。こうした視点から、政府は2002年12月の「国際平和協力懇談会」(注19)報告書における提言を受け、「国際平和協力分野における人材育成検討会」を2003年10月から2004年4月にかけて開催した。そこでは、日本が国際平和協力の多様な分野において人的貢献を行うために必要な人材育成のメカニズムを検討し、具体的な行動計画を作成(注20)した。政府は同行動計画に基づき人材育成に努めている(注21)。
▼「平和の定着」を目指す日本の支援