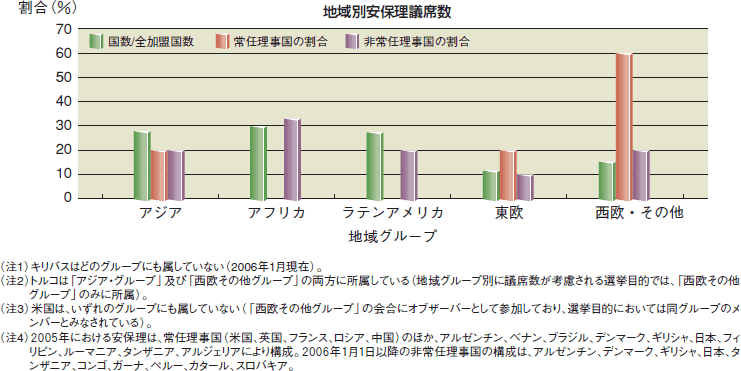【国連改革】
(1)安保理改革
テロ、大量破壊兵器の拡散、貧困、感染症等、国際社会が新たな課題に直面する中で、国連、とりわけ世界の平和と安全に大きな役割を担う安保理への期待はますます高まっている。その一方で、安保理の構成は国連創設後60年間、基本的には変化しておらず、国際社会の変遷に十分対応できていない。世界各国が国連を通じて21世紀の課題に効果的に対処していくために、国連、特に安保理を改革することは、今や国際社会の緊急課題である。また、日本が安保理常任理事国となることは、(1)国際平和への貢献や国際社会への財政的貢献に見合った発言力の獲得、(2)より建設的な国際社会への貢献の実現、(3)安全保障にかかわる重要な情報の迅速な入手、(4)非核兵器保有国としての常任理事国入りによる安保理の信頼性向上、(5)アジアの代表性の向上-などの点で大きな意義がある。日本は、その経験と持てる力を最大限に発揮し、安保理常任理事国として一層の責任を果たしたいと考えている。
3月20日、アナン国連事務総長は開発、平和と安全、法の支配と弱者の保護、国連の機構改革等についての包括的な提言を盛り込んだ報告「より大きな自由を求めて」を公表した。安保理改革については、2004年12月に提出された「ハイレベル委員会」の報告書を踏まえ、モデルA(常任6議席、非常任3議席の拡大)、モデルB(再選可能な4年任期の非常任8議席、非常任議席1議席の拡大)(注16)の2つの具体案を提示し、加盟国に対し、9月の国連首脳会合の前に決定を行うべきであり、また、決定はコンセンサスで行われることが望ましいが、そのことが行動を遅らせることの言い訳になってはならない旨勧告した。これを受けて、国連加盟国の間では、安保理改革に関する議論が一層活発化した。日本は、安保理の決議が着実かつ実効的に履行されるために、国際の平和と安全の維持において主要な役割を果たす意思と能力を有する国が、常に安保理の意思決定過程に加わることが必要との考えから、常任・非常任議席双方の拡大を含むモデルAを基礎として議論を進めていくべきと主張し、各国に理解と協力を呼びかけた。
日本は、2004年9月にブラジル、インド、ドイツとの間で、常任・非常任議席双方の拡大を通じた安保理改革の実現を推進する母体としてG4を結成して以来、ほかの3か国と緊密に連携しながら加盟国の間の安保理改革についての議論を主導した。3月の事務総長報告を受けて、G4はモデルAを基本にした安保理決議案を策定するための議論を加速させ、5月13日には拡大された安保理の構成について枠組みを定める「枠組み決議案」に合意した。この決議案は、常任理事国を6か国、非常任理事国を4か国増やして安保理議席の総数を25とするとともに、新常任理事国は現常任理事国と同じ責任及び義務を持つべきであるとの原則をうたうものであった。その後、G4は各国の反応を踏まえ、6月8日には決議案の修正に合意した。主な修正は、憲章改正の見直しのタイミングを、「2020年」から「改正憲章発効後15年後」に変更し、その見直しの際に拒否権拡大の決定がなされるまで、新常任理事国は拒否権を行使しないとされた点である。
安保理改革実現に不可欠な国連憲章の改正には、全加盟国の3分の2(128か国)以上の賛成及び常任理事国すべてを含む全加盟国の3分の2以上の批准が必要である。日本は5月に、すべての地域の大使を一堂に招集して大使会議を開催し、国連・安保理改革を主要なテーマの一つとしてとりあげ、各国への働きかけの準備を進めていたが、G4枠組み決議案の合意を受けて、同決議案の提出・採択に向け、ほかの3か国とともに、外交の総力を結集した働きかけを全世界で行った。また、国内では、公開シンポジウムや「安保理改革」をテーマにした町村外務大臣主催のタウンミーティング等を頻繁に開催し、政府の取組に対する国民の理解と支持の拡大に努めた。
G4の働きかけは、国際社会の安保理改革に向けた機運をかつてないほどに高めた。この勢いに乗って、G4枠組み決議案は7月6日に国連事務局に正式に提出され、11日に総会に上程された(最終的な共同提案国は32か国)。G4決議案の提出を受けて、13日に、新常任理事国への拒否権付与を主張するアフリカ連合(AU)が、21日には、イタリア、パキスタン等、常任理事国の拡大に反対し、非常任理事国のみの拡大を主張する「コンセンサスのための結集」(コンセンサス・グループ)が、それぞれ独自の決議案(注17)を提出した。
全加盟国の3分の2以上の賛成を得る上で、53か国の大票田であるアフリカの支持は不可欠であることから、日本を含むG4は、常任理事国の拡大について考えを一にするAU決議案とG4決議案の一本化を図るべく、アフリカ諸国への働きかけを強めた。しかしながら、最終的には、アフリカが新常任理事国への拒否権の付与等に固執したため、一本化には至らず、9月の第59回国連総会の会期をもってG4決議案はほかの2つの決議案とともに採決に付されることなく廃案となった。
9月14日から16日にかけての国連首脳会合で、小泉総理大臣は、演説において、日本の安保理常任理事国入りの意思を改めて表明するとともに、安保理改革について、第60回総会会期中の早期の決定を訴えた。同会合で採択された「成果文書」の中では、早期の安保理改革が「全般的な国連改革努力における不可欠の要素」として位置付けられ、総会に対して、「改革に関する進捗状況を本年末までにレビューすること」が要請された。
また、町村外務大臣も、9月13日から19日までニューヨークを訪問し、国連総会で一般討論演説を行った。町村外務大臣は、国連史上初となった安保理改革決議案の提出を踏まえ、加盟国に対して第60回総会会期中(2006年9月まで)における早期の決定を強く訴えた。
「成果文書」における安保理改革の位置付けを踏まえ、同会期において、安保理改革の議論は引き続き活発に行われている。11月10日から11日には、国連総会にて安保理改革が審議され、71か国が安保理拡大の在り方や安保理の作業方法の改善の必要性等に言及した。日本の大島国連大使は、「国際の平和と安全の維持において主要な役割を果たす明確な意思と真の能力のある加盟国を、恒常的に安保理に含めることによって拡大されるべき」、「前会期中に提出されたいかなる決議案も投票に付されなかったという事実を越え、これまでより一層幅広い支持を獲得することができる解決策を追求することが必要」と発言した。
12月19日、エリアソン第60回国連総会議長の書簡という形で、9月の「成果文書」で要請されていた総会による安保理改革の進捗状況のレビューが発出された。書簡は、安保理拡大の必要性について幅広い合意が存在することを確認し、2006年に安保理改革について協議を再開するよう加盟国に求めている。
▼2005年国連首脳会合
新千年紀の幕開けを目前に控えた2000年、国連ミレニアム・サミットが開催され、大量破壊兵器の拡散、テロ、感染症など国連創設当時に想定されていなかった新たな問題への対処や、国連強化など、21世紀における国連の役割が議論された。それから5年後の2005年9月、創設60年の節目を迎えた国連に、再び170か国以上の国家元首・政府代表が一堂に会して国連首脳会合(World Summit)が開催された。首脳会合に先立ち、2000年以降の改革の進捗状況を踏まえて「開発」、「平和と集団安全保障」、「人権、法の支配」、「国連の強化」の4つの分野で更なる取組を進めていくとの首脳の決意を表明する「成果文書(Outcome Document)」の発出に向けた加盟国間の交渉が行われた。しかし、幅広い分野において191か国もの意思統一を図る作業は決して容易ではなく、交渉は難航を極めた。首脳会合の直前まで詰めの交渉が行われ、夜を徹しての交渉作業の末、首脳会合開幕前日の9月13日にようやく加盟国の合意が成立し、16日、会合の閉会に当たり、成果文書が全会一致で採択された。 この成果文書には、加盟国間の立場の相違から、軍縮・不拡散に関する記述は盛り込まれなかったが、安保理改革の実現に向けた明確な記述のほか、旧敵国条項の削除、日本がイニシアティブをとっている「人間の安全保障」への言及、平和構築委員会や人権理事会の設置、マネジメント・事務局改革についての改善措置等が盛り込まれ、国連創設60周年の機会に、貧困の問題と国連改革の問題について、今後の方向性を示すものとなった。 |
この間にも決議案について新たな展開が見られた。まず、12月14日、アフリカの一部諸国により、新常任理事国への拒否権付与を特徴とする「AU決議案」が再提出された。さらに、2006年1月5日には、G4のうち日本を除くドイツ、インド、ブラジルの3か国から、第59回総会会期中に提出されたG4の枠組み決議案と実質的に同じ内容の決議案が提出された。いずれの決議案も当面、票決に付される予定はないが、引き続きその動向を注視していく必要がある。
安保理改革は、戦後の国際制度を大きく変革する試みであり、過去10年もの間様々な努力が行われてきたにもかかわらず、結論を見ていない難しい課題である。日本をはじめとするG4が過去1年間にわたり進めてきた運動は、決議案の採択には至らなかったものの、改革実現に向けた機運をいまだかつてないほどに高めた。日本としてはドイツ、インド、ブラジルとの協力の枠組みを維持しながら関係国と話合いを続け、安保理改革実現に向けて引き続き努力していく。
▼非常任理事国選出回数の上位国(2006年3月現在)
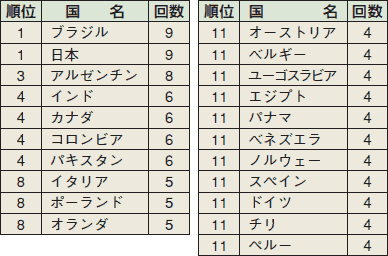
▼国連加盟国と安保理常任・非常任理事国の地域別構成