2.テロ対策
【総 論】
2001年9月11日の米国同時多発テロ以降、国際社会はテロ対策を最優先課題の一つと位置付け、国連やG8など多国間の枠組み、アジア太平洋経済協力(APEC)など地域的な協力、二国間協力など様々な場において、テロ対策の強化が合意・確認され、テロとの闘いに関する政治的意思の強化と実質的協力が進展している。具体的には、アフガニスタン等でテロリストの摘発が継続され、テロ資金対策をはじめとする幅広い分野で関係国間の協力が展開されており、テロ対処能力が不足している途上国等に対する能力向上のための支援(キャパシティ・ビルディング支援)も実施されている。また、2005年は、海洋航行不法行為防止条約(注6)及び核物質防護条約(注7)の改正並びに核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(仮称。以下、核テロリズム防止条約)の採択等、新たな法的枠組みが整備された。このように、テロによる悲劇を防止するための努力が推進され、着実に成果を上げている。
近年の国際社会のテロとの闘いにより、国際テロ組織アル・カーイダ等の指導部の能力は減退し、戦闘員も減少していると考えられるが、いまだにその勢力を軽視することはできない。加えて、同組織の支援や思想的な影響を受けた関連組織や、独立しつつもその思想を信奉すると考えられるローカルな組織による世界規模のイスラム過激主義運動が新たな脅威となっている。2005年にも、フィリピン・マニラ等での連続爆弾テロ事件(2月14日)、ロンドンでの連続爆弾テロ事件(7月7日)、日本人1名が犠牲となったインドネシア・バリ島での同時爆弾テロ事件(10月1日)、ヨルダン・アンマンでの同時自爆テロ事件(11月9日)など、世界各地で多くのテロ事件が発生している。このように、日本人旅行者や在留邦人、日本企業が多く存在し、政治、経済、社会全般に深い関係を有する東南アジア地域を含め、国際テロの脅威は依然として深刻である。
科学技術の発展に支えられ、国際社会でヒト・モノ・カネ・情報の流動性が飛躍的に高まっている中、国際テロリストもまた、インターネットや国際交通網など現代社会の特性を最大限に活用して、一般市民の日常生活を脅かす活動を展開している。こうした状況下で、テロ防止のためには、国際社会が協調してテロに対し断固とした姿勢を示すとともに、テロリストに活動の拠点を与えない、資金・武器などテロを実行するための手段を絶つ、テロの標的となり得る施設・機関等の脆弱性を克服する、また、テロ対処能力が不足している途上国を支援することが重要となっている。具体的には、テロリストを厳正に処罰するための国際的な法的枠組みの強化、テロ資金対策、交通保安体制の強化、出入国管理の強化、大量破壊兵器などの不拡散といった幅広い分野における取組を継続・強化していくことが必要である。
▼2005年に発生した主なテロ事件の例
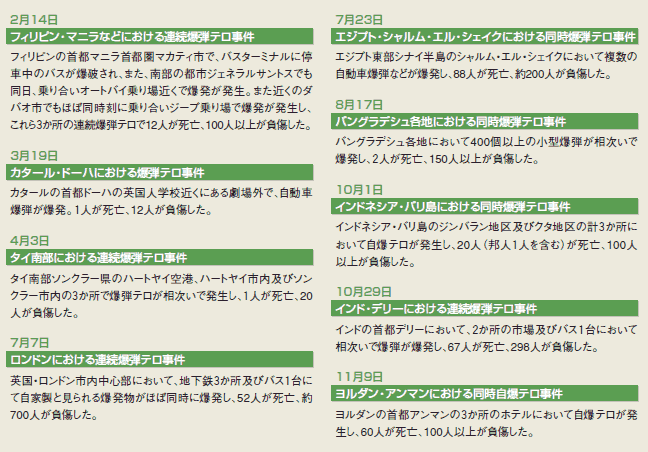
テロは国家及び国民の安全上の問題のみならず、投資・観光・貿易等に対する影響を通じ、一般市民の経済生活にも重大な影響を与え得る問題である。我々一人ひとりがテロを市民生活に対する挑戦としてとらえ、テロ防止に協力することが必要である。日本は、いかなる理由をもってしてもテロを正当化することはできず、断じて容認できないとの立場から、テロ対策を自らの問題ととらえ、他国に対する支援や国際的な法的枠組みの強化をはじめとする多岐にわたる分野で、引き続き国際社会と協力して積極的にテロ対策を強化していく考えである。