イラクの政治プロセスはおおむね順調に進んできたが、他方で、治安状況は依然として予断を許さず、復興については道半ばにあるのが現状である。イラクが平和的な民主国家として再建されることは、中東地域の安定に不可欠であり、特に同地域に原油供給の約9割を依存する日本にとっては国益に直結する問題として極めて重要である。また、イラクが不安定化すれば同国はテロの温床となりかねず、今やイラクの再建は、国際社会共通の課題と言える。国連安保理決議が加盟国等に対しイラクの復興を支援するよう求め、米国をはじめとする各国及び国連等の国際機関が実際に支援を進める中で、日本も、国際社会の責任ある一員として日本にふさわしい支援を行う必要があるとの認識の下、人道復興支援のために自衛隊をイラクに派遣するとともにODAを提供し、これらを「車の両輪」として最大限努力してきている。また、このほかに文化・教育面においても支援してきており、こうした日本の取組は、国際社会やイラクの人々から高い評価を得ている。
(イ)ODAによる支援
ODAによる支援は、経済・社会面での復興に向けたイラクの主体的な取組を支援するとともに、イラクの政治プロセスを後押しする役割も担っている。日本は、2003年10月にマドリードで開催されたイラク復興支援国際会議で、2007年までに最大50億ドルの支援を行うことを表明した。このうち、総額15億ドル分の無償資金協力 (注6) による「当面の支援」が本格的に進展し、2005年5月までに全額につき実施を決定した。この支援は、イラク国民の生活基盤の再建及び治安の改善に重点を置き、電力(発電所のリハビリ、移動式変電機の供与、サマーワ大型発電所の建設)、医療・保健(11総合病院リハビリ・機材供与等)、水・衛生(浄水装置、ゴミ・下水処理設備の供与等)、環境(国連環境計画(UNEP)が実施する信託基金の事業に拠出し、メソポタミア湿原の環境管理等に協力)、治安(警察車両等の供与)、教育、文化、スポーツ等の分野で行われてきた。
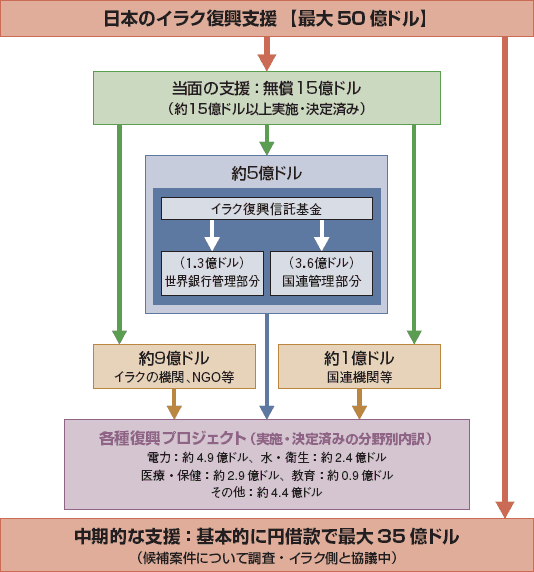
また、日本が表明している支援のうち残りの最大35億ドルについては円借款を中心に行う予定であり、対象分野としては、電力、教育、医療・保健、水・衛生等の従来の支援分野に加え、運輸等のインフラ整備も視野に入れていく。この支援は、現地の情勢を見つつ、現在行っている無償資金協力と可能な限り継ぎ目のない形で実施できるよう、両政府間でできる限り早期に具体的な支援案件として確定すべく作業を進めている。
また、復興が着実に進展するためには、直接支援や国際機関経由による資金協力に加え、人材育成が極めて重要との考えから、日本は、エジプトやヨルダンといった周辺国や日本国内において医療、電力、統計、水資源、上下水道、テレビ放送技術、選挙支援等の分野で研修を実施してきており、12月末時点で総計1,143名のイラク人に研修を行った。
自衛隊が派遣されている南部のムサンナー県では、ODAによる支援と自衛隊の活動を有機的に連携させつつ(「(ロ)自衛隊による支援とODAの連携」参照)、また、国連開発計画(UNDP)、国連人間居住計画(UN‐HABITAT)等の国際機関と協力して、復興需要の高い電力、給水、医療・保健、教育、道路、雇用等の分野において、多くの支援案件を実施し、現地の生活水準の向上に寄与している。なお、ムサンナー県では、在サマーワ外務省連絡事務所に所長以下5名が常駐している。
6月には、ブリュッセルで米国とEUの共催によりイラク国際会議が行われ、80以上の国・機関が参加し、政治、経済・復興、治安・法の支配の3分野で国際社会がイラクを支援していくことが表明された。同会議において、日本は経済・復興分野の共同議長を務めた。また、7月、イラク復興信託基金のドナー委員会 (注7) 会合がヨルダンで開催され、イラクから中期的な復興の指針を示す開発戦略が発表された。
また、日本はパリクラブ債権国の中で最大の対イラク公的債権保有国であるが、2004年11月にパリクラブにて債権諸国とイラクとの間でイラクの公的債務の削減に関する合意(3段階にわたり公的債務を計80%削減)がなされたことを受けて、2005年11月にズィーバーリー・イラク外相が訪日した際に、麻生外務大臣との間で保有債権額の8割に当たる約7,100億円の債務削減に係る合意に署名した。
2003年5月に全会一致で採択された安保理決議1483により、国際社会が団結してイラクの復興に取り組むことの重要性が確認されたことを受け、日本としても、イラクの復興のために主体的かつ積極的な貢献を行うことを目的とするイラク人道復興支援特別措置法を制定し、同法に基づく対応措置に関する基本計画が閣議決定された。これに基づき、航空自衛隊の先遣隊及び陸上自衛隊の先遣隊が現地入りした。その後順次本隊が派遣され、サマーワを中心とした医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備といった人道復興支援活動が本格的に開始された。
2004年6月、イラクの完全な主権回復に対する歓迎やイラク暫定政府から国際社会への支援要請を内容とする安保理決議1546が全会一致で採択されたのを受けて (注8) 、同月末のイラクの主権の回復をもって、自衛隊は多国籍軍の中で活動を行うこととなった。こうして自衛隊は、多国籍軍の中で、統合された司令部の下にあって、同司令部との間で連絡・調整することとなったが、同司令部の指揮下にはなく、日本の主体的な判断の下に、日本の指揮に従い、イラク人道復興支援特別措置法及びその基本計画に基づいて人道復興支援活動等を行ってきている。
これまで自衛隊が行ってきた医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備といった人道復興支援を中心とする活動は、ODAによる支援との連携により、現地の人々の生活基盤を回復、充実させるとともに、雇用も生み出してきた (注9) 。2005年12月現在の実績としては、ムサンナー県内の学校のうち、陸上自衛隊により22校、ODA(UN‐HABITAT経由)により59校が改修されている。道路については約1,000kmの道路が改修を必要とする状態であり、陸上自衛隊とODAを活用し、合計113km程度を改修している。また、県内32か所のプライマリー・ヘルス・センターのうち、陸上自衛隊は21か所を改修、ODAで32か所すべての機材が整備される。
自衛隊が行ってきたこうした人道復興支援活動に対しては、ジャアファリー首相やズィーバーリー外相、イラク移行政府や現地の人々から感謝の意とともに活動継続の要望が表明されていた。

▲ 診療所の補修現場で地元の子供たちの歓迎を受ける自衛隊(12月31日、イラク・サマーワ 写真提供:防衛庁)
11月8日、イラク政府からの要請に基づき、安保理は、イラクに駐留する多国籍軍の権限を2006年末まで1年間延長する安保理決議1637を全会一致で採択した。他方、イラク人自身による国づくりは、12月15日の国民議会選挙実施後、新政府樹立に向けた取組が始まるなど、重要な局面を迎えている。そのような中で日本は、支援を継続しなければ国際社会の信頼を得ることはできず、また、イラクが平和で民主的な国家として復興することは、国際社会の安定に極めて重要であり、日本の国益にかなうとの主体的判断に基づき、12月8日、自衛隊による活動を継続するために、基本計画を2006年12月14日まで延長する閣議決定を行った。
(ハ)文化・教育面での協力
日本はイラクの文化・教育分野の復興を支援し、また日本について、親しみやすく礼節があるというソフトなイメージが普及することを目的として、イラクの文化面で様々な支援を行っており、草の根文化無償資金協力のスキームを用いた様々なスポーツ関連支援や国際交流基金や国連教育科学文化機関(UNESCO)等を通じた文化・教育面での協力を行った (注10) 。