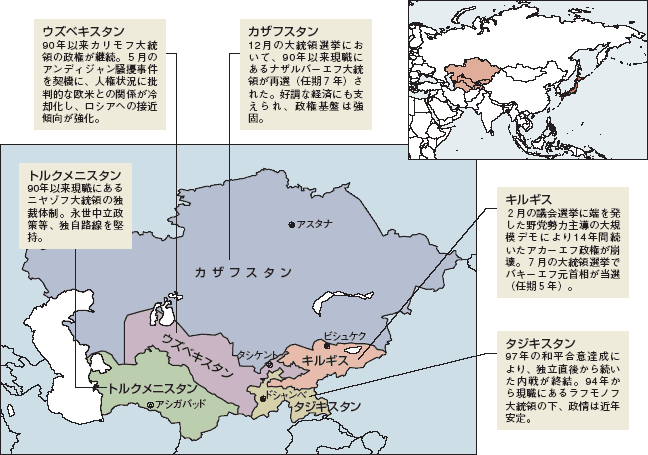キルギスでは、2月の議会選挙を発端として、14年にわたり政権を維持してきたアカーエフ政権が崩壊し、新たにバキーエフ大統領が就任した。ウズベキスタンでは、5月にアンディジャンで暴動が発生し、鎮圧の過程で治安当局により数百人の一般市民が殺害されたとも言われ、カリモフ政権の強硬な対応が国際的な批判を招いた。また、7月にカザフスタンのアスタナで開催された上海協力機構(SCO)首脳会合が、アフガニスタンでの反テロ作戦のため加盟国領域内に駐留する外国部隊に駐留期限の設定を求めたのを受け、ウズベキスタンは駐留米軍の撤退を求め(11月に完了)、ロシアと同盟関係条約を締結するなど、ロシアとの関係を強めている。
一方、11月の議会選挙で与党が圧勝したアゼルバイジャンと、12月の大統領選挙で現職のナザルバーエフ大統領が圧倒的な勝利を収めたカザフスタンは、石油生産に支えられた高い経済成長を維持しつつ相対的に安定した政権運営を行っており、エネルギー資源に恵まれた国と持たざる国の経済的格差が各国の政治状況に影響を及ぼす傾向が強まっている。
地域内紛争を抱えるコーカサス諸国では、グルジア国内のアブハジア自治共和国及び南オセチア自治州の分離・独立問題、アゼルバイジャンとアルメニアとの間のナゴルノ・カラバフ問題の解決に向けたOSCE等による調停作業が継続されたが、大きな進展は見られなかった。
地域内協力の動きとしては、10月の中央アジア協力機構(CACO)首脳会合で、CACOをロシア主導のユーラシア経済共同体(EAEC)に統合することが合意され (注10) 、ウズベキスタンがEAECへの加盟申請を行うなど、ロシアを中心とする新たな域内協力の動きが見られた。これに対し独自路線を歩むトルクメニスタンは、8月のCIS首脳会議でCISを脱退し、準加盟国となる意向を表明した。
3月、日本と中央アジア諸国は「中央アジア+日本」対話の第1回高級事務レベル会合(SOM)をタシケントで開催し、今後の協力の柱として、(1)政治対話、(2)地域内協力(テロ、麻薬、地雷、貧困撲滅、医療・保健、環境、水、エネルギー、貿易・投資、輸送の10分野)、(3)ビジネス振興、(4)知的対話、(5)文化交流・人的交流、を進めていくことで意見が一致した。日本は、この対話を通じて、各国との二国間関係の増進に加え、中央アジア地域全体との関係強化に取り組む方針である。
要人の往来では、「愛・地球博」のナショナルデーに際し、アフメトフ・カザフスタン首相(6月)、マルガリャン・アルメニア首相(6月)、シャリフォフ・アゼルバイジャン副首相(5月)が博覧会賓客として訪日した。日本からは、逢沢外務副大臣がアゼルバイジャン及びトルクメニスタン(1月)、小野寺五典外務大臣政務官がカザフスタン(4月)、福島外務大臣政務官がカザフスタン及びキルギス(7月)、原田義昭衆議院外務委員長を団長とする衆議院公式議員派遣団がキルギス(11月)をそれぞれ訪問した。
▼中央アジアの政治情勢