(イ)ロシア内政
プーチン大統領は2005年も高い支持率を背景に、安定した政権運営を行った。
2005年はソ連が大きな犠牲を出して勝利した第2次世界大戦の終了から60周年に当たることを踏まえ、5月9日、モスクワで大規模な記念式典が行われた。国連総会決議に基づき「追悼と和解の精神」の下で行われたこの式典には、小泉総理大臣をはじめ50以上の国や国際機関から首脳・代表が出席し、内外の注目を集めた。
社会制度改革としては、年金受給者等が享受してきた公共サービスの無料利用等の特典を現金支給に変更する法律が1月に施行され、プーチン政権下では初の大規模な抗議行動が国内各地で見られたが、年金引上げの繰上げ実施により沈静化した。10月には、プーチン大統領が保健、教育、住宅建設及び農業の4分野にわたる大規模な社会改革計画「優先的国家プロジェクト」を発表し、これを推進するための政府機能強化等を理由として、11月にメドヴェージェフ大統領府長官を第一副首相に任命するなど一連の人事を行った。
12月にはロシアで活動する非営利団体などに関する法改正が行われた(プーチン大統領による署名は2006年1月)。これは非営利団体を装ったテロ活動等の防止等を目的とし、特に外国人を設立者とする団体への規制を強化するものであり、審議過程において日本及び欧米諸国より懸念表明等がなされ、法案は修正された。
内政上大きな課題であるチェチェン問題に関しては、3月に独立派武装勢力の穏健派指導者マスハドフがロシア治安部隊との戦闘中に死亡し、10月にチェチェンに近いカバルダ・バルカル共和国で武装勢力による治安当局等への襲撃事件が発生するなど、緊迫した状況が続く一方、11月には1997年以来初のチェチェン共和国議会選挙が厳重な警備の下で実施された。
(ロ)ロシア経済
2005年のロシア経済は、前年から減速は見られるものの、7年連続の成長(対前年比GDP6.4%増)を維持した。経済の好調は、主として石油の国際価格高騰を背景とするものであり、エネルギー輸出に大きく依存した構造は変わっていない。経済基盤強化のため、加工、ハイテクを中心とする国内産業の育成・発展や地方の開発が課題となっている。この関連で、「経済特区法」が採択され(2006年から運用開始)、6つの経済特区が指定された。
外国人のアクセス制限を内容とする地下資源法改正に向けた動き、国営天然ガス企業「ガスプロム」による民間石油会社「シブネフチ」の買収、石油会社「ユコス」のホドルコフスキー元社長の有罪確定等、経済への国家管理の傾向が強まった。
▼最近のロシア経済指標
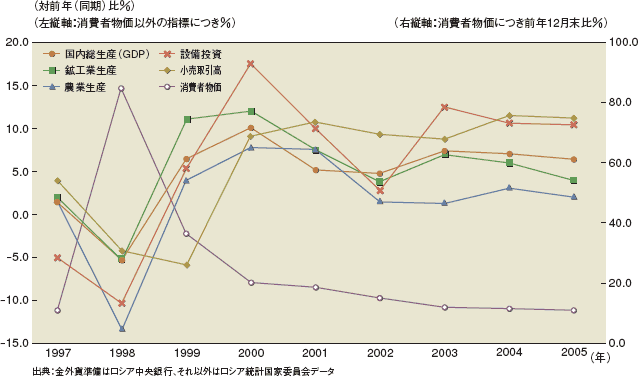
(ハ)ロシア外交
プーチン大統領は、2005年も活発な首脳外交を展開し、欧米諸国との協調を維持する一方、中国との協調路線やアジア太平洋地域重視を強く打ち出した。他方、歴史認識や天然ガス価格等を巡る周辺諸国への強硬な姿勢も見られた。米国のブッシュ大統領とは5回の首脳会談を行い、二国間問題、国際問題、ロシア国内情勢等を話し合った。欧州とは、2回のロシア・EU首脳会合を行い、「4つの共通空間」 (注9) の実現に向けたロードマップを中心に協議した。他方、ラトビア及びエストニアとの国境条約拒否等、歴史認識を巡って関係が複雑化する事例も見られた。
中国との関係では、4回の首脳会談、初の中露共同軍事演習、2度の印中露3か国による外相会談により連携を強化した。また、プーチン大統領は、11月に韓国と日本を歴訪し、12月には初の露・ASEAN首脳会合を実現、同時期に行われた第1回東アジア首脳会議(EAS)にゲスト参加して、改めてEAS正式参加の意思を表明するなど、アジア太平洋外交に意欲的な姿勢を示した。
CIS諸国のうち、親欧米国のグルジア、ウクライナ、モルドバに対しては2006年以降の天然ガス輸出価格の大幅引上げを通告する一方で、ウズベキスタンとは11月に同盟関係条約に調印、ベラルーシとは憲法的文書の準備等の連合国家創設に向けた協議を進め、関係強化に努めた。
