EASの開催は、2004年11月にラオスのビエンチャンで開催されたASEAN+3首脳会議で決まり、2005年4月のASEAN非公式外相会議で、ASEAN+3以外の国にもEAS参加の道を開くことが合意された。5月には日本の提案で、EASの内容と形式について議論するためのASEAN+3非公式外相会議が京都で開催された。町村外務大臣はEAS参加をASEAN+3以外の国にも開放するというASEANの決定を評価するとともに、EASは深化していくプロセスであり、引き続き、その内容・形式について、ASEANの主体性を尊重しつつ考えていくべきであると主張した。こうした流れを受けて、7月にビエンチャンで開催されたASEAN+3外相会議で、EASの参加国をASEAN+3にインド、オーストラリア、ニュージーランドを加えた16か国とすることが決まった。
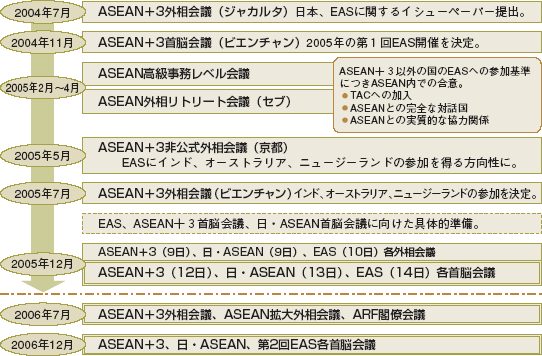
日本はEASの準備過程で、将来の東アジア共同体形成を視野に入れた東アジア地域協力が、地域内外の理解と支持を得ながら更なる発展を遂げ、地域の平和と繁栄に一層貢献するものとなるために確保すべき幾つかの基本原則を提案してきた。具体的には、第一に、地域協力の成果を域外とも広く共有し(開放性)、協力内容についての透明性を確保し、重要な協力パートナーを広く協力枠組みに取り込んでいくこと(包含性)、第二に、自由、民主主義、人権、法の支配等の普遍的な価値を尊重し、グローバルなルールを遵守すること、第三に、政治的制度化を急がず、個別分野での協力促進を通じて地域協力を深化させること(いわゆる「機能的アプローチ」)などである。こうした考え方は徐々に地域各国にも浸透してきた。
12月14日にマレーシアのクアラルンプールで開催された第1回EASでは、各国首脳が東アジアの将来と地域協力の在り方について自由闊達に議論した。小泉総理大臣は、将来の共同体形成も視野に入れて、EASを地域協力の理念や原則、共通課題への対処について戦略的・大局的観点から議論する場に発展させたいと表明した。また、鳥インフルエンザ、テロ、海賊対策、エネルギー問題等について具体的協力を進め、参加国の一体感を醸成すれば、EASは共同体形成に重要な役割を果たすことができると述べた。
こうした議論を経て、首脳会議終了後に採択された「クアラルンプール宣言」では、先に述べた日本の主張する考え方が相当程度反映されるとともに、EASの毎年開催が決定されるなど、EASの今後の発展に資する成果が得られた (注55) 。EASと共同体形成の関係の在り方については、EASが「共同体形成に重要な役割を果たし得る」との文言を宣言に盛り込むことで合意が得られた。これは、今後EASが地域協力の発展に寄与するための重要な基礎を築く成果と言える。さらに今後、EASが共同体形成に実際に重要な役割を果たせるようにするため、参加16か国間で各分野の具体的協力の実績を上げる必要があるが、第1回EASで鳥インフルエンザ対策に関する別個のEAS宣言が発出されたことは、その重要なきっかけとなるものである。

▲EAS参加国による外相会議(昼食会)に出席する麻生外務大臣(12月10日、マレーシア・クアラルンプール)
なお、会議の一部にプーチン・ロシア大統領がゲスト参加し、次回以降のEASに正式参加したいと表明した。これについては今後、参加国間で対応を検討することになっている。次回のEASは、2006年12月13日にフィリピンのセブ島で開催される予定である。