アジア通貨危機を直接の契機として誕生したASEAN+3は、以後8年の歴史を経て、貿易・投資、金融から環境や国境を越える犯罪まで、17分野で48件の協力枠組みを有するまでに発展してきた。2005年には、経済、通貨・金融、農林、環境、国境を越える犯罪、情報通信、文化芸術の分野で担当閣僚会合が開催されるなど、引き続きASEAN+3協力が進展し、日本はこれら協力の発展に貢献した。
また、日本が2005年に行った貢献で特筆すべきは、将来の東アジア共同体形成を視野に入れた地域協力全体の発展に資する取組である。具体的には、東アジア地域協力のデータベースづくりがある。日本は、ASEAN+3をはじめとする地域協力の一層の発展のためには、重層的に積み重ねられてきた地域協力の実態を正確に把握することが不可欠であると考え、東アジア地域協力の包括的なデータベースを作成し、7月のASEAN+3外相会議に提出した。このデータベースは、ASEAN+3協力を72件、それ以外の地域協力を30件列挙するものとなり、東アジア地域協力がASEAN+3を中心に、それ以外の国も広範に巻き込んで多方面に展開していることを地域で初めて明らかにした。現在、ASEAN事務局で日本作成のデータベースを参考に、地域全体で共有できるASEANとしてのデータベース作成準備が進められている。
また、民間部門の動きとしては、8月に東京で「東アジア・シンクタンク・ネットワーク」の第3回総会が開催され、東アジア共同体形成に向けた政策提言をとりまとめた。この政策提言には、開かれた地域主義といった地域協力の健全な発展に資する提言が数多く含まれている。この政策提言は、政府当局者間の協議でも議論の参考としてとりあげられた。
12月12日にクアラルンプールで開催された第9回ASEAN+3首脳会議では、ASEAN+3協力の現状や今後の協力の在り方について議論が行われた。小泉総理大臣からは、鳥インフルエンザやテロ等の地域の脅威に対処する能力向上の必要性を主張するとともに、アジアの鳥インフルエンザ対策支援として1.35億ドルの支援策を表明した。また、経済連携や通貨金融協力等を通じた地域の一層の繁栄確保及び共通意識の形成促進、ASEAN統合支援の重要性等について発言した。
▼ASEAN+3協力の進展
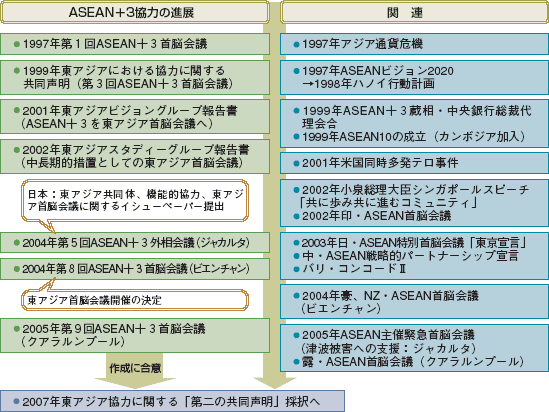
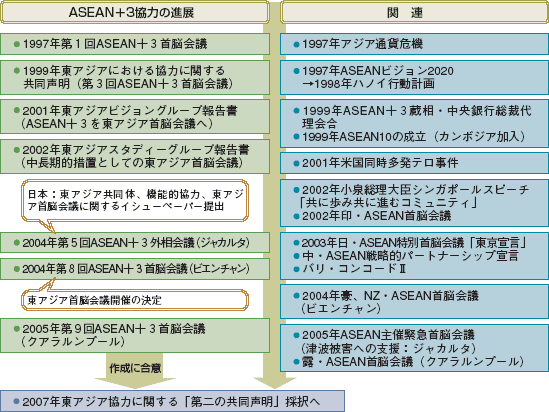
首脳会議後に出された「クアラルンプール宣言」では、ASEAN+3協力が引き続き東アジア共同体形成の「主要な手段」であることを確認するとともに、2007年に、東アジア協力に関する第二共同声明等を作成するための努力を開始することなどが確認された。特に、この「第二共同声明」作成合意は、豊富な実績を有するASEAN+3協力の勢いを維持・強化し、将来の東アジア共同体形成を視野に入れた地域協力を推進する上で新たな前進と言える。また、地域全体の喫緊の課題である鳥インフルエンザ対策について、日本が大規模な包括的支援策を打ち出したことにより、日本の存在感を改めて示すこととなった。