(ロ)中国情勢
(i)内政
(a)胡錦濤政権の基本路線
3月の全国人民代表大会 (注35) の第10期第3回会議 (注36) で、胡錦濤指導部は「科学的発展観」 (注37) に基づいた「調和のとれた社会」の建設を目指すとともに、農業・農村振興、雇用確保、格差是正、行政能力の向上等に取り組むなど、民衆の利益を重視する「親民路線」の姿勢を改めて明確にした。これを受けて、10月の中国共産党中央委員会 (注38) 第16期第5回全体会議(五中全会)では、2006年から2010年までの新たな5か年計画(第11次五か年規画)の基本方針が策定され、エネルギー効率や環境への影響、生活の豊かさに配慮した質的成長と、人民の利益を重視した清廉な政治が強調された。7月中旬から9月上旬にかけて、「世界反ファシズム戦争及び抗日戦争勝利60周年」の記念行事が全国各地で開催され、9月3日には北京で現・旧中央指導部の出席の下、6,000人規模の記念大会が開催された。また、10月には、中国としては2度目となる国産ロケット「神舟6号」による有人宇宙飛行が成功し、盛大な式典が催された。
(b)様々な社会問題への対応
中国国内では、急速に進む経済発展の陰で、様々な社会問題が指摘されている。2月の遼寧省における炭鉱事故 (注39) や12月の吉林省での化学工場事故に起因する松花江の水質汚染等、人命や環境に甚大な被害をもたらす大規模事故が多発した。これに対し、中国政府は、炭鉱・工場の閉鎖や中央及び地方政府を含めた責任者の処分を行ったほか、2006年1月には突発的な大規模事故・事件の緊急対策マニュアルを制定し、情報の公開、通報に関する義務規定を設けるなど、対策に力を入れている。一方で、9月にインターネット報道に関する管理規定が公布され、大型事故を報じた国内メディア関係者が処分されるなど、中国当局のメディアに対する管理強化の動きも見られる。
また、近年、土地収用に伴う補償問題、労働者の待遇問題、環境汚染等に起因する地方当局等に対する民衆抗議行動が頻発している。これに対しても中国政府は、陳情条例の改正、公務員管理規定の整備等の対策を急いでいる。
こうした状況の中で共産党指導部は、1月から1年半にわたり、全共産党員の資質向上と民衆へのサービス向上を目指した教育キャンペーンを展開している。さらに10月には、中国政府が民主政治に関する初めての白書を発表し、共産党の指導の下、中国の国情にあった民主政治を建設することを強調した。
(c)国防・安全保障
中国の2006年度の国防費は約2,807億元、前年度比14.7%の伸びと、2006年3月の全人代で発表された。公表された国防費では、18年連続で10%以上の伸びとなったが、中国側はその要因について、人件費や装備費等の増額であると説明している。日本は、中国のこうした国防費の増額や軍事力の近代化において、なお不透明な部分があることに引き続き注目しており、今後とも、より一層の透明性の向上を求めていく考えである。
(ii)経済
2005年の中国のGDP(名目額)は18兆2,321億元となり、GDPの実質成長率は9.9%を記録した(2006年3月の全人代で提起された目標は8%前後)。貿易総額は前年比23.2%増の1兆4,221.2億ドルで、貿易黒字は1,018.8億ドルとなった。胡錦濤指導部は、2020年までにGDPを2000年時の4倍増とする方針 (注40) を掲げる一方で、経済成長のみを追求せず、社会全体の持続的な均衡発展を目指す「科学的発展観」を提唱し、経済格差の是正、三農問題 (注41) 、社会保障問題、エネルギー・環境問題等に取り組んでいる。
10月の第16期五中全会では、胡錦濤指導部として初めて策定する5か年計画の基本方針が決まり、「調和のとれた社会」、「科学的発展観」を強く打ち出すとともに、新たな数値目標として、(1)2010年に2000年比で一人当たりGDPを倍増させる、(2)GDP単位当たりのエネルギー消費量を第10次五か年規画末(2005年)比で約20%減少させる-の2点が示された。
また、人民元切り上げとして、7月21日、人民元の対米ドルレートを1ドル=8.276元から8.11元に切り上げ、同時に事実上のドルペッグ(連動)から、通貨バスケット (注42) を参考に調節を行う「管理変動相場制」へと移行した。▼中国の経済成長
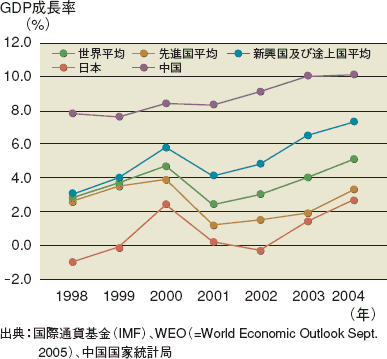
(iii)対外関係
(a)総論
中国は、最優先課題である経済発展のためにも、安定した国際環境を必要としており、米国、ロシア、欧州諸国等の主要国との関係発展、近隣諸国との関係強化等の全方位外交を展開している。また、上海協力機構、ASEAN+3、APEC等の地域協力の枠組みへの積極的な取組も見られる。北朝鮮の核開発問題においても、朝鮮半島の非核化及び対話による平和的解決を望むとの立場から、7月、9月、11月に六者会合を開催、10月に胡錦濤国家主席が訪朝するなど、問題解決のために積極的な役割を果たしてきている。そのほか、急速な国内経済の発展を支えるエネルギーの確保を主な目的として、要人往来の機会等を通じ、中東、アフリカ、中南米諸国等との関係も強化しつつある。
(b)米中関係
米中両国は、様々な対話の機会を通じて、互いの「建設的協力関係」を確認するとともに、北朝鮮問題、台湾問題、通商貿易問題、通貨問題等の幅広い問題に関する意見交換を行っている。要人往来も盛んで、首脳・閣僚では、3月と7月にライス国務長官が、10月にラムズフェルド国防長官が、それぞれ訪中した。また、9月にはニューヨークで、11月にはブッシュ大統領が訪中した際に、それぞれ首脳会談が行われた。事務レベルでも、8月と12月に行われたゼーリック国務副長官と戴秉国外交部筆頭副部長による「米中シニア対話」を中心に、個別の分野での協議が行われている。
(c)ロシア、インド、EUとの関係
ロシアとの関係では、7月に胡錦濤国家主席が同国を訪問した際に「中露共同コミュニケ」が発表され、2004年10月のプーチン大統領訪中以来の両国関係の発展成果が総括された。また、同月、カザフスタンで上海協力機構(SCO)首脳会議が開催された。8月には、両国が前年に取り交わした覚書に基づき、初の共同軍事演習である「平和の使命2005」を、ウラジオストク及び山東半島とその周辺海域で実施した。
インドとの関係では、4月に温家宝総理が同国を訪問し、「中印戦略協力パートナーシップ」構築に関する共同声明のほか、国境問題、経済、航空、文化交流等の分野での協力に関する12の共同文書に合意、12月には両国海軍による合同軍事演習が行われるなど、関係を強化しつつある。
EUとの関係では、9月にブレア英国首相が訪中し、中国・EU首脳会談等を実施した。また、中国側からも、11月に胡錦濤国家主席が英国、ドイツ等を訪問、翌12月にも温家宝総理がフランス等を訪問し、引き続き積極的な首脳外交の展開が見られた。
(iv)香港
香港では、3月、董建華行政長官が2年の任期を残して辞任、同日、曾蔭権(ドナルド・ツァン)政務長官が行政長官代理に就任した。その後、6月の行政長官補欠選挙で曾蔭権行政長官代理が無投票で当選し、同月、国務院から新行政長官に任命された(任期は2007年6月30日まで)。
香港政府は10月、2007年の行政長官選挙と2008年の立法会議員選挙に向けた香港基本法附属文書の改正に関する政府案を発表、12月21日、「政治体制改革政府案」として立法会に提出し、漸進的な民主化に理解を求めたが、あくまで普通選挙の早期実現を目指す民主派議員の反対により、可決に必要な3分の2以上の賛成を得ることができず同政府案は否決された。
経済面ではアジア経済危機、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)発生により大きな打撃を受けたものの、外部経済の好況、中国本土から香港への個人旅行業解禁による旅行業の回復、「経済連携緊密化取決め」等の中国政府による香港経済てこ入れ策等により大きく好転し、2004年の実質GDP成長率は8.2%を達成、2005年の成長率は7.3%と引き続き高い成長率を維持している。2003年に7.9%を記録した失業率は5.5%(2005年7月~9月期)に低下、消費者物価指数(CPI)も2004年7月から前年同月比増(2005年9月は+1.6%)となり、1998年末以降6年続いたデフレからの脱却の兆しを見せている。
日本との関係では、「日港交流年2005」が実施され、日本と香港で各種イベントが開催された。