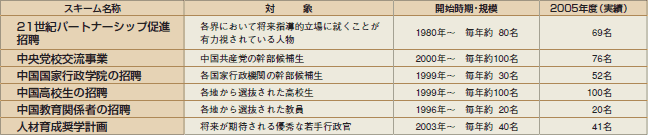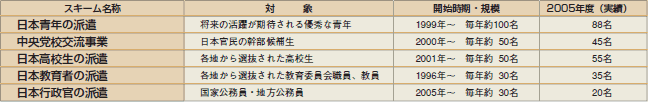(イ)日中関係
(i)あらゆるレベルでの対話
日中間では、前年までと同様、2005年にもあらゆるレベルでの対話が行われ、日中関係や地域及び国際社会の抱える課題について率直な意見交換が行われた。
4月のインドネシア・ジャカルタでのアジア・アフリカ首脳会議の際には、小泉総理大臣と胡錦濤国家主席が会談し、両国の友好的な発展と協力関係の強化が、二国間のみならず、地域・国際社会全体にとっても極めて重要であるとの認識を改めて共有し、両国間の共通利益の拡大と諸懸案の解決に向けて、「日中共同作業計画」 (注27) の検討作業を更に進めるなど、未来志向で幅広い分野における協力関係を推進していくことで意見が一致した。外相間でも、4月の町村信孝外務大臣訪中の際や5月の京都でのASEM外相会合の際に会談が行われ、両国のみならずアジアや世界が日中友好関係を望んでいるという共通の認識が得られた。また、4月に路甬祥全国人民代表大会(全人代)常務委員会筆頭副委員長が訪日し、河野衆議院議長等と会談したのに引き続き、11月には角田参議院副議長が全人代の招請を受けて公式に訪中し、新たな議会交流枠組みの創設で合意するなど、議会レベルの交流も活発に行われた。

▲ASEM外相会合に際し、会談に臨む町村外務大臣と李肇星(り・ちょうせい)中国外交部長(5月7日、京都)
事務レベルでは、2005年5月、6月、10月と2006年2月に日中総合政策対話(外務事務次官と中国外交部筆頭副部長)、7月に日中治安当局間協議(局長級)、5月と9月末に東シナ海等に関する日中協議(局長級)、12月に日中経済パートナーシップ協議(外務審議官級)、2006年1月に日中非公式協議(局長級)が実施されるなど、様々な枠組みで政府間の緊密な対話が行われた(図表「2005年の主な日中政府間対話」参照)。これらのほかにも、関係省庁等による実務協議が、幅広い分野で累次行われている。
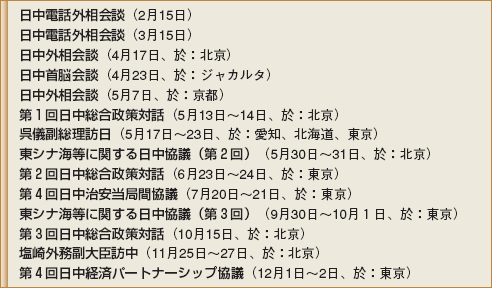
さらに、両国の外交当局が事務局を務める民間有識者の会議として、「新日中友好21世紀委員会」 (注28) の第3回会合が7月に中国・雲南省昆明で開催され、(1)日中国交正常化35周年(2007年)に向けての日中文化・スポーツ交流年の設定、(2)日中共通の社会問題(高齢化、福祉、環境、エネルギー)に関するシンポジウムの開催、(3)青少年交流の促進、(4)日中交流基金構想の早期実現に向けての努力-に関する提言が出された。
これらの対話の場で、中国側からは、小泉総理大臣の靖国神社参拝を含めた歴史認識を巡る問題の解決が重要であるとの提起が累次なされているが、政府としては、個別の分野での意見の相違が日中関係全体の発展の支障になってはならないとの立場であり、引き続き、以上のような重層的な対話の枠組みを通じて、相互理解と信頼の増進に努めていく考えである。
(ii)活発な人的交流
(a)人的交流促進のための環境整備
2005年、日中間の人的交流は前年より更に拡大し、約417万人に達した(訪日者数約78万人、訪中者数約339万人)。こうした国民間の直接の交流を通じて、相互理解と相互信頼を増進することは、未来志向の日中関係を構築していく上で極めて重要である。政府としては、このような観点から、様々な施策を組み合わせつつ、日中間の人的交流の拡大・深化を促進するための環境整備に努めている。その一環として、「愛・地球博」期間中の7月に、中国国民訪日団体観光旅行の査証を発給する対象地域を、従来の北京市、上海市、広東省、遼寧省等の一部の地域から中国全土に拡大した。また、日中間の交流の緊密化に伴い、1月、日本の重慶出張駐在官事務所を総領事館に格上げするとともに、10月に東京、大阪、札幌、福岡、長崎に次ぐ中国の在日公館として、在名古屋領事館の開設を認めた。
人的交流の深化に伴い重要性を増している領事・治安分野でも、6月に日中領事協定締結に向けた交渉を行うとともに、7月には第4回日中治安当局間協議を実施し、捜査共助・銃器・薬物・不法出入国・訪日団体観光等の問題について意見交換するなど、協力を促進している。
(b)人的交流に対する積極的な支援
日中間で相互理解と信頼を増進させるためには、両国の幅広い層の国民に互いに関する「直接体験」の機会をより多く提供し、国民レベルで相互の「等身大」の姿に対する理解を深めていくことが重要である。このため、政府は人的交流、特に青年交流を通じて、日中関係の将来を担う人材の相互理解を深めるよう、様々な枠組み(図表「外務省による招聘事業・派遣事業」参照)による積極的な支援を行ってきており、引き続きこうした枠組みを活用しつつ、人的交流を促進していく考えである。
(c)対日理解促進のための取組
さらに、日中間では、4月に中国各地で発生したデモ活動に伴う暴力的行為のように、中国国内における対日感情の問題がクローズアップされるようになってきており、この背景には、中国における、日本の政策や文化に対する理解が不足していることがあると考えられる。これに対し、政府としては、前述のような人的往来の促進とあわせ、中国国民に対して日本に関する正確な情報を発信し、現在の日本に対する理解を深めるべく、諸施策(図表「対日理解促進のための施策一覧」参照)を推進しているところである。
|
(iii)経済関係の深化(対中経済協力を含む)
(a)日中経済関係の発展
日本と中国の経済関係は拡大を続けている。2005年には貿易総額が1,894億ドル(前年比12.7%増)に上り、中国(香港を含む)は昨年に引き続き、日本にとって最大の貿易相手国となった (注29) 。なお、2005年のデータでは中国から日本への輸入が堅調な伸び(15.7%増)を示す一方、日本から中国への輸出は8.9%と減速しているが、この背景には、中国に生産拠点を移した日本企業からの製品の輸入が増加した一方で、輸出減の要因として部品等の現地調達率の上昇、中国政府による過熱投資抑制策等があると考えられる。
日本の対中投資(届出額)は、2004年度で45.6億ドル(前年度比45.3%増)と増加しており、対外投資総額に占める割合も12.8%(前年度は8.7%)と大きく拡大している。2001年12月の中国のWTO加盟を経て、多くの日本企業が中国を加工輸出基地としてのみならず、有望な市場と位置付けて進出を加速させており、日中経済の相互補完関係は一層の深化を遂げている。
このように、緊密化の度合いを増す日中経済関係の中では、発生し得る経済摩擦を未然に防ぐことが重要である。日本としては、日中経済パートナーシップ協議(外務審議官級) (注30) 等の二国間協議の場で、知的財産権問題をはじめとする貿易、投資に係る様々な問題を協議するとともに、WTO・対中TRM (注31) でも、中国によるWTO加盟約束の履行状況等について問題提起を行っている。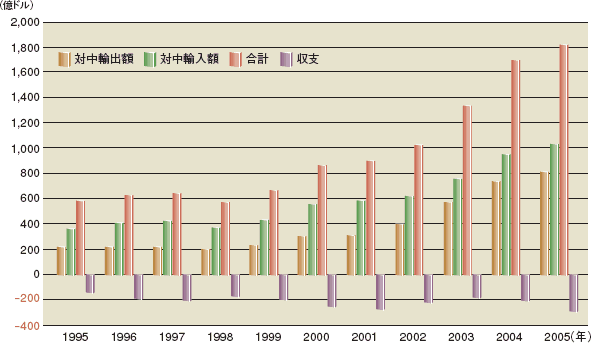
(b)対中国経済協力
近年、中国は沿海部を中心に著しい経済発展を遂げており、それに伴い、日本の対中政府開発援助(ODA)も大幅な減少傾向にある。その一方で、日本にも直接影響を及ぼし得る問題である中国の環境汚染や感染症等、両国民が直面する共通課題も数多く存在している。日本のODAは、そうした問題の解決や人的交流の促進を通じた両国国民の相互理解の増進といった分野を中心に供与されており、2004年度の実績は、円借款858.75億円、無償資金協力41.10億円(以上、交換公文の額)、技術協力59.23億円(国際協力機構(JICA)によるもの)であった。
なお、対中ODAの大部分を占める円借款については、4月の日中外相会談で、2008年の北京オリンピック前までに新規供与を終了するという共通認識に達しており、事務レベルでその細部について更なる協議を行っている。他方、円借款以外の技術協力等については、日本の国益を踏まえつつ、個々の案件を精査しながら、日中関係全体の中で検討していく考えである。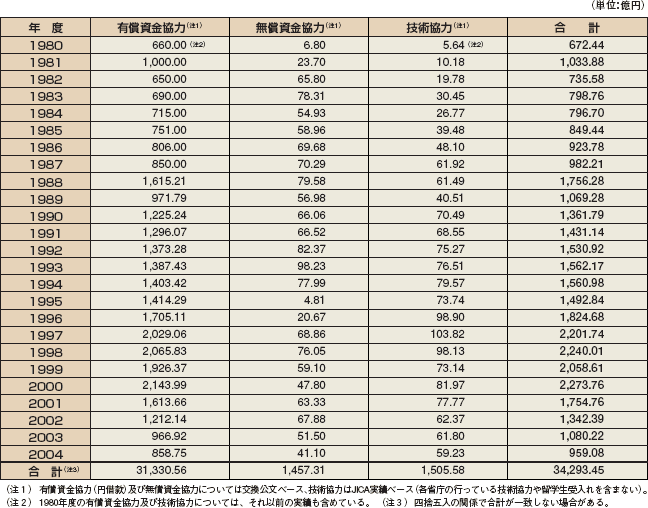
(iv)個別の分野における懸案
(a)中国各地における日本公館及び日系企業等に対する暴力的行為
4月の週末(2日・3日、9日・10日、16日・17日)に連続した中国各地での抗議デモ活動で、在中国日本公館や日系企業等が投石等の暴力的行為を受け、ガラス損壊等の被害が生じた。日本は10日、町村外務大臣が王毅在京中国大使に抗議した上で、陳謝、損害の賠償、再発防止、加害者の処罰を申し入れ、さらにその後も累次にわたり申入れを行い、同月と5月の日中外相会談では改めて強く申し入れた。
これに対し、中国側は、国内法、国際法を尊重して、責任ある対応をしていきたいと表明、大使館、大使公邸等に生じた損害の原状回復について誠意をもって対応するとの意向が伝えられた。これを受け、公館の修復作業については既に開始され、順次終了しているものもある。
(b)東シナ海における資源開発問題
前年から懸案となっている東シナ海の資源開発問題については、5月と9月末から10月にかけて、東シナ海等に関する日中協議が行われた。東シナ海を「対立の海」ではなく、「協力の海」にするという認識は、首脳・外相間で共有されており、政府としては、共同開発の可能性も視野に入れつつ、中国側との対話を通じた解決を引き続き目指していく考えである。
9月から10月にかけての第3回協議では、日本側から、開発作業の中止及び関連情報の提供を申し入れ、試掘に関する国内の厳しい客観的情勢を説明した。また、漁業関係者の安全操業、海洋環境の保全の観点から関連情報の提供を求めたほか、中国海軍の活動についても申し入れた。さらに、前回協議で中国側から共同開発の提案があったのを受け、日本側から、共同開発を含んだ解決策を提案し、これに対し、中国側から、真剣に検討し、次回協議で中国側の考え方を示したいとの応答があった。また、2006年1月には北京において非公式の局長級協議が開催され、中国側から、次回の正式協議で共同開発の実現に向けた更なる提案を行うべく検討している旨の発言があったほか、次回協議をできるだけ早く開催すべきであるとの認識を共有した。
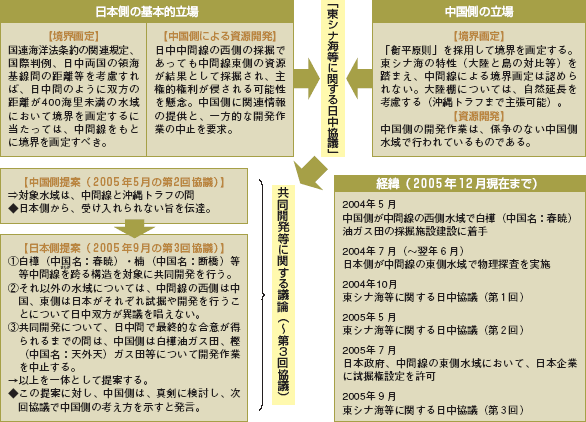
(c)中国遺棄化学兵器問題
中国における旧日本軍の遺棄化学兵器問題 (注32) に関しては、1997年に発効した化学兵器禁止条約に基づき、日本は同兵器廃棄のために、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供し、中国はこれに対する適切な協力を行うことになった。日中両国は、1999年に署名された「中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」 (注33) の枠組みの下、同兵器廃棄のため、現地調査や発掘・回収作業を共同で実施するとともに、専門的、技術的な諸事項について、両国の政府関係者や専門家が協議を重ねてきている。2004年に廃棄施設の立地場所及びすべての処理技術(燃焼法)が確定され、現在、吉林省ハルバ嶺地区に発掘・回収施設と廃棄施設を建設するため、技術面、体制整備面の両方から準備作業が進められている (注34) 。
黒龍江省チチハル市、吉林省敦化市等では遺棄化学兵器による毒ガス事故が発生しており、今後このような被害が生じないようにするためにも、化学兵器禁止条約に基づき、遺棄化学兵器をできるだけ早く処理するため、日中共同で適切に対処していく考えである。