【気候変動問題】
日本は、従来から気候変動問題に重点的に取り組んでいる。2004年11月、日本の度重なる働きかけもあり、ロシアが京都議定書(225ページ参照)を締結したことで、同議定書は、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3:京都会議)における採択から7年余りを経て2005年2月16日に発効することとなり、地球温暖化防止の第一歩が踏み出された。
2004年12月6日から18日までアルゼンチンのブエノスアイレスにおいて開催された気候変動枠組条約第10回締約国会議(COP10)は、京都議定書が付属する本体条約である気候変動枠組条約の発効10周年に当たるとともに、同議定書の発効を目前に控えた重要な会議となった。京都議定書の約束期間以降(2013年~)を視野に入れた将来の枠組みに関する検討が2005年末までに始まることを踏まえ、COP10では、すべての国の参加の下に、中・長期的な将来の行動に向けた情報交換を通じた取組を開始することが決定された。また、洪水、干ばつなど気候変動の悪影響への適応策として、途上国に対する資金支援や人材育成支援に加え、「5カ年行動計画」(注4)の策定が決議された。日本は、途上国への支援について、ODAを中心とした温暖化対策支援である「京都イニシアティブ」(注5)の着実な実施ぶりなどを紹介しつつ、引き続き支援していく旨表明し、参加各国より高い評価を得た。その一方で、京都議定書が発効しても、地球温暖化対策の実効性を一層確保していくため(注6)、今後すべての国が参加する共通のルール構築が必要であり、その考えから日本はCOP10において、将来の枠組みに関する議論を開始すべきであることについても積極的に関係国に働きかけた。日本は、地球規模で温室効果ガス排出を削減するためには米国や開発途上国に対する働きかけが重要であるとの立場から、日米政府間ハイレベル・事務レベル協議等を通じて、京都議定書への米国の参加及び一層の温室効果ガス排出削減の努力を求めている。また、2003年に引き続き2004年9月に東京で「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合(注7)をブラジルとの共同議長の下で主要先進国及び途上国を招いて開催し、今後の排出削減に向けた具体的な行動について率直な意見交換を行い、各国より高い評価を得ている。

▲気候変動枠組条約第10回締約国会議出席後、インタビューを受ける小野寺五典外務大臣政務官(12月)
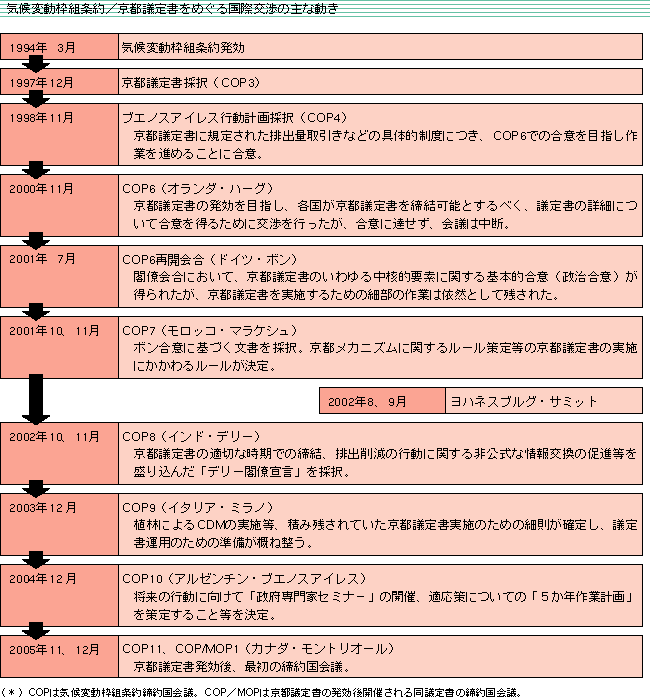
Excelファイルはこちら
京都議定書Q&A テキスト形式のファイルはこちら |