【エネルギー安全保障】
2004年においては、中国等をはじめとする経済成長に伴う需要の増加などを受け、多くの資源の価格に急激な上昇が見られた。例えば、原油価格は、10月末には1バレルあたり約55ドルの史上最高値を記録し、その後下落したものの引き続き高水準にある(2005年1月時点で同約45ドル)。高水準の原油価格の継続は世界経済に与えるリスク要因となり得るものであるが、日本は、エネルギー市場の透明性の向上、原油の安定的かつ適切な供給の確保、エネルギー効率の改善・省エネといった分野における国際協力の強化を積極的に推進した。
具体的には、エネルギー安全保障の分野で主導的役割を果たしている国際エネルギー機関(IEA)を通じ、他の先進国と協調して国際的な取組を強化している。特にアジア地域においては、急激にエネルギー需要が増大する中、地域のエネルギー安全保障の強化が緊急の課題となっているとの認識から、6月に青島で開催された第3回アジア協力対話(ACD)外相会合におけるエネルギー安全保障に関する政治文書の作成、11月のAPEC首脳・閣僚会議における「APECエネルギー安全保障に関する包括的イニシアティブ(ケアンズ・イニシアティブ)(注22)」の承認や同11月の日中韓首脳会談で採択された「三国間協力に関する行動戦略(注23)」におけるエネルギー安全保障に関する関係国の協調行動の策定など、日本は域内協力の推進に貢献した。
さらに、5月にオランダで開催された、生産国と消費国の対話の場である国際エネルギー・フォーラム(IEF)において、日本は、産油国に対し石油の安定的かつ適切な供給の継続やそのために必要な投資の促進や環境の整備を働きかけた。
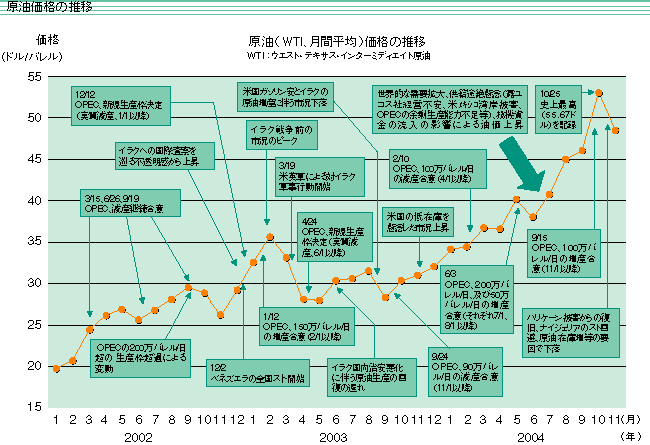
ドキュメントファイルはこちら