【国際社会の取組の進展】
2004年を通じ、国際社会は、多国間レベル、地域レベル、二国間レベルでの協力を深め、国際テロ対策を強化してきた。
多国間レベルに関しては、6月8日~10日に米国のシーアイランドで開催されたG8首脳会議において、「G8安全かつ容易な海外渡航イニシアティブ(G-8
Secure and Facilitated International Travel Initiative:SAFTI)」(注14)が採択され、交通保安分野等におけるテロ対策の強化が合意された。同イニシアティブには、「国際標準の構築を通じた文書の相互互換性」、「国際的な情報交換」、「携帯式地対空ミサイル(MANPADS)による脅威の削減」、「キャパシティ・ビルディング及びその協力」への取組が盛り込まれ、2005年末までに28のプロジェクトを完了させることが目標とされている。
国連においては、これまでも安保理決議1373(2001年9月28日採択)及び同決議に基づき設立されたテロ対策委員会(CTC:Counter-Terrorism
Committee)等によってテロ対策が進められてきたが、新たに安保理決議1535(2004年3月26日採択)、1566(同年10月8日採択)等によって、テロ対策が強化された(注15)。テロ資金対策の分野では、金融活動作業部会(FATF)(注16)が資金洗浄(マネー・ロンダリング)対策の知見と経験を基に一定の役割を果たしており、これまでに新「40の勧告」及び「テロ資金供与に関する8の特別勧告」を策定し、各国の同勧告実施を審査、促進している。さらに、2004年10月には、テロ資金の流通に関与していると考えられている「現金運び屋(キャッシュクーリエ)」に関する新たな特別勧告を採択した。また、FATFは国際通貨基金(IMF)や世界銀行、テロ対策行動グループ(CTAG)(注17)と協力しつつ、テロ資金対策についての技術支援等を含む国際的な対策と協力を進めている。
地域レベルでは、アジア太平洋経済協力(APEC)において、2003年に設置されたテロ対策タスクフォース(CTTF)(注18)でAPEC域内でのテロ対策強化に関する議論が継続され、その成果として2004年11月のAPEC首脳宣言(サンティアゴ宣言)に、テロ資金対策の推進や大量破壊兵器等の不拡散等、テロ対策強化に関する取組が盛り込まれた。アジア欧州会合(ASEM)においては、2002年9月の首脳による「国際テロリズムに関する協力のためのASEMコペンハーゲン宣言」に基づく第2回テロ対策セミナーが2004年10月にドイツにおいて開催された。ASEAN地域フォーラム(ARF)では、2004年7月の第11回ARF閣僚会合において「国際テロに対する輸送の安全強化に関するARF声明」が採択された。また、2004年2月にはインドネシア・バリ島においてテロ対策閣僚会議が開催され、アジア太平洋地域におけるテロ防止関連12条約の締結促進に関する協力を含む、法執行機関間の協力、法的枠組みの強化が合意された。
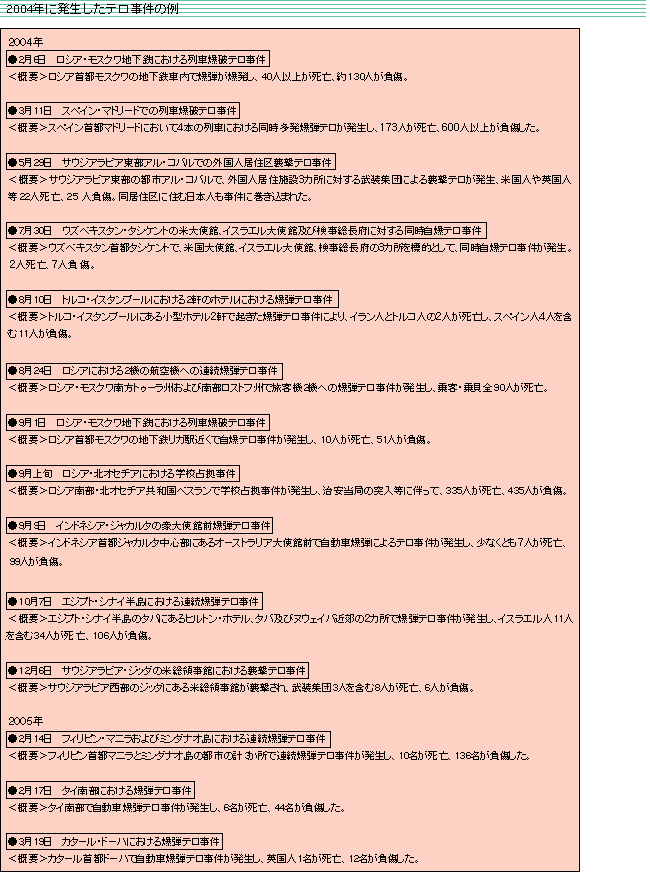
Excelファイルはこちら
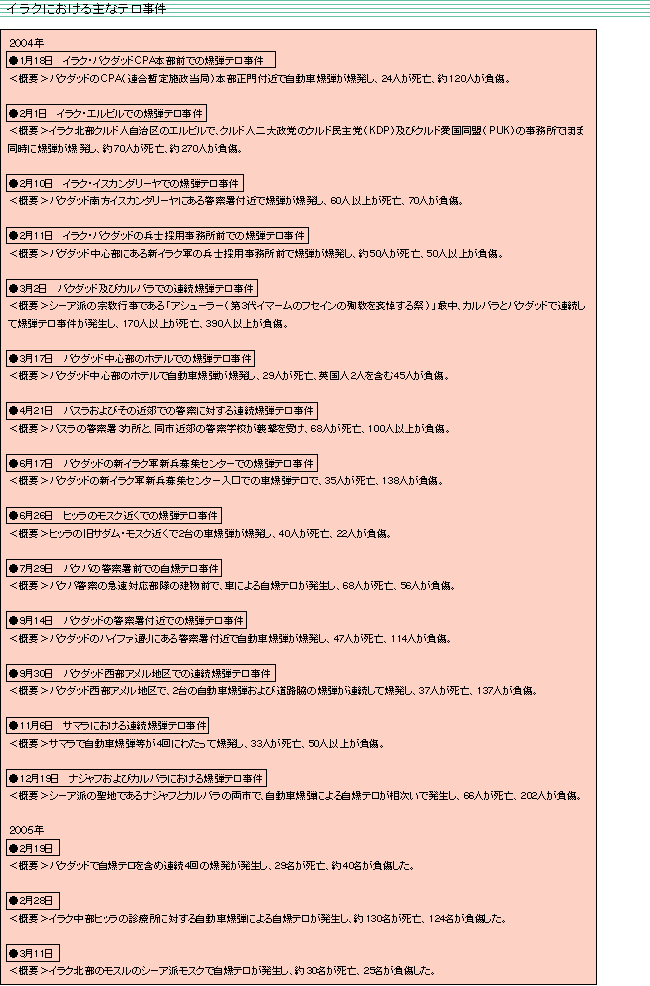
Excelファイルはこちら