【日本の取組】
<テロ対策特別措置法>
テロ対策特別措置法は、2001年9月11日に米国で発生した同時多発テロが国連安保理決議1368において国際の平和と安全に対する脅威と認められたことなどを踏まえ、日本が国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与することを目的として制定された法律である。
米国、英国、フランスをはじめとする諸外国は、インド洋上におけるテロリストの移動や武器弾薬等の関連物資の海上移動を阻止または抑止することを目的として、「不朽の自由作戦」に基づく海上阻止活動(OEF-MIO:Operation
Enduring Freedom-Maritime Interdiction Operation)を実施してきている。日本は、テロ対策特別措置法に基づく協力支援活動として、2001年12月から、海上阻止活動に従事する米英等の艦船に対し、海上自衛隊による給油支援などを実施している。
米国同時多発テロ以降、国際社会は国際テロリズムを根絶するため、軍事作戦のみならず、テロ資金対策など、広範な分野における取組を実施している。しかしながら、ウサマ・ビン・ラーディンやオマルといったタリバーン、アル・カーイダの幹部などは依然として逃亡中である上、アル・カーイダの関与の疑いのあるテロも続いている。また、米国同時多発テロによってもたらされている脅威の除去のための諸外国の活動は依然継続している。こうした状況を踏まえ、日本は、2003年11月にはテロ対策特別措置法を2年間延長し、さらに、2004年4月及び同年10月には、テロ対策特別措置法の基本計画をそれぞれ半年間延長した。特に同10月の延長時においては、海上阻止活動の効率性を促進するとの観点から、従来の艦船用燃料に加え、艦艇搭載ヘリコプター用燃料及び水の補給も行い得るように協力支援活動の内容を変更した。2004年10月現在、米国をはじめとする8か国、計16隻の艦船が海上阻止活動に従事しており、日本から燃料などの補給を受けている。
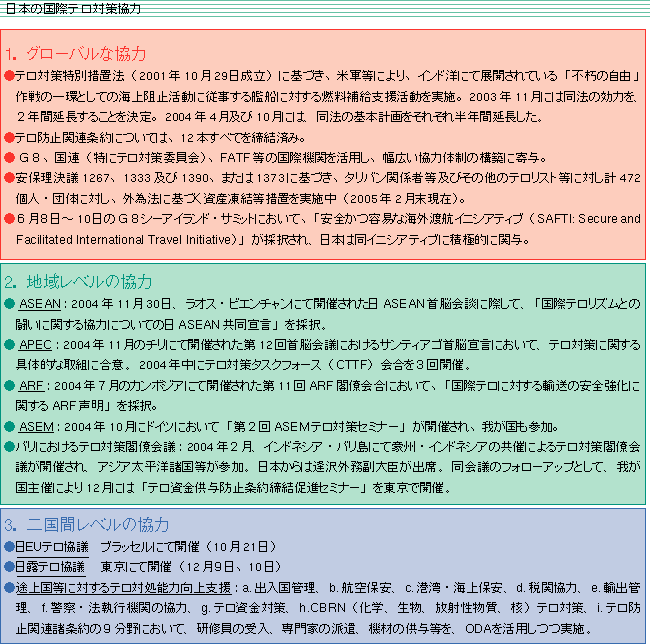
Excelファイルはこちら
<その他の分野における取組>
日本は、国際テロを防止するためには幅広い分野において国際社会が一致団結し、息の長い取組を継続することが重要との考えの下、政治的意思の形成、各分野における対策の強化、途上国に対する支援等いずれの面においても、国際社会におけるテロ対策の努力に積極的に参加してきている。
具体的には、2004年11月から国際刑事警察機構(ICPO)に紛失・盗難旅券情報の提供を開始したほか、IC旅券の早期導入に取り組むなど、SAFTIの策定及び実施や、CTAG等G8の取組に積極的に参画している。また、テロリストに対する制裁措置を定める安保理決議を誠実に履行し、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて、ウサマ・ビン・ラーディンやオマルをはじめとするタリバーン、アル・カーイダ関係者及びハマス、パレスチナ・イスラミック・ジハード、アル・アクサー殉教者旅団、ラシュカル・エ・トイバ、センデロ・ルミノソ等合計472のテロリスト個人・団体に対し、それらの資産凍結措置を実施している(2005年2月末現在)。さらに、2004年12月には、日本としては初めて、10月にイラクにおいて日本国民を人質として拘束・殺害したテロ組織に関して、英国及びドイツと共に同テロリスト情報(テロ組織「アル・タウヒード」の別称)の国連制裁リストへの登録を申請し、承認された(注19)
。
地域的な取組に関しては、APECにおいて、2004年11月のAPEC首脳宣言に、日本が提案した機械読取式渡航文書に関する項目が全APECメンバーによって推進されるべき対策として盛り込まれたほか、日本はCTTFにおいて副議長を担当するなど、積極的な活動を行った。バリ島テロ対策閣僚会議には日本政府代表として逢沢外務副大臣が出席し、日本が特に重視しているテロ防止関連条約の早期締結の重要性を訴え、同趣旨が議長声明に盛り込まれた。さらに同会議のフォローアップ・プロセスにおいても、日本は法的枠組みに関する作業部会においてテロ防止関連諸条約の締結および国内実施に関するコーディネーター(調整役)となり、2004年12月には東京において「テロ資金供与防止条約締結促進セミナー」を開催するなど、アジア・太平洋地域でのテロ対策に関する法的枠組みの強化に貢献している。また、11月にラオス・ビエンチャンで開催された日
ASEAN首脳会議の際に、「国際テロリズムとの闘いに関する協力についての日ASEAN共同宣言」(注20)が採択され、テロ対策の分野において日本とASEANとが今後一層の協力を行っていくことで合意した。
日本は、テロ防止関連諸条約の早期締結とともに、途上国に対するキャパシティ・ビルディング支援を重視しており、特に、日本の繁栄と安全にとって重要な東南アジア太平洋地域を重点として、ODAも活用しつつ支援を実施している。具体的には、1)出入国管理、2)航空保安、3)港湾・海上保安、4)税関協力、5)輸出管理、6)法執行協力、7)テロ資金対策、8)CBRN(化学、生物、放射性物質、核)テロ対策、9)テロ防止関連諸条約、の9分野において、セミナーの開催、研修員の受入れを積極的に実施し、2004年度に総計約310人の研修員を受け入れている。2004年7月には、マレーシア・クアラルンプールの東南アジア地域テロ対策センター(SEARCCT)において「化学テロの事前対処及び危機管理セミナー」を、東南アジア諸国を対象に開催した。同セミナーは、2002年10月のAPEC首脳会議の際に、小泉総理大臣がテロ対処面における危機管理能力向上を目的とした取組を2003年度より5年間実施する旨表明したことを踏まえて、2003年に東京で開催されたセミナーに引き続いて開催されたものである。機材供与に関しては、2004年5月に、インドネシアに対して空港、港湾の保安強化に関する7.47億円の無償資金協力を決定した。また、2004年7月には、アジア開発銀行(ADB)内に設置されたAPEC域内での交通保安、港湾保安・テロ資金対策などを強化するための「地域的貿易・金融安定化イニシアティブ(基金)」に対して100万ドルを拠出した。
さらに、二国間レベルでのテロ対策に関する取組に関しては、日本は国際テロ対策担当大使を中心として、各国とテロ情勢やテロ対策協力に関する意見交換を行っており、2004年は、10月にベルギー・ブリュッセルにおいて欧州連合(EU)との初のテロ協議を実施したほか、12月に東京においてロシアと第3回日露テロ協議を開催した。
また、2004年には、日本自身のテロ対処能力向上のため、国内的なテロ対策措置の強化が行われた。具体的には8月24日の閣議決定により、内閣官房長官を本部長とする国際組織犯罪等対策推進本部を、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部会合に改組し、国際テロの未然防止対策の検討が行われ、12月10日、今後速やかに講ずべきテロの未然防止対策16項目及び、今後検討を継続すべき対策3項目を明記した「テロの未然防止に関する行動計画」が決定された(注21)。