【米国情勢】
<内政>
2004年の米国政治情勢は、11月2日に行われた大統領選挙を中心に推移した。共和党は、ブッシュ大統領が再選に向け党内基盤を早々に固め、テロと闘う強い指導者、自由を拡大する信念の人として支持を訴えた。民主党は、ケリー上院議員が予備選に勝利し、民主党が伝統的に強いとされる経済政策よりも、自らが「ベトナムの英雄」であり、安全保障問題に強い候補であることを強調した。
選挙は、前回2000年の大統領選挙を想起させる接戦となったが、ブッシュ大統領がこれを制した要因としては、「戦時の大統領」として再選に臨み、選挙態勢を固めて、分かりやすいメッセージを送り、投票所への有権者動員にも組織的に成功したこと、雇用問題こそ争点化したが総じて経済が回復基調にあったこと、米国が政治的に保守化傾向にあること等が指摘されている。ブッシュ大統領の得票率は51%であったが、大統領当選者の得票率が過半数を超えたのは1988年以来であった。また、過去40年余り低下傾向にあった投票率は、60%に迫る勢いであり、1960年代後半の水準に戻った。なお、同時に行われた連邦議会選挙では、上下両院とも共和党が多数党を維持し、さらに議席を上積みした。
上記選挙において最も大きな論点となったイラク問題については、大量破壊兵器が発見されないこと、特に関連する情報の米国政府内での扱いに関する問題、3月からのファルージャを中心とするイラク情勢の悪化、4月のアブ・グレイブ収容所におけるイラク人捕虜虐待問題等により、米政府のイラク政策に関する米国各種世論調査では支持が不支持を下回るようになった。これを受けて、ブッシュ大統領の支持率も一時期40%半ばまで低下した。これに対しブッシュ大統領は、イラクにおける政権移行などの政治プロセスの進展を重視すること、アフガニスタン・イラクをはじめとする中東における民主化の動きを支援すること、イラクをテロとの闘いの最前線と位置づけるなどの演説を行い、国民の理解を求めた。
2004年7月22日に発表されたテロ攻撃に関する特別調査委員会(いわゆる9・11委員会)の最終報告は、米国の情報機関がアル・カーイダによる攻撃計画を防ぐ機会を逃したと指摘し、情報機関を統括する「国家情報長官」(閣僚級)ポストの新設を含む政府機関の改革を提言した。この提言を踏まえた情報組織改革法案は、一部議員の反対により成立が危ぶまれたが、大統領が強く支持し、第108議会閉会直前に成立した。
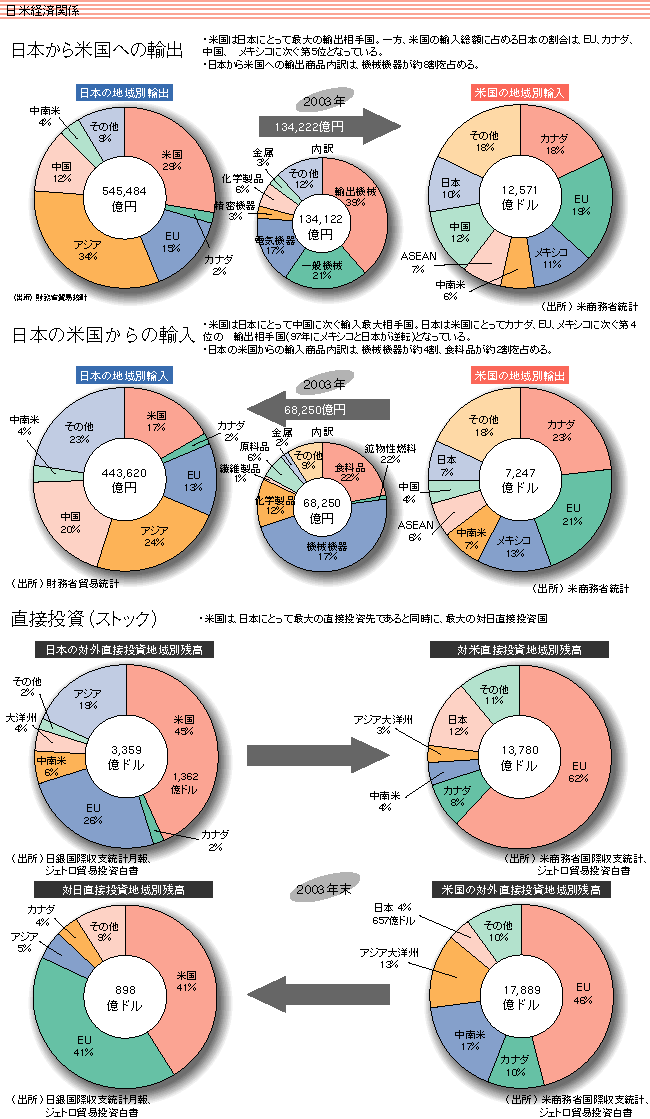
<経済>
米国経済は、ITバブル崩壊に伴う景気後退や米同時多発テロ事件の影響が重なり、一時マイナス成長を記録したが、その後は、雇用環境の改善を背景とした堅調な個人消費、循環的な回復力を強める民間設備投資が持続し、2001年第4四半期以降2004年末まで連続してプラス成長を記録している。現在、景気は拡大基調にあると見られており、今後も3.5%前後の成長が続くとの見方が一般的である。ブッシュ政権は、2001年9月の同時多発テロ発生以降、景気の下支えを目的として、一連の減税を中心とした対策を実施している(注4)。
金融面では、連邦準備制度理事会(FRB)が2004年6月に、堅調な個人消費や設備投資を受け、約4年ぶりとなる引き上げを実施した。以降計6回の利上げを経て、2005年2月末のFFレートは2.50%となっている。グリーンスパンFRB議長は、任期が終了する2006年1月末までに、超低金利政策の修正作業を終了させると見られており、2004年6月末から実施されている金利の引き上げ政策を来年も引き続き継承するとの見方が強い。
今後の米国経済において最大のリスクであるとの危機感が強い懸念材料は、近年増加傾向にある財政と貿易の赤字(いわゆる「双子の赤字」)である。市場においては、この「双子の赤字」の再燃は、金利の急上昇、為替調整圧力(ドル安)の高まり及び消費者の購買意欲の低下などの問題を引き起こす可能性があると指摘されている。ドルの急落及び長期金利の上昇は、民間投資のクラウディング・アウトの発生や株式市場の動揺につながり、ひいては世界経済の波乱要因となりかねないとの懸念がある。また雇用創出対策の強化や社会保障制度の改革もブッシュ政権第二期目の経済焦点となる。
貿易面では、2004年の商品貿易赤字が、6,508億ドル(前年比22.3%増)と過去最大を記録した。対日赤字は752億ドル(同13.9%増)と過去2番目の水準に減少したものの、対中国赤字は1,620億ドル(同30.6%増)と過去最大を更新し、中国が5年連続で国別赤字額の最大相手国となった。
また、財政面では、2004会計年度(2003年10月~2004年9月)の財政赤字額が4,126億ドル(約45.2兆円)を記録し、2年連続で過去最大を更新した。イラク関連支出の増加に加え、大型減税の実施が重なったことが赤字拡大の主な要因となっている。ブッシュ大統領は、2009年までに財政赤字を半分にすると公約しているが、財政収支の改善にとって否定的な要因も存在する。すなわち、1)歳出を抑えるための上限制に国防費が対象外となっていること、2)所得税減税等の恒久化が予定されていること、3)イラクとアフガニスタンの軍事費をまかなう補正予算の編成が確実視されていること、4)企業年金基金の支払いを保証する年金給付保証公社の財政状態が悪化していること、5)中期的にも、メディケア処方薬給付や戦後ベビーブーム世代の高齢化で社会保障費用の急増が予想されていること、などである。2003年6月以降19か月連続で雇用増を記録し、2004年12月までに約262万人の雇用が創出されたことから、雇用情勢は改善基調にあると見られている。
通商政策に関しては、自由貿易協定(FTA)締結に向けての動きが挙げられる。2004年中に米国政府は、オーストラリア、モロッコ、バーレーンとそれぞれ二国間FTAに署名した。今後も、アラブ首長国連邦、オマーン及び韓国とのFTA交渉開始に意欲を示している。今後とも米国のFTA政策が注目されるとともに、これらの動きが日本の経済外交や各地域経済に与える影響も注視していく必要がある。