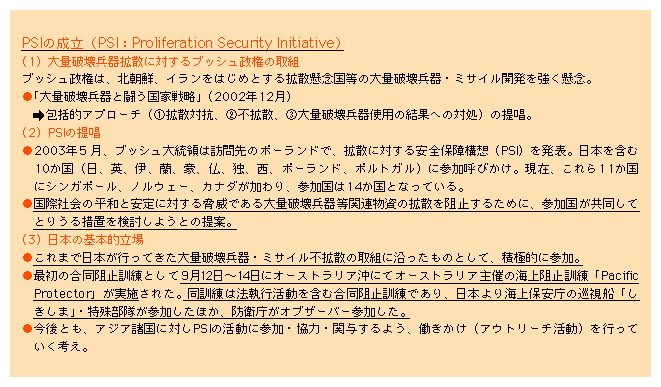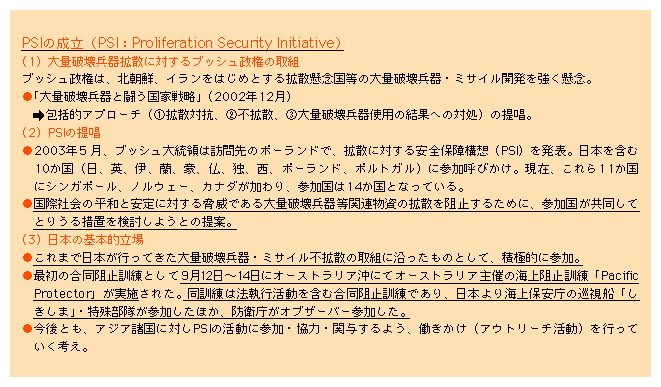【不拡散にかかわる新たな動き・取組】
大量破壊兵器やその運搬手段であるミサイルの拡散は国際社会の平和と安定に対する脅威となっており、不拡散のための取組の重要性が増している。このような取組は、核兵器不拡散条約(NPT)、生物兵器禁止条約(BWC)、化学兵器禁止条約(CWC)等の国際条約に基づく不拡散体制を通じて行われているほか、主要な供給国による輸出管理の協調のための国際的枠組み(原子力供給国グループ(NSG:原子力関係)
(注24)、オーストラリア・グループ(AG:化学・生物兵器関係)
(注25)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR:ミサイル関係)
(注26)、ワッセナー・アレンジメント(WA:通常兵器関係)
(注27)を通じても行われている。また、運搬手段の不拡散については、日本はミサイル問題への取組に力を入れている。近年、ミサイル技術を自ら開発する、またMTCR参加国以外のミサイル保有国からの協力を得る国もあり、先進諸国が技術流出を防ぐだけではミサイル技術の拡散を完全に食い止めることはできなくなってきている。こうしたミサイル拡散に対抗する取組として、2002年11月、オランダのハーグで弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範(HCOC)
(注28)が採択された。日本はその策定過程で具体的提案を行っただけでなく、規範の採択後にロケット打ち上げに際して事前発射通報を行ったほか、ASEAN諸国に対し、HCOCへの参加を働きかけるなど、規範の普遍化と実効性の確立に貢献している。
こうした国際的取組は、極めて重要であるが、関連条約を遵守しない国の存在などもあり、大量破壊兵器等の拡散を完全には防止できていないのが現状である。従来の国際的枠組みを補完し、拡散に対する国際社会の取組をより実効的なものとするため、2003年5月31日、ブッシュ米大統領は拡散を阻止するための新たな取組として「拡散に対する安全保障構想(PSI)」
(注29)を発表した。日本は、PSIの会合・活動に積極的に参加してきており、2003年9月に採択された阻止原則宣言
(注30)の草案作りに、積極的に関わってきたほか、9月12日~14日に開催されたオーストラリア政府主催による初の海上阻止訓練に、海上保安庁から巡視船「しきしま」及び特殊部隊を、また、防衛庁からもオブザーバーを参加させるなど、積極的な姿勢を示してきている。今後は、PSI非参加国の協力をいかに得るか(アウトリーチ)が課題となっており、日本としては、大量破壊兵器等関連物資の輸送段階での阻止のみならず、輸出入管理、国内管理等も含め、拡散のすべての過程において取組を強化する必要があるとの基本的立場の下、アジア地域の諸国を中心としたアウトリーチ活動を積極的に実施していく考えである。また、国内ではキャッチオール規制強化の一環として、大量破壊兵器の生産・開発に必要な物資・技術の不正流入を防ぐための輸出管理に関する法執行の強化など輸出管理の強化を図ってきたところである。