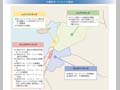第2章 > 第6節 中 東
【総論】
中東地域は長い歴史を有し、異なる民族、宗教が共存している地域である。米国同時多発テロの発生以降、中東地域ではテロや大量破壊兵器等の拡散の脅威が改めて深刻な問題となっている一方で、民族や宗教の違いに根ざした紛争も継続しており、この地域の平和と安定の確保が、日本を含む国際社会全体の平和・安定と繁栄の実現にとって大きな課題となっている。加えて、中東地域は日本がエネルギー資源の8割以上を依存しており、日本のエネルギーの長期安定的な供給の確保にとって死活的に重要な地域である。こうした認識から、日本は、中東地域全体の平和と安定の確保に向けて積極的に関与しており、また、中東地域の国々との関係の強化に取り組んできた。
中東和平をめぐる情勢の悪化は、イスラエルとアラブ・イスラム諸国との間の緊張や、中東諸国の体制の安定性への影響等、中東地域全体の安定を脅かし得る深刻な問題である。日本は、国際社会の責任ある一員として、また、宗教的、歴史的な束縛から自由であるという立場をいかし、中東和平への働きかけを積極的に行っている。
また、中東地域では、特に、イラクによる大量破壊兵器等の保有・開発疑惑が、日本を含む国際社会全体に対する深刻な脅威として高い関心がもたれている。この問題の解決のためには、イラクが査察を完全に受け入れ、大量破壊兵器等の廃棄が実際に実現されることが重要である。日本は、総理大臣特使を派遣するなどして、イラクに対して直接国連安全保障理事会(安保理)決議の履行を働きかけるとともに、関係諸国に対してイラクに対する働きかけを要請するなど積極的な外交を展開してきた。
アフガニスタンの安定と繁栄の確保は、地域の平和・安定と繁栄の実現に不可欠であり、また、テロの根絶・防止、麻薬対策という観点からも極めて重要である。アフガニスタンにおける復興支援は、長年にわたる紛争が終了した国が再び紛争と国家破綻〔はたん〕の悪循環に陥らぬよう支援する「平和の定着」に向けた取組の一つの模範例となり得るものである。日本は、引き続き国際社会の責任ある一員として、アフガニスタンの復興に向けて積極的に貢献を行っていく考えである。
【イラク】
2002年、イラクによる大量破壊兵器等の保有・開発疑惑が、改めて国際社会の大きな注目を集めた。日本は、イラクをめぐる問題への対応にあたって、国連等を通じ、国際社会が一致団結して外交努力を行っていくことが極めて重要であると考えており、米国を始めとする国際社会と緊密に連携をとってきた。イラクが国際社会に協力し、即時・無条件・無制限の査察を受け入れ、大量破壊兵器等の廃棄を始めとする関連安保理決議を履行することによって、国際社会の懸念を払拭〔ふっしょく〕することが重要であり、日本はこのために必要な外交努力を今後とも継続していく考えである。
イラク情勢早見表(2003年3月18日現在)

〈過去の経緯〉
1990年8月のクウェート侵攻以来、イラクは国連の経済制裁の下に置かれてきた。また、1991年4月3日に採択された安保理決議687によって、停戦の条件としてイラクは、化学兵器、生物兵器、核兵器、射程150km以上の弾道ミサイルといった大量破壊兵器等の廃棄を国際的監視の下で無条件に受け入れることなどを義務づけられ、イラクはそれを受諾している。
1997年6月以降、国連イラク特別委員会(UNSCOM)及び国際原子力機関(IAEA)による査察活動に対するイラクの査察拒否及び妨害活動が頻繁になった。1998年12月には、米英軍によってイラクに対して武力行使が行われたが、その後、大量破壊兵器等に対する査察は一切できない状況になった。こうした事態を受け、安保理での議論の結果、1999年12月、新たに国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)を設置し、軍縮分野で一定の進展が見られる場合には、制裁を「一時停止」するという新たな制度を導入した安保理決議1284が採択された。しかし、イラクは、同決議は制裁解除に新たな条件を追加するものであるとして受け入れを拒否してきた。
このように国連による経済制裁が長期化する中、イラク国内では医薬品や食料等の不足から人道状況が悪化した。こうした状況を踏まえ、1996年12月以降、イラクに対する経済制裁の例外として、国連監視下で石油を輸出することを許可し、石油代金によって人道物資を購入する計画(オイル・フォー・フード計画)が、安保理決議に基づき実施されてきた。
〈イラクをめぐる情勢と国際社会の取組〉
2001年9月11日の米国同時多発テロの発生以降、テロ対策と並び、大量破壊兵器等の拡散問題に国際社会の注目が集まった。こうした状況の中、ブッシュ米大統領は、2002年1月の一般教書演説の中で、北朝鮮、イランと共に、イラクを「悪の枢軸」と名指しし、「米国は、世界で最も危険な政権(フセイン・イラク政権)が、世界で最も破壊力のある兵器を用いて米国を脅かすことを許しはしない」と述べ、イラクをめぐる緊張が再び高まった。
事態の打開を目指し、アナン国連事務総長とサブリ・イラク外相は、2002年の3月、5月、7月の3度にわたり対話を実施したが、査察再開の合意には至らなかった。このようにイラクをめぐる緊張が一層高まる中、ブッシュ米大統領は、9月12日の国連での一般討論演説において、これまでのイラクの安保理決議の不履行を指摘した。国際社会の注目を浴びた同演説では、ブッシュ米大統領は安保理を通じた本件問題への対処の必要性を強調したが、一方で、イラクが対応しない場合には、武力行使は不可避であるとの考えも明確に示した。
国際社会による働きかけの結果、9月16日、イラクは無条件での査察の受け入れを表明し、9月30日及び10月1日に、国連及びIAEAとイラクとの間で、査察に関する実務協議が行われた。その後、査察を一層実効性の高いものとするため、国連安保理において約8週間に及ぶ議論が行われた。その結果、11月8日、イラクに対して強化された査察の受け入れを始めとする一連の義務の履行を強く求める安保理決議1441が、シリアを含む全会一致で採択され、11月13日、イラクは安保理決議1441を受諾することを国連に通報した。これを受け、11月18日には、UNMOVIC及びIAEAの先遣隊がバグダッドに到着し、11月27日、イラクでの査察が約4年振りに再開されることになった。なお、今回の査察においては、すべての場所に即時・無条件・無制限の査察が例外なく実施されることになっている。
一方で、2003年1月27日、ブリクスUNMOVIC委員長及びエルバラダイIAEA事務局長は安保理に対し、イラクから手続面での協力は得られているが、疑惑にこたえておらず大量破壊兵器等に関する疑惑が解消されていないと報告し、国際社会において、イラクによる実質的で積極的な協力の必要性が共有されるようになった。ブッシュ米大統領は、翌28日に行った一般教書演説の中で、でイラクが自ら大量破壊兵器の廃棄を行わなければならないと述べた。2月5日に開催された安保理会合では、パウエル米国務長官が安保理メンバー国に対してイラクの査察活動に対する非協力、大量破壊兵器の隠蔽〔いんぺい〕工作等を示す情報を提示し、これ以上イラクに時間を与えるべきではなく、安保理が判断を下すべきであると述べた。その後、2月14日には再度UNMOVIC及びIAEAによる安保理報告が行われ、査察に関してある程度の手続面での進展が見られたとする一方、大量破壊兵器等の廃棄という査察目的を達成するためにはイラクからの即時、無条件かつ積極的な協力が不可欠であると総括した。2月24日の安保理非公式協議では、米国、英国及びスペインにより、イラクが依然として関連安保理決議を履行しておらず、安保理決議1441により与えられた最後の機会をいかすことができなかったことを内容とする決議案が共同で提出された。3月7日には、修正決議案が提出され、安保理では、同修正決議案をめぐり議論が行われてきたが、同修正決議案を支持する米国、英国、スペイン等と査察の継続を求めるフランス、ロシア、ドイツ等との間で歩み寄りが見られず、16日、ポルトガル領アゾレス諸島で開催された米国、英国、スペイン、ポルトガル首脳会談を経て、17日には、パウエル米国務長官は、同修正決議案について安保理での投票を求めないことを決めたと述べた。また、同日、ブッシュ米大統領は演説を行い、フセイン・イラク大統領は48時間以内に同国を立ち去るよう、さもなければ武力紛争の結果を招く旨述べた(3月18日現在)。
シリアのアサド大統領と会談する茂木外務副大臣(11月)

〈日本の取組〉
日本は、イラクとの関係については、従来より、外交関係を維持しつつ、関連安保理決議の履行状況等を踏まえながら、二国間関係を進展させていくとの立場を堅持してきた。2002年には、イラクをめぐる緊張の高まりを受け、9月14日、ニューヨークでの国連総会に際して、川口外務大臣がサブリ・イラク外相と会談を行い、湾岸危機以来初めてイラクとの閣僚級の接触を行った。同会談で、川口外務大臣は、イラクに対して、査察の即時・無条件・無制限の受け入れ、大量破壊兵器等の廃棄を始めとした関連安保理決議の履行を強く求めた。さらに、2003年1月29日には、川口外務大臣が、シャーキル在京イラク臨時代理大臣を招致して、また、3月には茂木外務副大臣を総理大臣特使としてイラクに派遣して、イラクが安保理決議1441によって与えられた最後の機会に即時にこたえるべきであり、平和的解決のため、自ら積極的に疑惑を解消し、大量破壊兵器等の廃棄を始めとするすべての関連安保理決議を履行することを改めて強く求め、最後の翻意を促すなど、日本は、イラクに対して直接働きかけを行ってきた。
日本は、イラクをめぐる問題に対応するにあたって、安保理常任理事国を始めとする主要国やイラクの周辺諸国等との間で、あらゆる機会を通じて日本の考え方を伝えるなど、緊密に連携してきた。この観点から、イラクに大きな影響力を有する周辺諸国からもイラクに対して強く申し入れることが重要であると考え、11月下旬から12月にかけて、さらには2003年3月に中山元外務大臣、高村元外務大臣及び茂木外務副大臣を総理大臣特使としてイラン、エジプト、サウジアラビア、ヨルダン、シリア、トルコに派遣した。周辺諸国との一連の会談では、イラクへの働きかけを継続していくことが重要であることを伝えるとともに、中東地域の平和と安定に向けた取組につき意見交換を行った。
2003年2月24日に米国、英国及びスペインにより提出された安保理決議案及び3月7日に提出された同修正決議案については、日本は、国際協調を貫き、国際社会が一致してイラクに対し圧力をかけ、イラクが自ら武装解除するための真に最後の努力を行うものとして支持を表明してきた。3月17日、同決議案の安保理での投票を求めないことが発表されたが、イラクが大量破壊兵器等を廃棄すべきことについて国際社会は完全に一致しており、イラクは大量破壊兵器等の廃棄という義務から逃れることはできない。同日行われたブッシュ演説に対しては、小泉総理大臣は、国際協調を求めるこれまでの米国の外交努力を評価するとともに、同大統領の決断を支持する旨述べた(3月18日現在)。
【中東和平】
中東和平をめぐる情勢は、2002年を通じて更に悪化した。2000年9月の衝突発生以降、イスラエル、パレスチナ双方合わせて2,300人を超える死者が発生し、双方の経済や生活に深刻な影響を与えている。また、シリア、レバノンとイスラエルとの和平にも進展は見られなかった。
〈イスラエルとパレスチナの和平をめぐる情勢と国際社会の取組〉
イスラエルによるパレスチナ自治区への軍事侵攻とパレスチナ過激派によるテロという暴力の悪循環が継続する中、2002年2月中旬にサウジアラビアのアブドラ皇太子は、1967年の国境線までイスラエルが撤退することを条件に、アラブ諸国がイスラエルとの国交を正常化する提案を行った。同提案は、アラブの大国からの和平に向けたイニシアティブとして注目を集め、3月のアラブ首脳会議において、一部修正を経て、アラブ諸国全体によるアラブ和平提案として採択された。また、事態の悪化に対し、国連は、安保理決議1397、1402及び1403を発出し、イスラエル、パレスチナ両当事者に対して、暴力の応酬を停止することを繰り返し要請した。これらの動きを受けて、米国は4月にパウエル米国務長官を現地に派遣し、イスラエル、パレスチナ双方に停戦の実現を粘り強く働きかけたが、停戦は実現しなかった。
頻発するテロ事件に対して、パレスチナ自身による治安確保への取組が強く求められるようになった。こうした状況を踏まえ、パレスチナ内部からもパレスチナ暫定自治政府の改革や透明性の向上を求める声が挙がり、5月、同政府長官であるアラファト・パレスチナ解放機構(PLO)議長は一般市民に対するテロを改めて非難し、選挙の実施、治安・行政機関の改革を行うことを表明した。その後公表された自治政府改革のための「100日計画」で、改革の基本方針が示され、6月初めの内閣改造においては、改革派の指導者が財務、経済分野等の閣僚に就任した。
パレスチナ自身による改革の動きが見られる中、和平への展望を示すことが、和平の実現のみならず、暴力の停止にも不可欠であるとの認識が強まった。こうした状況を背景に、ブッシュ米大統領は、6月に中東和平に関する演説を行い、イスラエル、パレスチナ二国家の平和共存(two-state vision)に基づく解決を目指すとの基本的立場を確認し、 新指導部の選出を含むパレスチナ改革、
新指導部の選出を含むパレスチナ改革、 暫定的な国境及び主権を有するパレスチナ国家の樹立、
暫定的な国境及び主権を有するパレスチナ国家の樹立、 今後3年以内の最終合意を目指すとの展望を示した。現在、この構想を具体化するため、今後3年間の各々の期間におけるイスラエル、パレスチナ双方の義務を明示したロードマップの策定に向けた努力が、主に米国、欧州連合(EU)、ロシア、国連の4者により継続されている。
今後3年以内の最終合意を目指すとの展望を示した。現在、この構想を具体化するため、今後3年間の各々の期間におけるイスラエル、パレスチナ双方の義務を明示したロードマップの策定に向けた努力が、主に米国、欧州連合(EU)、ロシア、国連の4者により継続されている。
また、ブッシュ米大統領の演説を受け、パレスチナ改革を国際社会としても支援するため、パレスチナ改革タスクフォース(日本、米国、ロシア、EU、ノルウェー、国連、世界銀行、国際通貨基金(IMF)により構成)が形成され、7月に第1回会合を開催した。それ以降、2003年3月現在で本会合が8月、11月、2003年2月の計4回開かれてきたが、このタスクフォースでは、財政、選挙、司法、市民社会、行政機構、地方自治、市場経済の七つの部会において、パレスチナによる改革の進捗〔しんちょく〕状況と、国際社会による支援のあり方が協議されてきた。また、同タスクフォースでは、改革を実施する上で大きな障害である経済封鎖の解除、パレスチナへの税収の還付や自治区からの撤退をイスラエルに対して働きかけてきた。
こうした取組にもかかわらず、イスラエル、パレスチナ双方による暴力の応酬は止まらなかった。パレスチナ過激派によるイスラエル市民をねらった自爆テロは継続し、これに呼応する形で、イスラエルによるパレスチナ自治区への侵攻は継続され、2002年4月及び9月には、イスラエルがパレスチナ自治政府長官府を包囲する事態にまで至った。
イスラエル軍によるパレスチナ自治区の封鎖は、自治区の経済を困窮させ、人道状況を著しく悪化させた。自治区の失業率は50~60%、貧困率は60~70%にも達する。一方で、自爆テロの危険に晒〔さら〕されているイスラエル一般市民の治安への懸念も高まっている。こうした状況下では、イスラエル、パレスチナ双方の世論は、和平を望みつつも、まずは治安の確保が第一であるとする意見が圧倒的多数を占めており、イスラエル、パレスチナ双方の人々の間の相互の信頼が著しく低下することとなった。こうした中、イスラエルでは、10月末に和平推進派の労働党が、入植地予算をめぐる対立により連立与党から離脱した。これを受けて議会(クネセット)における与党リクード党の議席は過半数割れの状態となり、シャロン・イスラエル首相は、早期選挙の実施に追い込まれたものの、2003年1月の総選挙では同首相率いるリクード党が現有議席から大幅に議席を伸ばして勝利し、2月28日シャロン第二次連立政権が成立した。
中東和平プロセスの現状
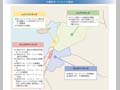
アラファトPLO議長との会談に際し、握手をする川口外務大臣(6月)

〈イスラエルとシリア及びレバノンとの和平をめぐる状況〉
イスラエルとシリアとの和平をめぐる状況については、1999年12月に、当時のバラク・イスラエル首相とシャラ・シリア外相との間で交渉が再開されたが、その後中断され、依然として再開のめどが立っていない。
また、イスラエルとレバノンとの和平をめぐる状況については、2000年5月、イスラエル軍の南レバノンからの一方的撤退を受け、国連も、イスラエルの安保理決議425に基づく撤退を確認する安保理議長声明を発出したが、シェバア村の帰属をめぐる対立が継続し、ヒズボラとイスラエル軍の間で散発的に衝突が発生している状況にある。また、レバノンとイスラエルとの間を流れるハツバニ川の取水問題でも、両国の意見が対立している。
対パレスチナ支援

〈日本の取組〉
日本は、暴力の悪循環を断ち切るため、イスラエル、パレスチナ両当事者、周辺諸国、さらにはG8諸国等との間で、緊密な協議と働きかけを行ってきた。さらに、和平の実現のためには、パレスチナ人の自立が不可欠であるとの認識の下、1993年以降、累計6億4,000万米ドル以上(2003年3月現在)に及ぶ対パレスチナ支援を実施してきた。特に、イスラエル、パレスチナ二国家の平和共存の実現に向けた準備を進めるため、日本の対パレスチナ支援ロードマップを策定し、パレスチナの国家建設の一環としてのパレスチナ改革を支援してきた。日本は、同ロードマップに従って、暴力の継続により極度に悪化したパレスチナ人の人道状況を改善する人道援助、ライフラインの復旧に加え、国造りを担う行政機構の人材育成、政府機関の修復等のパレスチナ改革を後押しするための支援を行っている。
2002年3月、アブドラ提案へのアラブ諸国の対応が注目されたアラブ首脳会議を前に、小泉総理大臣は親書を発出し、アラブ諸国が和平に向けた建設的なメッセージを発出するよう呼びかけた。3月下旬以降、川口外務大臣は、アラファト議長、ペレス外相を始めとするパレスチナ、イスラエル両当事者、また、パウエル米国務長官を始めとするG8各国関係者らと相次いで会談や電話会談を行い、暴力の悪循環を停止するため積極的な働きかけを行った。6月には、川口外務大臣が、イスラエル及びパレスチナ自治区を訪問し、シャロン首相及びアラファト議長を始めとする双方の要人に対して、暴力停止と交渉の再開を要請した。また、日本の対パレスチナ支援の基本方針として、和平の進展に従って更なる支援を行うことを示した対パレスチナ支援ロードマップを提示した。こうした政治的な働きかけや支援に加え、日本は、イスラエル・パレスチナ間の信頼の回復を後押しするため、青年、若手外交官や女性等をイスラエル、パレスチナ双方から招聘〔しょうへい〕し、交流を通じた信頼醸成を図る地道な取組も継続している。
また、日本は、5月末に有馬中東和平担当特使を任命し、イスラエル、パレスチナ自治区のみならず、エジプト、ヨルダン、サウジアラビア、シリア、レバノン等、和平推進の鍵となる周辺諸国の首脳等との対話を通じ、和平への取組を働きかける多角的外交を展開してきた。さらに、日本は、1996年以降、イスラエル・シリア間で係争中のゴラン高原に展開する国連兵力引き離し部隊(UNDOF)に対し要員を派遣している。
【アフガニスタン】
2001年9月11日の米国同時多発テロの発生後、米国や英国等による武力行使の結果、アフガニスタンを支配していたタリバン政権は崩壊した。タリバン後のアフガニスタンについては、ブラヒミ・アフガニスタン担当国連事務総長特別代表の構想に基づき、ドイツのボンで行われたアフガニスタン各派代表者会合において、暫定政権の設立、緊急ロヤジルガ(国民大会議)の招集等について合意し、今後のアフガニスタン和平プロセスの道筋が示された(ボン合意)。2002年1月に東京で、日本、米国、EU及びサウジアラビアが共同議長となり、61か国、21の国際機関が参加してアフガニスタン復興支援国際会議が開催された。同会議において、国際社会は、2002年中に18億米ドル以上、総額で45億米ドル以上の支援を表明し、今後のアフガニスタンの復興へ向けた道筋が示された。
〈アフガニスタン情勢と国際社会の取組〉
アフガニスタンの和平については、2001年12月22日に暫定政権が発足し、2002年6月には緊急ロヤジルガが開催されるなど進展が見られた。緊急ロヤジルガには、アフガニスタン全土から1,650名の代表が出席し、カルザイ暫定政権議長が、秘密投票において約8割の票を獲得し、アフガニスタン移行政権の首班に選出された。また、同会議では、ザヒル・シャー元国王が、国父としての象徴的な地位を占めることが決定された。
2002年6月までの暫定政権下では、アフガニスタンの最大民族であるパシュトゥン人が、政権内でのタジク人への権力集中に対して不満を抱えていることが問題となっていた。こうした背景もあり、緊急ロヤジルガ後に成立した移行政権の下では、タジク人の有力者であるカヌニ内相、アブドラ外相、ファヒム国防相のうち、カヌニ内相が内相ポストから外れ、その代わりにパシュトゥン人のハッジ・カディール氏が内相に就任することになった。しかし、7月にはカディール副大統領兼内相が暗殺され、9月にはカルザイ大統領暗殺未遂事件が発生するなど、カルザイ大統領の政治基盤は盤石ではなく、移行政権の支配地域は、事実上、首都カブールの周辺に限定されている状態にある。
こうした状況の下、12月2日には、ドイツにて、ボン会合1周年記念閣僚会合が開催され、アフガニスタンの政治的な安定の確保に向けて協議が行われた。同会合では、アフガニスタン国軍の規模を7万人程度とし、今後1年以内に地方軍閥などの武装解除を進めていくとのカルザイ大統領の布告が発表された。今後、アフガニスタン、そして国際社会にとって、地方軍閥の武装解除と国軍の創設をいかに実施していくかが大きな課題となっている。また、12月22日には、アフガニスタン移行政権が成立して初めての閣僚級国際会議であるカブール善隣友好会議が開催され、日本からは新藤外務大臣政務官が出席した。会議では、アフガニスタンと周辺諸国との善隣友好、相互不可侵を内容とするカブール宣言が署名・発表された。2003年2月22日には、日本においてアフガニスタン「平和の定着」東京会議が開催され、アフガニスタン移行政権から、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR(注))についての決意と具体的な方針が表明されるとともに、国際社会の更なる支援と協力が求められた。
アフガニスタンの治安については、カブールでは、2002年1月に国際治安支援部隊(ISAF)が本格的に展開したことによって、ある程度安定した状態にある。しかしながら、地方では現在も数十万と見られる武装勢力が存在し、軍閥間による武力衝突も散発的に発生しており、アフガニスタンの治安を不安定化させる要因となっている。
米軍等による「不朽の自由作戦」は、テロ撲滅に一定の成果を上げつつあるが、アルカイダの残党もいまだ活動しており、タリバンの再結集化も進んでいるとも言われている。加えて、米国同時多発テロの首謀者であるウサマ・ビンラディンやオマル師等の行方は依然としてつかめていない状況にある。こうした状況を踏まえ、国際社会では、アフガニスタンにおける治安の確保は、復興支援の前提条件であり、国際社会が重点的に取り組まなければならない課題であるとの共通の認識が広まるようになった。こうした認識を踏まえ、具体的には、米国が国軍の創設、日本と国連アフガニスタン支援団(UNAMA)がDDR、ドイツが警察の再建、イタリアが司法制度の再建、英国が麻薬対策にそれぞれ取り組んでおり、2002年を通じてアフガニスタンの安定と繁栄に向けた国際社会の取組が進展してきた。
ザヒル・シャー元国王の帰国式典に参列するためにアフガニスタンを訪問し、同元国王を表敬する松浪外務大臣政務官(4月)

国際治安支援部隊(ISAF)の活動状況

〈日本の取組〉
アフガニスタン復興支援に関して、2002年1月の東京でのアフガニスタン復興支援国際会議で表明された支援は、これまでのところ国際社会によりほぼ順調に実施されてきている。日本は、同会議で、地域共同体の再建、地雷・不発弾の除去、教育、保健・医療、メディア・インフラ、女性の地位向上といった分野を中心に、向こう2年半で最大5億米ドルまで、最初の1年間で最大2.5億米ドルまでの支援を行うことを表明した。日本は、既に約3億5,800万米ドルの復旧・復興支援を実施又は決定した。この結果、米国同時多発テロ以降にアフガニスタンに対して実施した人道支援を含めた日本の支援額の合計は、約4億5,000万米ドルとなった。
5月には、川口外務大臣がアフガニスタンを訪問し、和平プロセスの進展、国内の安定・治安の確保、人道・復興支援への協力を行うことによって、アフガニスタンに平和を定着させることが重要であることを指摘した。また、9月の国連総会の際には、小泉総理大臣とカルザイ大統領との間で首脳会談が行われ、日本は、5,000万米ドルをめどに、米国、サウジアラビアと共に、カブール・カンダハル間の幹線道路の修復のための支援を行うことを発表した。そのほかにも、日本は、アフガニスタンにおける大量の難民・避難民の帰還と再定住、受け皿となる各地域の総合的な復興・開発を目指す取組(緒方イニシアティブ)を推進している。また、2003年2月のアフガニスタン「平和の定着」東京会議においては、UNAMAと共に策定した平和のためのパートナーシップ計画に対し3,500万米ドルの支援を表明しており、今後ともこうした支援を継続していく考えである。
(コラム:バーミヤン遺跡を訪れて)
【イラン】
〈イランをめぐる情勢と国際社会の取組〉
2002年のイランでは、政府・国会等における改革派と司法・法案監督機関等の保守派の対立が継続した。保守派は、改革派要人の逮捕や訴追、改革関連法案の否認に加え、11月には、改革派の知識人であるアガジャリ教授へ死刑判決を出すなど、改革に向けた動きに激しく抵抗した。こうした保守派の動きに対して、イラン政府は、保守系機関による憲法違反や、恣意〔しい〕的な国会選挙への立候補者の資格審査を抑制するため、9月には、大統領権限強化法案と国会選挙法改正法案を提出して巻き返しを図った。また、7月や11月には、改革が遅々として進捗しない状況やアガジャリ教授への死刑判決等に不満を有した若者による大規模な抗議デモが行われた。
外交面では、EUとの関係強化が進捗した。ハタミ大統領によるオーストリア(3月)、ギリシャ(3月)、スペイン(10月)訪問や、ソラナEU共通外交安全保障政策(CFSP)上級代表のイラン訪問(8月)に加え、EUとイランとの間では、政府・議会関係者の交流も活発に行われた。また、12月には、EU・イラン間の貿易・協力協定締結交渉が開始された。一方で、米国との間では、米国同時多発テロ以降のアフガニスタン情勢への対応にあたって一定の協力が行われたものの、2002年1月のブッシュ米大統領の一般教書演説における「悪の枢軸」発言以後、両国関係は急速に悪化した。
また、国際社会の緊急の課題となっているイラクによる大量破壊兵器等の開発・保有をめぐっては、イランは地域の緊張緩和の観点から、イラク周辺国と緊密な意見交換を行いつつ、米国のイラクへの単独攻撃に反対する一方、イラクに対しては関連安保理決議の実施を呼びかけている。
〈日本の取組〉
日本は、中東地域の大国であるイランが国内改革や国際社会との対話を一層推進し、中東地域や国際社会の平和と安定の確保のために、一層積極的な役割を果たすよう、イランに対し対話を通じた働きかけを行っている。2002年1月には、緒方アフガニスタン支援総理大臣特別代表がイランを訪問したほか、小泉総理大臣が、アフガニスタン復興支援国際会議出席のため訪日したハラジ・イラン外相との間でアフガニスタンの復興支援につき協議を行った。5月には、川口外務大臣がイランを訪問し、文化交流、人的交流の促進に合意したほか、地域・国際情勢について意見交換を行った。
政府レベルでの交流に加え、議員交流も頻繁に行われた。イランよりハタミ大統領の実弟で、改革派最大政党の党首であるレザー・ハタミ国会第二副議長(10月)や、改革派の重鎮であるアンサーリ国会計画・予算・決算委員長(12月)が訪日した。日本からは、9月に渡部衆議院副議長、11月には、イラク情勢に関連して、中山元外務大臣(日・イラン友好議連会長)が総理大臣特使としてイランを訪問した。
経済面では、9月の国際エネルギー・フォーラム出席のため、ザンギャネ石油相が訪日し、平沼経済産業大臣との間で、アザデガン油田開発契約交渉に関連する諸契約を2003年春までに締結することを促していくこと、また、イランの石油・ガス油田開発プロジェクトへの日本企業の参加を歓迎することなどを内容とする共同声明に署名した。
【湾岸諸国】
〈湾岸諸国情勢〉
湾岸諸国は、中東地域に大きな影響力を有するイラン及びイラクとの政治的なバランスをとりつつ、米国に湾岸地域の安全保障を依存している。2002年には、イラクの大量破壊兵器等の開発・保有をめぐって国際社会の緊張が高まった。イラクの近隣に位置する湾岸諸国は、イラクへの武力行使に慎重な立場を示し、安保理決議に基づく平和的解決を支持する姿勢を見せる一方で、予想される米国等による軍事行動への対応振りとの間で、微妙な舵〔かじ〕取りを迫られることになった。また、米国同時多発テロの発生以降、湾岸諸国はテロを強く非難し、国際社会によるテロとの闘いに協力してきた。一方で、米国同時多発テロの実行犯にサウジアラビア国籍の者が多かったことから、米国においてサウジアラビアがテロの温床となっているのではないかとの批判が高まり、米国との関係で、サウジアラビアが苦しい立場に置かれるようになった。
〈日本の取組〉
日本は、中東地域の平和・安定の確保は、国際社会全体の平和・安定と繁栄の実現に大きな影響を与え得るものであること、また、中東地域は、日本がエネルギー資源の8割以上を依存している戦略的に重要な地域であることから、同地域の平和・安定と繁栄の実現に向けて、湾岸諸国が抱える様々な事情に配慮しつつ、対湾岸外交を積極的に展開していく考えである。
緊迫するイラク情勢との関連では、2002年12月及び2003年3月に、高村元外務大臣が総理大臣特使としてサウジアラビアを訪問し、イラクが関連安保理決議を履行し査察へ協力するよう、サウジアラビアがイラクに対して積極的に働きかけを行うことを求めた。
また、日本は、中長期的な視点に立って対湾岸諸国外交を強化するため、人的交流や文化交流を始めとする湾岸諸国との幅広い協力関係を構築していく考えである。具体的には、イスラム世界との文明の対話の促進、水資源開発・環境協力及び幅広い政策対話の促進を3本柱に据えた、いわゆる河野イニシアティブ(注)の具体化に努めてきた。2002年3月には、バーレーンにおいて、イスラム世界との文明間対話セミナーを開催し、6月には、日本・サウジアラビア合同委員会を東京で開催した。さらに、9月には、国連においてサウジアラビアとの間で外相会談を行ったほか、同じく9月には、杉浦外務副大臣がイエメンを訪問し、また、松浪外務大臣政務官がクウェート及びバーレーンを訪問し、湾岸諸国との間で、二国間関係や国際情勢等について幅広い政策対話を行った。
日本のエネルギー安全保障の観点から、湾岸地域における日本の自主開発油田採掘権の延長問題は懸案事項の一つであり、2002年3月には古屋経済産業副大臣がサウジアラビア、クウェート、カタールを訪問し、経済面における日本と湾岸諸国の関係強化に取り組んだ。また、9月には大阪で、日本とアラブ首長国連邦が共同議長を務めた第8回国際エネルギー・フォーラムが開催され、石油の生産国と消費国が集まり、有意義な意見交換を行った。

 次頁
次頁

 新指導部の選出を含むパレスチナ改革、
新指導部の選出を含むパレスチナ改革、 暫定的な国境及び主権を有するパレスチナ国家の樹立、
暫定的な国境及び主権を有するパレスチナ国家の樹立、 今後3年以内の最終合意を目指すとの展望を示した。現在、この構想を具体化するため、今後3年間の各々の期間におけるイスラエル、パレスチナ双方の義務を明示したロードマップの策定に向けた努力が、主に米国、欧州連合(EU)、ロシア、国連の4者により継続されている。
今後3年以内の最終合意を目指すとの展望を示した。現在、この構想を具体化するため、今後3年間の各々の期間におけるイスラエル、パレスチナ双方の義務を明示したロードマップの策定に向けた努力が、主に米国、欧州連合(EU)、ロシア、国連の4者により継続されている。