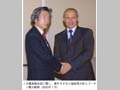第2章 > 第5節 ロシア及び旧ソ連新独立国家(NIS)諸国
【総論】
ロシアでは、プーチン大統領が、2002年も国民の強い支持(世論調査の示す支持率はおおむね70%強)と好調な経済を背景に安定的な政権運営を行ってきた。また、対外的には首脳外交を軸として積極的な外交を展開し、特に米国、北大西洋条約機構(NATO)を始めとする欧米諸国との協調路線を定着させた。
日本は、2002年も引き続き、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、日露関係の完全な正常化を達成するために努力を継続してきた。同時に、ロシアの改革努力を支持しつつ、幅広い分野における関係の強化を図ることを対露外交の基本政策とし、ハイレベルでの頻繁な対話などを通じて日露関係の進展を図ってきた。その結果、政治、経済、安全保障、人的交流、国際問題に関する協力等の分野において、日露間の協力が着実に進展した。
旧ソ連新独立国家(NIS)諸国との関係では、NIS諸国の安定は、ユーラシア大陸周辺地域の安定に直接影響を及ぼし得るものであり、ひいては東アジアの安定にも影響を及ぼし得るとの観点も踏まえ、引き続き関係の強化に努めてきた。
【日露関係】
〈緊密な政治対話の継続と国際問題における協力の進展〉
2002年も、日露両国間では緊密な政治対話が行われてきた。まず、首脳レベルにおいて、6月のG8カナナスキス・サミットの際に、小泉総理大臣がプーチン大統領と首脳会談を行った。同首脳会談では、2002年末又は2003年初めの小泉総理大臣のロシア公式訪問、2003年をロシアにおいて日本に関する文化行事を集中的に行う年とすることなどで合意した。また、2002年後半に国際社会の大きな関心を集めた北朝鮮をめぐる問題について、9月の小泉総理大臣の訪朝の前後に、プーチン大統領との間で2度の電話会談が実施された。2003年1月には、小泉総理大臣がロシアを訪問し、日露両国間の幅広い分野でのこれまでの協力と今後の協力の方向性をとりまとめた、今後の両国関係の海図となる日露行動計画を発表した。
また、2002年を通じて、外相レベルにおける対話も頻繁に行われ、直接会談の数は6回にものぼった。まず2月に、イワノフ外相が訪日し、日露外相会談が行われ、その成果として国際テロリズムとの闘いに関する共同声明を発表した。10月には川口外務大臣がロシアを公式訪問し、日露外相会談及び第6回貿易経済日露政府間委員会を開催した。イワノフ外相は12月にも訪日し、川口外務大臣との間で、2003年1月の小泉総理大臣の訪露に向けて最終的な準備作業を行った。このほかにも両外相は、6月のカナダ・ウィスラーにおけるG8外相会合、8月のブルネイにおける第9回ASEAN地域フォーラム(ARF)閣僚会合、9月のニューヨークにおける国連総会の機会を利用し、対話を継続した。これら一連の会談や電話会談では、北朝鮮をめぐる問題に加え、アフガニスタン、イラク情勢等、幅広い国際情勢について緊密な意見交換が行われた。
日露行動計画(骨子)

(トピック:北方領土問題)
〈平和条約締結交渉〉
2001年3月のイルクーツク声明は、日露両国がクラスノヤルスク合意に基づき平和条約の締結に向けて全力で取り組んできた結果を総括し、今後の平和条約交渉の新たな基礎を形成するものとなった。両国は、この声明の中で、1956年の日ソ共同宣言(注1)が交渉の出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、その上で、1993年の東京宣言(注2)に基づき、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、日露関係を完全に正常化することを確認した。
2002年も、これまで日露間で達成された諸合意を基礎として、精力的な交渉が継続された。首脳レベルでは、6月の首脳会談において、これまでの成果を踏まえ、引き続き交渉を進めていくことが確認された。また外相レベルでは、2月の外相会談で、平和条約交渉を今後継続するにあたって、これまでの合意をすべて遵守していくことが再確認されたほか、10月の外相会談では、平和条約締結問題が日露行動計画における重要な柱の一つとなることについて意見の一致を見た。12月の外相会談では川口外務大臣より、日露関係を質的に新たなレベルに引き上げるためにも、平和条約の締結が不可欠であることを指摘した。また、2002年を通じて行われた事務レベルの対話においても、平和条約締結問題は継続的に議論されてきた。
2003年1月に小泉総理大臣がロシアを訪問した際には、両国は、四島の帰属の問題を解決し、平和条約を可能な限り早期に締結し、もって両国関係を完全に正常化すべきとの決意を確認し、両首脳の強い政治的意思を表明した。また、日露行動計画においては、1956年日ソ共同宣言、1993年東京宣言、2001年イルクーツク声明の3文書を具体的に列挙した上で今後の平和条約交渉の基礎となるとの認識で一致した。
日露首脳会談に際し、握手をする小泉総理大臣とプーチン露大統領(2003年1月)
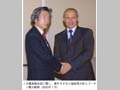
【日露経済関係】
政府レベルでは、10月の川口外務大臣の訪露の機会に第6回貿易経済日露政府間委員会を開催し、ロシア経済、ロシアの制度改革、貿易投資促進機構の創設、エネルギー・科学技術等の分野における協力などに関し、幅広い意見交換が行われた。
また、6月のロシア東欧貿易会ミッションの極東訪問、7月の経済同友会ミッションのロシア訪問、9月の日本経団連によるロシアでの日露ビジネス促進セミナーの実施、10月の東京での日露経済合同会議の開催等、民間経済界の交流が活発に行われてきた。
また、日本企業が参加するロシアでも最大規模の石油・ガス開発プロジェクトであるサハリン・プロジェクトは、サハリン1が2005年からの原油の生産開始を目指し、サハリン2が1999年の原油の生産開始に続き2006年からの天然ガスの生産開始を目指し、開発を本格化させつつある。
日本は、ロシアの経済改革努力に対する支援として、日本センターを通じた支援を始め、経営関連講座や日本での研修等、ロシアの市場経済の発展及び日露間の貿易経済関係の強化に向けた技術協力を実施している。
また、2003年1月の小泉総理大臣の訪露の際には、両国はロシア極東及びシベリア地域におけるエネルギー資源開発及び輸送の分野等、エネルギー分野の協力を始めとし、経済分野の協力を互恵の原則の下で発展させることで一致した。
日本の対ロシア支援

【様々な分野の日露間の交流・協力】
政治対話や経済分野の協力の進展にあわせて、日露両国間の人的交流及び防衛交流も一層進展した。安全保障対話・防衛交流の分野では、2002年には、ミハイロフ空軍総司令官の訪日や中谷陸上幕僚長の訪露、ロシア海軍艦艇の神奈川県横須賀港訪問等が行われ、2003年1月には石破防衛庁長官が訪露した。治安当局間の交流の分野では、トツキー国境警備庁長官が訪日した。また、2002年には両国の議会間交流が活発に行われ、日本からは綿貫衆議院議長一行、ロシアからはセレズニョフ国家院議長一行を始めとして、両国から多数の議員が往来し、交流を深めた。
文化・広報分野では、5月にサンクトペテルブルグにおいて、総合研究開発機構(NIRA)とロシア戦略策定センターの共催で、21世紀の平和・安全保障、テロ分野における日露協力及び日露文化交流の三つをテーマとした日露有識者による第2回日露フォーラムが開催された。また、ロシアにおいて日本に関する行事を集中的に行う年とするという首脳間の合意に基づき、2003年を通じて、「ロシアにおける日本文化フェスティバル」を開催することとし、現在、準備が進められている。
【ロシア内政】
プーチン大統領への高い支持率、好調なロシア経済を背景として、政治情勢は引き続き安定している。
ロシア議会では、大統領支持を標榜する「統一」と中道勢力の「祖国」及び「全ロシア」が統合して創設された政権支持政党「統一ロシア」が、議会内で他の中道勢力と協力して過半数を確保しており、安定した議会運営が行われてきた。その一方で、4月には共産党が院内委員会議長職からの排斥を契機として政権に対する批判的姿勢を強めている。
地方との関係では、連邦制度改革の下に、中央と地方の権限関係を明確化する方向で調整が行われてきた。具体的には、これまで中央と地方の間にあった権限分割条約の多くが破棄又は改正されたほか、政府の特別委員会により中央と地方の権限関係を統一、明確化するための一連の法案が策定され、現在議会で議論が行われている。
現在の内政上の大きな課題であるチェチェン問題については、2002年4月の年次教書でプーチン大統領は、「既に軍事的段階は終了した」と述べたが、その後もチェチェンとその周辺地域では紛争が頻発しており、解決のめどは立っていない。
10月にはモスクワでチェチェン武装勢力による劇場占拠事件が起こったが、プーチン大統領は、「テロには決して屈しない」との強い姿勢に立って救出作戦を実施し、130名近い犠牲者を出したものの、比較的短期間に武装勢力を制圧した。この事件に対して、日本は、一般市民を巻き込んだテロ行為は断じて許されてはならないことであり、いかなる理由をもっても正当化することはできないとの内容の小泉総理大臣発プーチン大統領宛のメッセージを発出した。さらに、12月末にはグロズヌイでチェチェン政府庁舎に対し自爆テロが行われ、72名が死亡した。
チェチェン紛争(クロノロジー)

【ロシア経済】
2001年に引き続き、2002年にもロシア経済はおおむね好調に推移した。主として2001年9月の米国同時多発テロ以降の世界経済の減速とそれに伴う国際石油価格の低下により、2001年後半から2002年初めにかけては、ロシア経済にも成長の鈍化が見られたが、春ごろより石油価格が上昇に転じ、成長率も回復した(2002年の経済成長率は4.3%(速報))。
財政収支も好調で、2002年度の連邦予算は、当初から財政黒字を組み込んでいたが、決算ベースでも計上額を上回る黒字になる見込みである。2003年の予算でも、歳出が対前年度比で20%近く増加するにもかかわらず、黒字が計上されている。これらの黒字によって蓄積された資金は、主として対外債務の返済(2003年がピークで返済額は170億米ドル以上になる)に充てられる予定であり、対外債務の返済は滞りなく行われると見られている。
経済改革の面でも、ロシアは、2001年に引き続き構造改革に取り組んできた。懸案となっていた自然独占体(ガス、電気、鉄道の独占的企業体)の改革のうち、電気及び鉄道の改革法案が議会に上程された。また、世界貿易機関(WTO)への早期加盟を目指して、一連の改革努力がなされている。一方で、金融制度や行政制度等については、全般に改革の遅れを懸念する向きもある。
最近のロシア経済指標

【ロシアの対外関係】
外交面では、プーチン大統領は、2002年も引き続き活発な首脳外交を展開した。特に、米国を始め西側諸国との協調路線を維持し、5月の米露首脳会談では、戦略核兵器削減条約(モスクワ条約)に調印し、「新たな戦略関係に関する共同宣言」を発表した。さらに、テロとの闘いにおいて米露両国が「同盟国」であることを確認するなど、米露関係が新たな段階に入ったことを印象づけた。
NATOとの関係では、5月のNATO・ロシア首脳会合において、21世紀の新たな脅威や課題へ対応するためNATO・ロシア理事会(NRC)の設置に合意し(ローマ宣言)、当面テロとの闘いなど、九つの分野についてNATOの意思決定へのロシアの参加を確保した。NATOの拡大については、ロシアは、原則反対の立場を変えていないものの、11月のNATO首脳会議で拡大が決定した際には、ロシアはこれを事実上黙認した。
また、6月のG8カナナスキス・サミットでは、2006年にロシアがG8サミットを主催することが決定された。
独立国家共同体(CIS)(注1)諸国との関係については、9月にグルジアとの間でパンキシ渓谷等グルジア領内に在住するチェチェン武装勢力への対応をめぐって緊張が高まった。また、ベラルーシとの間では、国家統合に向けたプロセスが進められているが、統合の方法をめぐって両国首脳間の見解の相違が表面化したものの、その後収まった模様で、2003年1月の首脳会談では、共通通貨の導入を2005年1月から行うことに合意した。
また、プーチン大統領はアジア地域に対しても目を向けており、中国に関しては、2002年6月にロシア及びカザフスタンにおいて、12月には自らが訪中して首脳会談を行い、軍事及び経済面での両国の協力を強化した。また、プーチン大統領は8月にはロシア極東を訪問し、ウラジオストクで北朝鮮の金正日〔キムジョンイル〕国防委員長と通算3度目となる会談を行い、北朝鮮との関係におけるロシアの存在感を印象づけた。
【NIS諸国情勢と日本外交】
NIS諸国(注2)は、独立当初から一様に政治的・経済的な自立の困難に直面してきたが、独立後10年以上が経過し、現在は国によって、政治・社会面における民主化、経済面における市場経済化の状況等、発展の度合いがますます多様化してきた。
このような中、2002年、NIS各国は、周辺諸国、欧米諸国との協力を個別に進展させてきた。中央アジア地域においては、米国同時多発テロ以降、軍事面を中心に米国との協力が強化されたほか、域内においては中央アジア協力機構、上海協力機構等の地域協力推進の動きが見られた。また、コーカサス及び欧州地域諸国では、欧州統合やNATO拡大を視野に入れた外交の動きが見られた。CIS全体については、2002年10月のモルドバでの首脳会議で、機構の効率性の向上について協議が行われたものの、テロ対策以外の分野では協力の方向性について特段一致するには至らなかった。なお、2002年には、グルジアやベラルーシとロシアとの関係が一時的に緊張ないし冷却化する場面が見られ、また、ロシアについては、全般的にCIS全体より各国との個別関係を優先する傾向が見られた。
日本は、アフガニスタンをめぐる情勢の変化を踏まえ、1月にウズベキスタン及びタジキスタンに総理大臣特使を派遣し、両国に対して支援を表明した。4月には、杉浦外務副大臣が中央アジア諸国を訪問したほか、7月には、エネルギー面での協力の可能性を検討するため、杉浦外務副大臣を団長とする産学官からなる調査団を中央アジア及びコーカサス地域に派遣した。7月にはカリモフ・ウズベキスタン大統領が訪日し、12月にはトカーエフ・カザフスタン国務長官兼外相が訪日し、各国との更なる関係の強化に努めた。これら諸国からは、日本の対シルクロード地域外交への高い評価と感謝に加え、より一層の関係強化への希望が表明された。

 次頁
次頁