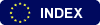| (1) |
就労を目的とする第3国国民の入居・居住要件に関する指令★
| (a) |
欧州委は本年7月に「就労を目的とする第3国国民の入居・居住要件に関する指令案」を採択し、理事会に提出されたと承知している。我が方はEU域内で就労しようとする我が国国民が負担する事務の軽減につながることを期待する。 |
| (b) |
指令案では許可申請の処理期限は一般労働許可の場合は180日間、企業内転勤を含む特別の場合は45日間となっている。本年8月のEU側回答によれば、欧州各国の処理期間は概ね1ヶ月程度となっているため、特に、一般労働許可に該当すると推察される教育等に従事する場合、処理期間の大幅な長期化を懸念する。 |
| (c) |
指令案の「善行証明」及び「技能証明」の具体的内容について不明なところ、明確化を要望する。 |
| (d) |
我が国企業の従業員の転勤の際には「企業内転勤者」に該当するものとして許可の申請をすることが予想されるが、申請の際の混乱を避けるため右基準の一層の明確化を要望する。 |
|
| (2) |
シェンゲン協定に関する欧州委員会の指令案★
欧州委員会は、本年7月、「シェンゲン協定に関する欧州委員会の指令案」を提案した。我が国としては、本指令案がそのまま実施される場合には、これまで我が国と欧州各国との査免協定に基づいて行われてきた欧州への我が国国民の渡航に多大な影響を与えると思料される。その具体的な効果については、現在、我が国官民において、鋭意調査中であり、EU側においては、かかる影響に鑑み、今後我が国との間で緊密な情報交換を行った上、充分な時間をかけて最終的な指令案のとりまとめを行うことを要望する。
|
| (3) |
伊における滞在・労働査証取得等の改善
| (a) |
労働許可証に関し、役員クラスが対象となる独立事業者枠及び管理職が対象となる従属事業者枠とも枠数が少なく、新規の労働許可証取得が極めて困難であり、駐在員の交代に支障が出ている。我が方は労働許可証の増枠を要望する。 |
| (b) |
従属事業者枠の暫定措置として発行された2年間の期間限定労働許可証については、延長・更新が認められないが故に、新規に申請・取得せざるを得ず、かつ伊での就労・滞在のために新たな入国査証が必要とされることから、一時帰国を余儀なくされ、事業活動に障害が出ている。期間限定労働許可証が発給されたのは53人で、これは従属事業者枠を受けた人の25%にあたるためその影響は大きく、労働許可証の更新は域内での実施状況から見て、多くの場合、国内で手続可能と承知しており、我が方は早急に有効期限の延長及び伊国内での更新を可能とすることを要望する。 |
| (c) |
滞在許可証取得につき、依然取得までに平均3ヶ月と長期間かかることが多いため、短期化を要望する。また、ミラノ及びトリノにおいて日本人等に対して滞在許可申請の専用窓口が開設されたことを評価する。引き続き、邦人の多い他の地域についても早急に同様の措置が取られることを要望する。 |
| (d) |
労働査証申請場所や申請担当者によって、必要であるといわれる書類が異なる。これは規則を含み運用等に変更があっても、末端の窓口まで徹底されていないためと見られる。必要書類の明確化(説明書類の発行等)および担当者に対する指導の徹底を引き続き要望する。 |
| (e) |
駐在員と一括ではなく単独で申請する配偶者の場合は、申請する書類が多く、徴求に時間がかかることから多大な負担となっている。引き続き改善を要望する。 |
| (f) |
自動車購入のために住民登録が必要とされており、住民登録の前提となる滞在許可証取得に時間を要するところ、本年8月の伊側回答には本件について回答がなく、住民登録を不要とする等の改善を引き続き要望する。 |
| (g) |
伊では出生地が重んじられ、査証等の取得時、その都度戸籍謄本のイタリア語訳を提出する必要があり、手続の簡素化を要望する。日本ではパスポート取得時に戸籍謄本を徴求し、本人であることを確認の上パスポートを発給していることをふまえ、パスポートに記載されている本籍をもって伊政府が出生地を確認すれば必要十分である。本年8月の伊側回答には本件について回答がなく、伊側の見解を求める。 |
|
| (4) |
西における労働査証取得等の改善
| (a) |
本年8月の西側回答によれば、西当局は申請者の母国又は過去5年間に居住した国の犯罪歴に関する情報を求めることがある、とのことであるが、母国でも現居住国でもない国であって申請者が過去5年間に居住した国による無犯罪証明書は、労働査証申請時に必ず必要な書類ではない(すなわち、求められなければ提出しなくても良い)と理解してよいのか、また具体的にどのようなケースにおいてかかる書類の提出を求められるのか再度確認したい。他方、我が国が労働査証申請にあたり居住国の無犯罪証明書を求めていない事実にも鑑み、申請者の負担を軽減する観点から、少なくとも母国たる我が国又は現居住国が発行する証明書で足りる扱いを求める。 |
| (b) |
査証発行に係る手続は以前に比し全般的に迅速化が進んでいるものの、半年以上要しているケースも見られ、迅速化を要望する。 |
|
| (5) |
希における労働許可証
| (a) |
希では非EU国民への労働許可発行に当たり、①非EU国民1人を雇うには少なくとも5人のEU加盟国民を雇用しなければならない、②5人を上回るEU国民を雇用する企業は、EU国民と非EU国民の比率を10:1に維持しなければならないとの条件が適用されている(但し、当該非EU国民が幹部職員である又は特定の技術的・科学的知見を有する場合には適用されない)。
現在、本件につき具体的に問題となっている日系企業はなく、また、本年8月の希側回答によれば、希当局は本制度を改正する予定はないとのことであるが、右を緩和することにより、日本を含む各国企業にとっての投資活動条件が大幅に改善されるところ、我が国としては、かかる要件の廃止を引き続き要望する。 |
| (b) |
労働査証申請場所や申請担当者によって、必要であるといわれる書類が異なる。これは本年6月に「新入国管理法」が制定されても、末端の窓口まで徹底されていないためと見られる。必要書類の明確化(説明書類の発行等)および担当者に対する指導の徹底を要望する。 |
|
| (6) |
独における労働許可制度等の改善
| (a) |
昨年12月に「外国人施行令」が改正されたが、地方の外国人局等では同改正の内容を正確に把握していない事例が見られることから、周知徹底を求める。 |
| (b) |
日独ワーキング・ホリデー制度では、我が国に1年間滞在するドイツ人青年に就労期間の制限はないが、ドイツに1年間滞在する日本人青年には90日間の就労制限がある。本年8月の独側回答には本件について回答がないところ、引き続き就労制限の理由につき回答を求める。 |
|
| (7) |
白における労働査証等
| (a) |
労働査証及びプロフェッショナルカードの発給については迅速化が図られているようだが、依然として長期間かかっている例も見られ、引き続き手続期間の短縮を希望する。 |
| (b) |
若年層を中心に最長滞在期間を4年までに限定する査証が出てきており、IT技術など専門性を持つ若年層を配置するのに障害となっている。本年8月の白側回答において、管理職の区分で申請できることを示唆しているが、労働許可証の区分及びその認定基準について白側の説明は不十分であり、明確な説明を求める。また、最長滞在期間の制限について白側より説得力のある説明はなく、本制度が早期に廃止されることを要望する。 |
|
| (8) |
仏におけるビジネス滞在許可、就労ビザの発行・延長・更新手続の改善・迅速化
| (a) |
仏側による家族呼び寄せの手続きの改善及び長期滞在許可、就労ビザの発給手続の改善を評価するが、労働許可申請から取得まで最低2ヶ月、滞在許可証の更新手続に1ヶ月を要するというように、手続に要する日数が長く日本人駐在員の円滑な移動・配置転換に支障をきたす場合があり、また緊急事態に対応不可能となっている。家族の呼び寄せについても、現行手続では少なくとも半年は要すと承知している。本年8月の仏側回答によれば、現行制度を見直すつもりはないとのことであるが、更なる手続の短縮及び簡素化を要望する。 |
| (b) |
また、滞在許可証の有効期限の現在の1年から2年への延長を引き続き要望する。 |
| (c) |
労働査証申請場所や申請担当者によって、必要であるといわれる書類が異なる。これはルール変更があっても、末端の窓口まで徹底されていないためと見られる。担当者に対する指導の徹底を引き続き要望する。 |
|
| (9) |
仏の商業人手帳
| (a) |
非EU加盟国の国民がフランスの会社の取締役に就任する時には、商業人手帳の取得が必要とされているが、申請に必要な書類が多く、かつ各県によって異なりわかりにくい。例えば日・仏無犯罪証明書、履歴書、無破産宣誓書、無犯罪宣誓書、銀行残高証明書等の書類が必要であるが、県によっては上記に加え、戸籍抄本、卒業証明書等の書類を要求される。本年8月の仏側回答ではこれらの書類を徴求する明確な理由がなく、商業人手帳申請のために必要な書類を簡素化するとともに仏全体で統一することを要望する。 |
| (b) |
また、商業人手帳の取得のためには4~5ヶ月かかり、かつ毎年更新が必要である。商業人手帳の有効期限の延長(2~3年)を要望する。 |
|
| (10) |
フィンランドにおける労働査証★
日フィンランド経済貿易協議において、フィンランド側より在京フィンランド大が発給可能な労働査証の有効期限は1年間であり、フィンランドに赴任1年後に所管の地方警察署にて同査証を更新する際は、滞在予定期間に合わせて数年間有効の査証取得が可能との回答を得ているが、多くのケースでは有効期限1年のものしか発行されず、また、更新審査期間も3ヶ月程度かかっている。申請者が海外出張を行う際、申請者のパスポートを当局に預けているため、必要の都度当局から引き上げなければならず、大きな負担となっていることから、我が方は滞在期間に応じた有効期間の査証を迅速に発給することを要望する。 |