|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 犯罪 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 犯罪 |
| 国際組織犯罪 |
平成11年4月
(国際組織犯罪取り組みの経緯及び現状)(1)リヨン・グループ(G8)
95年のハリファックス・サミットの結果、設置され、40の勧告を策定。これまでコンピュータ・ハイテク犯罪、銃器の不正取引、人の密輸、司法共助・犯罪人引渡等を中心に取り組んできている。これまでは、情報交換、行動計画の策定等が主要な活動になっている。なお、薬物、マネー・ローンダリング、テロ等は別フォーラムが既にあることから活動の主たる対象にはなっていない。(2)金融活動作業部会(FATF)
89年のアルシュ・サミットにおいて、国際的な資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策に関する予防策を検討することを目的として召集された。主要先進国を含む28カ国・地域及び国際機関の金融、司法、取締当局が参加。「40の勧告」を策定。関連条約としては、ウイーン条約(麻薬新条約)がある。日本としては、上程中の「組織的犯罪処罰法案」で、上記勧告を実施するため、資金洗浄罪の前提犯罪の拡大、金融機関等における疑わしい取引の届出範囲の拡充(併せてその一元的管理機関となるFIU機能の金融監督庁への付与)等を期している。(3)金融犯罪に関するG7作業部会
デンヴァー・サミットの7ヶ国声明を受けて設置されたG7金融犯罪作業部会で、金融犯罪に関する情報交換につき国際協力の改善が模索されている。(4)薬物
国連では経社理の下に麻薬委員会があり、その事務局として国連薬物統制計画(UNDCP)が積極的な活動を行っている。また、先進国間では米国の提案により15カ国プラス国際機関からなる「ダブリン・グループ」がある。3つの関連条約があり、薬物犯罪に係る不法収益の資金洗浄の犯罪化を義務づけている。(5)テロ
国連では第6委員会で審議。サミットの下にG8テロ専門家会合あり。イッシュー別に約10のテロ関連条約あり。(6)国連国際組織犯罪条約
93年以来毎年開催されている国連犯罪防止刑事司法委員会(経社理の機能委員会)において、96年末より、国際犯罪を包括的に取り扱う条約の作成が検討され、対象犯罪の範囲、資金洗浄(マネー・ローンダリング)、引渡・訴追、司法共助等幅広い事項が、国連の枠組みで議論されている。銃器や人の密輸といった犯罪も議定書の形で条約化される案も出ている。・日本の銃器分野におけるこれまでの貢献
(1)サミット
・リヨン・グループにおける銃器不正取引問題の検討を提唱し、当初からこの活動をリード。
・同グループ「銃器サブグループ」の議長国を引き受け、積極的にとりまとめ作業を行っている。(2)国連
・95年の国連犯罪防止会議(カイロ)で、我が国より銃器規制決議案「犯罪の防止と社会の安全のための銃器規制」を提出し、採択された。同決議に基づき、国連銃器プロジェクト(各国における銃器関連調査、調査結果の分析)を実施中。日本は同プロジェクトに資金拠出を行っている他、専門家を派遣した。なお、95年のカイロ決議に加え、国連犯罪防止刑事司法委員会において、同年~98年まで4年連続で関連決議を提出し、採択されてきている。(3)ICPO
・95年(平成7年)10月に中国・北京で開催されたICPO(国際刑事警察機構)第64回総会においても、銃器規制に関する決議を成立させるイニシアティブを採った。(参考)
1.G8における銃器規制等の状況※ 国連銃器規制国際調査による。イタリアは未回答。
殺人被害者数 人口10万人当たりの被害者数 銃器による殺人被害者数 人口10万人当たりの被害者数 イギリス 788 1.40 72 0.13 ドイツ 1,476 1.81 168 0.21 日本 752 0.60 34 0.03 ロシア データ無し データ無し データ無し データ無し カナダ 586 1.99 176 0.60 フランス 1,336 2.30 回答無し 回答無し アメリカ 23,692 8.95 16,524 6.24
銃器による殺人の比率 (%) 所有許可制度の有無 銃器所有被許可者 民間所有の銃器数(推計) イギリス 9.14 有 861,958 2,124,000 ドイツ 11.38 有 2,000,000 データ無し 日本 4.52 有 239,380 410,417 ロシア --- 有 回答無し 3,636,000 カナダ 30.03 有 600,000 7,100,000 フランス --- 回答無し 回答無し 回答無し アメリカ 69.75 無 該当無し データ無し
※ 国連調査では回答無しとなっているが、フランスにも、銃器の所有許可制度は存在する。
※ 米国の民間所有銃器については、約2億丁との推計がある。同国では、憲法に武器携帯の権利に関する規定があること、右権利の擁護を目的に掲げる強力なロビー団体(全米ライフル協会)があることなどから、銃器規制が非常に機微な政治的問題となっている。2.我が国におけるけん銃の押収状況
平成9年中におけるけん銃の押収丁数は1,225丁であり、このうち、暴力団からの押収丁数は761丁、暴力団以外からの押収は464丁であった。また、暴力団の武器庫(組織管理の下に3丁以上銃器が隠匿されている場所)の摘発は31事件、157丁であった。
昭63年 平元年 平2年 平3年 平4年 押収丁数 1,264 1,019 963 1,032 1,450 暴力団 1,160 943 918 954 1,072 構成比 91.8% 92.5% 95.3% 92.4% 73.9% 暴力団以外 104 76 45 78 378 構成比 8.2% 7.5% 4.7% 7.6% 26.1%
平5年 平6年 平7年 平8年 平9年 押収丁数 1,672 1,747 1,880 1,549 1,225 暴力団 1,196 1,242 1,396 1,035 761 構成比 71.5% 71.1% 74.3% 66.8% 62.1% 暴力団以外 476 505 484 514 464 構成比 28.5% 28.9% 25.7% 33.2% 37.9%
(出典:警察庁「日本の銃器情勢」)3.押収したけん銃の製造国別状況
平成9年中のけん銃の押収数1,225丁のうち、真正けん銃は1,064丁(86.9%)、改造けん銃は161丁(13.1%)であった。真正けん銃を製造国別に見ると、アメリカ製が374丁(35.2%)と最も多く、フィリピン、中国製がこれに続いている。
最近10年間の真正けん銃の押収数の累計は12,142丁に上るが、これらの約9割は、外国の銃器メーカーが海外で製造したものであり、この数字からも、我が国で押収されるけん銃のほとんどが海外から密輸されたものであることがわかる。押収した真正けん銃の製造国別状況の推移
平5年 平6年 平7年 平8年 平9年 アメリカ 469 489 591 436 374 フィリピン 103 140 169 159 122 中国 297 311 304 207 115 ブラジル 56 71 91 79 51 ベルギー 33 54 75 56 37 ドイツ 37 46 48 45 34 スペイン 23 67 50 40 26 イタリア 91 82 81 49 19 その他 247 253 293 329 286 合 計 1356 1513 1702 1400 1064 押収した真正けん銃の製造国別割合(平成9年)
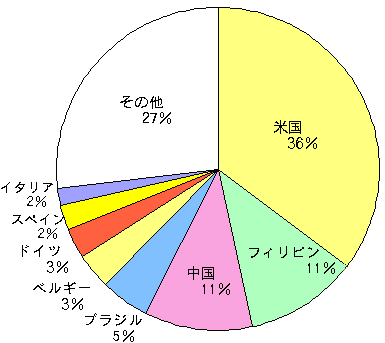
(出典:警察庁「日本の銃器情勢」)
(マネー・ローンダリング)1.マネー・ローンダリングとは
(1)マネー・ローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理すること。こうした犯罪収益が将来の犯罪活動に用いられること及び合法的な経済活動に影響を与えることが、国際社会に大きな脅威を与えていることから世界的に問題化。
(2)マネー・ローンダリングは世界経済のGDPの2~5%を占め、マクロ経済政策や銀行監督政策にも大きな影響を与えている(IMF推計)。
(3)マネー・ローンダリングは、規制が緩い国が抜け穴となって汚い資金が流れていくという性質から、各国が協調して取り組みを行うことが不可欠。
2.国際社会における取組み
(1)FATFの設置(Financial Action Task Force。金融活動作業部会)
ウイーン条約(麻薬新条約)等資金洗浄に関する取組みを受け、1989年のアルシュ・サミットにおいて、資金洗浄問題に対する追加的予防策を検討することを目的に召集された国際的な枠組み。現在のマンデートは、1999年までであるが、デンヴァー・サミットの結果(注)を受け、活動を更に5年間延長することで合意した。OECD内に事務局を設け、28ヶ国・地域及び国際機関(EC、GCC)が参加。日本は1998年後半から1年間FATFの議長国を務める。
(注)デンヴァー・サミットにおいて、FATFに対し、バーミンガム・サミットにてFATFの任務を5年間更新するに先立って、その活動内容及びメンバーシップの拡大を検討するよう指示がなされた。
- (2)FATFの主要な活動
- (イ)資金洗浄対策に関する「40の勧告」の実施状況監視
「40の勧告」は、普遍的に活用可能な資金洗浄対策の基本的な枠組みとして90年に策定(96年に改訂)されたものであり、刑事司法制度及び法執行制度、金融制度及びその規則、並びに当局間の国際協力を網羅している。- (ロ)新たな資金洗浄手法・対策の研究
- (ハ)非参加国への勧告実施慫慂
- (3)地域的取り組み
アジア・太平洋地域の資金洗浄対策については、FATFがこの地域における資金洗浄対策の促進及び域内諸国・地域に対する資金洗浄問題に関する啓蒙活動の一環として、数度のシンポジウム等を開催してきた。第4回シンポジウム(97年2月、於バンコック)にて、アジア・太平洋地域の資金洗浄対策の一層の推進を図るべく、より恒常的な対話の場としてアジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ(Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG))が正式に発足し、本年3月10~12日、第一回年次会合が東京において開催された。(APGメンバーは豪、バングラデシュ、フィジー、チャイニーズ・タイペイ、香港、印、日本、NZ、中国(参加調整中)、韓国、比、シンガポール、スリランカ、タイ、米、ヴァヌアツ。)3.我が国の取組み
(1)現在日本はFATFの中心メンバーとして、議事運営及びFATF活動の方向性の決定に携わっており、98年7月から99年6月までFATFの議長国を務める。
(2)前提犯罪拡大に伴う疑わしい取引届出制度の見直し及び金融情報機関(FIU)の設置96年6月の全体会合において「40の勧告」の改訂が行われ、資金洗浄罪の前提犯罪拡大が義務化された。これを受け、我が国としては、「組織的犯罪処罰法案」において資金洗浄罪の前提犯罪を薬物犯罪から一定の重大犯罪に拡大するとともに、金融機関等における疑わしい取引に関する情報を一元的に管理する金融情報機関(FIU)機能の金融監督庁への付与等を内容とする法整備を行うこととしている。同法案は3月13日に閣議決定され、国会に提出中。
(参考)FIU(Financial Intelligence Units、金融情報機関)
資金洗浄の捜査の端緒となる金融情報(疑わしい取引届出)を一元的に受理、分析、配布する組織。資金洗浄対策を効果的に実施するためには資金の動きを一括して把握しておくことが極めて重要であるとの観点から、その情報を一元的に受理、分析し、捜査当局等へその情報を提供するシステム構築の必要性が増大しているが、主要先進国ではFIUに当たる組織作りを早い段階から進めてきており(注)、FIU間での金融情報ネットワークを構築しようとする動きが進められている。
(注)G8において、FIUが設立されていない国は、日本、独、加(露は不明)であるが、日本、加においては、その設置が国会等において検討されている。 1.現状
(1)ハイテク犯罪やサイバーテロは、情報通信社会にとり大きな脅威となっており、その健全な発展のためにも適切な対策をとることが必要。特に各国が協力し、国際的な犯罪対策の穴を作らないことが重要。
(2)我が国としても、ワシントンにおける閣僚会合を踏まえ、ハイテク犯罪を捜査・訴追する能力の向上、法執行機関の体制整備、国際捜査協力の強化、法制度の検討等を進めることが重要。
2.リヨン・グループにおける成果
(1)「ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画」を採択
(G8司法・内務閣僚級会合(97年12月)(主要ポイント)
- (イ)24時間体制のコンタクトポイント設置(警察庁に設置済み。他省においても設置を検討中)
- (ロ)捜査力強化のための体制の整備
- (ハ)ハイテク犯罪捜査促進のための法制度の検討
- (ニ)産業界との協力
- (ホ)捜査共助要請に対する迅速な対応
- (ヘ)国際間の交信データの捜索に関する方策の検討・開発
- (2)24時間のコンタクトポイントについてディレクトリーを配布
(3)国境をまたぐ電子データの捜索・差押えについての原則を議論(継続)
3.産業界との協力
我が国政府も、産業界の意向聴取を開始。通信事業者による通信記録等のデータは捜査上唯一の手がかりであるとともに犯罪防止の観点からも重要な役割を果たすもの。通信事業者による通信記録等のデータの長期保存等にはコストがかかり、企業に負担を課すことになること(コンピューター容量(メモリ)との関係)、プライバシーの保護との関係等を踏まえ、今後検討していく必要がある。※
(1)経緯
国連国際組織犯罪条約は、国際組織犯罪に有効に対処するため、各国の法制度の相違や主権の問題による困難を克服し、資金洗浄対策、捜査・司法共助、犯罪人引渡、犯罪収益の没収等を対象とした条約を作成しようとの流れを受けたものである。本条約は、94年の組織犯罪に関するナポリ閣僚級会議、95年の第9回国連犯罪防止会議で取り上げられたのを受けて、国連における本件分野の専門家委員会である国連犯罪防止刑事司法委員会において過去4回審議が行われた。また、昨年12月の国連総会決議を受けて、本条約の正式な審議のための国連アドホック委員会が設置され、本年1月に第1回、3月に第2回委員会が開催されたところである。
(2)意義
- (イ)社会のグローバル化に伴い、銃器・薬物の取引、人の密輸などに関わる国際組織犯罪が近年増加している。我が国においても、このような傾向が明らかになっている。こうした犯罪は各国市民及び社会への脅威であるとともに社会の民主的及び経済的な基盤を損ないかねない。
従って、各国とも国際組織犯罪対策が急務となっている。このような国際組織犯罪の効率的な対策のためには、一国の努力のみでは限界があり、国際的な協力が重要である。しかし各国の法制度の相違や主権の問題もあり、これまで十分に効果的な協力が行われてきたとは言い難く、これに対しては捜査・司法共助、犯罪人引渡、犯罪収益の没収、処罰すべき資金洗浄行為の前提犯罪の拡大等を内容とした条約を作成しようという声が国際社会の中で高まっている。(ロ)本条約の内容については、現在検討中であるが、国際組織犯罪の特性をもふまえた犯罪処罰義務、刑事手続き、各国の協力の枠組み等を定めることを目指して検討されている。
(ハ)同条約の策定にあたっては、国際組織犯罪対策に大いに資するものにする必要がある。
- (3)国際組織犯罪条約と議定書の関係
特定の犯罪分野の対策に関しては、国際組織犯罪対策条約交渉を行う特別委員会において銃器、人の密輸、女性と児童の密輸の3分野に関し、同条約の議定書の策定作業を検討する旨の決議が採択された。今後は、条約本体の内容に応じてこれら3つの犯罪分野に関する対策を目的とする議定書の検討作業が進められていく見込みである。
(4)今後の我が方の対処ぶり
今後、2000年の採択を目指して条約審議のためのアドホック委員会は数ヶ月に1回の頻度で開催されていくこととなるが、国際組織犯罪を防圧するための各国の協力体制を築くことが極めて重要であり、我が国としてもこのような観点から本条約を有用で実効的な内容とすべく、同委員会のビューロー(起草委員会)の副議長として本件検討に積極的に関与していきたいと考えている。
I.薬物乱用をめぐる問題等
1.各薬物の乱用状況
(1)ヘロインは原料となる「けし」が「黄金の三角地帯」(タイ、ミャンマー、ラオス)及び「黄金の三日月地帯」(アフガニスタン、パキスタン、イラン)の主要生産地で栽培され、密造の後、タイ、中国、ベトナム、バルカン半島を通じ欧米各地に密輸され、乱用されている。
(2)コカインは、主にペルー、ボリビア、コロンビアの南米・アンデス諸国で生産され、キューバ等のカリブ地域を経由し米国等に密輸され、乱用されている。
(3)大麻については、世界各地に繁殖している麻の葉が大麻となる。麻は繁殖力も強く世界中で栽培され、最も広範に乱用されている。
(4)覚せい剤は、世界的にも従来のヘロイン、コカイン、大麻に加えて新たに乱用が広まりつつある傾向にある。我が国では戦後ヒロポンの名で乱用され(第一次乱用期)たことがあるが、現在は第三次の乱用期に入ったものと考えられている。また、我が国の薬物事犯の約9割が覚せい剤事犯である。
我が国に密輸されている覚せい剤の大半は、中国で漢方薬の材料として栽培されているマオウから作られたエフェドリンが横流しされて、中国本土、東南アジアで密造されたものである。2.その他の問題
(1)欧米、中南米の犯罪組織の活発化に伴い、薬物の不正取引を中心とした「資金洗浄(マネーローンダリング)」が大きな問題となってきていることや、薬物に対する需要自体を如何にして削減、抑制していくかの「需要抑制問題」、犯人引渡しや手続移管等のいわゆる「司法共助」のあり方をどうすべきかの問題、その他、薬物自体ではなくそれらの「原料物質統制」をどうするかの問題、薬物生産地における不正作物除去後の「代替開発」をどうするかといった問題等がクローズアップされてきている。これらは、その重要性から国連麻薬特別総会(麻薬特総)での採択文書に含まれている。
(2)更に、近年の大きな特徴として、薬物乱用者に対し従来までの処罰に代わり教育治療による対応(非刑罰化)推進を主張する国(ヨーロッパ諸国の一部)が増加している点も注視すべきである。
II.国連麻薬特別総会(麻薬特総)
1.国連麻薬特別総会は、本年6月8日から10日までクリントン米大統領、シラク仏大統領等31カ国の首脳を含む153カ国及び5国際機関代表が出席してニューヨーク国連本部において開催された。我が国からは、高村外務政務次官(当時)が首席代表として出席した他、関口警察庁長官ほか薬物関連省庁幹部が出席した。
2.高村政務次官(当時)は、代表演説において、去る5月26日に公表された我が国「薬物乱用防止5カ年戦略」を紹介するとともに、覚せい剤対策や青少年に対する世界的取組みの重要性、国連薬物統制計画(UNDCP)を中心とした国際協力、とりわけ我が国が推進している東南アジア地域への協力の重要性についても強調した。
3.同特別総会は、10日、最終セッションにおいて、「政治宣言」他の21世紀に向けた国際麻薬政策の道標となる文書を全会一致で採択した。
(参考)
1.国連薬物統制計画(UNDCP)
国連薬物統制計画(UNDCP)は、国連における薬物対策活動の中心機関として、国連内の薬物対策活動の調整、薬物関係条約の実施確保、各種の薬物対策プロジェクトの作成・資金提供等を行っている。2.薬物乱用防止五カ年戦略
総理を本部長とする薬物乱用対策推進本部が、我が国の中期的な薬物乱用防止対策の指針として定めたもの。現在が「第三次の覚せい剤乱用期」にあるという認識に基づき、その終息を図ることを基本目標としている。3.麻薬特総政治宣言概要
・麻薬問題に関する基本認識の表明と他の各作業文書の引用による関連性言及
・麻薬関係の国連条約への未加入国への加入呼びかけ
・2008年までの不正栽培作物の撲滅乃至重大な削減III.その他
1.国際的取り組み状況
(1)サミット
サミットでは、85年ボン・サミットで議題として取り上げられて以来、議長声明において国際協力の強化が強調されてきている。98年5月のバーミンガム・サミットでは、6月の麻薬特総は国際社会の決意を示すものと言及されている。(2)薬物関連諸条約の整備
国際的な薬物対策への取組みを強化すべく、従来より薬物関連諸条約の整備が進められてきている。1961年には麻薬単一条約を、1971年には向精神薬条約を、更に1988年には麻薬新条約をそれぞれ採択し、各国とも早期批准を進めている。
(わが国は既に上記3条約とも批准済み)2.我が国の取組み状況
(1)国連薬物統制計画(UNDCP)への活動支援
わが国は、91年度以来UNDCP(本部:ウィーン、事務局長アルラッキ(伊)。)には継続して資金を拠出。厳しい国内の財政事情にもかかわらず、引き続き可能な限り拠出増に努力する方針(94年度550万ドル、95年度600万ドル、96年度670万ドル、97年度500万ドルを拠出)。(2)国連支援募金活動
わが国は、93年より国内麻薬乱用撲滅啓発活動として(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターを中心に「ダメ。ゼッタイ運動」を開始し、同運動と並行し、国連を通じ世界各国で予防啓発活動を行うNGOに資金支援を行う目的で「国連支援募金活動」を実施。募金贈呈は全国から選出された中高校生で代表団(国連支援募金民間ヤング大使)を結成、94年度42万ドル、95年度50万ドル、96年度50万ドル、97年度5,000万円を寄贈した。・今後の課題・対策等(我が国を取り巻く問題)
(1)密航においては、国際的な密航ブローカーが我が国暴力団等と手を組み、犯罪ビジネスとして組織化する傾向とともに、その手法も貨物船やコンテナに潜伏する密航のほか、漁船を仕立てた集団密航が急増している。さらに、GPS等の装置を用い、洋上で会合し、日本漁船や韓国漁船を中国漁船からの密航者受取船として使用する事例など、その形態も巧妙化していきている。
(2)人の密輸と地下銀行は表裏一体であり、犯罪組織が介在する場合が多い。不法入国に際し、蛇頭や暴力団系の組織が関与し、不法入国請負・ほう助による手数料を収益源とする。犯罪によって得た収益は、地下銀行を通じて出身国等に送金され、また、蛇頭や暴力団の資金取り引きも地下銀行を通じて決済されている。
(3)旅券を偽変造する技術の巧妙化により、偽変造の発見が困難となっている。そのため、偽変造旅券の入手ルートの解明と取締りが必要である。
1.児童買春とは
広い意味では、児童買春とは、金銭等を供して(約束を含む。)児童から性的サービスの提供を受ける行為を言い、児童ポルノとは、児童を描いたポルノグラフィーを言う。これらは、いずれも児童の権利を著しく侵害する行為であり、児童の権利条約の採択(平成元年、わが国の批准は平成6年)以降、これらの問題に対する関心が内外で高まっている。
2.規制状況
わが国においては、児童買春・児童ポルノに関して、児童福祉法や青少年保護育成条例等の法令により規制がされているほか、13歳未満の児童が児童買春の対象となる場合には、刑法の強姦罪等の規定により処罰の対象となり、児童ポルノがわいせつ性を有すると認められる場合には、刑法のわいせつ図画頒布等罪の規定により処罰の対象となる。なお、現在、強姦罪等に該当しない児童買春の国外犯や、わいせつ性を有すると認められない児童ポルノの問題等に対処するための議員立法の動きがある。
3.組織犯罪との関連
児童買春・児童ポルノに金銭等を支払う小児性愛者は、組織犯罪が目をつけやすい資金源獲得対象であり、特に欧州においては、児童を商業的性的搾取の対象とする組織の存在が問題となっている(※事例)。また、わが国においても、例えば児童福祉法違反事件に係る検挙人員の21.0%が暴力団関係者であり(平成9年)、今後、児童買春・児童ポルノに係る法規制が整備されるにつれ、暴力団関係者や国際的組織犯罪の関与が更に問題となることが予想される。
4.取締状況等
児童買春・児童ポルノについては、現在、警察等において、関係法令を駆使した取締に努めているが、国内的には、いわゆる「援助交際」の延等、児童買春等の拡大が社会問題化している。
また、取締りと並行して、この種事案の潜在化を防止し、児童の立ち直りに資するため、児童が安心して相談や届け出ができる環境の整備や、カウンセリングなど必要な支援体制の整備に努めている。5.リヨン・グループにおける議論
法執行プロジェクト・サブ・グループのプロジェクトの一つとして検討されている。
※事例 (ベルギー連続少女誘拐殺害事件)
1995年(平成7年)6月、ベルギー東部のリエージュ市で当時8歳の少女2名が失踪、1年2ヶ月後に同国南部シャルロア地区に住む男の自宅裏庭から発見された。誘拐後監禁しレイプを繰り返して餓死させる残忍な手口であった。同事件をきっかけに性的搾取目的の国際的な人身売買組織の存在が明らかになり、逮捕者10名を出す全欧規模の事件となった。リヨン・グループでのその他の取り組み
リヨン・グループでは、特定の犯罪類型、犯罪組織を取上げ、捜査の経験、手法等につき情報交換、共同研究を行うことを目的に、種々のプロジェクトを取り上げ、ないし今後取り上げることとしている。例えば、ロシア東欧組織犯罪、児童ポルノ、盗難車両、支払いカード。
| 目次 |
|
| ||||||||||