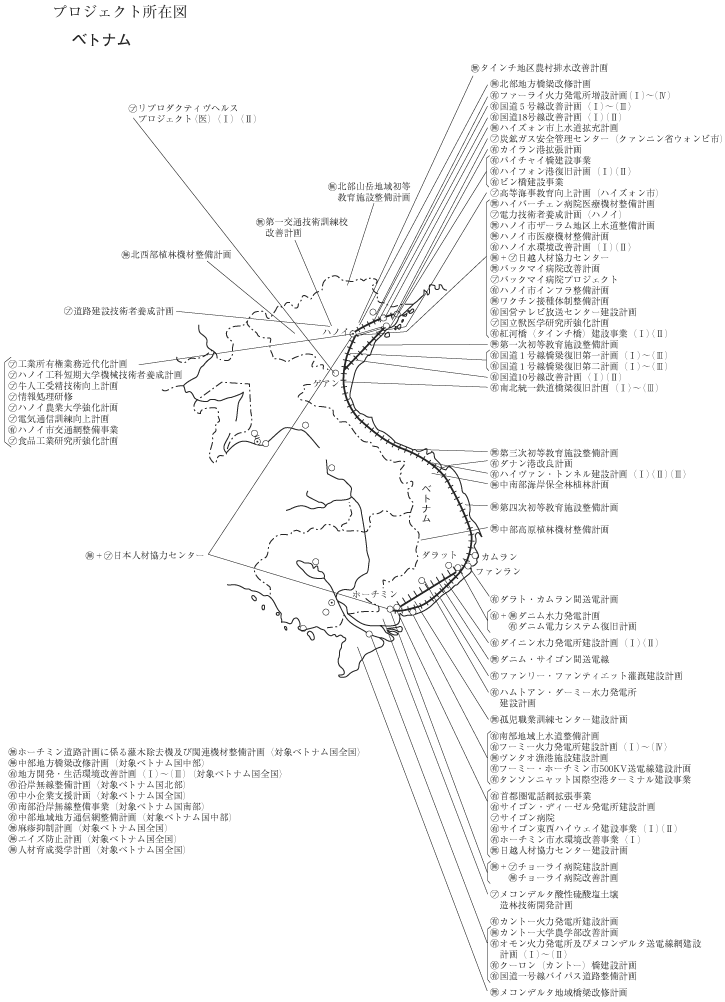我が国は、べトナムの安定はインドシナの平和と安定にとり極めて重要であること、人口約7,800万人を有し、また、一人当たりGDP(390米ドル、2000年、IMF)は低く、援助需要が高いこと、91年10月のカンボジア和平合意を受け、我が国が円借款を再開したことを契機に、両国関係は将来を見据えた新たな発展段階に入り、政治面、経済面のみならず文化面等でも緊密化しつつあること、86年より「ドイモイ(刷新)」路線の下市場経済化を推進するとともに、我が国を含む域内外諸国との関係改善・拡大を進めてきていること等を踏まえ、援助を実施している。
我が国は、2000年6月、今後5年間を目途とする具体的な案件形成の指針となる対越国別援助計画を公表した。同計画は、これまでの政策協議等によるベトナム側との政策対話等を踏まえ、各国の政治・経済・社会情勢の認識、また、開発計画や開発上の課題を勘案し策定されたものであり、以下の分野を援助の重点分野としている。
自立的・持続的発展のための基礎としての人造り・制度造りに対する支援が重要である。具体的には、持続的成長のための開発政策の立案・実施と人材育成、市場経済化に即応した行政体制、法制度の整備・金融システムの整備に係る支援が中核である。更に、次世代の人材育成を担う人材を確保しておくことも肝要である。
(ロ) 電力・運輸等の経済インフラ整備
将来的な需要の増加に対応するために、発電・送配電・地方電化等ハード面の整備に加え、効率的な事業計画、運営能力向上等ソフト面への協力を行っていくことが必要である。運輸分野では、越国内の基幹輸送網や地方道路の一層の整備とともに、周辺国等との物流の増加のための東西回廊等広域プロジェクトにも対応する運輸インフラ整備が重要である。
(ハ) 農業・農村開発
農家の多角経営、商業性を高めるべく側面支援することが必要。具体的には農業部門の生産性の向上と食糧増産、農産物の市場アクセスの確保を図るための支援とともに、農村工業化等経営多角化により、農村の余剰人口を吸収し、農家所得向上を図るための支援の検討が必要である。
(ニ) 教育、保健・医療
教育全体の就学達成度の向上を図るために、初等教育等における施設整備に加えて、学校の運営・管理へのアドバイス、教員訓練等教育の質的向上を図ることが重要である。保健・医療分野では、急速な経済成長の陰で対応が遅れている弱者保護、貧困対策の観点から、プライマリーヘルスケア(PHC)を中心とした保健医療サービスの拡充が急務である。また、ハノイの中核病院の機能強化及びエイズ対策等の地球的規模の視点に立った協力の拡充も必要である。
(ホ) 環境
ベトナムで深刻化している森林破壊や水質、大気、土壌の汚染に対する支援の検討が必要。またベトナム制定の環境保全法に実効性を与えるガイドラインや環境基準の整備が必要である。
2001年度のベトナムに対する援助実績は905.94億円。うち、有償資金協力は743.14億円、無償資金協力は83.71億円(以上交換公文ベース)、技術協力は79.09億円(国際協力事業団(JICA)経費実績ベース)であった。2001年度までの援助実績は、有償資金協力7667.33億円、無償資金協力は983.44億円(以上、交換公文ベース)、技術協力434.69億円(国際協力事業団(JICA)経費実績ベース)である。
(ロ) 有償資金協力
有償資金協力は92年から再開。持続的な経済成長のボトルネックとなっている運輸・電力といった経済インフラへの支援を中心としつつ、社会セクター、環境、人材育成、経済改革支援を実施している。99年度からは、向こう3年間のロングリスト方式(候補案件を列挙し、その中からベトナム政府が要請を行い、可能なものを採り上げる方式)を採用している。2001年度は、上記対越国別援助計画に基づき、運輸・電力分野を始めとする経済社会インフラ整備のため、計6案件に対する総額743.1億円の円借款を供与した。
(ハ) 無償資金協力
無償資金協力については、92年度に緊急かつ人道的考慮から「チョーライ病院改善計画」に対する協力を実施し、その他の分野においても本格的な支援を再開している。2001年度には、インフラ整備として「メコンデルタ地域橋梁改修計画」を実施したほか、教育分野、医療分野及び環境分野等への支援を行っている。
(ニ) 技術協力
技術協力についても援助再開後の92年度から急激に拡大し、協力分野は行政分野、市場経済関連をはじめ、保健・医療、農業、教育等幅広く人造りに協力しており、その援助総額(投入額)は全世界で2位(2001年度、JICA実績ベース)となっている。特に、日越首脳会談での合意を受け、95年度から2000年度まで石川滋一橋大学名誉教授を中心に政策策定支援のための開発調査「ベトナム市場経済化支援計画策定調査」(石川プロジェクト)を実施し、越政府に対しての政策提言を行ってきた。これらの提言は越第6次5ケ年計画(96年3月策定)、第7次5ケ年計画、10ケ年戦略(2001年4月策定)に反映され、高い評価を得ている。また、2000年度からは、ベトナムの市場経済移行を支える人材の育成のため、「人材協力センター」への支援を行っている。2001年度からは、初等教育セクタープログラム開発調査を実施し、ベトナムの初等教育分野に係る開発戦略策定の支援を行っている。
(ホ) その他
ベトナムにおいては援助国・機関の間での援助協議が盛んであり、20以上のパートナーシップ・グループ会合が存在している。我が国は、そのうち中小企業支援、運輸、ホーチミン市ODAといったグループ会合の共同議長を務める等積極的に参加してきている。また、UNDPの主催による定期的なドナー会合等も開催されている。ベトナム政府は、国家計画及び戦略に加え、貧困削減ペーパー(PRSP)策定作業を進めており、2001年3月に暫定(interim)版を、更に、その後の作業を踏まえ、2002年6月には最終(full)版を「ベトナム貧困削減成長戦略(CPRGS)」として策定した。なお、これら一連の援助活動の管理を支援し、国民に対する説明責任を果たすため、2001年度に国別評価を実施した。