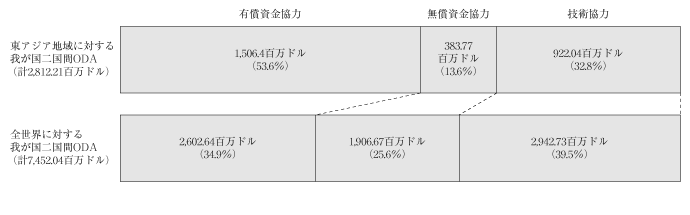東アジア地域に対する開発援助の重要性
東アジア地域は、我が国にとり近隣諸国として歴史的に密接な関係を有するのみならず、政治・経済両面において密接な相互依存関係を有する。この地域は、近年、経済危機の影響を受けたものの、世界の中で特に目覚ましい成長を遂げた地域であり、その経済発展の回復と維持が世界経済の発展のために重要であること、その一方で、環境問題や社会セクターの問題等の課題についての取り組みを強めていること、依然として貧困に苦しむ多数の人々が存在すること等、援助需要は多大である。
また、域内には経済の離陸に成功し、他の開発途上国を援助する国もあり、そうした国の発展の経験も活用し、より効果的な援助を行っていくことが必要である。97年12月の橋本総理(当時)のASEAN訪問の際には、21世紀に向けた我が国とASEANの新たな協力の柱として、様々なレベルでの相互交流の拡大・深化、国内改革・民間部門、通貨・金融安定、人材育成、競争力強化等、ASEAN経済への協力の推進、環境・保健・福祉向上・麻薬問題等の地球的規模の諸課題への協力の強化等が表明された。なお、ODA大綱及び平成11年公表された政府開発援助に関する中期政策(ODA中期政策)においても引き続き重点地域と位置付けている。
我が国の東アジア向け援助の基本方針
我が国は、経済を含む多くの面でこの地域と特に密接な関係を有しており、今後とも、所得水準や市場経済の段階、更には社会状況や自然状況の異なる東アジアの多様な状況を踏まえ適切な支援を行う必要がある。
東南アジアの中で近年まで高い成長を示していた諸国については、現下の困難な状況を乗り越え順調な経済発展を回復し、政治的・社会的な安定を維持し得るよう支援することが我が国にとり重要である。また、依然所得水準の低いインドシナ諸国やモンゴルについては、貧困削減に取り組むとともに、これら諸国の市場経済への移行及び持続的な成長を引き続き支援していく必要がある。更に、12億を超える人口を抱え、その動向が世界的に大きな影響を与え得る中国については、その改革・開放路線を支援し、国際社会のより一層建設的なパートナーとなるよう促すとともに、国内の地域間格差是正や環境問題等に重点を置きつつ支援していく必要がある。東アジア地域においては広域的な開発への取り組み、地域協力の深化と拡大が進みつつあるほか、他の開発途上国への支援を開始したいわゆる「新興援助国」が登場しており、このような動きを支援していく必要がある。
以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。
経済構造調整をはじめとした経済危機克服と経済再生のための支援
国民生活及び国内の安定に資するための社会的弱者への積極的支援
裾野産業育成や適切な経済・社会運営のための人材育成と制度造り等の支援
貧困対策、経済・社会インフラ整備、環境保全対策、農業・農村開発における各国の実績に応じた援助の実施
地域における広域的な開発(ASEAN域内協力、APEC地域協力、メコン地域開発等)の取組及び「南南協力」への支援
経済危機克服のための援助
アジア経済危機の克服は我が国経済回復にも深く関わる課題であり、我が国として引き続き積極的にアジア経済の回復に関わっていくとの立場から、99年11月の日・ASEAN首脳会議で、小渕総理(当時)は小渕イニシアティヴ(人材育成・交流の強化(小渕プラン(既述))、社会的弱者支援、ASEAN発展のための協力、経済再生基盤強化・情報化時代への対応のための協力、海賊問題への対応)を表明した。
ASEAN諸国のように急速な経済成長を遂げてきた諸国への援助は、より高度な技術移転や人造りの支援に加え、民間部門活性化への公的資金の活用、環境問題や地域間・階層間格差などの経済開発によってもたらされた歪みの是正、保健・医療等の基礎生活分野に力点を置く。特に、新宮澤構想や特別円借款等を活用した支援策のほか、社会的弱者に対する影響に対しては引き続き支援を行っていく。
地域の多様性及び発展段階に応じた具体的援助
我が国は、国により経済の発展段階が大きく異なる東アジア諸国に対し、各国の実情に応じ、きめ細かい援助を実施している。
インドシナ諸国及びモンゴル(貧困国)
LDCであるラオス、カンボジアについては基礎生活分野・基礎インフラ整備に対する無償資金協力や技術協力が中心となっている。また、ベトナムについては、インフラ整備を中心とした有償資金協力、基礎生活分野を中心とした無償資金協力を並行して進めている。モンゴルを含むこれら諸国に対しては市場経済化への移行も引き続き支援している。
中国(低所得国)
環境など地球規模問題への対処、改革・開放支援、相互理解の増進、内陸部の生活環境改善等の貧困克服、民間の経済関係拡大のための環境整備などを実施している。
インドネシア(貧困国)、フィリピン(低所得国)
有償資金協力や無償資金協力、技術協力により社会開発分野や人造り、経済基盤整備、貧困対策、環境分野などへの幅広い協力を実施している。
タイ(中所得国)
原則として無償資金協力は行わず、貧困対策や地域格差是正などの社会開発分野及び経済基盤整備や環境分野などに対する有償資金協力や比較的高度な技術協力を実施するとともに、周辺諸国に裨益する地域協力の拠点国となっている。
マレーシア(中進国)
有償資金協力について、近年の急激な経済成長に伴って生じた歪みの是正を目的とする案件(環境改善など)を対象に検討を行うこととしている。
シンガポール、ブルネイ(高所得国)
96年よりDAC援助受取国・地域リストパートIからパートIIへと移行したことに伴い、技術協力に限り実施しているODAを3年間の経過期間中逓減させていき、98年度をもって終了した。
南南協力
我が国は、開発途上国間における協力である「南南協力」への支援を積極的に推進している。東アジア地域における事例としては、以下のようなものが挙げられる。例えば、我が国は、ASEAN諸国の協力を得てカンボジアにおいて農村開発プロジェクト(いわゆる三角協力)を現在実施しているが、これは、UNDPへの我が国拠出金を活用してASEAN諸国の専門家をカンボジアに派遣し、我が国から派遣される専門家、青年海外協力隊と共同で技術協力を実施するものである。このほか、TICAD(アフリカ開発会議)プロセスを通じ、アジア・アフリカ協力の推進にも力を入れており、2000年5月にはアジアの開発経験についての交流を目指す第3回アジア・アフリカフォーラムが、同年10月にはアジア・アフリカ間の直接投資と貿易の促進を図るため「アジア・アフリカ・ビジネス・フォーラム」が、マレーシアでそれぞれ開催された。
また、98年度はインドネシアの南南技術協力センターに対し、無償資金協力による機材整備を実施した。更に、比較的高い発展段階にある開発途上国と対等な立場で他国を援助するために、シンガポールとの間では「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム」を、また、タイとの間では「日本・タイ・パートナーシップ・プログラムII」を、更に、フィリピンとの間では2002年1月の小泉総理のASEAN諸国訪問の際、「日・比パートナーシップ・プログラム」枠組み文書について署名した。これらの「パートナーシップ・プログラム」においては、専門家の共同派遣、第三国研修のコース数や費用負担等に関する中期的な目標・計画を設定し、総合的な協力を実施しており、今後とも、このようなパートナーシップ・プログラムを暫時拡大していく予定である。
更に、「国際寄生虫対策」として、タイのマヒドン大学にWHOとも協力して人材育成と研究活動のためのセンターを設置し、周辺諸国の技術者に対する研修等、アジアにおける寄生虫分野の南南協力の推進拠点となっている。
復興開発支援
騒乱や紛争によって国家の基本的な枠組みが破壊され、現地政府がないか、あるいは統治能力が極めて脆弱化した国や地域(いわゆる破綻国家)への支援が国際社会の大きな課題となってきており、我が国は、平和の定着と国造りへの取組に対し、積極的に貢献している。2002年5月の東ティモールの独立は、我が国を初めとする国際社会の協力が効果的に発揮された成果といえる。これまでに我が国は、99年に第1回東ティモール支援国会合を開催するとともに、支援国として最大の3年間で約1億3千万ドルの支援を表明し、着実に実施してきた。また、独立直前に開催された第6回支援国会合では独立後3年間で6千万ドルを上限とする支援を行う旨表明するなど、東ティモールの自立に向けた国造りの努力を積極的に支援している。
ODA大綱原則の運用状況
東アジア地域においても、我が国はODA大綱の原則に従って援助を実施してきている。すなわち、民主化、経済自由化・開放政策といった好ましい動きに対しては、大綱の原則に照らしてODAを通じてもそのような好ましい動きを積極的に促進している。例えば、これまでにインドシナ総合開発フォーラム閣僚会合、モンゴル支援国会合、カンボジア復興国際委員会(ICORC)、カンボジア支援国会合をそれぞれ主催する等、これら諸国に対する国際的支援の枠組みの構築においても主導的な役割を果たしている。
中国に対しては同国の核実験実施を受け、95年8月、核実験停止が明らかにならない限り、対中無償資金協力を原則凍結するとの措置を採ったが、96年9月より中国が包括的禁止条約(CTBT)に署名したこと等を踏まえ、97年3月より無償資金協力を再開している。その後は、改革・開放政策に基づく近代化努力の継続、国連人権規約への署名、国防白書、人権白書の発表等、好ましい動きも見られる。国防費については、発表された国防予算以外にも不透明な部分があると言われており、また、近年の国防予算の伸び率が高い水準で推移していることから、今後の動向を注視していくと共に、あらゆる機会を捉えて中国の国防政策の透明性を高めるよう働きかける必要がある。
ミャンマーに対しては、2002年度は、BHN分野の4案件約20億円の一般プロジェクト無償の他、専門家派遣、研修員受入れを中心とした技術協力、債務救済、草の根無償、文化無償を実施した。しかし、2003年5月30日にアウン・サン・スーチー女史がミャンマー政府に拘束された状況に鑑み、基本的に新規案件の実施を見合わせているが、緊急性が高く、真に人道的な案件等については、個別に慎重に吟味した上で順次実施している。