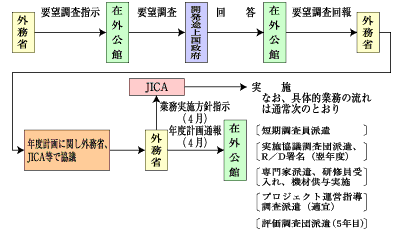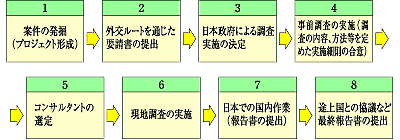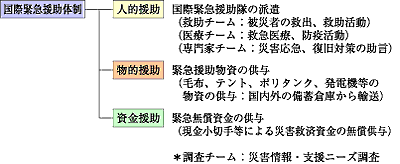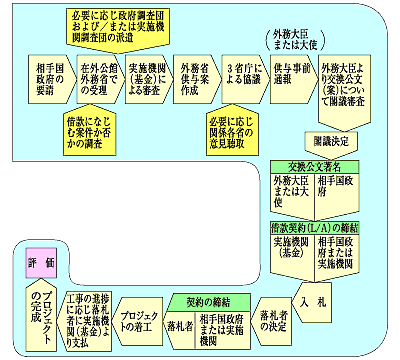(1) 総説
無償資金協力は、被援助国に返済義務を課さずに資金を供与する援助である。
この形態の援助は、開発途上国の中でも比較的所得水準の低い諸国を中心として実施している。具体的な供与対象国は、その国の経済社会開発状況と開発需要、日本との二国間関係、要請案件の内容等を総合的に考え合わせ、必要な調査を実施の上決定している。同時に、援助実施対象国の決定に際しては、国際開発協会(IDA)の無利子融資適格国基準を一応の目安としており、2000年度については、98年の一人当たりGNPが1,460ドル(ただし、文化無償については5,280ドル―世銀統計)以下の国を原則的に無償資金協力の供与対象国としている。
対象分野としては、基本的には収益性が低く、借款で対応することが困難な医療・保健、衛生、水供給、初等・中等教育、農村・農業開発等の基礎生活分野(Basic Human Needs、BHN)、環境、及び人造り分野が大きな柱となっている。
- (イ) 一般無償資金協力
- (i) 一般プロジェクト無償
一般プロジェクト無償は、幅広い分野におけるプロジェクト型の無償資金協力を行うものである。対象分野は民生・環境改善、通 信・運輸、医療・保健、教育・研究、農林業に大別される。但し、これまで基本的に円借款で対応してきた道路、橋梁、港湾、通 信等経済インフラについても、LLDCを中心とする開発途上国の経済インフラの悪化等を考慮し、個別 の状況に応じて協力の対象に組み込んできており、一般プロジェクト無償の対象分野は多様化している。 - (ii) 債務救済無償
債務救済無償は深刻な債務返済困難に直面する開発途上国に対し、円借款債務の返済があった場合に、返済額の一部または全部に相当する金額を無償資金協力として供与するものである。78年、国連貿易開発会議(UNCTAD)の特別 貿易開発理事会(TDB)において、多くの開発途上国が深刻な債務返済困難に直面 していることに鑑み、先進援助供与国がこれらの国に対し債務救済措置をとるよう決議されたことを受けて開始した。具体的には、後発開発途上国(LLDC、対象国20ヶ国)から円借款(87年度以前交換公文締結分)の債務が返済された場合には、返済された元利合計額と同額の無償資金を供与し、石油危機で最も深刻な影響を受けた開発途上国(MSAC、対象国6ヶ国)から円借款(77年度以前締結分)の債務が返済された場合には、金利の調整額(約定利息をより低く設定した場合に生じたであろう差額分)に相当する無償資金の供与を行っている。98年度より、従来より債務救済無償を実施してきているLLDC5ヶ国(ウガンダ、ギニア、タンザニア、マラウィ、モーリタニア)については、97年度の交換公文締結分まで救済対象債務を拡大し、また、新たにマリ、ザンビアに対し、88年度から97年度までの交換公文締結分の円借款債務を対象に債務救済無償を実施することとした。
なお、98年度より、IMF・世銀により、一定基準を満たし、債務負担が継続不可能な状態にあると認められた国を対象に、当初16年間は利子返済分、据置期間以降は返済される元利合計額と同額の無償資金を供与する重債務貧困国支援無償を予算化した。99年6月のケルン・サミットで合意されたケルン債務イニシアティブに基づく債務救済は、重債務貧困国支援無償の供与の形で行われることとなる。- (iii) 経済構造改善努力支援無償(ノン・プロジェクト無償)
ノン・プロジェクト無償は、累積債務の増大、国際収支赤字拡大等の経済困難が深刻化している開発途上国が、世銀・IMFの指導の下に経済構造調整政策を推進していく上で緊急に必要とする物資の輸入を支援するものである。この援助は国際収支支援の性格を有し、即効性が期待されている。
また、被援助国政府は、わが国が援助資金(外貨)を供与することによる内貨の余剰分を積み立て(見返り資金)、わが国と使途につき協議の上、経済・社会開発に資する事業に使用することができる。
98年度より、被援助国が社会開発や環境問題の分野別計画を進めている場合、見返り資金をこれら計画に集中的に使用する「環境・社会開発セクタープログラム無償」を新設した。
- (iv) 草の根無償
草の根無償は、開発途上国の地方公共団体、研究・医療機関及び開発途上国において活動しているNGO等からの要請に対し援助を行うものである。従来の政府間における無償資金協力では対応が困難であった比較的小規模な案件に対し、当該途上国の経済・社会状況等の諸事情に精通 している日本の在外公館が迅速かつ的確に対応することにより、開発途上国の多様な需要に対応できるようにすることを狙いとしている。
- (iii) 経済構造改善努力支援無償(ノン・プロジェクト無償)
- (ロ) 水産無償
開発途上国の水産振興に寄与するために、漁船、漁具、漁業訓練施設、訓練船、漁港施設、水産研究施設建設等の水産関係案件に協力するための資金供与である。 - (ハ) 緊急無償
- (i) 災害緊急援助
海外における自然災害及び内戦の被災民や難民・避難民等の救済のために緊急に供与される人道的資金援助である。被災民等への救済活動に資するための資金を直接被災国政府に対し供与する場合と、世界食糧計画(WFP)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等の国連機関や日本赤十字社、赤十字国際委員会(ICRC)等の国際的な援助実施機関に対し供与する場合がある。
災害が発生した場合、直ちに現地の日本大使館や国際機関からの情報及び被災国政府あるいは国際機関の要請を踏まえ、被害の規模、日本としての援助の必要性等を総合的に考慮した上で、供与金額、内容を決定する。災害緊急援助の実施は緊急性を要することから、その他の無償資金協力の手続とは違った、極めて迅速化された手続によって決定、実施されている。 - (ii) 民主化支援
開発途上国における選挙等の民主化促進事業を成功させるために必要な投票箱、投票ブース、投票用紙等にかかる費用につき、途上国政府あるいは選挙等を実施管理している国際機関を通 じて支援するものであり、95年度より開始している。 - (iii) 復興開発支援
和平成立後地域紛争から復興に向けて努力している国において、通常の二国間経済協力が実施可能とするような国内情勢の安定が得られるまでの間、復興に向けた足どりを確かなものとすることを目的に、国際機関あるいは国際機関設立の信託基金を通 じた資金援助として復興開発支援を96年度より開始している。 - (iv) NGO緊急活動支援無償
近年、自然災害や内戦等により発生した多数の被災者・難民等を救済するための国際緊急援助活動において、高い機動性を有するNGOの役割の重要性が高まっていることを受け、わが国NGOの緊急人道活動を支援するため、2000年度より新たに開始した。 - (ニ) 文化無償
- (ホ) 食糧援助
- (ヘ) 食糧増産援助
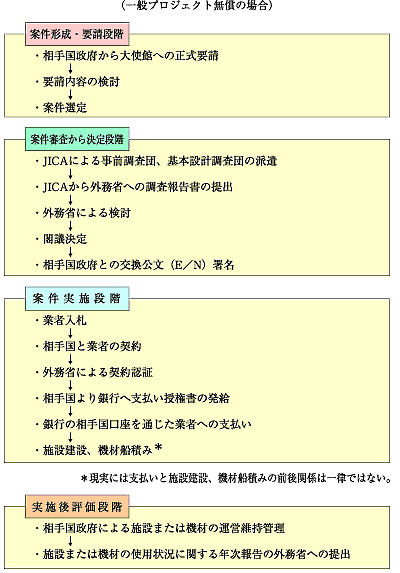 |
文化無償は、文化交流に関する国際協力の一環として、75年度より開始された。これは社会の経済的な発展とともに、開発途上国等において固有の文化の維持・振興に対する関心が高まり、文化面 を含む広い視野からバランスのとれた国家開発の努力がなされていることから、こうした努力に対し協力するものである。具体的には、開発途上国等における文化財及び文化遺産の保存活用、文化関係の公演及び展示の開催、並びに教育及び研究の振興のために使用される資機材の購入に必要な資金の供与を行う援助であり、1件につき5,000万円以内で実施されることになっている。
食糧援助は、食糧不足に直面する開発途上国に対し、小麦、米、メイズ等の主要穀物を購入するための資金を供与するものである。日本の食糧援助は、食糧援助規約に基づいて実施されており、日本は小麦換算で30万トンの年間最小拠出量 を義務づけられている。
食糧増産援助は、食糧自給達成に向け努力している開発途上国の増産計画を支援するものとして、肥料、農薬、農業機械等農業機材の購入に必要な資金を供与するものである。