(1) 国連開発計画(UNDP)
UNDPは、国連システムにおける技術協力活動の中核的資金供与機関である。途上国132ヶ国に常駐代表事務所を置き、その広範なネットワークを通じ、各国政府及び他の国際機関、NGO等と協力して、175の国や地域で6,000件を上回る開発プロジェクトを実施している。UNDPは、「持続可能な人間開発」(Sustainable Human Development, SHD)を開発の基本原則に掲げ(94年執行理事会で承認)、貧困撲滅、女性の地位向上、良い統治の確立、環境保全及び紛争後等特別な状況下での開発の5分野に活動の重点を置いている。そして、途上国がこれら5分野においてSHDを達成しうるよう、各国のキャパシティ・ビルディング(能力開発)向上に焦点を当て、途上国のニーズに即した援助を実施している。特に貧困撲滅を最重要課題に位置づけており、UNDPのコア・ファンドの90%が、一人当たり国民所得が900ドル以下の途上国向けに充てられている。
UNDPの活動資金は、各国からの任意拠出により賄われており、99年の拠出金総合計(コア・ファンド、トラスト・ファンド等を含む)は、19億8,000万ドルであり、そのうち、使途の特定されないコア・ファンドは6億8,000万ドルである。UNDPでは、各国からの拠出金見込み額をベースに、原則3年毎に向こう3年間の国別援助割当額を定め、これをもとに、各国のUNDP常駐代表事務所が中心となって、援助の重点分野や主要プロジェクトの概要を示した国別協力フレームワークを策定し、その上で、被援助国政府及び他のドナー国等との協議を踏まえて具体的なプロジェクトを確定する(99年の日本のコア・ファンド拠出金は8,000万ドルで、全コア・ファンドに占める率は11.7%(2位)となっている)。コア・ファンド以外にも、日本は、UNDP内に「日本・UNDP人造り基金」、「日本パレスチナ開発基金」等の使途を特定した基金を設置し、それぞれの設立目的別に援助を実施している。
国際的な人道援助・災害救済活動が必要とされる緊急事態に対して国連が適切に対応するための調整機能を改善するため、97年12月、第52回国連総会決議(52/168)が採択され、国連人道問題調整事務所(UNOCHA)が設置された。
UNOCHAは現在、世界各地の人道問題に対処するため、災害の情報収集及び分析に努めると共に、UNHCR、WFP、UNICEF等それぞれの分野で知見を有する人道援助機関が相互に協力して効率的に支援を行えるよう各国連機関の活動を調整することを目的としている。そのため国際社会に対して国連統一アピールを発出し人道援助のための協力を要請したり、また、人道援助機関間における人道に関する課題を国際社会に啓蒙するなど、人道問題の解決に積極的に取り組んでいる。近年では、コソヴォ、東チモール、アフリカの各地域等の紛争、またアフガニスタンの干魃、モザーンビークの洪水等の自然災害による人道危機に際し国連統一アピールが発出されており、国際社会もこれに対して支援を行っている。
(4) 国際移住機関(IOM)
第二次世界大戦後間もなく、欧州、中南米における移民・人口・難民問題解決のために発足した国際機関であり、現在では難民等の輸送活動をはじめ、人の移動に関わる支援を幅広く世界中で行っている。
(5) 赤十字国際委員会(ICRC)
スイス人アンリ・デュナンの提唱により、1863年に設立された。人道・公平・中立等の国際赤十字、赤新月運動の基本原則を掲げ、紛争地域において中立かつ独立の機関として紛争犠牲者等に対する保護・医療・水供給・衛生活動・食糧・衣料等の援助、離散家族間の通信等の活動を行う他、国際人道法の発展・普及のための活動を行っている。
1996~97年の在ペルー日本大使公邸占拠事件においては、水、食糧、医薬品の搬入等の人道的な支援を行うとともに、中立的な立場から犯人グループとペルー政府の対話・交渉の仲介を行い、多大な貢献を果たした。
5. 地球規模問題他
(1) 国連人口基金(UNFPA)
67年に設立されたUNFPAは、家族計画、人口問題についての啓発・教育、人口基盤データの収集等の分野における各国政府、援助機関、研究機関に対する資金の供与、技術提供を行っており、94年9月カイロで開催された「国際人口開発会議」のフォローアップのための中心機関として、最近では特に人口と環境のかかわり、女性の地位の向上といった分野に努力を傾けている。99年6月には上記「国際人口開発会議」の5年後のレビューを行う目的で、UNFPAが事務局となって国連人口開発特別総会が開催された。日本は、71年に拠出を開始して以来、地球規模の取り組みが求められている人口問題の重要性に鑑み、UNFPAの活動を積極的に支援しており、86年から99年までは最大拠出国となっている。
(2) 国連薬物統制計画(UNDCP)
91年、地球規模で深刻度を増している麻薬問題に対処するために、三機関(国連麻薬委員会、国連麻薬統制委員会、国連麻薬統制基金)の事務局機能を統合するものとしてUNDCPが設立された。
UNDCPの役割としては(1)薬物に関する情報・ノウハウの集積機関としての役割、(2)適切な薬物対策を勧告するため、麻薬に係わるあらゆる状況の進行の予測、(3)各国政府に対し薬物統制のあらゆる方向にわたる技術援助の供与の三つがあげられる。
また、日本は、UNDCPの活動を支援するため、2000年は338万ドルの任意拠出を行い、国連を通じた薬物対策に積極的に取り組んできている。
(3) 国連環境計画(UNEP)
72年にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を受けて同年の国連総会決議により設立されたUNEPは、環境問題に関する国連内外の事業に関し総合調整を行うとともに、自らも地球環境のモニタリング、調査、情報収集、情報提供、条約作成作業等の事業や活動を行っている。
(4) 世界保健機関(WHO)
1946年にニューヨークで開かれた国際保健会議が採択した世界保健憲章(48年4月7日発効)によって設立された、保健衛生分野における国連の専門機関である。「すべての人が可能な最高の健康水準に到達すること」(憲章第1条)を目的とし、国際的な保健事項に関し指導、調整の役割を果たしており、疾病対策、衛生、栄養問題等の分野での技術協力の促進、医薬品等の国際的な基準作り、保健分野の研究促進等様々な活動を行っている。日本は51年の加盟以来、財政面及び人的な面で積極的な支援、協力を行っている。99年の日本の分担金は約7,220万ドル(分担率19.665%)で米国に次いで第2位である。
67年に設立されたUNFPAは、家族計画、人口問題についての啓発・教育、人口基盤データの収集等の分野における各国政府、援助機関、研究機関に対する資金の供与、技術提供を行っており、94年9月カイロで開催された「国際人口開発会議」のフォローアップのための中心機関として、最近では特に人口と環境のかかわり、女性の地位の向上といった分野に努力を傾けている。99年6月には上記「国際人口開発会議」の5年後のレビューを行う目的で、UNFPAが事務局となって国連人口開発特別総会が開催された。日本は、71年に拠出を開始して以来、地球規模の取り組みが求められている人口問題の重要性に鑑み、UNFPAの活動を積極的に支援しており、86年から99年までは最大拠出国となっている。
(2) 国連薬物統制計画(UNDCP)
91年、地球規模で深刻度を増している麻薬問題に対処するために、三機関(国連麻薬委員会、国連麻薬統制委員会、国連麻薬統制基金)の事務局機能を統合するものとしてUNDCPが設立された。
UNDCPの役割としては(1)薬物に関する情報・ノウハウの集積機関としての役割、(2)適切な薬物対策を勧告するため、麻薬に係わるあらゆる状況の進行の予測、(3)各国政府に対し薬物統制のあらゆる方向にわたる技術援助の供与の三つがあげられる。
また、日本は、UNDCPの活動を支援するため、2000年は338万ドルの任意拠出を行い、国連を通じた薬物対策に積極的に取り組んできている。
(3) 国連環境計画(UNEP)
72年にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を受けて同年の国連総会決議により設立されたUNEPは、環境問題に関する国連内外の事業に関し総合調整を行うとともに、自らも地球環境のモニタリング、調査、情報収集、情報提供、条約作成作業等の事業や活動を行っている。
(4) 世界保健機関(WHO)
1946年にニューヨークで開かれた国際保健会議が採択した世界保健憲章(48年4月7日発効)によって設立された、保健衛生分野における国連の専門機関である。「すべての人が可能な最高の健康水準に到達すること」(憲章第1条)を目的とし、国際的な保健事項に関し指導、調整の役割を果たしており、疾病対策、衛生、栄養問題等の分野での技術協力の促進、医薬品等の国際的な基準作り、保健分野の研究促進等様々な活動を行っている。日本は51年の加盟以来、財政面及び人的な面で積極的な支援、協力を行っている。99年の日本の分担金は約7,220万ドル(分担率19.665%)で米国に次いで第2位である。
図表―153 国連人口基金(UNFPA)主要拠出国一覧(コア拠出)
図表―154 国連環境計画(UNEP)主要拠出国一覧
図表―155 世界保健機関(WHO)主要拠出国一覧
WHOは80年に天然痘の撲滅を果たして以来、ポリオ、メジナ虫症等の撲滅に向けて着実な成果を上げており、ポリオは、欧州地域、アメリカ地域に次いで西太平洋地域においても2000年10月に根絶を確認する宣言が出された。
98年7月に就任したブルントラント事務局長(元ノールウェー首相)は、途上国の開発のためには保健向上が不可欠との考えから、エイズ、結核、マラリア等の感染症対策に極めて熱心に取り組んでおり、世銀等関係国際機関や民間、NGO等幅広い関係者の参画を得るなど、国際的な保健問題への関心を高めている。我が国も地球規模問題イニシアティヴ等を通じて途上国の感染症問題に積極的に取り組んできたが、2000年の九州・沖縄サミットにおいてG8各国の感染症対策の一層の強化と先進国、途上国、国際機関、民間、NGOとの間で「新たなパートナーシップ」を確立するべく中心的な役割を果たした。また、同年12月には九州・沖縄サミットのフォローアップとして、「感染症対策沖縄会議」が開催された。
日本のODAとの協調実績としては、WHOの拡大予防接種事業の中で大きな比重を占めているポリオ根絶計画に関し、WHO西太平洋地域事務局管内での2000年の根絶宣言に向け着実に成果を挙げた。90年には5,991例あった同地域内のポリオ報告例はその後激減し、上述の通り2000年10月にはWHOより同地域内の野生ポリオ・ウィルス発生終息宣言が出された。西太平洋地域でのポリオ根絶計画が、継続的な日本の支援と協力を通じて初めて可能となったことは、被援助国のみならず、支援国、国際機関の間で広く認識され、評価されている。日本のODAによる全国一斉投与経口ポリオワクチンの供与、冷蔵・運搬機材及び車両等の供給は、WHOの助言、要請を基に当該国政府との二国間政府協力の形で実施されている。
(5) 地球規模問題他
(イ) 国際原子力機関(IAEA)
アイゼンハワー米大統領(当時)の提唱を受けて、1957年に発足した国際原子力機関(IAEA)は、「全世界における平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、増大するように努力する」こと(原子力の平和利用)並びに機関の「援助がいずれかの軍事目的を助長するような方法で利用されないことを確保する」こと(核不拡散)を2大目的としている(IAEA憲章第2条)。(開発途上国への)技術協力は、IAEAの任務のひとつである原子力の平和利用を促進するための主要な一手段であると位置づけられている。
技術協力に関する財源は、技術協力基金、締約国からの特別拠出及び締約国によるイン・カインド(現物拠出)からなり、そのうち技術協力基金は、技術協力の財源全体の93%(1999年)を占めている。技術協力基金は、技術協力の財源の安定的確保を図るため1961年及び1971年の総会における決議(経済的先進国は基本分担率相当を負担する)に基づき設立され、各締約国の拠出は義務的経費として認識されている。
98年7月に就任したブルントラント事務局長(元ノールウェー首相)は、途上国の開発のためには保健向上が不可欠との考えから、エイズ、結核、マラリア等の感染症対策に極めて熱心に取り組んでおり、世銀等関係国際機関や民間、NGO等幅広い関係者の参画を得るなど、国際的な保健問題への関心を高めている。我が国も地球規模問題イニシアティヴ等を通じて途上国の感染症問題に積極的に取り組んできたが、2000年の九州・沖縄サミットにおいてG8各国の感染症対策の一層の強化と先進国、途上国、国際機関、民間、NGOとの間で「新たなパートナーシップ」を確立するべく中心的な役割を果たした。また、同年12月には九州・沖縄サミットのフォローアップとして、「感染症対策沖縄会議」が開催された。
日本のODAとの協調実績としては、WHOの拡大予防接種事業の中で大きな比重を占めているポリオ根絶計画に関し、WHO西太平洋地域事務局管内での2000年の根絶宣言に向け着実に成果を挙げた。90年には5,991例あった同地域内のポリオ報告例はその後激減し、上述の通り2000年10月にはWHOより同地域内の野生ポリオ・ウィルス発生終息宣言が出された。西太平洋地域でのポリオ根絶計画が、継続的な日本の支援と協力を通じて初めて可能となったことは、被援助国のみならず、支援国、国際機関の間で広く認識され、評価されている。日本のODAによる全国一斉投与経口ポリオワクチンの供与、冷蔵・運搬機材及び車両等の供給は、WHOの助言、要請を基に当該国政府との二国間政府協力の形で実施されている。
(5) 地球規模問題他
(イ) 国際原子力機関(IAEA)
アイゼンハワー米大統領(当時)の提唱を受けて、1957年に発足した国際原子力機関(IAEA)は、「全世界における平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、増大するように努力する」こと(原子力の平和利用)並びに機関の「援助がいずれかの軍事目的を助長するような方法で利用されないことを確保する」こと(核不拡散)を2大目的としている(IAEA憲章第2条)。(開発途上国への)技術協力は、IAEAの任務のひとつである原子力の平和利用を促進するための主要な一手段であると位置づけられている。
技術協力に関する財源は、技術協力基金、締約国からの特別拠出及び締約国によるイン・カインド(現物拠出)からなり、そのうち技術協力基金は、技術協力の財源全体の93%(1999年)を占めている。技術協力基金は、技術協力の財源の安定的確保を図るため1961年及び1971年の総会における決議(経済的先進国は基本分担率相当を負担する)に基づき設立され、各締約国の拠出は義務的経費として認識されている。
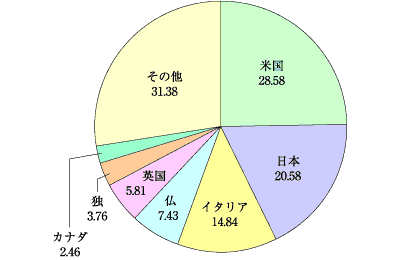 |
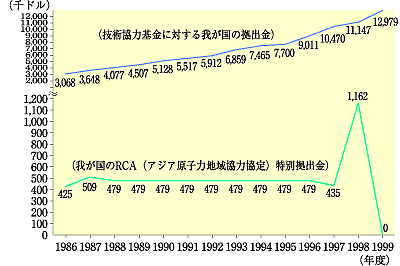 |
現在、実施されている技術協力プロジェクトは約700件。プロジェクトの分野は、1999年実績で支出額の多い順にヒューマン・ヘルス分野(21%)、原子力安全(20%)、食料・農業分野(16%)、海洋環境・水資源・工業(15%)、物理・化学分野(13%)、人材開発及び能力向上(5%)、核燃料サイクル及び廃棄技術(4%)、原子力(4%)、その他(2%)。地域別には、1999年実績で欧州地域(25.5%)を筆頭に、アフリカ地域(23.1%)、東アジア・太平洋地域(19.3%)、中南米地域(17.0%)、西アジア(10.5%)、地域横断的プロジェクト(4.6%)。 事業種類の内訳は、専門家派遣、機材供与、訓練コースの開催等である。
日本は、99年には約1,300万ドル(20.58%)を拠出している。
日本は、99年には約1,300万ドル(20.58%)を拠出している。
前ページへ 次ページへ