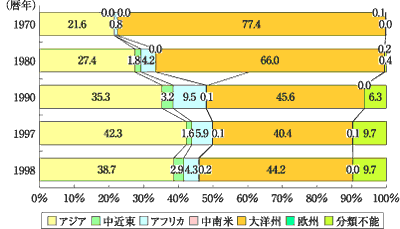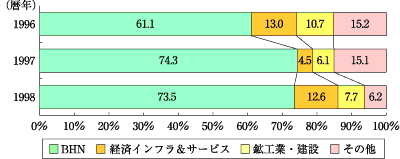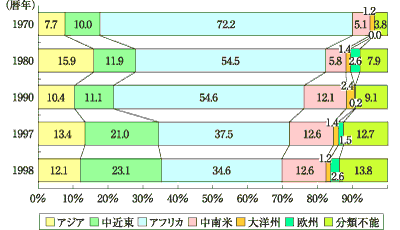(1) 援助政策等
オーストラリアでは、96年3月に行われた総選挙の結果13年ぶりに保守連合政権が発足した後、選挙公約通り援助政策の大幅な見直しが行われた。現政権は、前労働党政権時代の「オーストラリアの商業的利益に則した援助」という政策を批判し、「貧困対策を中心とした人道的援助」というスローガンの下に、比較的小規模できめの細かい援助に焦点を当てて援助政策を実施している。
具体的な援助政策の見直しについては、従来の援助政策を総合的に見直すことを目的として設置されたサイモンズ委員会が97年5月にまとめた援助評価報告書(「サイモンズ・レポート」)を受け、同年11月豪州政府が公表した「Better Aid for a Better Future」と題する文書の中に示されている。この文書においては、援助政策の目標を「途上国の貧困を削減し、持続可能な発展を達成することにより、オーストラリアの国益を前進させる」ことに置き、重点分野として(イ)保健、(ロ)教育、(ハ)インフラ整備、(ニ)農村開発、(ホ)良い統治の5分野を挙げるとともに、パプア・ニューギニア、太平洋島嶼国、東アジア等のアジア太平洋地域を重点地域としている。さらに、途上国における女性の地位向上及び、環境問題を重視するとともに、今後とも国際機関および従来から援助実施において主要な役割を果たしているNGOとの連携を戦略的に進めることも方針として記されている(2000/01年度予算においては、援助総額のうち、国際機関を通じた援助は約22%、NGOを通じた援助は約3%を占めている)。
99年の実績は9.82億ドル(DAC報告ベース)で、GNP比は0.26%であった。2000/01年度予算(2000年7月から2001年6月まで)における援助総額は15億9,900万豪ドルで、前年度予算に比べて4%の増加となっている(対GNP比は0.25%)。2000/01年度予算の内容は、上記の「Better Aid for a Better Future」の指針・原則を引き続き実現するものとされている。さらに、2000/01年度予算においては、アジア太平洋地域の長期的な開発のニーズに焦点を当て、この地域の政治、経済、社会的変化に対応することを目指すとしており、具体的な施策としては、東チモール復興支援としての4年間での1億5,000万豪ドルの支援表明、総額1億2,000万豪ドルの対インドネシア支援、新援助条約に基づくパプア・ニューギニアに対する約3億豪ドルの支援などが含まれている。
(2) 実施体制
74年に、それまで各省庁の下に個別に存在していた援助部門を統合して、オーストラリア開発援助庁(ADAA)を設置したものの、外務省との意思疎通の欠如が問題となり、77年外務省が吸収し、その後外務省(87年より外務貿易省)の外局(AIDAB)になった。さらに、95年3月、ODA活動の国民的理解を深めるという目的から、呼称を
オーストラリア国際開発庁(AusAID:Australian Agency for International Development)に変更した。前労働党政権時代には、開発協力大臣(閣外大臣)がAusAIDを所管していたが、現政権下においては同ポストは廃止されたため、AusAIDは外務大臣が所管している。
韓国はDAC加盟国ではないが、近年、開発途上国に対する援助を活発化している。また、
アフリカ開発会議(TICAD)やアジア・アフリカ・フォーラムといった援助協議にも積極的に参加しており、韓国としての支援策を表明するなど活発な動きが見られる。
日本との関係では、これまで、韓国は日本が主催するカンボディア復興閣僚委員会、モンゴル及びインドネシア支援国会合に参加したほか、93年には日韓の間で初めて実務者レベルの援助政策協議を開催し、また、95年には日・米・韓三国間の援助政策協議を行い、99年には韓国において日韓共同で
第三国研修を実施する等、協力関係も進みつつある。
(1) 援助政策等
韓国の援助対象国は、韓国より一人当たり国民所得の低い開発途上国であり、開発途上国の自助努力と人的資源開発を支援するとの原則に基づいて決定される。援助対象国としては、大部分の開発途上国を含むが、韓国と関係の深いアジア諸国に重点が置かれている。援助対象分野としては、経済インフラの他、教育、水供給などの社会インフラを重視しているが、今後は、情報格差の解消や女性の能力開発といった分野にも対象を広げる方向で検討を行っている。
99年のODA実績は、3億1,750万ドルであった。韓国は、ODAのうち国際機関を通じた援助が占める比率が高く、国際機関を通じた援助の大部分が
世銀グループ等国際機関への出資により構成されるため、毎年、この出資実績に従って、ODA実績が左右される状況にあった。最近は、ODA借款の供与の増大に伴い、二国間援助の割合が増大する傾向にあり、97年末の通貨・金融危機の影響から98年は一時的に減少したものの、この傾向は今後も続くと思われる。また、通貨・金融危機の結果、98年度はODA実績が対前年比で減少したところ、今後は、被援助国との外交・通商関係や人道的な側面を考慮しつつ、被援助国の実状にあった効率的な援助政策を目指している。
(2) 実施体制
韓国は、60年代半ばから研修員受入等の小規模の技術協力を実施し、77年からは無償援助を開始した。87年7月には、「
対外経済協力基金(EDCF)」を設立し、開発途上国への借款供与も行っている。この機関の業務は、途上国向け借款、海外投融資資金貸付に大別され、監督・管理は財政経済部が担当し、実務は韓国輸出入銀行内の経済協力基金部が担当している。89年からは韓国海外青年奉仕団派遣事業が開始された(90年より実際の派遣開始)。91年には、それまで各所管官庁別に実施してきた途上国協力事業を外務部(現在の外交通商部)に統合し、外務部の下に無償資金協力と技術協力を担当する実施機関として「
韓国国際協力団(KOICA)」を設立した。なお、KOICAの実員は2000年2月現在で173名である。
(1) 援助政策等
EU(欧州連合)は、開発協力をその対外政策の一環として位置づけ、EU加盟各国の二国間援助の調整に加え、欧州共同体(European Community(EC))としての援助の強化に努めている。
EU条約は、EUの開発協力の目的を、(イ)途上国、特に最貧国の持続可能な経済力・社会的発展、(ロ)途上国の世界経済への円滑且つ漸進的な統合、(ハ)途上国の貧困削減、(ニ)民主主義と法の支配の発展と強化、人権及び基本的自由の尊重、と規定している(177~181条)。
EUのODA総額(ディスバースメント・ベース)は、日、米、仏、独に次ぐ世界第5位であり、また、世銀グループに次ぐ世界第2の国際援助機関である。93年~97年の5年間のODA総額の増加率は平均3.3%とDACで報告されている。なお、98年のODA総額は、45億9,500万ユーロであり、前年に比べ1%減少した(DAC統計値)。
(イ) アフリカ・カリブ・太平洋(ACP)71カ国に対する援助
EUは伝統的に加盟国の旧植民地諸国に対する援助を重視しており、過去10年間の援助額の平均で約4割がACP諸国(African, Caribbean, and Pacific Countries)向けであり、その内約78%がサハラ以南のアフリカ諸国向けである。また、EUとACP諸国の間では、貿易及び経済協力に関する枠組協定としてのロメ協定が75年2月から2000年2月まで継続されたが、同年6月にベナンのコトヌで同協定の後継となる新協定(ACPとEUのパートナーシップ協定)が署名された。新協定の期間は20年で、資金協力の予算規模としては第9次EDF(2000~2007年)として135億ユーロと
欧州投資銀行(EIB)からの17億ユーロの合計の152億ユーロが合意された。新協定の特色は、政治対話、貿易、経済協力における関係を規律し、これまでの旧宗主国と旧植民地国の関係に基づく構造を打破し、新たなパートナーシップを求めていくことであり、長期的(2020年)にはACPとEU間で自由貿易地域の形成を目指している。
(ロ) アジア、ラテン・アメリカ、地中海・中東に対する援助
財政議定書(5年毎に改定)に基づきEU通常予算及びEIBより実施。98年統計では、ECの援助額(コミットメント・ベース)に占めるアジア、ラテン・アメリカ、地中海・中東の各地域向けの援助の割合はそれぞれ7.2%、5.6%、15.9%である。
(ハ) 中東欧、NIS諸国に対する援助
中東欧の市場経済移行国向けの技術・資金協力スキームであるPHARE(中東欧12カ国を対象)及び旧ソ連諸国向け技術支援スキームであるTACIS(旧ソ連12カ国及び94年以降モンゴルが対象)という特別の枠組みにより実施されている。99年の援助額(コミットメント・ベース)は、PHARE15億1,520万ユーロ(99年推計値)、TACIS4億6,250万ユーロ(99年推計値)となっている。また、2000年から、新規加盟候補国(主としてEU側が候補国と認定した中東欧10カ国)に対して新たな援助枠組みが実施されている。この支援枠組みはPHARE(従来のPHAREを改訂)、ISPA(運輸及び環境分野での支援)及びSAPARD(農業及び農村開発分野での支援)の3つのプログラムからなり、2000年から2006年までの7年間について中期財政枠組み(支援上限設定)が採択されている。各項目の予算規模は、PHARE(年15億6,000万ユーロ)、ISPA(年10億4,000万ユーロ)及びSAPARD(年5億2,000万ユーロ)であり、7年間で総計218億4,000万ユーロとなっている。
(ニ) 食糧援助
EU通常予算より二国間援助とNGOや国際機関を通じた援助を実施。98年の食糧援助総額(コミットメント・ベース)は、6億9,000万ユーロであり、EUの援助総額に占める割合は、8.2%である。
(ホ) 緊急・人道援助
EC通常予算及び一部EDF資金等の財源から、欧州共同体人道局(ECHO:European Community Humanitarian Office)が実施。ECの緊急・人道援助予算は、大規模な紛争や自然災害が生じた場合は、理事会の決定により予算の積み増しが可能となっており、93年から96年にかけては旧ユーゴスラヴィア地域や大湖地域の紛争、99年はコソボ紛争に対する緊急・人道援助のため、ECHO予算が大幅に増額された。98年の緊急・人道援助総額(コミットメント・ベース)は、9億3,600万ユーロであり、ECのODA総額の10.9%を占めている。
(ヘ) 地域協力への支援
EUは開発途上国における地域協力への支援にも積極的に取り組んでおり、西アフリカ経済通貨同盟、中部アフリカ経済関税同盟、南部アフリカ開発共同体、インド洋委員会、カリコム、メルコスール等に対して支援を行っている。