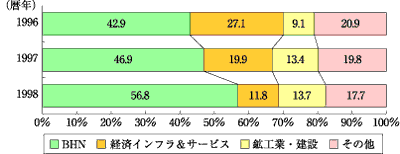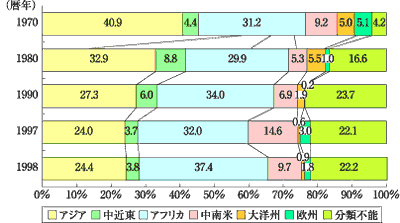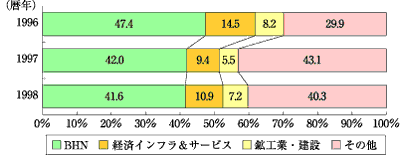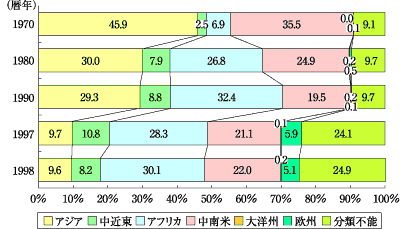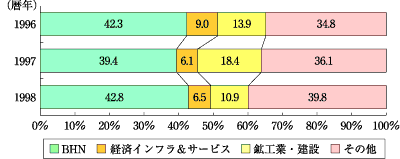(1) 援助政策等
近年、ドイツの財政事情が更に厳しくなったことに加え、東西対立の終焉によりイデオロギーが開発戦略の要素でなくなったため、援助全体の大幅な見直しが行われてきた。その一環として、91年10月には新たな援助政策の基準が発表された。そこでは、(イ)人権の尊重、(ロ)政策決定過程への住民参加、(ハ)法の支配、(ニ)市場指向型経済の創出、(ホ)貧困克服を目指す被援助国政府の開発促進のための政策の5つが、援助を供与する最重要な基準として設定されており、また、援助受取国の軍事支出の対GNP比、武器輸入の輸入総額に占める割合等、開発途上国の防衛支出も援助の際に考慮に入れることとされている。
また、96年、
経済協力省(BMZ)は、84年に策定された援助政策コンセプトを改定し、貧困削減、環境保全、資源保護、教育及び人材育成を経済協力の重点分野としている。また、援助の効率性を重視し、援助案件の的確な事後評価を行う方針を明らかにしているが、同時に、難民問題や緊急援助の関連にも留意することとなっている。
このほか、90年代にはドイツの二国間援助に占める環境案件の割合は3割近くを占めるに至っており、また、貧困削減、ジェンダー問題への取り組みも強化されつつある。
ODAの実績で見ると、これまで厳しい予算上の制約にもかかわらず、援助の拡充に努めてきたが、99年の実績は55.15億ドル(DAC報告ベース)となり、前年と比較して約1.2%減少した。対GNP比は0.26%であった。なお、この数値には、90年の東西統一以降に引き継がれた旧東独の援助案件も含まれている。
二国間援助と国際機関を通じた援助のODA全体に占める割合は、99年には59.4%対40.6%となっている。
98年の二国間援助の内訳を見ると、技術協力が56.9%、無償資金協力等が38.0%、借款供与が5.0%となっている。97年のグラント・エレメントは97.2%となっている。
(2) 実施体制
二国間援助、国際機関を通じた援助あるいは資金協力の如何を問わず、BMZが、援助計画の企画・立案を掌所している。予算は、外務省に計上されている緊急援助予算等を除き、原則としてBMZに計上されている。個々の案件の決定に当たっては、外交政策の面から外務省、予算面から大蔵省、その他必要に応じて経済省等の省庁と協議する。実施に当たって、資金協力については復興金融公庫(KFW)、技術協力については技術協力公社(GTZ)が中心的役割を果たす。
(1) 援助政策等
英国は、途上国における貧困撲滅を援助の最終目標として掲げ、このために貿易、投資、債務、農業、環境等関連分野をも統合した総合的見地から途上国の開発支援を目指している。この目的達成のための具体的アプローチとして、(イ)開発課題の明確化、(ロ)パートナーシップの構築、(ハ)政策の整合性、(ニ)開発への理解と支援の確立より構成される「開発に関する白書(1997 White Paper on International Development)」が97年11月に発表された。
また、この白書では、(イ)貧困層とのパートナーシップの確立、(ロ)他のドナー国、国際機関、民間、ボランティア部門、研究機関との連携強化、(ハ)貧困国に対する政策の一貫性を確保するための他省庁との連携強化、(ニ)開発に関する知見、資源の効果的、効率的利用等の具体的施策を通じ、特に、(イ)持続可能な生活促進のための政策、(ロ)貧困層の人々への教育、医療の改善、(ハ)自然環境の保全、改善等を重点分野として掲げている。
援助対象国としては、98/99年度では二国間援助の73%が低所得国に集中しており、特にサハラ以南アフリカ等の低所得国、LLDCを重視している。
また、かつて広範な地域に植民地、自治領を有してきたことから、その歴史的関係を踏まえ、旧英連邦諸国に対する援助が58.2%と大きな比重を占めていることも特徴である。
99年の英国の援助実績(DAC報告ベース)は、34.01億ドルであり、対前年比11.98%の減少となっている。英の援助は原則として無償(うち技術協力が二国間援助の43%(98/99年度)を占める)であり、97/98年平均で贈与比率、グラント・エレメントともに各々95.8%、100%となっており、援助の質は国際的に見ても高いものとなっている。また、調達に関して、二国間援助におけるアンタイド率は79.6%(98年)とDAC諸国中9位に位置するが、DACアンタイド化議論の中でも主導的な立場をとっている。
英国の援助に占める多国間援助の比率は約50%と高く、中でもEUを通じた援助が63%と過半を占めるのも大きな特徴で、このため、英国はEUの援助及び国連等国際機関を通じた援助の効率的実施を重視し、国連機関の統廃合等にも積極的である。
また、99年12月には重債務貧困国向け非ODA債権(19億ポンド)の100%放棄を発表するなど、途上国の債務救済に関しても積極的である。
援助予算に関しては、2000年7月、包括的歳出見直しをうけ、2000/01年度の31億1,500万ポンドから2003/04年度には35億6,000万ポンドに増加し、対GNP比についても同期間中0.29%から0.33%に増加する見込みである。
また、英国には、古い歴史と確固とした組織基盤を持ったNGOが多数存在するが(約130)、英国政府はかかるNGOを災害援助、ボランティア派遣等の面で積極的に支援しており、98/99年度では1億8,200万ポンド(前年度比1,000万ポンド増)の援助をNGO経由で行うなど重要な援助チャンネルと位置付けている。
(2) 実施体制
英国の政府開発援助は、援助政策の立案から実施まで閣内大臣を有する
国際開発省(Department for International Development:DFID)の責任の下に一元的に行われている。また、貿易、投資、債務、農業、環境等途上国の開発問題に関する政策の一貫性を確保すべく、国際経済政策課(the International Economic Policy Department)を通じて他関係省庁との連携にも力を入れている。
DFID職員は99/2000年度で1,212名、海外事務所は11ヶ所(ケニア、ジンバブエ、南ア、タンザニア、ウガンダ、タイ、インド、バングラディシュ、ネパール、バルバドス、フィジー)となっている。DFIDは海外事務所への権限委譲が進んでおり、200万ポンドまでの案件で政策的判断が必要とされる場合以外の案件の発掘・形成は現地で行われている。
なお、DFIDの関連組織として、開発途上国の民間部門に対するローン、株式投資の形態による支援を担当する英連邦開発公社(The Commonwealth Development Corporation)、人材育成分野での援助を実施するブリティッシュ・カウンシル(The British Council)があるとともに、97年3月に民営化された援助の資材・サービスの調達等を実施するクラウン・エージェンツ(Crown Agents)等がある。
(1) 援助政策等
オランダは援助政策の基本方針として、96年に、援助の効果的・効率的実施を目指して、「Aid in Progress」を発表した。ここでは、(イ)援助政策の外交政策への統合、外務省とその他関係省庁の間での政策の整合性(decompartmentalisation)、(ロ)国・地域毎ではなく、主要な援助分野に従った二国間援助の方向付けと、可能な範囲でのプロジェクト援助からプログラム援助への移行、(ハ)オーナシップとパートナーシップに基づき、各国事情を反映した国別アプローチの強化、(ニ)人間開発分野(特に貧困削減と社会開発)への取り組み強化、(ホ)評価・モニタリングの強化をオランダの新たな援助方針として打ち出している。
また、オランダ政府は、開発援助の効果的・効率的実施の観点から、99年に「新二国間援助政策(New Bilateral Aid Policy:Targeting the Poorest Countries)」を発表した。新二国間援助政策は、長期的な支援を行う「二国間構造援助(structural bilateral aid)」と「テーマ別援助(Theme-based aid)」等に分類している。
二国間構造援助の対象国としては、社会・経済政策、ガヴァナンス、貧困レベルの三つの基準に基づき、17ヶ国
(注)が選定されており、本年9月、経済政策、ガヴァナンス等の観点から進展が見られたとして、ザンビアをこれに加え、計18ヶ国とすることが決定された。
また、「テーマ別援助」では、環境プログラム、人権・平和構築・「良い統治」、民間セクター開発(主にオランダ製品輸出促進)の三分野を取り挙げ、各々の分野で特別に支援が必要と思われる国々を対象国として選定している。
オランダの経済協力実績は、99年には31.34億ドル(DAC報告ベース)で、金額では世界第6位の援助国となっている。ODAの対GNP比では0.79%である。93年以降は、借款をすべて贈与に切り替えるなど途上国援助に対する国民及び議会の理解は深い。さらにNGOによる援助活動も活発であり、経済協力予算の約9.4%はNGOを通じて実施されている。なお、予算の規模について、従来は国民所得の1.5%を割り当てることとしていたが、近年これを国民総生産の0.81%と改めている。地域的にはサハラ以南のアフリカや中南米、ヨーロッパなどへの援助が多い。
(2) 援助実施体制
援助の基本的枠組みは、外務省(援助政策に従事する職員数は99年当初で287名、専任の開発協力大臣が存在)が各省と調整の上作成、発表する。具体的な援助案件は外務省を含め各省において実施している。
各省間の調整の必要が生じた場合、国際協力問題関係各省連絡会議(議長は外務省国際協力総局長)及びその上部組織たる関係大臣会合(議長は開発協力大臣)が開催され、これらの場で調整が図られている。両会合において各省の権限は等しく、仮に複数省庁間の調整が事務レベルでつかない場合は大臣レベルで決着がつくまで調整が行われる。これらの会合には執行予算を持たない経済省も参加する。ちなみにODA予算の約9割が外務・大蔵の両省に計上され、残り1割が合計9省に分散計上されている。
経済援助実施上の手続代行機関として、オランダ開発途上国投資銀行(NIO:オランダ国立投資銀行(NIB)の100%出資の機関)があり、二国間援助すなわち贈与の支出を政府に代わって行っている。