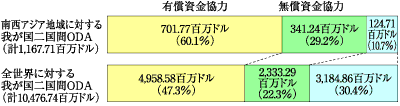(1) 南西アジア地域の位置付け
南西アジア地域の貧困人口は5億人を超え、世界で最も貧しい地域の一つである。域内各国は困難な経済社会問題に直面しながら国内開発に取り組んでおり、援助に対する需要は高い。また、我が国との間には伝統的に友好関係が維持されており、同地域に対し経済社会インフラ整備から基礎生活分野に至る幅広い分野で積極的に支援している。我が国としては、引き続き南西アジア地域を援助の重点対象地域として位置付け、援助を行っている。
同時に、ODA大綱の原則(被援助国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向、民主化の努力等に注意を払う)に十分留意していく必要がある。この点に関し、核兵器開発の可能性に対する我が国及び国際社会の懸念を踏まえ、これまでにインドとは93年3月、94年1月及び95年8月、パキスタンとは93年2月、11月及び95年1月にそれぞれ協議を行い、核不拡散条約(NPT)への加盟、包括的核実験禁止条約(CTBT)への署名・批准を働きかけるとともに、核関連プログラムの透明性を高めるよう求めてきた。更に、インドに対しては、ヴァジパイ政権成立後の98年3月、橋本総理(当時)よりヴァジパイ首相に対し、親書においてインド側の自制を働きかけてきた。
しかし、98年5月11日、インドは地下核実験を実施したため、我が国はインドに対し核実験の即時中止及び核兵器開発の停止、並びにNPT及びCTBTへの早期加入を求めるとともに、新規無償資金協力の停止(緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く)、98年6月に東京で開催を予定していた対インド支援国会合(IDF)の我が国での開催見合わせ等を内容とする措置をとった。インドは、更に2日後の同13日、二度目の地下核実験を実施したため、核実験及び核兵器開発の中止を繰り返し強く求めるとともに、新規円借款の停止、国際開発金融機関による対インド融資について慎重に対応すること等を決定した。
更に、パキスタンに対しては、インドに対抗して核実験を行うことのないよう総理特使を派遣し最大限の自制を行うよう働きかけた。しかしながら、パキスタンは、98年5月28日及び30日に地下核実験を実施したため、我が国はパキスタンに対し、インドに対してと同様に、核実験及び核兵器開発の即時中止、NPT及びCTBTへの無条件の参加を求めるとともに、援助に関しては新規無償資金協力の停止(緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く)、新規円借款の停止、国際開発金融機関による対パキスタン融資について慎重に対応することを内容とする措置を決定した。
98年6月のG8外相会合で合意された世銀等の国際金融機関による基礎生活分野(BHN分野)以外の対パキスタン融資の審議延期に加え、主要各国による経済措置を受け、もとより不安定であった経済情勢が急速に悪化する中、パキスタンのシャリフ首相は98年9月の国連総会で99年9月までにCTBTに参加する旨を表明した。一方、インドのヴァジパイ首相も98年9月の国連総会でCTBTに署名する可能性を示唆し、99年2月にはインド首相として10年ぶりにパキスタンを訪問し、シャリフ首相との首脳会談に臨み、両首脳は「ラホール宣言」を発出する等、緊張緩和及び信頼醸成への取り組みを進めた。
98年11月のパキスタン外相訪日の際、99年9月までのCTBTへの参加、及び核・ミサイル関連資機材・技術の厳格な輸出管理に向けた国内法制化への着手の2点について明確な意図表明があったことから、我が国はパキスタンの経済的窮状にも鑑み、例外的措置として、他のG8諸国と協調してIMFによる緊急的な対パキスタン支援パッケージを支持するとともに、上記の通り、表明された措置の実施が確認されれば、二国間経済協力の部分的な再開を検討しうる旨表明した。我が国は、99年1月に日印次官級政務協議を行い、CTBTへの署名・批准等核不拡散への取り組みを強く申し入れたほか、同年11月にはジャスワント・シン外相、2000年1月にはフェルナンデス国防相が訪日し、同年2月には橋本外交最高顧問・元総理が訪印するなど二国間ハイレベルの対話を継続している。また、2000年8月には、森総理が南西アジアを訪問した際、インド、パキスタン両国にCTBT署名等を改めて求めたのに対し、両国からCTBT発効まで核実験モラトリアムを継続する旨の確認を得た。これに対し、我が方の経済措置を見直すことはしなかったが、我が国は両国への一部経済協力継続案件を進める旨を先方に伝え、CTBT署名等に向けての一層の努力を求めた。
(2) 援助対象分野
南西アジア地域では、貧困に苦しむ多数の人口を抱えていることから、貧困対策に資する保健・医療、教育等の基礎生活分野の援助に対する需要は大きい。こうした分野に対しては、無償・技協のほか、NGO事業補助金や草の根無償によるきめ細かい援助により対応しており、人口・エイズの問題や「途上国の女性支援」(WID)へ配慮しつつ協力を行っている。人口・エイズについては地球的規模の問題として重視し、プロジェクト形成調査団の派遣等により積極的な案件形成に努めている。また、子供の死亡率改善の観点から、ポリオ等の予防接種を進めるなどの「子供の健康」への協力も進めている。WIDの関連では、国連の統計によれば、南西アジアは世界で妊産婦死亡率、識字率の男女格差の最も大きい地域の一つとなっており、我が国としてもこの地域での女性支援を強化していく必要がある。
また、南西アジアに対する我が国からの民間直接投資は増加傾向にあるものの、各国の経済社会インフラ、投資環境の未整備のために未だ低い水準にとどまっていることから、インフラ整備等への援助が呼び水となり、民間直接投資の促進に資することが期待されている。
環境問題については、我が国はODA大綱において重点的に取り組んでいくことを表明しているが、南西アジア地域においても人口増加、貧困等を原因とした森林破壊や都市の生活環境悪化が見られる。こうした問題に対しては、従来より、森林保全や上下水道などの居住環境改善、また洪水対策など防災等の分野に対する協力を行ってきており、今後も拡充・強化していく方針である。
(3) 政策対話の推進
南西アジア諸国への援助に伴う問題点としては、援助対象国の政府部内の調整体制が一般的に不十分なこと、ローカル・コストを賄う予算が恒常的に不足していることなどが挙げられる。こうした状況に対し、我が国としては、現地日本大使館及びJICA事務所・JBIC事務所を通じ、援助政策、実施上の問題点及びニーズの把握のための対話・協議に常時努めている。またこれに加え、各国との経済協力政策協議、各種調査団の派遣などの機会にも被援助国との緊密な対話に努めている。
政府は、これまでに、インド、バングラデシュ、パキスタン、スリ・ランカ、ネパールに対し、経済協力総合調査団を派遣し、中長期的観点から相手国との政策対話を行っている。