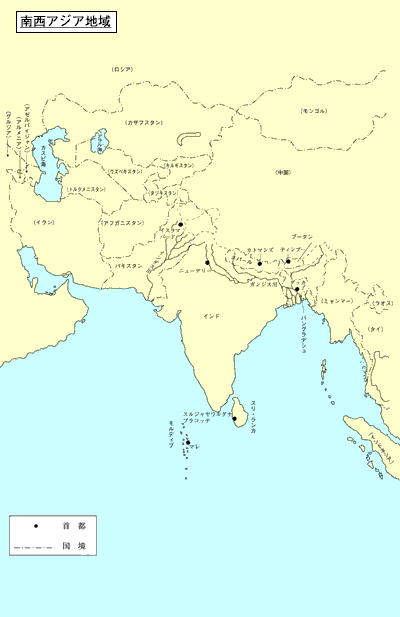(1) 南西アジア地域は、ヒマラヤ山脈とインド洋などにより地理的に他の地域から隔離されて、歴史的に独立性の高い小世界を形成していたと言ってもよい。インドは従来から地理的にも政治的にもこの地域の中心であり、今日まで南西アジア諸国相互の関係はインドを核とする放射状の構造を有していたと言える。
南西アジア諸国は、ネパール、ブータンを除きいずれも第二次世界大戦まで英国の支配下にあったという共通の歴史を持つが、800以上の言語を有する多種多様な民族、ヒンドゥー教、仏教、イスラム教、シーク教、キリスト教等の多数の宗教を抱え多様性に富んでいる。気候についても、万年雪の積もるヒマラヤ山脈から熱帯モンスーン、砂漠まで多様である。南西アジア諸国は、こうした民族、言語、宗教などの多様性に起因する不安定要因を内包しており、経済・所得水準の低さとともに、社会問題、政治問題の背景となっている。
(2) 冷戦体制は、南西アジア地域に「米・中・パキスタン対ソ連・インド」という対立構造を生じさせ、各国の独自の外交政策には一定の限界があったが、冷戦終結後は、経済的な潜在力と従前からの政治力を背景として、インドに対する米国、欧州諸国等の関心が飛躍的に高まり、昨今もクリントン米大統領(当時)の南アジア訪問(2000年3月)を始め、主要国による積極外交が展開されている。
カシミール問題を巡り対立しているインド・パキスタン関係については、地域にとり最大の懸念要因である。97年前半に約3年ぶりに外務次官級協議が再開され、外相級・首脳級会談も開催されたが、両国の核兵器及びミサイル開発は域内の不安定要因となっていた。こうした中で、インドは98年5月11日、13日と二度にわたる地下核実験を行った。国際社会は核不拡散の流れに逆行するものとしてこれを非難し、5月15日のバーミンガム・サミットにおける「G8首脳による声明」を通じてインドに対し核実験の停止、核不拡散条約(NPT)及び包括的核実験禁止条約(CTBT)への参加等を求めるとともに、パキスタンに対しては最大限の自制を促した。しかし、パキスタンもインドに対抗する形で5月28日、30日の二度にわたり地下核実験を実施したため、6月6日に両国の核実験を非難しNPT、CTBTへの加入を求める国連安保理決議がなされ、さらに6月12日のG8外相会合において国際金融機関融資についての審議延期に努めるなどの内容を含む「インド及びパキスタンの核実験に関するG8外相声明」が採択された。
両国の核実験に伴う緊張の高まりの中、印パ間の対話の先行きも懸念されたが、98年7月の南アジア地域協力連合(SAARC)首脳会議及び9月の国連総会における印パ首脳会談、10月のイスラマバードでの印パ外務次官級協議等を通じて対話のチャンネルは維持された。また、99年2月、ラホールで印パ首脳会談が行われ、対話による信頼醸成を謳ったラホール宣言を含む三文書が発出された。
その反面、99年4月にはインド及びパキスタンが相次いで弾道ミサイル発射実験を実施した。また、同年5月、カシミール地域における両国間の管理ライン(LOC:71年の第三次印パ戦争の停戦時点での両国の支配地域に基づき画定された境界)を超えて武装勢力がパキスタン側からインド側に侵入したため、インド側は、空爆を行う等激しく反撃する一方、侵入した武装勢力がパキスタンに支援されているとしてパキスタンを厳しく非難したが、パキスタン側は一貫して関与を否定している。その後、この戦闘は7月下旬に収束したが、インド軍によるパキスタン海軍機撃墜事件、インド国家安全保障諮問委員会による核ドクトリン草案の発表等、両国間の緊張関係は継続した。10月にはパキスタンにおいて、首相による陸軍参謀長の解任を発端として軍事クーデターが発生した。行政長官に就任したムシャラフ陸軍参謀長は、インドとの緊張緩和の希望を表明し、国境配備軍の一方的削減等の対応を取ったが、インドはパキスタンによる「越境テロ」を理由に対話再開に応じていない。更に、12月にはインディアン航空機ハイジャック事件が発生し、その背景を巡って両国が非難しあうなど、両国関係は一層悪化することとなった。
(3) 南西アジア地域は、世界人口の5分の1を占め、また、多くの貧困層を抱えているため、開発ニーズが高い。観光・漁業に依存するモルディヴを除き、依然農業を主要産業としており、経済は天候の影響を受けやすい。貿易は、概して農産物等の一次産品や繊維製品等の軽工業製品を輸出し、機械類などの資本材を輸入するという構造をもつ点で、一次産品価格等の国際経済の動向に左右されやすいという脆弱性を有しており、多くの国が恒常的に貿易赤字、経常収支赤字を抱えている。
南西アジア諸国は、戦後の多くの独立国と同じく、当初は国内産業を保護し輸入代替を進めるとの経済開発戦略を推進した。しかし、現在は、77年より自由化を進めていたスリ・ランカに続き、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパールも経済の自由化・規制緩和等の経済改革の実施に積極的に取り組んでいる。
(4) 85年12月に発足した南アジア地域協力連合(SAARC)は、80年にバングラデシュのジアウル・ラーマン大統領が提唱した南アジア地域協力構想が結実したものであり、政治的側面を排除し、経済・文化面での現実的な協力関係の構築を目指したものである。近年は域内諸国の経済自由化政策の後押しを受け、SAARC活動も貿易協力に比重を移しており、95年には域内貿易の活発化を目的としたSAARC特恵貿易協定(SAPTA)が発足した他、2001年までに南アジア自由貿易地域(SAFTA)の法的枠組みを作成することに合意している。他方、上記パキスタンのクーデターを受け、SAARC首脳会議は現在延期され、域内の経済交流にも影を落としている。
(5) 南西アジア諸国はいずれも親日的であり、我が国は従来より全般的に良好な関係を維持してきている。90年4~5月の海部総理(当時)の南西アジア4カ国訪問を契機として、我が国は91年以来、貿易・投資関係の拡充を目的とする政府派遣経済使節団を、バングラデシュ、スリ・ランカ(二度)、インド(二度)、パキスタン(二度)、ネパールにそれぞれ派遣した。日本の産業界に対する期待の大きさを背景として、97年2月にデリーで開催されたインド国際貿易見本市には、日本がアジアで初の共催国となった。要人の往来としては、92年6月にラオ・インド首相、同年12月にシャリフ・パキスタン首相、94年3月にはバングラデシュのジア首相、96年1月にブットー・パキスタン首相、96年5月にクマーラトゥンガ・スリ・ランカ大統領、97年7月にハシナ・バングラデシュ首相、98年11月にはコイララ・ネパール首相が訪日した。我が国からは秋篠宮・同妃両殿下が92年11月にスリ・ランカ、パキスタン、インドを、97年2~3月にネパール、ブータンを御訪問されたほか、95年1月に橋本通産大臣(当時)のインド、パキスタン訪問、97年7月に池田外務大臣(当時)のインド、パキスタン訪問、99年3月に橋本前総理のネパール訪問、2000年2月に橋本外交最高顧問のインド訪問が行われ、二国間関係の緊密化に貢献した。更に、93年度にはSAARC諸国間及び我が国とSAARC間の交流を強化するため、「日本・SAARC特別基金」が設立され、93年度は30万ドル、94年度以降は96年度まで毎年50万ドルを拠出したが、97年度は全体的なODA予算削減の影響を受けて若干減額され、以降は毎年総額約45万ドル弱を拠出している。2000年8月森総理は、南西アジア歴訪に際し、SAARCの南西アジアにおける信頼醸成に果たす役割等に鑑み、SAARC活動に対する支援を拡充していく姿勢を示した。
(6) 2000年8月には、森総理が日本の総理としては10年振りに、インド、パキスタン、バングラデシュを、また、日本の総理として初めてネパールを訪問したが、各国との間で友好協力関係の増進に努め、特にインドとの間では、「21世紀における日印グローバル・パートナーシップ」の構築に合意し、国際社会で戦略的重要性を増しつつあるインドとの関係強化を図った。