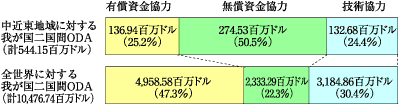(1) 中近東地域の経済的・戦略的重要性は、73年の第1次石油危機を契機として改めて認識され、同年以降同地域に対する我が国の経済協力は大幅に拡充された。72年には0.8%であった我が国二国間ODAに占める同地域のシェアは77年には24.5%にまで達したが、その後石油の安定供給、我が国エネルギー構造の変化等もあり、79年以降のシェアは10%前後で推移していた。91年の対中近東地域二国間ODAは、湾岸危機に際して周辺国支援として供与された円借款(主に緊急商品借款)の支出が進んだことから、二国間ODA総額の20.4%に相当する18億656万ドルとなり、絶対額では過去最高の水準となったが、92年以降は再び湾岸危機以前の水準に戻り、99年の我が国の対中近東地域二国間ODAは、5億4,415万ドルで、二国間ODA総額の5.2%を占めている。
(2) 我が国の対中近東地域二国間ODAの形態別構成は、比較的所得水準の高い国が多いことを反映して、従来から有償資金協力の比重が高いことが特徴である。特に91年の湾岸危機の際に周辺国支援として供与された円借款の支出を反映して、98年までの累計では対中近東地域二国間ODA(支出純額)の62.8%を占めている。しかし、近年、パレスチナ支援等に見られるように、無償資金協力の比重も高まり、99年における無償資金協力の割合は支出純額ベースで50.5%になっている。
有償資金協力については、近年我が国の有償資金協力全体の約10%が同地域に対し配分されていたが、99年においては2.8%となっている。有償資金協力の対象としては、運輸・交通、エネルギー、通信等を中心に、農業、水供給等の分野に対しても供与を行っている。また、国際収支の悪化等経済の構造的な問題を抱える国に対し、持続的な経済成長と国際収支安定の回復、維持に必要な制度改革を支援するためのプログラム借款のほか、農業分野においては小規模事業者の支援を図るためツー・ステップ・ローンも供与している。また、95年6月にはジョルダン、シリア、トルコ、レバノンに対し初の円借款政府調査団を派遣したほか、96年よりテュニジア、モロッコを円借款年次供与国と位置づけ、毎年円借款政府調査団を派遣している。
無償資金協力については、近年我が国無償資金協力全体の約10%前後が同地域に対し配分され、99年においては二国間総額の8.3%を占めている。最近は、中東和平プロセス支援の一環として、中東和平当事国への協力を拡充しており、域内の最重要国と位置付けられるエジプト、近年無償資金協力の対象となったジョルダン、シリア、更に95年度より対象となったパレスチナに対して積極的な協力を行っている。無償資金協力の対象は、上水道整備、保健・医療、農業、環境、教育、運輸分野等広範にわたっている。
技術協力については、近年我が国技術協力全体の約5%前後が同地域に対して配分され、99年においては二国間総額の5.0%を占めている。技術協力の対象は、行政、工業、保健・医療等の分野での研修員受入、保健・医療、運輸・交通、工業、農林水産業等の分野での専門家派遣、社会基盤、教育、文化・スポーツ等の分野での青年海外協力隊派遣、社会開発、保健・医療、人口・家族計画、農林水産業等の分野でのプロジェクト方式技術協力、農業、水資源、鉱工業等の分野での開発調査を実施している。生活環境、習慣が我が国と大きく異なることや技術移転の対象となる人材が限られている等の制約もある。
(3) 難民への支援は中近東地域における大きな課題であり、人道的立場及び中近東地域の安定に貢献するとの立場から、従来からほぼ毎年度パレスチナ難民に対する無償資金協力(99年度800億円)や技術協力を国連パレスチナ難民救済機関(UNRWA)を通じて実施している。また、アフガン難民に対しても国連世界食糧計画(WFP)や国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等を通じ80年度以降毎年度人道援助を実施している。