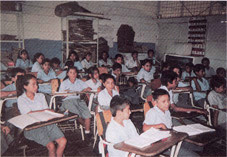第4章 事後評価の概要
本章では、外務省、JICA、JBICによる事後評価の結果の内、主な評価の概要を取りまとめました。
なお、外務省による「在外公館による評価」、「被援助国関係者による評価」、「現地コンサルタントによる評価」は件数が多いため、各形態ごとの概要のみ掲載しました。
外務省による評価については本報告書の各論編、JICAについては「事業評価報告書」及びJBICについては「円借款案件事後評価報告書」に詳細を掲載しています。
1.外務省による事後評価
(1)国別評価
国別評価は、主要な被援助国を対象に、日本のODAがその国の経済開発及び民生の向上にどのような効果をもたらしたかをマクロ的視点から調査・分類する評価で、評価結果は、被援助国に対する日本のODA政策策定に資するよう活用されている。
さらに、評価調査実施後、評価対象国において政府や民間の関係者などの参加を得てODA評価セミナーを開催し、評価結果の報告、討議を行うことにより、被援助国関係者への評価結果のフィードバックを行っている。
(イ)エル・サルヴァドル
松下洋・神戸大学大学院国際協力研究科教授を団長に、田中高・中部大学国際関係学部助教授、小池康弘・愛知県立大学外国語学部助教授、長町昭・(財)国際開発高等教育機構事業部調査役、藤田伸子・同事業部職員に依頼し、エル・サルヴァドルに対する日本のODAが同国の経済開発及び民政向上においていかなる効果をあげたかについてマクロ的視点から評価を行った。 また、評価結果をエル・サルヴァドル政府関係者にフィードバックするために、99年9月に現地でセミナーを開催した。
日本のエル・サルヴァドルに対する援助は、同国における和平の実現と民主化の進展を受け、90年代に顕著に増加した。 90年代以降の日本の対エル・サルヴァドル援助が、運輸、電力、給水設備の拡充、学校建設等の基礎的インフラ部門に重点が置かれてきたことは、内戦の痛手からの復興を目指した同国の国内事情に適っており、また、復興が一段落した90年代半ばから、農村復旧計画や、看護教育強化などの長期的視野に立った援助に重点を移してきたことも援助政策の方向として妥当であったとしている。 こうした日本による協力は、エル・サルヴァドルの復興、民生向上に大きく寄与し、また、日本の援助は総じてハード面にやや力点が置かれてきたと指摘する一方で、開発調査、青年海外協力隊による教育指導等の技術協力も順調に成果を上げていると評価している。
今後は、90年代のエル・サルヴァドルにおける援助に関わる諸条件の変化への対応が必要である。 すなわち、同国の一般無償資金協力からの卒業という状況を踏まえ、同国の最大の課題である貧困問題の対応として、貧困層に直接裨益する草の根無償協力の増加、現地で様々な貧困救済に取り組んでいるNGOへの支援・協調促進は課題であり、また、急速に進展する民営化・地方分権化や、経済統合が進む中米地域域内協力の進展等を踏まえた新たな対応が求められていると提言している。
エル・サルヴァドルの最大の課題である貧困問題への対応として、貧困層に直接裨益する、草の根無償資金協力等を増加し、現地で様々な貧困救済に取り組んでいるNGOを支援し、右との協調を深めていくことが極めて重要であることを提言している。
ポルチス村の小学校の授業風景 「飲料水供給計画」(サンタモニカ村)
(ロ)モンゴル
日本のODAがモンゴルの経済開発及び民生部門の向上にどのような効果をもたらしたかをマクロ的視点等から調査・分析するために、広野良吉・成蹊大学名誉教授を団長に、吉田恒昭・東京大学工学部教授、栗林純夫・東京国際大学経済学部教授、石井幸造・国際開発センター研究員、外務省職員からなる調査団により現地調査が99年3月に実施された。 また、評価結果をモンゴル政府関係者にフィードバックするために99年9月にセミナーを開催し、モンゴルの社会経済開発と開発援助のあり方についての意見交換を行った。
日本が91年及び92年に重点的に実施した国際収支支援型の緊急援助は、モンゴル経済の危機的状況の回避に向けての緊急救済措置として大きな役割を果たした。 緊急援助に引き続きタイムリーな形で経済・社会インフラの整備に重点を置きつつ援助プログラムを実施したことは、モンゴルの経済安定化に貢献した。 農業プロジェクトなど一部モンゴル側の政策転換により必ずしも予定した効果が得られていない案件も存在するが、市場経済への移行過渡期においては、援助に関しても試行錯誤は避けられず、市場経済システムの導入 は時間を要するプロセスであることから対モンゴル支援を進めるには長期的視野を持つことが重要である旨指摘している。 また、日本が援助を本格化した90年から現在までは、市場経済化支援に向けての基盤造りを行ってきた10年間であり、さらなるインフラ整備を行うとともに、今後ともモンゴルの市場経済体制の充実・安定に向け、支援を継続していくことが重要であると指摘している。
モンゴルにおける今後の最大の課題は、現在人口の約36%を占める貧困層の生活水準を引き上げるための貧困対策であるが、その解決に向け、社会セクターへの支援、特に地方においてさらなる援助を展開していくことが必要である。 また、援助をより効果的・効率的に実施するためにはモンゴル側の援助受け入れ調整問題の解決に向け、人的・制度的能力の向上に努めることが必要である。
政府関係者からのインタビュー ダルハン食肉工場の視察
(2)援助実施体制評価(セネガル・マリ)
援助実施体制評価は、日本のODA主要受取国を対象とし、無償資金協力、技術協力、有償資金協力の援助全般に関わる資金の適正使用、援助実施手続きの適正さなど、評価対象国における援助実施体制、実施環境全般について調査し、改善すべき点などがあれば、これを是正・改善するような措置の勧告・提言を行う評価であり、政策、実務双方に通暁した有識者の協力を得て実施している。
98年度は、貧困及び環境問題を抱え、TICAD
II等を通じ、今後日本の積極的な援助展開が予想されるアフリカ諸国のうち、セネガル及びマリを対象国として、日本のODAの実施に係る相手国側及び日本側の援助実施体制の改善点を明らかにし、具体的な提言を得ることを目的として本件調査は実施された。
調査団の構成は、中村清・元会計検査院長、大林稔・龍谷大学経済学部教授、小泉肇・コーエイ総合研究所取締役、石田洋子・同総研研究員、塩畑真里子・同総研研究員、外務省員により構成された。
評価の主な結果は以下のとおりである。
現地でODAの実施に携わる日本国大使館とJICA事務所は、限られた要員を可能な限り活用し、セネガルを中心とした兼轄国に対する開発援助が推進されている。
セネガルでは、援助受入窓口機関及び実施機関の連携は概ね良好に推移しているが、実施機関が縦割りになっていることから、セクターやサブ・セクター間での横の連携が不十分である。
さらに一部の実施機関の民営化が進められており、日本の援助が関係する各種事業の民営化に関する動向を慎重に見極める必要がある。
また、セネガルにおける政府機関の組織制度整備については、IMF及び世界銀行の支援のもとで「良い統治プログラム」を実施しており、効果が待たれる。
一方、セネガル側援助受入体制に関して、(1)セネガル側窓口機関を通じた連携推進による実施体制の強化、(2)参加型開発の促進に向けた実施体制の強化、(3)透明性の確保に向けた実施体制の確立、等が提言された。
また、日本の援助実施体制に関しては、(1)国別プログラム・アプローチの確立、(2)他ドナーとの連携、(3)先方政府のオーナーシップ強化への支援、等が提言された。
 |
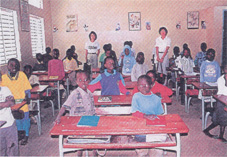 |
| 我が国無償資金協力によって建設された小学校教室 (セネガル、ダカール市近郊) |
教室内の状況 |
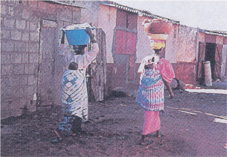 |
 |
| セネガルの漁村風景-女性の水産物小売業者 (セネガル、カヤール) |
我が国無償資金協力により拡張中のダカール 中央魚卸売市場(セネガル、ダカール) |
(3)特定テーマ評価(カンボディア(貧困))
特定テーマ評価は、国別評価同様、マクロ的視点からの評価であり、日本のODA及びODA評価に関する経済協力団体に委託して実施する。
特定セクター又は援助形態をテーマとして日本のODAを横断的に捉え、援助効果や問題点を分析する。
本評価では、世界経営協議会に委託し、日本政府がカンボディアに対して供与したプロジェクトである「プノンペン市上水道整備計画」、「母子健康センター」、「カンボディア難民再定住・農村開発プロジェクト」の調査を行い、日本国際ボランティアセンターや曹洞宗国際ボランティア会(現在はシャンティ国際ボランティア会)による事業を視察し、「貧困」問題への協力のあり方を検討した。
プノンペン市上水道整備計画は、同市2地区を対象とする配水管網の整備だけでも2万7千世帯、16万人の市民へ安全な水を供給し、同地区の漏水率を50%から10~15%へと改善させ、汚水の混入のリスクの大幅削減が期待されると評価されている。
母子健康センターは、97年4月~98年12月の期間で、904人の医学部生及び73人の助産婦に基礎訓練、172人のスタッフに超音波診断訓練を実施した。
また、外来診療で99,553人、入院で15,948人の患者を診療している。
同センターの機能を強化することは各診療地区の産科サービスの向上につながり安全な母性の確立に資するものである。
難民再定住・農村開発プロジェクトは、92年以降UNHCRやUNDPへの日本の拠出金の供与の他、JICA専門家や青年海外協力隊員並びにASEAN4ヶ国(インドネシア、マレイシア、フィリピン、タイ)の専門家により実施されてきており、約3万人の帰還難民を再定住させ、農業、職業訓練、教育、公衆衛生の分野で帰還難民以外の農村の住民をも含め住民参加による農村開発プロジェクトとして大きな援助効果を上げている。
日本は第一位の援助国であり、カンボディアを重視し、同国の復興と発展を支援している。
援助重点分野としては、経済インフラ、保健・医療等の基礎的生活分野、農業、人材育成などを位置づけており、また、96年に採択されたDACの新開発戦略(21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献)を具体的に実施する対象国としている。
今後のカンボディアへの貧困削減に向けた援助を行う際には、(1)政治的安定の確保と行政機構面の整備、(2)NGOと連携し母子家庭や地雷被害者など社会的弱者に対する「貧困プロジェクト」を開発計画の中に位置づけること、(3)農業基盤の拡充に留意しながら、(イ)グランド・デザイン、ナショナル・プランの作成、(ロ)本格的な農業・農村開発援助、(ハ)草の根無償資金協力の強化の充実を図ることを提言している。
 |
 |
 |
| 母子保健センター(プノンペン市) | ||
(4)NGOとの共同評価(カンボディア)
「NGO・外務省相互学習と共同評価」は、NGO・外務省定期協議会において、NGOとODAとの具体的協力・連携の方向性を模索するための方策として提案されたものであり、NGO関係者とODA関係者が共同で双方のプロジェクトを観ることにより、相互に学習・評価、提言することをその目的としている。
97年にバングラデシュにて行われた最初の共同評価に引き続き、98年度ではカンボディアで調査を実施することとなった。
調査団には、NGO側からステファニ・レナト名古屋NGOセンター理事長、神田浩史APECモニター・NGOネットワーク代表、秦辰也曹洞宗国際ボランティア会事務局長、重田康博NGO活動推進センター主幹、ODA側から外務省経済協力局評価室事務官、JICA評価監理室職員、とりまとめを行うために三島光恵OPMAC企画部課長(コンサルタント)が参加した。
バングラデシュでの調査で得られた教訓を活かし、相互学習と共同評価をより有意義なものとするために、調査団に援助実施機関であるJICAからの参加を得て、よりODAの現場に近い意見も取り入れることとなった。
NGO案件として曹洞宗国際ボランティア会(現シャンティ国際ボランティア会)の「基礎教育環境整備事業」及びODA案件として「カンボディア難民再定住・農村開発プロジェクト(三角協力)」を対象として評価調査を行うこととした。
また、NGO側参加者からの提案により、住民参加を調査項目に取り入れることとなった。
評価の結果、次のような提言が出された。
「基礎教育環境整備事業」は、教育事情の改善に貢献しているが、更なる教育及び公衆衛生に対する理解の促進のために、校舎建設と併せて教師の質の改善などソフト面の配慮が必要と思われる。
また、「カンボディア難民再定住・農村開発プロジェクト」は、日本の専門家及び協力隊に加え、ASEAN専門家やカンボディア人スタッフ、総勢約250名の人員により、農村におけるニーズの調査を踏まえた技術協力などNGOが得意とする草の根レベルでの柔軟で細やかな支援を広範囲で行うことが可能となっており、NGOとODAの良い面を取り入れたプロジェクトと言える。
また、ASEANの専門家を活用することで南南協力を推進することにも意義があろう。
今後は、カンボディアの自立発展性が課題である。
さらに、NGOとODA連携に向けて、(1)NGO・ODA間の人材交流、(2)案件形成段階からの協働、(3)柔軟なNGO支援スキームの創設、(4)定期協議会の開催、(5)「相互学習と共同評価」の充実にかかる提言を行った。
 |
 |
| ASEAN専門家からのヒヤリング | 授業風景 |
(5)有識者評価
有識者評価は、開発経済などの分野で高度な専門知識を有する学者をはじめ、文化人、報道関係者、NGO関係者、外国の専門家など、外部の有識者に依頼して実施する評価である。
それぞれの評価者の知識・経験を生かした独自の視点から評価が行われることが特色である。
(6)シンクタンクによる評価 フィリピン「金融セクター」(イ)中国「北京市上水道整備計画」「4都市ガス整備計画」:江部進経団連国際副本部長他
経済団体連合会の江部進・国際本部副本部長および根本勝則・同欧州グループ長に依頼して、中国における経済インフラをテーマに評価を実施した。
「北京市上水道整備計画」は、北京市に浄水施設(50万立方メートル/日)および取水、導水(総延長70.5km)、排水(52km)施設を建設し、北京市の給水能力を100万立方メートル/日まで高めるために、95年に第2期工事が完成した。 国家発展計画委員会、対外貿易経済合作部や北京自来水公司によれば浄水場は成功していると評価しており、給水対象人口は650万人であり需要の7割が民生用、3割が商工用に使用されている。
しかし、事業の採算性に問題があり、供給コストが1元/tであるのに対し、工場用は0.4元/t、民生用は0.7元/t、商業用は1元/t(最高値)となっているため、北京自来水公司は、北京市から補助金を受けている。 他方、料金徴収率は98%と良好であり漏水率も7.5%に過ぎない。 総体としては赤字体質であり、事業の独立性や発展性に懸念は残るが、水道事業は日本でも公営であり、世界的に見ても、英国が民営化している程度である状況なので、中国政府に依存する同公司の形態も理解が出来る旨述べている。
「4都市ガス整備計画」の一部分のハルピンの計画は、60万立方メートル/日の生産能力をもつ石炭ガス製造プラントを建設し、同市へのガス需要への対応を目的とし、93年には、石炭の洗炭、粉砕、選炭、ガス化、メタノール生産等のための9つの工場群から構成されるプラントが完成した。 なお、ガス化施設はドイツ資金によるドイツ製であり、メタノール生産設備はロシア製である。 同プラントの設計生産能力は189万立方メートル/年であるが、97年の時点では55万立方メートル/年であり、需要が少ないので採算割れの状況にあり設備の稼働率も51%である。 このため需要拡大を図り年間5万戸の需要増を実現したが、個別の需要量が大きい商工需要を開拓することが重要である。
需要量については、計画値が大きすぎたきらいがあり、ガス化設備5基のうち3基のみが稼働しているが、日本における石炭ガス化の事例がないことから、安定供給のためにどの程度の余裕を見込んで計画すべきだったかを判定することは困難であった可能性がある。
プラント建設の効果として特記すべきことは大気の浄化であり、煤塵の排出量は19万トン(92年)から3万9千トン(96年)に減少し、SO2の排出量も4.5万トン(92年)から2.3万トン(96年)に減少した。
なお、水の供給及びガス化関連プロジェクトとして今後必要となるのは、汚水処理を含め環境関係のプロジェクトである旨提言している。
(ロ)フィリピン「家族計画・母子保健」:菊池京子津田塾大学教授他
近年、国際協力に対する若者の関心が高まっていること、また国際協力に貢献し得る人材育成の重要性が唱えられていることから、実際の評価を通じて日本の経済協力に対する理解を深めてもらうための初めての試みとしてフィリピンでの有識者評価調査を大学院生2名の参加を得て実施した。
菊池京子津田塾大学教授がフィリピンにおいて実施した有識者評価に東京都立大学大学院社会学科研究科社会人類学専攻博士課程の石井洋子、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際関係学選考修士課程の小林由美の2名の院生が参加し、フィリピン人家庭に泊まり込み、フィールド調査を行った。
評価対象としては、プロジェクト方式技術協力により実施された「家族計画・母子保健」が選ばれ、調査時には、92年より開始された第一フェーズが終了し、「人造り」と「住民参加」を基本理念として、「助産婦活動改善プログラム(セミナー支援)」、「母子保健手帳導入プログラム」「協同薬局支援プログラム」などの活動が実施されていた。
調査団は、プロジェクトが家族計画・母子保健を中心とした地域医療活動と地域住民にどのような影響を与えたのか、そしてどのような成果が得られたのかについて調査を行った。 プロジェクトサイトであるタルラック州の農村に泊まり込み、村人の医療に関する意識などについての聞き取り調査を行った結果、母子保健・家族計画プロジェクトは、プロジェクトの性質上、成果を短期間に定量的に測定することは困難であるが、概ね効果的に機能している。 これまでプログラムやアクセスしていなかった人々の動員を目指し、広報活動の強化や地元の女性グループや村人のネットワークを使用したプロジェクトの普及活動が今後の課題であると、報告している。
予防接種の様子 伝統的産婆による骨折治療
(ハ)ラオス「サバナケート農業総合開発計画」「ラオス婦人同盟訓練所用寄宿舎建設事業」:星野昌子敬愛大学国際学部教授
ラオスへの最初の青年海外協力隊隊員であり、長年にわたりNGO活動の経験を有する星野昌子・敬愛大学国際学部教授(兼日本国際ヴォランティアセンター特別顧問)に依頼し、ラオスにおける農業とジェンダーをテーマとする評価を実施した。
「サバナケート農業農村総合開発計画」は、ラオス中部のサバナケート県のホワイバック上流およびナムプー両地区の潅漑施設、農業支援センター、農村道路、給水施設の建設・改修、並びに機材供与を行ったもので、両地区では農家2,504戸、人口15,753人を有し、潅漑面積は1,360haを対象としている。 ダム建設については、農民から否定的な意見はなく、これは、ダムの規模が小さく人口密度が低いことから、代替地がそれまでの居住地より肥沃であったり、川や道路に近くて条件が良かったことが原因と思われると推測している。
本件と他の組織(UNDP、IFAD、ADB、EU)との間には理念、活動地の重複その他の齟齬は生じておらず、本件による潅漑、給水の効果は大きく、県内や隣接県の行政関係者や農民が毎週視察や研修のため現場を訪問し、食糧生産の増加や作付けの多様化も見られ、同県のみならず他の地域にも大きなインパクトを与えている。
水利組合は以前からあった農民組織が再編成されたものであり、参加は強制されていないが、干魃の際の水路の成果を見て組合員は次第に増加している。 農民自身が農業振興銀行から資金を借りて第三次水路の建設を行っていることから農民の自主的参加は顕著であると評価している。 ラオスの伝統的習慣より不動産は末子(多くの場合娘)が相続するために銀行から金を借りることができるのは女性であり、またリスクも負うこととなるので女性は開発の受益者のみならず主体的に開発に参画している。
他方、在来種(餅米)は、新種(粳米)より、病虫害に強く化学肥料がいらないので、生産量が低くとも安定した収穫が得られるので、自給のために在来種を栽培したいと希望する一部の農民もいる。 同県当局のように換金作物栽培を奨励し自給自足農業よりの脱却を余りにも急げば、折角自主的に関わろうとしている農民の意欲を削ぐこともあり得るので彼らの意識に見合った速度の変化を支援する姿勢が望まれるとの意見を述べている。 そして、「ラオス側自治体(サバナケート県)」および「ラオス側NGO(水利組合)」と「日本側いずれかの自治体」および「日本のその地域に本拠を置くNGO(中高年の農民を巻き込む可能性をもつ団体)」というあわせて4者が立案の段階から対等に参加し、これをODAが支援する新しい型を提言している。
住民に対するヒヤリングの様子
「ラオス婦人同盟訓練所用宿舎建設事業」は、ラオス婦人同盟が首都ビエンチャンの訓練センターには宿泊施設がないために、地方からの参加者に対する効果的な訓練ができず、ラオスの全国的女性活動の推進を図るために多大な支障を来していたので、96年の草の根無償資金協力により、木造2階建て、25~30人が宿泊できる訓練用宿舎を建設した。 96年12月に宿舎は同連盟に引き渡された。
同連盟の訓練コースの内容は、男女の役割、職業訓練の計画の立て方、プロジェクトの計画の立て方の3つに絞られている。 また、同連盟は、農業、畜産、織物、縫製、生け花、外国語研修に関心を有している。 同連盟は、社会主義国には結社の自由はないので「QUANGO(疑似NGO)」と呼ばれる「政府主導の団体」であり、地域における自発的な女性の力は発揮されがたい。 現在は、少数であってもボトムアップのNGOのような活動がラオスで散見されるので、今後は、ODAによる女性分野の協力は同連盟の他の団体を通じて行うことも検討する必要がある旨提言している。
なお、UNDPの「HUMAN DEVELOPMENT REPORT 95」によれば、人間開発指数(HDI)からジェンダー、社会的・文化的性差関連の開発指数(GDI)を引いた数値がプラスの場合は平均的人間開発の達成度に比べてより良い男女平等度を示すとしているが、日本はマイナス5、ラオスはプラス4であり、日本は平均的人間開発の達成度に比べて男女平等度が低く、この点を十分考慮して、今後のジェンダー(WID)案件に対応する必要がある旨指摘している。(ニ)タイ「レム・チャバン港建設」「バンコック東部外環状道路建設事業計画」「電話網拡充計画」:土谷英夫日経新聞論説副主幹
土谷英夫・日本経済新聞論説副主幹に依頼して、タイにおける経済インフラをテーマに評価を実施した。
「レム・チャバン港建設」は東部臨海開発プロジェクトの一環として、バンコックの南東約110kmのレム・チャバン地区に、主要商業港として、また大型船の入港が困難なバンコック港の代替機能も合わせ持つ深海港を建設するものであり、そのための浚渫・埋め立て、護岸整備、防波堤整備、係留施設整備等を実施するものである。
同港は91年に開港し、順調に貨物取扱量を増やし、96年からは北米定期航路のコンテナ船が寄港するようになり、4海運グループが北米定期航路をそれぞれ週1回運行している。 97会計年度には、コンテナ扱い量が103.6万TEU(※1)と初めて100万台の大台に乗りタイ全体の45%を占めた。 98年会計年度は142.4万TEUでバンコック港を凌駕している。
東部臨海地区の工業集積の進展、水深が浅いバンコック港の限界、レム・チャバン港の国際的な認知度から、本プロジェクトの有用性は裏付けられると評価している。 レム・チャバン港の将来は、同港はシャム湾の湾奥にあり東南アジアのハブ港湾として確固たる地位を占めるシンガポールに近いという地理的条件により東南アジアのハブポートになりにくいが、ラオス、カンボディアを含むいわゆる「バーツ経済圏」の中心港になる潜在的可能性は十分あり、ラオスやカンボディアと結ぶ高速道路の整備が重要であると示唆している。
「バンコック東部外環状道路建設事業計画」は、バンコック市内の通過交通をバイパスさせる「外環状道路」計画のうち、東部分の高速道路(バンパイン-バンプリ間、約64km)を建設するものである。 建設資金はタイ政府資金と円借款が50%ずつ負担している。 東部外環状道路は、当初は97年7月に完成予定であったが、土地収容の遅れ、軟弱地盤による設計変更、洪水、アジア経済危機に伴う建設業者への打撃により完成が1年4ヶ月遅延し98年12月に開通した。 バンコック市内の交通混雑の緩和のため、通過交通を市外に出す外環状道路の建設は不可欠であり、バンコック~チョンブリ間の高速道路(円借款)と結んで東部臨海地区から市北方にいたる道路交通の時間短縮効果も期待できる。 バンコック市の交通問題については、日本は98年に陸上交通調整委員会を調整窓口にした交通政策・計画の立案や、交通施設改善プロジェクトに初の円借款41億円の供与を決めたので効果を見守りたいと述べている。
「電話網拡充計画」は、89と90年度にタイ電話公社に対し交換局管内のケーブル敷設工事費、資材・機材購入費の外貨分に対し貸付を行ったものであり工事は完了している。
電話網は情報化社会の基礎インフラであり、電話公社への円借款は、68年の第1次借款以来、累計で千億円を超えており、タイの電話網充実に果たした役割は大きいと評価している。ただ、近年BOT方式による民間企業の参入や電話公社の民営企業への移行(99年1月を予定)により新たな円借款の要請はなくなっている。
タイへのインフラ整備に対する今後の協力については、地方の生活水準の底上げのための社会資本整備は公的セクターが中心になるべきであり円借款による協力の余地があること、輸出指導型の製造業の育成の見直し、農業や観光インフラの整備、情報・サービス・観光等第3次産業の発展のための中等教育の拡充に日本が協力する余地があること、庶民の目に映りやすい「顔が見える」無償や技術協力とは異なり、円借款は「日本の協力事業」であることが伝わりにくいので、もっとPRする工夫が欲しい旨提言している。
(※1) Twenty-feet Equivalent Unitの略、20フィートコンテナ換算量をいう。 コンテナの大きさには20フィートコンテナ(8×8×20フィート)、40フィートコンテナなどがあるが、これらを20フィートコンテナに換算したコンテナ個数で、コンテナの貨物量を表す単位である。 (ホ)インド「サンジャイガンジー医科学大学院」:新崎康博国立国際医療センター医師
途上国における医療協力について豊富な現地経験と専門知識を有する国立国際医療センターの新崎康博・国立国際医療センター医師に委託して実施した。
サンジャイガンジー医科学大学院は、高度専門分野のみを対象とした医学の超最高学府を目指している。 プロジェクトの目標は研究と特殊医療の促進と、これに要する高度先進医療機器の運用に要される技術の移転であった。 現状から判断してこれは十分に達成されていると言えるだろう。 プロジェクトの資源投入は大部分がウッタルプラデッシュ州によるものであり、州側の人的投入、JICAの人的投入を考慮すれば、全体の投入の10%内外がJICAの寄与分と考えられる。 日本からの高度先進機器の投入と専門家の投入がなければ、このような短期間に、インドではAll India Medical Instituteと1、2位を争うような高度研究機関にはなれなかった筈である。 日本側の投入の質を考えれば、金銭で表わされたものより寄与度は高い筈である。
プロジェクトが実施されたことによる波及効果(impact)については、サンジャイガンジー医科学研究所設立の基本理念、技術協力プロジェクトの目標に基づき、診療活動のインパクト、人材育成に関するインパクト、研究に関するインパクトの3つの観点から評価した結果、とくに診療活動の実績、博士課程を通じた人材育成の実績、学会での多数の研究論文の発表などを中心に好ましいインパクトが出ていることが確認された一方で、いくつかの教訓も得られた。 但し、無償機材贈与から12~3年、技術協力終了からほぼ2年を経た99年5月の時点におけるインパクト評価であり、インパクトが全て出尽くすにはまだ時間がかかる筈である。
ウッタルプラデッシュ州政府は、法制的にも財政的にもこの医科大学院の将来にわたる発展に深くコミットしており、州政府の最高責任者(First Secretary)が医科大学の総裁(President)を兼務している。 それからUP州政府のインプットにJICAの無償、プロ技が加わったこの壮大なる事業の最大の受益者は同医科大学院の教授以下の教授陣、研究者であり、彼らは、この自立発展性に努力することに、最高のインセンテイブを有している。
病院入り口 現地ヒヤリング中
(ヘ)スリ・ランカ「食糧増産援助」:弦間正彦早稲田大学教授
弦間正彦・早稲田大学教授に委託し、スリランカにおける「食糧増産援助」についての評価を実施した。
日本は、スリ・ランカに対し77年以来「食糧増産援助」を実施してきている。 「食糧増産援助」とは、食糧不足の状態にある途上国を対象に実施されており、単位あたりの収量の向上を達成するために必要になる生産投入材である肥料、農薬、農業機械などを調達するための資金を無償供与するものである。 食糧増産援助においては、被助国は我が国援助の結果生じる内貨余裕分の一定割合を見返り資金という形でプールし、経済開発プロジェクト等に使用することとなっている。
効率性については、本プロジェクトは、肥料、農業機械などの農業生産投入材は納期に納品され、最終受益者である農民や農民組織が遅滞なく資材を受け取っているなど効率的な実施が行われている。
目標達成度については、供与された農業機材は、食糧生産地域で使用され、食糧増産に役立っており、稼働率も高く、小農のニーズに適っているといえる。 本機材の供与は、農家経営の安定化に繋がっており、農家レベルにおいて一定の経済効果を生み出している。 一方、肥料供与については、供与された硫安の多くは、プランテーション作物の生産に使用されており、外貨をもたらし、経済発展には寄与しているものの、食糧増産、食糧不足の解消には、直接は繋がっていない。 本来の食糧増産援助の目標達成のためには、政府が稲作用に使用を推奨している尿素肥料の供与を中心とすべきであったと指摘している。
また、見返り資金を使ったプロジェクトについては、長期的に小農の所得向上を通じた生活の質の改善に役立っており、また、農家レベルにおける経済効果も高いと評価している。
提言としては、継続して食糧生産投入材の供与を行っていく場合には、ニーズに併せて供与肥料の種類の変更を行っていくこと、また、稲作地帯を中心に機材の普及を図ることが食糧増産に結びつく方策であること、さらに、現在のスリ・ランカにおける食糧生産状況を考えると、試験研究と普及活動の強化のための協力を重点的に推進していくことが、中長期的に重要である旨指摘している。
農業国工省でのインタビュー調査 田植えの風景
(ト)シリア「ジャンダール火力発電所建設計画」「ダマスカス市ごみ処理機材改善計画」:畑中美樹国際経済研究所主席研究員
畑中美樹・国際経済研究所主席研究員に依頼しシリアにおけるエネルギーと環境をテーマとする評価を実施した。
「ジャンダール火力発電所建設計画」は、シリアの国内の電力不足を緩和し、電力の安定供給化を実現するとともに、国産天然ガスの有効利用を図るために、ガス・タービンと蒸気タービンからなるコンバインド・サイクル発電所を建設した。
目標達成度及びインパクトについては、電力需要に関しては当初の予測通り、国内需要が年平均8%(90-96年)で著しく増加しており、ジャンダール発電所は、国内最大の発電シェア(98年1~11月実績で約20%)を持つ発電所として電力の安定的供給を通じてシリア経済の発展に大きく貢献しているとの評価を得ている。
(ジャンダール火力発電所建設計画)
発電設備(ジャンダール火力発電所建設計画)
管理設備
効率性については、発電所の運営、維持、補修の現状については、熱効率46%、平均操業率70%を達成しており、当初の期待にあった成果を上げている。 98年12月現在で運転開始から約3年しか経過していないので、今後の維持補修時での対応の優劣が本件の正否の鍵となる。
妥当性については、シリアの開発において電力供給力の拡大に伴い高い優先順位が与えられてきたこと、熱効率・柔軟性に優れ、さらに環境保全上も望ましいコンバインドサイクル発電所の建設は、目的の設定においても妥当であった。
自立発展性については、同発電所の運営、維持、補修は発電所所在地域の職員により行われ、機材設備も整理され有効に活用されている。 しかし同発電所はシリア初のコンバインドサイクル発電所であり、今後は職員の訓練が必要となる。 また、通常型発電所に比し部品の損傷が著しく定期的取替が必要となるので、部品購入の財源確保がこれからの課題となるとしている。 このため、部品の取り替え費用や職員の追加訓練費用を含めたトータルコストの面からは、熱効率性や柔軟性、環境保全でやや落ちるとしても、天然ガスを熱源とする通常型の発電所の推進も検討に値するとしている。
「ダマスカス市ごみ処理機材改善計画」は、道路幅の狭い旧市街地域・丘陵地域への小型清掃車両の導入と埋め立て処分の可能な機材の導入によるダマスカス市の衛生状態の改善及び環境保全の向上を目的とした。
目標達成度およびインパクトについては、小型の清掃車両の投入以後は、年間修理車両数が約3割減少し、清掃局の維持費用が節約され、更に道幅の狭い地域での収集が可能となりごみ処理量が増大している。 加えてコンパクター、ダンプカー、ブルドーザー等の新規機材の投入でごみの埋め立て処分が可能となり、ハエの発生や、プラスティックの空中浮遊や悪臭がなくなり、プロジェクトの効果が認められる。
効率性については、新規投入のごみ処理機材は全て有効利用され保管状況は良好であった。 本件の対象ではないが、最終処分場は早晩許容量の限界に達すると思われる。
妥当性については、ダマスカス市は、ゴミ収集の効率化、最終処分場の環境保全に高い優先順位を与えており、小型車両及び必要機材の供与は目的の設定において妥当であった。
自立発展性については、清掃車両及び最終処分場の管理・維持はダマスカス市清掃局の職員により独自に行われており今後も支障はない。 但し、ダマスカス市のごみ収集・最終処分に関わる財政収支状況は、市民からのごみ収集処分料金の徴収が不完全であるので大幅赤字となっている。 今後は料金徴収の徹底化による財政事情の改善が不可欠である。
(ダマスカス市ごみ処理機材改善計画)
清掃車両(ダマスカス市ごみ処理機材改善計画)
ごみ収集作業
教訓と提言としては、本件は、日本の援助である旨が英語、アラビア語で明記されたステッカーを貼った車両がごみ収集のため市内を走っているのでODAの宣伝効果が大きい。
今後の収集ごみの効率的な処分については、収集ごみの仕分けセンター、医療ごみの処理施設の確立によるトータルシステムでの対応が不可欠であり、車両維持・補修に必要な知識技術の供与を目的とする訓練コースの新設も必要であろう。
なお、アラブ諸国への援助を行う際の留意点として、アラブ諸国では、(1)豊かな者が貧しい者に施しを与えるといういわゆる喜捨の考え方が強いこと、(2)欧州諸国の植民地支配を経験した諸国が多く、一般的に西側先進国に対して愛憎半ばする感情を抱いていること、(3)時間感覚が往々にして西側世界とは異なること、(4)援助国がアラブ世界のこうした文化的、社会的、宗教的特質を十分に理解し、援助の成果の上がる方向へと被援助国側の対応を誘導してゆくことを提言している。
(チ)コスタ・リカ「中米域内産業技術育成センター建設計画」及び「中米域内産業育成計画」:小野五郎埼玉大学教授
小野五郎・埼玉大学経済学部教授に委託し、コスタ・リカを拠点とした中米地域における産業技術育成をテーマに評価を実施した。
「中米域内産業技術育成センター(CEFOF)建設計画」及び「中米域内産業育成計画」は、中米諸国の財政、貿易収支の改善を図るため、農業中心の産業構造から工業中心の産業構造への移行を目指して、品質生産管理及び情報処理分野における人材育成、品質及び工程管理の技術の向上を図るものである。
日本は、同センターの建設を行うとともに、人材育成を支援するため、機材供与と併せて(2億200万円)、専門家の派遣(長期16名、短期32名)、研修員受け入れ(29名)などの技術協力を行った。
効率性については、同センター施設は教育訓練施設として十分な機能を発揮しており、同プロジェクトの研修コース及びセミナーの実施状況は年々着実に増加しており、効率性は高まっている。 また、宿泊施設も、機材についても有効に活用されている。
目標の達成度については、民間企業の指導的社員に対する研修や個別指導等を通じて当初計画を上回る成果をあげている。 既に域内他国からの研修生受け入れも始まっており、当初予定の5か国から8か国に拡大され、中米全体のセンターとしての形も整い始めているとの印象を受けた。
工場における作業の様子 コスタリカ側関係者との意見交換の模様
インパクトについては、協力が行われている工場においては、品質改善、工程短縮と在庫削減などに伴う平均30%に達する生産性向上及び労災の減少、さらに、素材に関わる品質管理/機械メンテナンスの改善、新製品の開発など、生産現場において多大なプラスの効果をもたらしている。
妥当性については、コスタ・リカ政府が力を入れている輸出振興/中小企業育成政策双方に対する協力事業として十分な妥当性を有するものである。 既に相当程度の効果が認められることに鑑みても、同プロジェクトの目的と実際のカリキュラムの運営とは合致していると評価できる。
自立発展性については、コスタリカ側は、政府/実施機関共に十分な熱意と能力を有しており、かつ産業界などからの同センターに対する信頼も厚い。 また、コスタ・リカ政府は、センター運営に対し、継続的な予算的負担を行っている。
同センターは、第三国研修も軌道に乗りつつあり、近い将来、中米における生産性向上教育等の中核となることが期待される。 同センターの地歩を一層確かなものとし、上位目標である産業構造の高度化に寄与するに至らしめるためには、現地スタッフによる自立性が十分に定着するまで、より長期的継続的な視点に立った日本側からの支援の継続が望ましいと指摘している。
(リ)チリ、アルゼンチン「胃癌対策」「消化器がん」:滝原章宏帯津三敬病院外科部長
滝原章宏・帯津三敬病院外科部長に依頼してチリにおける医療と技術協力をテーマとする評価を実施した。
計画の妥当性については、74年、チリ国政府は早期胃癌診断技術の向上と集団検診技術の実施を目指し、日本に協力を要請してきた。 77年、「胃癌対策」により専門家派遣、日本での研修(チリ人医師35人)、第三国研修(専門家44人)、機材供与が実施された。 早期胃癌の発見率は10~20%に達し、供与機材がフル稼働し、検査件数は高い数値を維持している。
日本チリ消化器研究所は第三国研修の場となり、大学の研修機関として専門家養成になくてはならない機関となった。 疫学構造から見ても、消化器がんはまだチリの主要疾患であるため、今後も消化器病学の知識、技術は必要であり、本件はチリにとり妥当な選択であった。
目標の達成度については、「胃癌対策」では(1)早期胃癌診断技術の向上、(2)集団検診技術の向上を目指し、他方「消化器がん」では、(1)内視鏡診断技術の向上、(2)画像診断技術の向上、(3)治療技術の向上、(4)病理学検査技術の向上、(5)大腸がん集団検診体制の確立を目指し、食道がん、胃がん、直腸・大腸がん、胆臓がん、膵臓がんをカバーできることが目標であった。 専門家の技術移転、多数の研修参加者が第一線で活躍していること、検査件数の維持、研究所が大学の研修施設に指定されていることで、技術移転は問題なく行われた。
インパクトについては、本件により消化器がんの診断、治療の技術がチリに根付いたことが大きな成果であり、現在は、同研究所がチリをはじめ南米消化器病の診断、治療、研究のモデルになっている。
自立発展性については、チリ担当当局は、18年にわたった協力を成功したものと評価している。 「消化器がん」は既に成人に達したと評価でき、自立的に発展する枠組みも出来上がっている。 今後問題となるのは投入された医療機材が、更新時期を迎えることである。 資金難により医療機材の更新の遅れもあるかもしれないが、既に電子内視鏡の更新を自力で行っており、今後チリ側の自助努力に期待できる。
提言としては、(1)本研究所を、中南米のモデルとして近隣からの視察、経験交流の場として利用すること、(2)北米、中南米を中心とする医学会での交流、英文版文献の相互送付、インターネットの活用に見られる症 例検討会の開催、映像資料を文化広報の一部として医療協力先に送付、(3)これまでの人材ネットワークを核として日本、チリ両国間の交流を継続すること等を挙げている。
(ヌ)トンガ「トンガタプ島道路改良計画」、サモア「地方電化計画」「地方電話網整備計画」、評価者:高千穂安長さくら総合研究所主任研究員
地方インフラ開発に幅広い知見を有する高千穂安長・さくら総合研究所主任研究員(現玉川大学教授)に依頼して、南太平洋の諸国に対する援助案件を評価した。 トンガの首都があるトンガタプ島は、同国の政治経済の中心地であり、良質の観光資源にも恵まれているが、島内の道路整備が不十分であるため、主要産業である一次産品の輸出港への輸送、観光事業の振興等に悪影響を及ぼしている。 本件「トンガタプ島道路改良計画」の実施により、道路状況の改善については十分達成されている。 「従来、トンガの道路は、穴凹だらけで砂埃や雨後の泥水跳ねがたいへんだった。 また、タクシーも目的地をちょっと離れると凸凹道で車体が痛むため嫌がっていたが、本件道路完成後はそのようなことはなくなった。 この成功を見て、トンガ政府自身も独自に舗装地域を広げるなどの努力をするようになった。」など、現地の人々からの評価も高いことが確認できた。
西サモアでは、将来の需要増に対処するとともに貴重な外貨を費消する輸入石油による発電を水力エネルギーに切り替える計画を進めているが、それに伴い未電化地域での配電網整備が必要であり、本件「地方電化計画」を実施した。 その結果同国の電化率は、案件実施前の75%から実施後は90%以上に向上し、未電化地域でも電灯は無論、冷蔵庫なども使えるようになり、地域住民の生活の向上に役立っていると評価された。 また、「地方電話網整備計画」も、地域の通話網の拡大に寄与し、住民生活の利便性が向上したと評価された。
電線と電話線
(上部が電線、下部が電話線)中継機はソーラーシステムで稼働している
本評価は、三和総合研究所への委託により実施され、日本がフィリピンに対して行った金融セクター構造調整融資が、同国の金融セクターの問題解決にどの程度寄与し、その後の経済成長にいかに貢献したかを検証することを目的としたものである。
日本は、フィリピンの金融セクターの構造調整を目的として、89年~93年、3億ドルに相当する、商品借款による融資を実施した。
本融資に際して、フィリピンに提示されたコンディショナリティは概ね達成されたものと評価することが出来、さらに現在のフィリピンの金融セクターにもプラスの効果を及ぼしているととらえることが出来る。
目標達成度の観点からは、法改正、ガイドラインその他の制度の確立等ほぼ全ての分野で目標は達成された。また、マクロ経済指標についても、概して改善の方向にあり、本融資の貢献度は大きかったものと評価できる。
効率性の観点からは、コンディショナリティ達成のために最終トランシェのリリースは遅れたが、資機材の調達、見返り資金の活用が適切に行われ、資金のディスバースも適切な時期に行われた。
インパクトとしては、フィリピンが本融資を用いた輸入決済により直接生産部門の拡大を達成し、輸出を通じた経済成長を達成するとともに、それを支える国内基盤として金融セクターの信用拡大を達成していった。
すなわち、本融資は銀行の預金残高の拡大、収益率の改善を通じ、フィリピンの内需部門の効率性改善に貢献した。
特にコンディショナリティとされた項目に加え、その後の環境変化を通じて表出したあらたな課題についてもモニタリング項目に含めていく必要がある。
(7)国際機関の評価 タイ「アジア工科大学院」
日本が継続的に支援してきている国際機関が実施してきているプロジェクトの活動・運営状況などについて調査・分析し、今後その国際機関のとるべき方向性を提言することを目的とした評価である。
99年1月、アジア工科大学院(Asian Institute of Technology:AIT)に対し調査団を派遣、AITの活動及び日本の支援につき評価を行った。
アジア工科大学院は、経済開発のために不可欠な土木工学の技術者の人材を育成・強化を行うことを目的として67年に設立された工学系大学院であり。
98年現在、AITでは37カ国から1,367名(98年現在)が学んでおり、タイ国内への工科系人材の輩出に留まらず、周辺国の人材育成にも著しい貢献をしている。
98年現在の学生の国籍を見ると、多い順からタイ(495名)、ベトナム(145名)、ネパール(96名)、中国(81名)、バングラデシュ(64名)となっている。
AITは、言わば「東南アジア地域の一大拠点大学院」に成長したと言えるだろう。
本件評価調査時(98年)までに、9,110人(53カ国)の卒業生をAITは輩出していた。
やや古くなるが86年(卒業生累計総数8,667人)の卒業生追跡調査によれば、卒業生の89%はアジアにおいて活躍しており、就職先業種別では官庁と民間企業がそれぞれ27%、教育機関に就職した者25%である。
以上から、AITの設立の背景のひとつとなった域外への頭脳流出防止の目的はほぼ達成され、同時に今日のアジアの経済発展に多大な貢献を果たしてきたと評価できる。
タイを含むアジア地域のいくつかの国が世界の経済成長センターとしての高い評価を得てきた背景には、積極的な外資導入、新しい技術の移転に熱心に取り組んできた各国政府部門及び民間部門の双方の努力があったとの定説があるが、更にこれら外国から導入された資本・技術を吸収・消化する受け皿としての人的能力の高さを指摘することができる。
AITの卒業生はその意味で各国の経済成長のための資本・技術の受け皿として社会インフラ整備の側面で大きな貢献をしてきたと評価できるだろう。
日本によるAITへの協力は、69年以来、継続してJICA長期専門家としての教官派遣及び奨学金の拠出を行ってきている。
常時教官を10~12名も派遣してきたことは日本の顔の見える援助としてAIT側より高く評価されている。
因みに98年における日本政府からのAITへの支援は修士、博士課程の学生への奨学金の他、設備・機材費41,600千円、運営費補助8万2千米ドル、インドシナ教官招聘プログラム7万5千米ドルであった。
他方、日本側としてもかかる協力を通じて日本人派遣教官は国際開発分野での経験の機会を獲得しており、AIT支援から得るものは大きいと言える。
東南アジア地域には、AITと同種の工科系大学院が次々と設立されており、従来この分野において人材育成のリード役を果たしてきたAITを巡る環境が従来とは異なってきているものの、引き続きAITが、アジア地域特有の問題及び多国籍のリージョナルな分野における良き研究の場であることは疑いない。
タイと並びAITのトップ・ドナーたる日本としてはAITの運営についても在タイ日本大使館を通じ、日本政府の関与を積極化していく必要がある。
(8)在外公館による評価
援助の実務に携わる日本大使館または総領事館の館員が、管轄国の日本のODAプロジェクトを対象に、ガイドライン(在外公館評価実施要領)にもとづいて実施する評価である。
限られた評価予算の中で、多く評価調査を実施しており、援助プロジェクトの経済的・社会的効果、運営管理状況などの実状を効率的に把握できるものとして重要である。
98年度は、46カ国、71案件について実施された。
その内訳は、アジアが32案件(13カ国)、中近東が7案件(5カ国)、アフリカが10案件(8カ国)、中南米が15件(12カ国)、大洋州が6案件(5カ国)であった(個別の案件名については巻末の一覧表を参照)。
(9)被援助国関係者による評価
被援助国関係者に委嘱して実施する評価である。
被援助国側の視点でODAプロジェクトを評価することにより、被援助国関係者にODA活動の意義や解決すべき課題を認識する機会を提供し、日本のODAの一層の効果的・効率的実施に資する。
98年度は、12カ国、14案件について実施された。
内訳は、アジアが5案件(4カ国)、アフリカが1案件(1カ国)、中南米が6件(5カ国)、大洋州が2案件(2カ国)、であった(個別の案件名については巻末の一覧表を参照)。
(10)現地コンサルタントによる評価
被援助国内の調査活動に実績を有する現地コンサルタントの社会・経済・文化事情などについての知見、情報収集力・分析力を活用して実施する評価である。
98年度は、9案件(5カ国)で実施された。
とくにギニアでは、草の根無償案件5件について、現地コンサルタントによる評価が実施され、草の根無償資金協力が現地の人々のニーズにきめ細かく応えていることが確認された。
(個別の案件名については巻末の一覧表を参照)