第1章 ODA評価を巡る最近の動向
2.ODA評価活動に関する我が国の動向
 ODAは、我が国の外交政策の柱の一つとされる国際的な活動ですから、その評価には国際的に認知された手法が早くから取り入れられてきました。我が国ODAにおいては、75年から評価活動が開始され、すでに25年の実績がありますが、その過程において個別プロジェクトの評価から発展し、国別・テーマ別評価や援助実施体制の評価なども実施されてきました。先進国が加盟している経済協力開発機構(OECD)には、開発援助委員会(DAC)という下部組織があり、DAC加盟国のなかから毎年いくつかの国を選んでODA実施体制を評価しています。96年に我が国のODA実施体制についてDACが行なった評価では、日本の援助評価システムについて「評価で判明した問題点を解決するための体制を日本のように備えている国はDAC加盟国の中でも極めて少ない」と指摘されるなど、国際的に高い評価を得ています。
ODAは、我が国の外交政策の柱の一つとされる国際的な活動ですから、その評価には国際的に認知された手法が早くから取り入れられてきました。我が国ODAにおいては、75年から評価活動が開始され、すでに25年の実績がありますが、その過程において個別プロジェクトの評価から発展し、国別・テーマ別評価や援助実施体制の評価なども実施されてきました。先進国が加盟している経済協力開発機構(OECD)には、開発援助委員会(DAC)という下部組織があり、DAC加盟国のなかから毎年いくつかの国を選んでODA実施体制を評価しています。96年に我が国のODA実施体制についてDACが行なった評価では、日本の援助評価システムについて「評価で判明した問題点を解決するための体制を日本のように備えている国はDAC加盟国の中でも極めて少ない」と指摘されるなど、国際的に高い評価を得ています。
しかしながら、ODAを取り巻く環境が大きく変化する中で、日本のODA評価システムがそれに対応して、十分に満足のできるレベルに達している訳ではありません。DACが98年に我が国のODA実施体制について行なった評価では、「事業の形成、モニタリングおよび評価にあたっては、費用対効果、持続性、技術的適性、社会・経済的効果および影響等が重視されるべきである」という指摘がなされています。さらに世界的な大きな潮流として、成果重視の援助(Result Based Management)とその成果測定(Performance
Measurement)の改善をいかに進めるかが、DACの援助評価作業部会でも議論されており、各国の評価担当者の課題となっています。
我が国の行政改革における議論
日本国内においても、行政改革の議論を通じて、援助政策を評価する体制の確立と評価を反映するシステムの確立が強く求められています。97年3月発表の行政改革会議の最終報告書では「政策立案部門と実施部門の連携と政策評価」と題して、「政策の評価体制を確立し、合理的で的確な評価を行い、その結果を迅速かつ適切に反映させる仕組みと体制が重要である」ことが謳われています。そして、98年6月に制定された中央省庁等改革基本法では、各省庁が「客観的な評価機能を強化するとともに、評価の結果が政策に適切に反映されるようにする」ことを明記しています。
ODA改革懇談会の提言
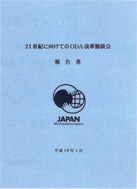 日本のODAに関する今後のあり方について、行政改革の議論と平行して進められた「21世紀に向けてのODA改革懇談会」(座長:河合三良 国際開発センター会長)の最終報告書では、我が国のODA評価体制について次のような指摘がされています。
日本のODAに関する今後のあり方について、行政改革の議論と平行して進められた「21世紀に向けてのODA改革懇談会」(座長:河合三良 国際開発センター会長)の最終報告書では、我が国のODA評価体制について次のような指摘がされています。
「現在の行政改革の議論の中では、政策の見直し、実施した事業の効果の検証など政策を評価する体制の確立と評価結果の反映が強く求められている。ODAについては既に長年にわたり評価が行なわれているが、ODAの更なる質の向上が求められている現在、評価システムの一層の改善に努める必要がある。」
この指摘に続き同報告書では、評価の手法の改善、外務省と実施機関(JICA・JBIC)との役割分担の明確化、評価結果の公表等について言及し、現在の評価システムの更なる改善を求めています。
援助評価検討部会での議論と、評価研究作業委員会の設置
この提言を受けて、日本のODA評価体制の改善について具体的に議論するため、従来から経済協力局長の私的諮問機関である「援助評価検討部会」(会長:河合三良 国際開発センター会長)の下に、大学教授、ジャーナリスト、シンクタンク、会計監査法人、外務省評価室、実施機関(JICA・JBIC)の評価担当部署の関係者等で構成される「評価研究作業委員会」(委員長:牟田博光 東京工業大学教授)が98年10月に設置されました。それ以来、約1年間、計13回の委員会を開催して議論した結果を、ODA評価体制の改善に関する提言としてまとめられ、援助評価検討部会と評価研究作業委員会の連名で下記のとおり発表されました。
「ODA評価体制」の改善に関する提言(中間報告)の提出(99年11月)
99年11月に、当時の段階でとりあえず早急に提起すべきであると考えた諸問題とその解決の方向について、10項目の提言がまとめられ、東外務総括政務次官(当時)に提出されました。主要な提言は次のとおりです。
(1)従来は事後評価を中心に行われていたODA評価を拡充し、「事前から事後への一貫した評価プロセスの確立」を実現するため、事前段階での評価指標の導入・評価計画の策定と定量的評価手法を一層導入する。(2)従来は個別プロジェクトを主な対象としてODA評価を実施してきたが、今後は「政策レベル及びプログラム・レベルの評価の導入・拡充」を推進する。(3)インターネットの活用等による評価結果の迅速な公開や、ODA民間モニター制度の拡充などの「情報公開の拡充と迅速化」を推進する。(4)その他、有識者等による第三者評価の拡充や、評価人材の育成、評価に関する更なる研究を行なう。
「ODA評価体制」の改善に関する報告書の提出(2000年3月)
 評価研究作業委員会は、上記の中間提言を提出後もさらに検討と議論を進めました。ODA評価に関して、「何のために」(目的)、「何を」(対象)、「いつ」(時期)、「だれが」(体系、人材)、「どうやって」(体制、手法)、さらに「どのように活用」(フィードバック、情報公開・広報)するのかという体系的かつ包括的な議論を行い、それぞれについて現状分析をした上で、改革に向けての課題を明確にし、具体的な改革案を提示しました。これは、日本のODA評価を体系的に議論した初めての試みでした。こうして取り纏められた報告書は、2000年3月15日に、援助評価検討部会の河合三良部会長から、河野外務大臣に提出され、その模様は新聞・テレビ等でも報道されました。
評価研究作業委員会は、上記の中間提言を提出後もさらに検討と議論を進めました。ODA評価に関して、「何のために」(目的)、「何を」(対象)、「いつ」(時期)、「だれが」(体系、人材)、「どうやって」(体制、手法)、さらに「どのように活用」(フィードバック、情報公開・広報)するのかという体系的かつ包括的な議論を行い、それぞれについて現状分析をした上で、改革に向けての課題を明確にし、具体的な改革案を提示しました。これは、日本のODA評価を体系的に議論した初めての試みでした。こうして取り纏められた報告書は、2000年3月15日に、援助評価検討部会の河合三良部会長から、河野外務大臣に提出され、その模様は新聞・テレビ等でも報道されました。
報告書の提出の経緯は次ページのとおりですが、さらに次節(1.3)で提言内容を解説しました。当然のことながら、中間報告で言及された項目を含み、さらにその後検討された新しい提言を体系的にとりまとめた内容になっています。
なお、本報告書で提言された政策及びプログラム・レベル評価の導入に必要な調査、評価人材の育成と有効活用のために必要な調査、プロジェクトの事前評価の試行的実施、第三者評価の拡充等、中間報告の提言を実施するための新たな各種予算措置が講じられ、本年4月に2000年度のODA評価関連予算として新たに認められています。