01. ポスト2015年開発アジェンダ
2001年、国際社会の共通の開発目標であるミレニアム開発目標(MDGs)が作られました。MDGsは貧困削減を中心とする8つの目標を2015年までに達成すべきものとして掲げており、日本もODAなどを活用し、積極的に目標達成に貢献しています。
MDGs達成に向けた国際社会の努力により、特定の分野ではかなりの成果が見られました。たとえば、1日1.25ドル未満で生活する極度の貧困者の割合は、1990年から2010年にかけて半減しました。一方、成長の裏側で国内の格差が拡大し、成長から取り残されている人々もいます。
そしてMDGsの達成期限が近づく今、2015年より先の国際開発目標(ポスト2015年開発アジェンダ)をどうするべきかが問われています。ポスト2015年開発アジェンダにおいては、女性、子ども、若者、障害者、紛争地域で苦しむ人々などを含むあらゆる人々を成長に取り込み、開発の恩恵が広く行き渡るような包摂(ほうせつ)的な成長が求められます。そのためには、一人ひとりの異なる事情に着目し、人々が恐怖や欠乏から免れ、その可能性を開花させることを目指す「人間の安全保障」の考え方が鍵となります。(こちらを参照)
この考えの下に包摂的な成長を実現するためには、様々な課題があります。たとえば、貧しい人たちを直撃する自然災害が開発の成果を損ない、押し流してしまうことのないよう、「防災の主流化」が必要です。また、脆弱(ぜいじゃく)層を含めたすべての人々が基礎的保健医療サービスを受けられることを目指す「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」の実現は、人々の健康改善だけでなく、経済成長にも大きく寄与します。さらに、人々が貧困から脱出するには、生計を立てるための「雇用」を伴った成長が不可欠です。
ポスト2015年開発アジェンダについては、2012年7月に潘基文(パン・ギムン)国連事務総長が立ち上げたハイレベル・パネルや、2013年3月に発足した持続可能な開発目標(SDGs)※に関するオープン・ワーキンググループなど、これまで様々な場で議論が行われてきました。今後、2015年に向けて新しい枠組み策定のための本格的な議論が国連を中心に行われていきます。そうした中、2013年9月の国連総会では「ポスト2015年開発アジェンダ」をテーマとして、MDGsやその後継枠組みについての議論が行われました。日本からも安倍総理大臣や岸田外務大臣が出席し、ポスト2015年開発アジェンダにおいては人間の安全保障を指導理念とし、成長と雇用創出により極度の貧困撲滅を目指し、UHCや防災の主流化を特に重視することを発言しました。また、日本は人間の安全保障やUHCの有用性を発信するためのサイドイベントを主催しました。日本はこれまで行ってきたMDGs達成に向けた取組を加速させるとともに、ポスト2015年開発アジェンダの策定に向けた議論にも、引き続き積極的に貢献していきます。
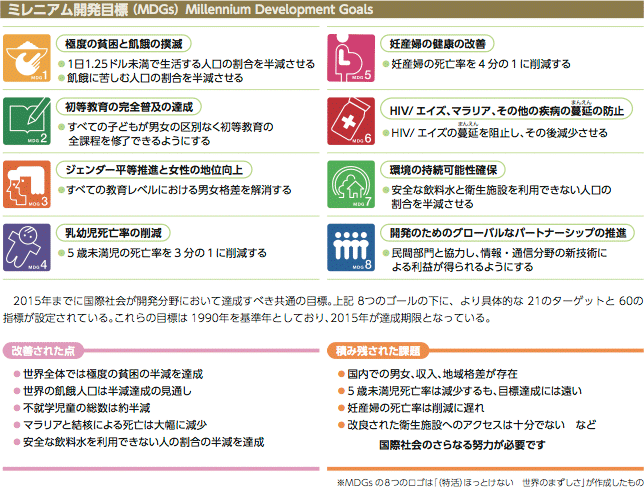
02. ポスト2015年開発アジェンダにおける雇用の重要性
ポスト2015年開発アジェンダを考えるに当たって、日本が重視する分野の一つが「雇用」です。これまで開発分野では、先進国から途上国への「富の移転」という側面が注目されてきました。しかし、貧困撲滅のためには、富を創出する源である成長・雇用に十分光を当てる必要があります。
このような問題意識に基づき、2012年5月にはポスト2015年開発アジェンダにおける「成長と雇用」をテーマとした国連主催の会合が東京で開催されました。また、ポスト2015年開発アジェンダの検討を行うハイレベル・パネルの報告書(2013年5月)や、潘基文国連事務総長の報告書(2013年8月)でも、雇用を伴う経済成長の重要性が指摘されています。
現在、日本でも、若年者が一層活躍し、成長の原動力になるような雇用制度改革が進行中です。雇用への関心が世界的な高まりを見せる中、日本が世界に貢献できることは多くあります。日本がこれまで培ってきた知見を活かしながら、国際機関、NGO・NPOといった課題解決にかかわる多くの担い手と連携を強化していくことで、各国の雇用基盤の強化と雇用促進に一層の効果が上がることが期待されます。
03. 日本の国際貢献の事例 〜ケニアでの若年者雇用プロジェクト〜
日本が国際機関と連携し、途上国で持続可能な若年者雇用に結びつけた具体例の一つとして、日本と国際労働機関(ILO)が2012年にケニアで実施した「持続可能な発展に向けた若者の雇用」プロジェクトがあります。この事業は、2,500人の青年に対し、丸石や「土のう」を用いた労働集約型農道補修技術の訓練を提供し、道路やバスの停留所などのインフラ整備を行うとともに、訓練を受けた青年たちが将来性のある小規模企業を立ち上げることで、雇用の創出を図ることを目的としています。この事業には、日本のNPOである「道普請人(みちぶしんびと)」がパートナーとして参加しました。
工事は、農民が自らの手で行うことができ、維持管理も容易です。ILO・NPOの技術訓練を受けた若者の中には、会社設立後、他の建設会社の工事に自ら参加し、土のう工法以外の道路建設技術を学ぶなど、積極的に職業能力開発に努めた者もいます。
若者が職業能力開発を行うことによって、地域が抱える問題を自ら解決し、貧困から脱するというサイクルは、地域の平和と安定、持続可能な発展にも役立つものです。日本は今後も国際機関やNGOと協働し、効果的な国際協力に取り組んでいきます。
(※用語解説を参照)

土のう工法の訓練を受けた地元住民により、道が生まれ変わる(写真:道普請人)