6. 中南米地域
中南米地域の人口は5億9,000万人で、この地域は域内総生産5.8兆ドルの巨大市場です。また、民主主義が根付き、安定した成長を続けてきた上、鉄鉱、銅鉱、銀鉱、レアメタル(希少金属)、原油、天然ガス、バイオ燃料などの鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあり、国際社会での存在感を高めつつあります。平均所得の水準はODA対象国の中では比較的高いものの、国内での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多いことも、この地域の特徴です。また、アマゾンの熱帯雨林をはじめとする豊かな自然が存在する一方、地震、ハリケーンなど自然災害に弱い地域でもあることから、環境・気候変動、防災での取組も重要となっています。
< 日本の取組 >
中南米地域は、地震、津波、ハリケーン、火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防災の知識・経験を有する日本の支援は重要です。日本は、2010年1月のマグニチュード7.1の大地震により壊滅的な被害を受けたハイチに対する緊急支援や復旧・復興支援をはじめ、太平洋に面した国々に地震、津波対策のための支援を行っています。また、中米域内については、コミュニティ・レベルでの防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな成果を上げています。
中南米は、近年、生産拠点や市場としても注目されており、多くの日本企業が進出しています。2011年にメキシコの医師を招聘(しょうへい)して実施した心臓カテーテル技術*の研修は、日本企業独自の技術の中南米地域における普及を後押しするものとして期待されています。また、中南米諸国の経済開発のための基盤整備の観点から、首都圏および地方におけるインフラ整備も積極的に行っています。
環境問題に対しては、日本は、気象現象に関する科学技術研究、生物多様性の保存、アマゾンの森林における炭素動態の広域評価や廃棄物処理場の建設など、幅広い協力を行っています。近年注目を集めている再生可能エネルギー分野においては、太陽光発電導入への支援を多くの国で実施しており、地熱発電所の建設に向けた支援も行う予定です。
医療・衛生分野でも、日本は中南米に対して様々な協力を行っています。中米地域では、同地域特有の寄生虫病であるシャーガス病撲滅のための技術支援を行い、感染リスクの減少に貢献しています。パラグアイやペルーでは、それぞれ大学病院の改築、医療機材の供与や障害者リハビリセンターの建設を行いました。衛生分野でも、日本は安全な飲料水の供給や生活用水の再利用のため、上下水道施設の整備への協力を数多く行っています。
今も多くの貧困が残存し、教育予算も十分でない中南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要です。日本は、小学校などの教育施設の建設への支援や、指導者の能力向上のためのボランティア派遣などを実施し、現地で高い評価を得ています。
長年の日本の開発協力の実績が実を結び、第三国への支援が可能な段階になっているブラジル、メキシコ、チリ、アルゼンチンの4か国は、南南協力*で実績を挙げています。これらの国と日本はパートナーシップ・プログラムを締結し、たとえば、ブラジルと共に、アフリカのモザンビークでの農業開発分野の協力を進めているほか、アルゼンチン、ドミニカ共和国等と協力し、震災後のハイチの復興支援などを行っています。
より効果的で効率的な援助を実施するため、中南米地域に共通した開発課題については中米統合機構(SICA)やカリブ共同体(CARICOM(カリコム))といった地域共同体とも協力しつつ、広い地域にかかわる案件の形成を進めています。
日本は官民連携で地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T方式)の普及に取り組み、2013年9月末時点までに中南米では12か国が、日本方式を採用しています。日本はこれら採用した国々に対して、同方式を円滑に導入できるよう技術移転を行い、人材育成を行っています。
また、2010年に大地震に見舞われたハイチに対し、日本はこれまで総額1.5億ドルを超える復興支援を実施してきており、引き続き中長期的観点から、保健・衛生や教育といった基礎社会サービス分野を中心に復興支援を行っています。
さらに、2012年10月に発生したハリケーンの被害を受けたハイチに対し、水・衛生、栄養分野の緊急支援を行ったほか、ジャマイカに対して学校および病院の復旧支援を実施しています。

マヌエル・カジェ学校初等・中等教室建設計画引き渡し式の様子(写真:在エクアドル日本大使館)

2013年5月、大統領就任式後の昼食会でのコレア・エクアドル大統領と若林健太前外務大臣政務官
用語解説
- *心臓カテーテル技術
- 具体的には、経橈骨(けいとうこつ)動脈冠動脈カテーテル技術。手首の大きな血管からカテーテルを挿入して、細くなったり閉塞したりしている心臓の血管を広げる方法。
- *南南協力
- より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験と人材などを活用して、他の途上国に対して行う協力。自然環境・文化・経済事情や開発段階などが似ている状況にある国々によって、主に技術協力を行う。また、援助国(ドナー)や国際機関が、このような途上国間の協力を支援する場合は、「三角協力」という。
●ハイチ
「対ハイチ農業技術研修コースプロジェクト」
技術協力プロジェクト(2010年10月~実施中)
ドミニカ共和国とハイチは、カリブ海に浮かぶイスパニョーラ島を東西に分け合って隣接しています。東側のドミニカ共和国が順調な経済成長を続ける一方、西側のハイチは長年の政情不安や度重なる自然災害により発展が遅れています。その両国を、日本が南南協力という形で結びつけました。
ハイチは、人口の5割以上が農業に従事していますが、資金不足、農作物の流通インフラが整っていないこと、また、農業技術が低いことなどにより、国内農業生産は食糧需給の49%しか満たせていません。そのハイチから2010年以降、各回15人程度の「農業普及員」をドミニカ共和国のサンティアゴ高等農業大学に招き、土壌管理・水管理・栽培技術などに関する研修を行っています。研修修了者は、帰国後、有機肥料の導入、廃タイヤを活用した土壌や水の管理を行うなど、研修で習得した技術を活用し、山間部の小規模農家の支援に取り組んでいます。また、研修のフォローアップとして、同大学講師と日本の専門家が研修修了者の活動する農村を訪れ、現地指導も行っています。
このプロジェクトは、2012年11月にウィーンで開催された「国連南南協力EXPO2012」にて、優れた南南協力の取組に対して贈られる「ソリューション賞」を受賞しました。この成果を踏まえ、今後も日本は、南南協力の支援に積極的に取り組んでいきます。(2013年8月時点)

2013年初級研修での測量の実習(写真:JICA)
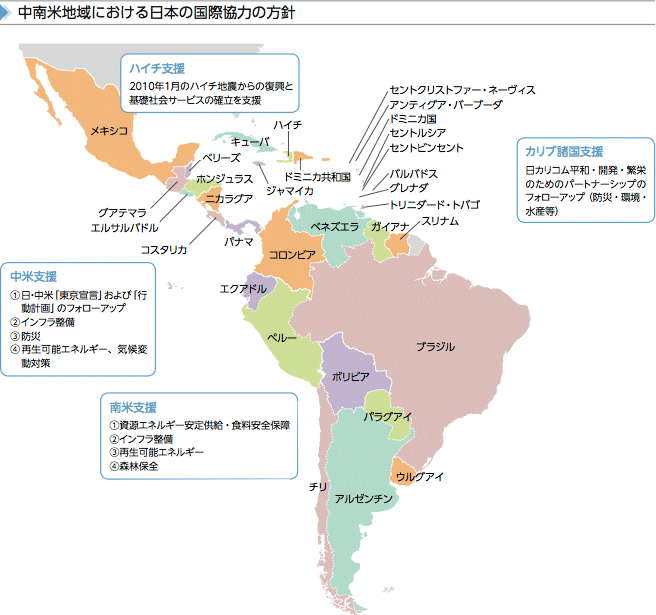

シニアボランティア(野菜栽培)がエルサルバドル東部モラサン県の家族農業開発センターで収穫量増加のための剪定作業の指導を小農に対して行っている(写真:エルネスト・マンサノ/JICAエルサルバドル事務所)
