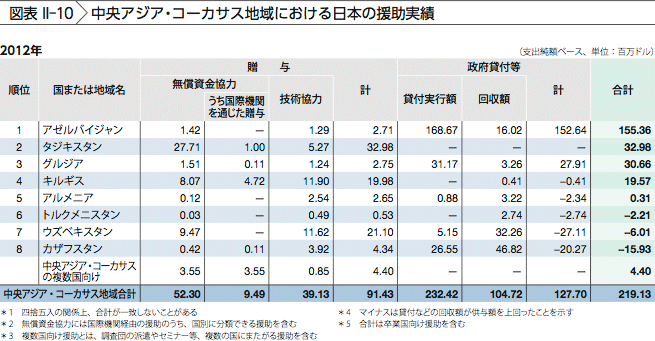3. 中央アジア・コーカサス地域
中央アジア・コーカサス地域は、ロシア、中国、南アジア、中東、欧州に囲まれていることから政治的にも地理的にも重要な地域です。また、石油、天然ガス、ウラン、レアメタル(希少金属)などのエネルギー・鉱物資源が豊富で、資源供給国の多様化を目指して、資源・エネルギー外交を展開する日本にとって戦略的に重要な地域です。そのため、この地域の安定と発展は、日本を含むユーラシア地域全体の安定と発展にとっても重要です。この観点から日本は、人権、民主主義、市場経済、法の支配といった普遍的価値が根付くよう、そして同時にアフガニスタンやパキスタンなど、中央アジアに接する地域を含む広域的な視点も踏まえつつ、この地域の長期的な安定と持続的発展のための国づくりを支援しています。

草の根・人間の安全保障無償資金協力で改修された、グルジア・トビリシ市の幼稚園の子どもたちと牧野たかお外務大臣政務官
< 日本の取組 >
日本は、計画経済体制から市場経済体制への移行と経済発展を支援するため、法制度の整備、保健医療など社会開発の再構築、経済発展に役立つインフラ整備(経済社会基盤)、市場経済化のための人材育成など様々な支援活動を行っています。たとえば、ウズベキスタン、およびキルギスにおける日本センター*では、日本の経験に基づくビジネスコースなどを提供することで、市場経済化に対応できる人材の育成に貢献しています。
カザフスタンおよびアゼルバイジャンのカスピ海沿岸には、世界有数の規模を誇る油田が存在し、日本企業も権益を有しています。この地域が安定し経済が発展することは、国際エネルギー市場の安定とエネルギー資源の確保のためにも重要であり、公共サービスの改善や人材育成、発電所などのインフラ整備といった支援を行っています。
また、日本は、2004年に中央アジア地域の地域内協力を進めることを目的として「中央アジア+日本」対話の枠組みを設立し、これまで外相会合を含めて様々なレベルでの対話や協力を実施しています。日本と中央アジア諸国との外交関係樹立20周年に当たる2012年には、11月に東京にて「中央アジア+日本」対話・第4回外相会合が開催されました。

アゼルバイジャンのシマル・ガス火力複合発電所(第2号機建設計画)
用語解説
- *日本センター
- 中央アジアやインドシナ地域の市場経済移行国における市場経済化を担う人材育成を目指し、日本の「顔の見える援助」として、また日本との人脈を築く拠点として市場経済を目指す9か国に10センターが設置され、現在、7か国8センターでJICAプロジェクトを継続中(プロジェクト終了の2センターも現地で活動を継続)。ビジネスコース、日本語コース、相互理解促進事業を活動の柱としている。
●ウズベキスタン
「ウズベキスタン共和国シルクロード蚕業振興計画」
草の根技協(草の根パートナー型)(2013年3月~実施中)
ウズベキスタンは古くからシルクロードの中継地として絹産業が盛んでしたが、ソビエト連邦崩壊により地域経済は大きな打撃を受け、伝統的な絹産業は衰退していきました。機械の老朽化や技術停滞により、質量とも国際競争に耐える品質の絹糸が生産できず、養蚕農家も激減し、美しい絹織物を生み出してきた伝統産業の継承が困難となっています。こうした状況のもと、東京農工大学は「草の根技術協力事業(草の根パートナー型)」を活用し、2009年よりウズベキスタン国立養蚕研究所と共に、フェルガナ州において女性を含むパイロット農家50軒とその周辺農家に養蚕技術改良のための支援を始め、農家生計向上モデルの構築に取り組んできました。
そこで培った経験を活かし、2013年からは28,000戸の養蚕農家を抱える西部ホレズム州においても、高品質な繭の蚕種自給生産体制の確立と住民の生計向上のための支援を開始しました。こうした取組により、養蚕地域の活性化と高品質蚕糸の安定生産実現を目指しています。日本の絣(かすり)のように織り上げる、古くから伝わる布地「アトラス」(「絹の王様」の意)やそれを用いた工芸品を開発し、それらの生産が農家の副業として定着すること、そしてゆくゆくは「新シルクロード」絹製品として海外に輸出されることも期待されています。(2013年8月時点)

フェルガナ州での養蚕指導(写真:東京農工大学)
●グルジア
「ゴリ地区ゼヴェラ村養鶏場施設建設計画」
草の根無償資金協力(2012年1月~実施中)
グルジアの首都トビリシの北西70㎞に位置するゴリ地区は、南オセチア・アブハジア周辺において2008年に起こった武力紛争の際に空爆を受け、住民の多くが家屋や財産を失うなど、深刻な被害を受けました。また、その時に南オセチアから逃れてきた国内避難民は、依然として経済的に苦しい生活を送っています。
ゴリ地区には、養鶏業で生計を立てている貧困層の小規模農家が600世帯ありますが、使用できる孵化(ふか)器の数は限られています。ほとんどの養鶏農家は、孵化器を使用せず、自宅で飼育している親鶏が温めて孵化していますが、孵化率は約30%と非常に低い状況です。そのため、養鶏農家は、孵化したヒナ鳥を業者から購入して飼育しなければならず、その費用が高いため十分な収入につながりません。
そこで、日本は、ゴリ地区ゼヴェラ村の小規模養鶏農家の協同組合が管理する養鶏場施設の整備を支援しました。協同組合の敷地4,500㎡に、鶏卵の孵化・養鶏・飼料生産が可能な510㎡の養鶏施設を建設し、養鶏用機材を供与しました。また、このプロジェクトは、ポーランドとの協力の下で行われ、日本が養鶏場施設を整備し、ポーランドが加工施設を整備することで、ゴリ地区の小規模養鶏農家が飼育した鶏を出荷しやすい環境が整えられました。
この結果、2012年4月から2013年3月にかけて約30,000羽のヒナ鳥が孵化し、ゴリ地区の小規模養鶏農家600世帯の収入が、1世帯当たり年間約400ドル増えました。(2013年8月時点)

ヒナ鳥の飼料を作る協同組合のメンバー(写真:Heifer International)