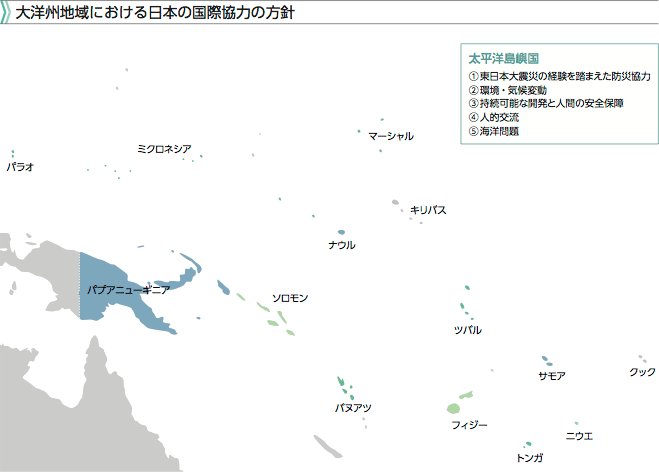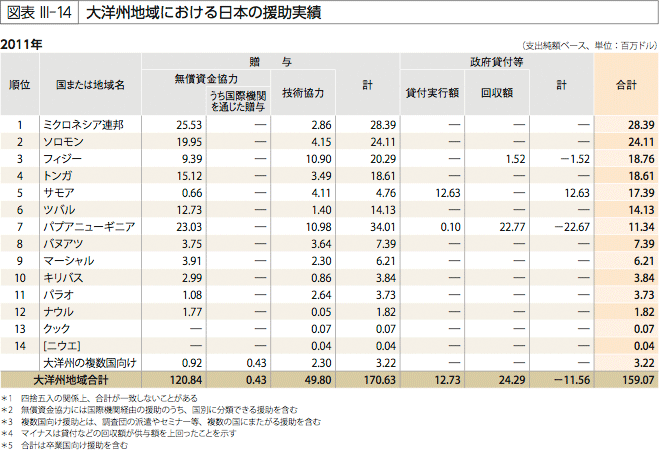7. 大洋州地域
太平洋島嶼(とうしょ)国・地域は、日本にとって太平洋を共有する「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国・地域は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)を持ち、日本にとって海上輸送の要となる地域である上、遠洋漁業にとって大切な漁場を提供しています。太平洋島嶼国・地域の平和と繁栄は日本にとって極めて重要です。
一方、太平洋島嶼国・地域には比較的新しい独立国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。加えて小規模で、第一次産業依存型の経済、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいこと、海面上昇により国土を失ってしまう可能性があることなど、島嶼国・地域に特有の共通の問題があります。さらにフィジーにおける民主化に関する問題も抱えています。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国・地域の良きパートナーとして、各国・地域の事情を考慮した援助を実施しています。

太平洋・島サミットで開催された首脳討議(写真:共同通信社)
< 日本の取組 >
太平洋島嶼国・地域における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的な脆弱(ぜいじゃく)性の克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国・地域で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに日本と太平洋島嶼国・地域との首脳会議である太平洋・島サミットを開催しています。
2012年5月に沖縄県名護市で開催された第6回太平洋・島サミットでは、「We are Islanders: 広げよう太平洋のキズナ」というキャッチフレーズの下、日本は、(1)東日本大震災の経験を踏まえた防災協力、(2)環境・気候変動、(3)持続可能な開発と人間の安全保障、(4)人的交流、(5)海洋問題という5本柱に沿って協力を進めるため、今後3年間で最大5億ドルの援助を行うべく最大限努力することを表明しました。この支援の5本柱の一つである「東日本大震災の経験を踏まえた防災協力」では、東日本大震災の教訓を共有しつつ、太平洋災害早期警報システムの整備などの協力を行っていくこととしています。
太平洋島嶼国・地域は、環境・気候変動、教育や保健などの分野においても課題を抱えており、これらの国々の持続的な発展のため、日本は、各国への協力のみならず、太平洋島嶼国・地域全体の利益を考慮した地域協力を実施しています。
たとえば、気候変動による影響が大きく、自然災害を受けやすい太平洋島嶼国・地域の防災能力を向上させるために、住民が適切に避難できる体制づくりなどを支援しています。また、サモアにある地域国際機関である南太平洋地域環境計画(SPREP)と連携し、国家廃棄物管理計画の策定や廃棄物管理に携わる人材の育成を支援しています。
●トンガ
「美ら島(ちゅらしま)ババウもったいない運動プロジェクト」
草の根技術協力(地域提案型)(2011年9月~実施中)
大洋州の島嶼(とうしょ)国トンガでは、生活様式の変化や輸入品の増加により、プラスチックなどの容器包装類や自家用車など、自然環境の中では処理が困難な廃棄物が増加しており、国土が小さいことも重なって、廃棄物の管理方法が社会問題の一つとなっています。首都ヌクアロファのあるトンガタプ島から300km弱離れたババウ島においては、廃棄物の処分は家庭や集落に任されており、廃棄物の回収システムの構築や有価物(鉄、アルミ、古紙類など他者に買い取ってもらえる不要物)の分別はほとんど行われていません。
島嶼国においては、最終処分場の整備や住民への啓発活動を行うだけではなく、缶やビンなどの有価物のリサイクル・ルート(輸出ルート)を確立し、廃棄物の減量を図る必要があります。特に、これら有価物の輸出を事業として成立させていくことが、持続的な廃棄物管理を行う上で重要となります。これはかつて沖縄が経験してきたことでもあります。
そこで、那覇市および沖縄リサイクル運動市民の会が中心となって、沖縄がこれまで培ってきた知識・経験を活かし、ババウ島での有価物リサイクルの仕組みの構築を目指した支援を行っています。(2012年12月時点)

リサイクルのワークショップを開催(写真:JICA)

キリバスのベシオ病院救急外来で活動する青年海外協力隊員(写真:木下史夫)