4. 平和構築
国際社会では、依然として民族・宗教・歴史などの違いによる対立を原因とした地域・国内紛争が問題となっています。紛争は、多数の難民や国内避難民を発生させ、人道問題や人権を侵害する問題を引き起こします。そして、長年にわたる開発の努力の成果を損ない、大きな経済的損失をもたらします。そのため、紛争の予防、再発の防止や、持続的な平和の定着のため、開発の基礎を築くことを念頭に置いた「平和構築」のための取組が国際社会全体の課題となっています。たとえば、2005年に設立された国連平和構築委員会などの場において、紛争の解決から復旧、復興および国づくりに至るまでの一貫した支援に関する議論が行われています。
< 日本の取組 >
日本は、紛争下における難民の支援や食糧支援、和平(政治)プロセスに向けた選挙の支援などを行っています。紛争の終結後は、平和が定着するように、元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰(DDR)への取組を支援します。そして治安部門を再建させ、国内の安定・治安の確保のための支援を行っています。また、難民や国内避難民の帰還、再定住への取組、基礎インフラ(経済社会基盤)の復旧など、その国の復興のための支援を行っています。さらに、平和が定着し、次の紛争が起こらないようにするため、その国の行政・司法・警察の機能を強化し、経済インフラや制度整備を支援し、保健や教育といった社会分野での取組を進めています。このような支援を継ぎ目なく行うために、国際機関を通じた二国間支援と、無償資金協力、技術協力や円借款といった支援を組み合わせて対応しています。

JICAのルワンダで行われている障害のある除隊兵士の社会復帰のための技能訓練プロジェクト(写真:渋谷敦志/JICA)
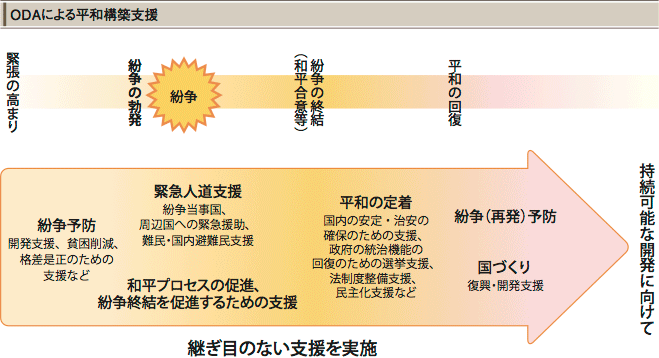
●エジプト
「エジプトの新しい国づくりへの支援」
選挙支援
いわゆる「アラブの春」で、30年続いたムバラク政権の崩壊後、エジプトは新しい国づくりという課題に直面しています。新議会と新大統領、新憲法をつくり上げていく政治プロセスが始まり、アラブの春が本当の「春」となるかどうか、「選挙」が重要な鍵となります。
日本は、ムバラク政権崩壊後の2011年2月、エジプト政府からの支援要請を受け、同年3月に選挙支援専門家をエジプトに派遣。次いで7月には現地セミナーをカイロにて開催し、日本人専門家が選挙制度、政治資金などについて選挙委員会をはじめ関係機関に解説し、選挙準備実施体制強化を図りました。10月には、投票日を控えたエジプトで、民主的な選挙報道をテーマに、エジプト国営放送局でメディア関係者向けのセミナーを開催しました。また、選挙委員会の新しい機能であるメディアセンター等の設置に際して機材支援を行い、新しい選挙に臨むエジプトの有権者への情報提供を促進し、投票率の向上、無効票の減少にも貢献しました。
「現地の自主性を尊重する」、「中立で公平な選挙の実現の鍵を握るメディアを支援」といった、日本が培った選挙支援の知識と経験は、今回のエジプト支援でも十分に活かされています。日本のエジプトでの選挙支援が、新発足する議会支援、常設機関となる中央・地方の選挙委員会への支援へとつながっていくことが期待されています。

人民議会選挙における投票所の様子(写真:松田泰幸/在エジプト日本大使館)
●スリランカ
「マナー県再定住コミュニティ緊急復旧計画プロジェクト」
有償勘定技術支援-円借款附帯プロジェクト(開発計画調査型)(2010年3月~2012年7月)
スリランカでは、約26年間続いた政府軍とタミル・イーラム解放の虎(LTTE)による紛争が2009年に終結し、約28万人とされた国内避難民(IDP)が紛争の舞台となった北部を中心に故郷に帰っています。中でも自然条件が厳しく、貧困率も高いマナー県には、内戦終結後、2012年7月までに約9万2,000人が帰還しましたが、同県は以前から開発が遅れていた上、戦闘により住居や公共施設、農業や漁業のための設備などが破壊され、帰還民は生計手段を再建することが難しい状況にあります。
このような状況の中、日本はマナー県の11の村の24コミュニティで、生活基盤の再建から生計手段の確保、住民組織の強化にわたるまで包括的な支援を行い、帰還民の再定住を支援しています。これまで給水設備の復旧、コミュニティセンターの再建、地鶏の孵化(ふか)場建設、マット(ござ)生産やパン製造のための機器機材の供与、漁業組合に対する会計マネジメント研修の実施などを通じ、同県の計約7,640人に支援を行いました。また、こうした地域に根ざした復旧事業を通じて得た生活再建における知識・経験を活かして、今後のマナー県全体の生産活動の再開に向けた総合的な開発計画を作成しました。今後、住民の大部分を帰還民が占める同県全域を対象に、日本が作成した計画を基にスリランカ自身による復興、開発が期待されます。

生計確保のために紛争前から作っていたござ作りを再開、生産施設の再建や機織り機の供与を行った(写真:JICA)
●平和構築分野での人材育成
平和構築の現場で求められるものは、多様化し複雑になってきています。これらに対応するため、日本は2007年度から、現場で活躍できる日本やアジアの文民専門家を育成する「平和構築人材育成事業」を実施しています。この事業は、平和構築の現場で必要とされる実践的な知識および技術を習得する国内研修、平和構築の現場にある国際機関などの現地事務所で実際の業務に当たる海外実務研修、ならびに修了生がキャリアを築くための支援を柱としています。これまでに185名の日本人およびその他のアジア人が研修コースに参加しました。その研修員の多くが、南スーダン、シエラレオネやアフガニスタンなどの平和構築の現場で活躍しています。