第4節 豊かな潜在力を持つメコン・インド・アフリカ
厳しさを増しつつある国内のビジネス環境の中で、新たな事業展開のため、また、市場を求めて、海外に進出を図る日本企業が増えています。そうした企業の事業拡大の受け皿としてメコン地域は改めて重要性を増しつつあります。巨大な人口と高い経済成長を遂げているインドとの経済関係も今後さらなる発展の可能性を持っています。インドを国内市場中心にではなく、輸出拠点として見る企業も出始めてきています。また、一部に成長の兆(きざ)しを見せ始めたアフリカは豊かな資源の供給元のみならず、将来の市場としての可能性も秘めています。豊かな潜在力を持つこうした国や地域において、援助を受ける側、援助を行う側の双方が共に成長を加速させるための支援を、日本としても積極的に行っていきます。
1. メコン
メコン川流域のメコン地域諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム)の多くは、長らく戦争、紛争の中にありました。1975年まで30年以上も続いたベトナムでの戦争後もカンボジアでのポルポト政権による虐殺などの悲劇が続きました。ようやく1991年のカンボジアの和平合意により、地域全体に平和が確立されたのは、今からわずか20年前のことです。日本政府はこの間、一貫してメコン地域の安定・発展をアジア外交の柱とし、地域の安定と発展に大きく貢献してきました。メコン地域諸国はいずれも伝統的な親日国で、豊富な天然資源と労働力を有し、日本企業の関心が特に高い地域です。メコン地域諸国は他のASEAN諸国とは違い、陸続きで国土が隣接しており、未開発の広大な内陸部が存在しています。つまり、発展のためには、インフラ整備、資源開発など地域内での協力が不可欠なのです。日本政府は、この点を踏まえ、メコン地域で活動を行っている産業界の具体的なニーズも把握しながら、メコン地域のインフラ開発・産業発展に向けた協力を進めています。また、地域開発に向けた域内協力に対しても日本として積極的に取り組んでいます。
日本とメコン諸国との関係は緊密です。2008年からは日メコン外相会議を、さらに2009年からは日メコン首脳会議をいずれも毎年開催しています。2012年4月に東京で開催された第4回日メコン首脳会議では、2015年までの日メコン協力の新たなビジョンを示す「東京戦略2012」を採択しました。この中で「メコン連結性を強化する」(域内の連結性支援)、「共に発展する」(投資・貿易の促進)、「人間の安全保障・環境の持続性を確保する」(災害対策、母子保健等への支援)という新たな協力の柱が示されています。また、日本は、この実現に向けた具体的手段として、ODAについて、2013年度以降3年間で、約6,000億円の支援を実施することを表明したほか、ラオスにおける国道9号線(メコン地域東西経済回廊)整備計画や南部地域電力系統整備事業計画、カンボジアにおけるネアックルン橋梁(きょうりょう)建設事業(メコン地域南北経済回廊)やミャンマーにおけるティラワ経済特別開発事業を含む事業総額約2兆3,000億円と見積もられる主要インフラ案件(57案件)のリストを各国に対して提示しました。さらに2012年7月にカンボジア・プノンペンで開催された第5回日メコン外相会議では、「東京戦略2012の実現のための日メコン行動計画」を採択しています。
また、官民が協力してインフラの建設や運営を行うことが増えてきたことも踏まえ、ODAにおいても、日本企業からの提案に基づき、円借款等の事業実施を前提とした案件を進めることとしています。具体的には、ベトナムのラックフェン国際港建設計画の実施、海外投融資を活用したロンアン省環境配慮型工業団地関連事業の実施やロンタイン新国際空港建設事業などについての案件形成に向けた調査が行われています。
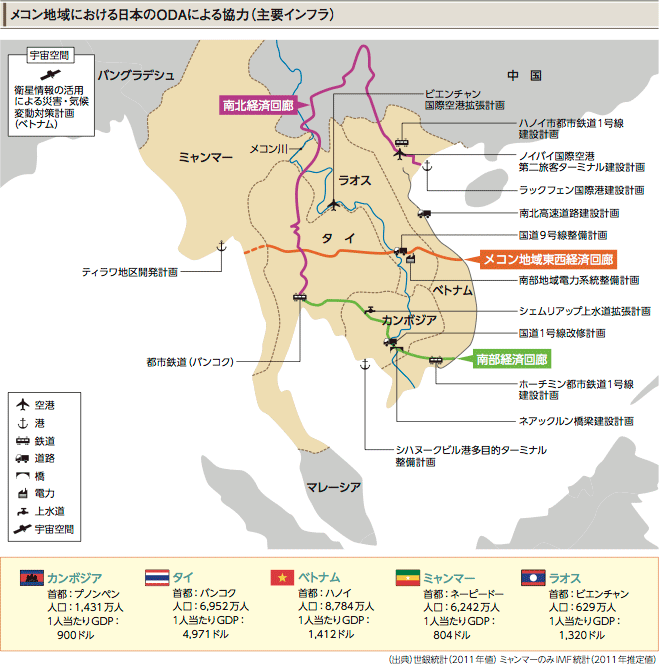

カンボジア「国道1号線改修計画」
改修済みの歩道では、子どもたちは、安全に通学できるようになっている。ネアックルンまでこのような道が続く(写真:高橋智史/JICA)

カンボジア「ネアックルン橋梁建設計画」ネアックルン橋梁建設予定地にて測量作業中のベトナム人技術者
(写真:佐藤浩治/JICA)
2. インド
インド進出を目指す日本企業はますます増えています。少子高齢化により国内市場が縮小する中で、インドを中国に次ぐ巨大市場ととらえる企業は多く、近年の高い経済成長率(2006-2011年の平均GDP成長率は8.5%)も相まって2012年10月時点で進出日系企業は926社に上りました。日インド貿易額も2002年の4,958億円から2011年の1兆4,253億円へ、直接投資も2002年の187億円から2012年2,215億円(暫定値)へと大幅に拡大しています。
インド政府側も規制緩和を行うなど外国資本の受入れに前向きになったこともあり、多くの日系企業が高い潜在成長性を持つインドに注目しているのです。2011年度の日本企業に対する国際協力銀行(JBIC)調査によれば、インドは事業展開先として長期的に有望な国の中で、中国を抑え第1位となっています。
2011年8月に発効した日インド包括的経済連携協定(CEPA)も追い風となっています。この協定の下で両国は今後10年間で貿易額の約94%の関税を撤廃することとなり、二国間貿易は大幅に増えることが期待されます。インドを輸出拠点としてとらえる日本企業も増えており、欧州・アフリカ向け輸出のためのグローバル拠点に位置付けている企業もあります。
ただし、企業進出にも問題がない訳ではありません。企業が投資先としてのインドの課題として第一に挙げるのは、インフラの未整備によるコストの問題です。たとえば、物流に関して、鉄道輸送では旅客優先のために運行スケジュールが乱れやすい上、貨物運賃は旅客に対して高めに設定されている、幹線道路未整備のために遅延や貨物の棄損が頻繁に起こる、などの問題があります。これに対して、日本の技術を活用し、デリー・ムンバイ間(西回廊)貨物専用鉄道建設事業を円借款により支援しています。これにより今後見込まれる貨物輸送需要に対応し、物流ネットワークの効率化を図ることができます。デリー、ムンバイを含む西回廊の周辺には多くの日系企業の拠点があるため、現在そうした企業の行う事業の障害となっている運輸インフラも改善されることになります。
インドでは、また、恒常的な電力不足と停電の頻発が深刻で、工場では自家発電設備が不可欠となっています。こうした状況に対し、日本は、タミル・ナド州送電網整備計画を支援することで、チェンナイ周辺をはじめとする州内全域の電力の安定供給を行い、州内の生活環境の改善、進出日本企業のビジネス環境の改善、投資促進に貢献しています。さらに、日本企業の進出が著しいインド南部における、運輸・電力セクターなどをはじめとする地域の総合開発を目的としたマスタープランづくりについても協力しています。
3. アフリカ
2000年以降のアフリカの平均経済成長率は5%を超えています。2001年からの10年間で名目GDPは約2.8倍(1兆6,200億ドル)、貿易量は約3.6倍(9,700億ドル)になりました。また、アフリカへの直接投資額はこの10年で約5倍(550億ドル)に上り、2007年には、アフリカへの直接投資額がアフリカへのODA額を超えています。アフリカは、アジアに次ぐ新たな経済フロンティアとして世界の注目を集めています。
アフリカ経済の好調を支えている大きな要因は、豊富な天然資源と高い人口成長率です。白金族(世界全体の埋蔵量の約95%)、ダイヤモンド(同約59%)、コバルト(同約49%)、クロム(同約42%)といった鉱物資源の埋蔵量はアフリカに集中しており、また、石油埋蔵量トップ20のうち4か国、天然ガス資源埋蔵量トップ20のうち3か国もアフリカが占めています。こうした天然資源の開発を進め、強固で持続可能な経済成長にも役立つインフラ整備はアフリカにとって差し迫った課題であり、現在、様々なレベルで、主要な港湾都市や内陸都市、さらに資源産出地を結ぶために、道路、鉄道、港湾、国境施設といったインフラ整備を目的とする回廊計画(南北回廊、ナカラ回廊など)などのインフラ開発計画が進行中です(世界銀行の試算によれば、アフリカのインフラ需要見込みは年間当たり930億ドルです)。
アフリカの平均人口成長率は2.3%と六大陸中最も高く、10年ごとに3億人増加する見込みです(2010年の総人口は約10億人)。2010年のアフリカの1人当たりGNIは1,570ドルで、同様の人口規模を有するインドの約1.2倍であり、将来の消費市場としての潜在性の大きさがうかがい知れます。現在、アフリカでは経済統合の動きが進んでおり、大陸レベルでは2017年までの自由貿易地域(FTA)の創設、地域レベルでも2014年までのFTA創設を目指しています。
アフリカは、同時に社会的課題(貧困削減、基礎的サービスの提供等)を抱えており、これら課題の解決とビジネスの両立を目指すBOPビジネス*が拡大しつつあります。日本企業のアフリカでのBOPビジネスに対する支援手段としては、JETROによる、パートナー発掘や現地ニーズ・市場調査のための個別相談対応、JICAによるBOP層の開発課題の解決に役立つビジネスモデルとの連携のための調査や関連事業への投融資等が整備されています。
2013年6月、横浜で開催されるTICAD(ティカッド) Vでは、質の高い成長を目指し、より強固で持続可能な経済を実現するため、官民連携の下、インフラ開発等へ民間セクターの関与を促進させる具体的な取組が議論されます。アフリカ経済の潜在性の大きさと、アジアに次ぐ経済フロンティアとしてのビジネスチャンスに世界の注目が集まる今、アフリカ各国から日本企業の投資増が期待されていることを踏まえ、TICAD Vが日本企業のアフリカでのビジネス展開を拡大する重要な契機となるよう、日本政府は、オールジャパンでアフリカの投資環境整備支援に取り組み、様々な施策を実施していく考えです。

エチオピア水技術センターを視察する松山政司外務副大臣。水技術センターに対して日本は長年技術指導を行っている(写真:在エチオピア日本大使館)
- *BOPビジネス(BOP:Base Of the economic Pyramid 開発途上国・地域の低所得階層)
- 途上国の低所得層※を対象にした社会的な課題解決に役立つことが期待されるビジネス。低所得層は約40億人、世界人口の約7割を占めるともいわれ、潜在的な成長市場として注目されている。低所得者層を消費者、生産者、販売者とすることで、持続可能な、現地における様々な社会的課題の解決に役立つことが期待される。
事例:洗剤やシャンプーなどの衛生商品、水質浄化剤、栄養食品、防虫剤を練り込んだ蚊帳、浄水装置、太陽光発電など。
※低所得層:1人当たりの年間所得が購買力平価で3,000ドル以下の層。購買力平価とは物価水準の差を除去することによって、異なる通貨の購買力を等しくしたもの。