第2節 日本への信頼を強化するODA-貧困削減を実現するための成長
2000年9月、国際社会はミレニアム宣言を採択し、21世紀にどのような世界を目指すのかというビジョンを共有しました。このミレニアム宣言と1990年代に主要な国際会議等で採択された国際開発目標を統合し、ミレニアム開発目標(MDGs)がまとめられました。MDGsは、極度の貧困と飢餓の撲滅、初等教育の完全普及、乳幼児死亡率の低減、妊産婦の健康改善、環境の持続可能性確保など人間・社会開発中心の目標であり、経済成長そのものを目指すものではありません。
しかし、この十数年を振り返ると、持続的な経済成長を遂げたアジア(特に中国・インド・東南アジア諸国の一部など)では、力強い成長に牽引されてMDGsの指標に大きな進展が見られます。日本は、これらの国に対して保健医療や教育など、貧困層が直接恩恵を受ける分野に加え、インフラ整備を支援し、さらに、貿易・投資の活性化、法制度整備、産業の育成と雇用機会の創出、技術移転と人材育成の促進を図ることで、その国の経済成長に直接つながる支援も行ってきました。経済成長は開発に必要な富をつくりだし、途上国の開発の大きな推進力となります。そして成長の過程に貧困層を巻き込み、成長の成果を分かち合うことが、貧困削減を進め、すべての人々に恩恵が行き渡る包摂(ほうせつ)的(注1)な成長を実現することになるのです。

ハノイで共同記者会見に臨む安倍晋三総理大臣とグエン・タン・ズン・ベトナム首相。両首脳は、貿易・投資・インフラ整備等の分野で協力を進めていくことで一致した
日本は、国際機関等への融資を通じて、インフラ整備を進めながら経済成長を実現し、戦後復興を成し遂げた経験を持っています。そして、その後、自らの経験を活かし、援助国として東アジアを中心に援助を行い、実績を上げてきました。無論、途上国の状況は国ごとに異なるため、東アジアの処方箋を画一的に他の国や地域に適用することは必ずしも適当ではありません。国、地域ごとの事情に対応する多様な手段による取組により、経済成長を実現することは、貧困削減のためには不可欠です。
しかし、単に国家の経済成長を追求し、国ごとの平均値の指標のみを見ていては、成長の裏側で富裕層と貧困層、都市部と農村部、男女、少数民族等の間に存在する格差が覆い隠され、本当に支援を必要とする弱い立場の人々に必ずしも支援が届かないという問題が出てくることもあります。そうした事態を避けるためには、あらゆる人々の状況を改善しながらも、より弱い立場の人々の状況については一層の底上げを図るという考え方である「衡平性」の確保が重要になります。これは、そのコミュニティにおける人間の安全保障を実現するために不可欠ともいえ、これらの考え方は相互に密接にかかわっています。
人間の安全保障とは、日本が、MDGs達成に向けた取組等を行うに当たり中心に置いている考え方であり、極度の貧困や感染症などの様々な恐怖にさらされている人間一人ひとりに着目し、人々が恐怖や欠乏から免れ、尊厳を持って生きることができるような社会を目指すものです。
人々が、貧しい人たちも含め、健康な心身を持ち、適切な教育を受けて、平等な機会の下でその能力を開花させ、雇用されて経済活動にも参画することが、コミュニティや国家の発展に結びつきます。
このようにして個人を成長に取り込み、成長の成果を共有して開発の恩恵が広く行き渡るような包摂的な成長が必要です。日本は人間の安全保障に基づいて多元的な支援を行うことで貧困削減と包摂的成長に貢献しています。こうした日本の取組は、諸外国の日本に対する信頼の強化に大いに役立っています。
しかしながら、2015年にMDGsの達成期限が来ても課題がなくなるという訳ではありません。では、2015年より先の開発目標(ポストMDGs)はどうあるべきでしょうか。質の高い経済成長を通じた貧困撲滅を目指し、人間の安全保障や衡平性の考え方に基づき、様々な開発の担い手が協力して相互に助け合う枠組みとする必要があります。日本は、これまで行ってきた支援や開発の成果も踏まえ、MDGs達成に向けた取組を加速させるとともに、ポストMDGsの議論にも引き続き積極的に貢献していきます。
注1 : 「包摂的」とは、異なる社会や文化的背景、障害を含む個人的特性などを理由にして起こる排斥や区別を排し、誰もが対等な関係でかかわり合い、社会や組織の一員として参加できる社会を提供すること。特に、社会的弱者や社会から阻害された集団に対して参加を容易にさせること
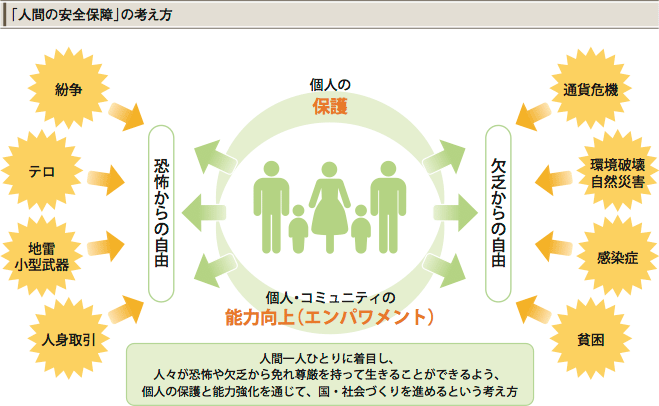
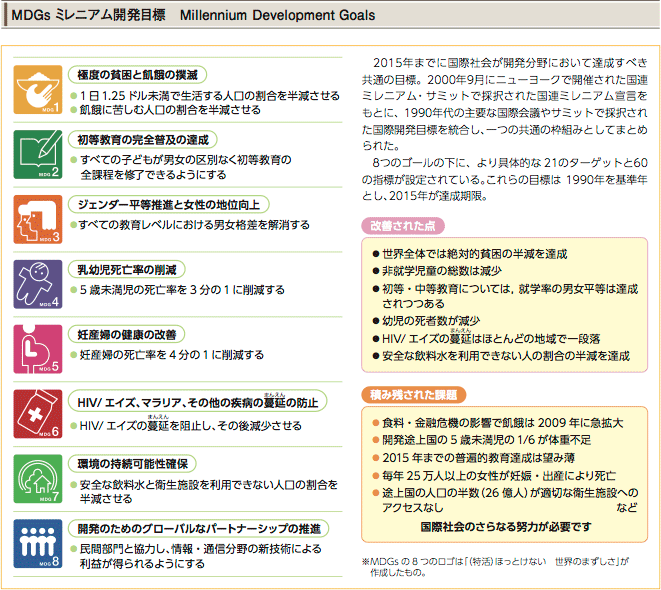

スリランカの幼稚園で活動する幼児教育隊員(写真:小椋知子)