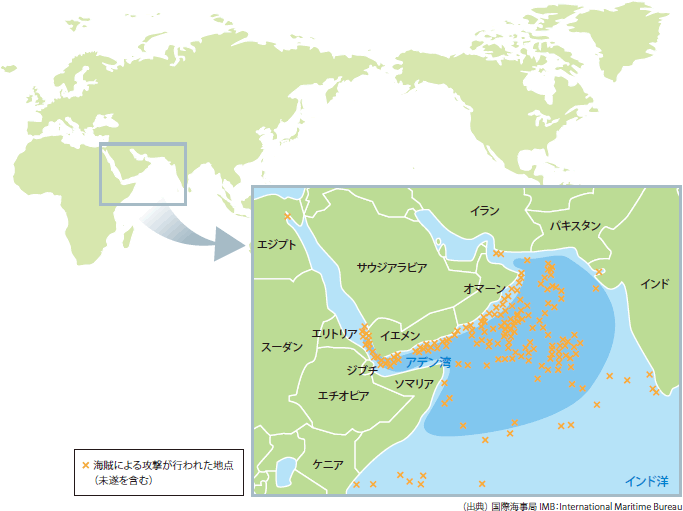(6)国境を越える犯罪・テロ
グローバル化やハイテク機器が進歩し、人々の移動の拡大などが進み、国際的な組織犯罪やテロ行為は、国際社会全体を脅かすものとなっています。薬物や銃器の不正な取引、不法な移民、女性や子どもの人身取引、現金の密輸出入、通貨の偽造および資金洗浄(マネーロンダリング)*などの国際的な組織犯罪は、近年、その手口が一層多様化して、巧妙に行われています。国際テロ組織「アル・カーイダ」は、指導者であったウサマ・ビン・ラーディンが死亡したものの、その勢力は今でも軽視できません。特に、アル・カーイダの思想やテロ手法の影響を受けている関連組織による過激主義運動が新たな脅威となっています。国境を越えて進行する国際組織犯罪やテロ行為に効果があるよう対応するには、一つの国のみの努力では限りがあります。そのため各国による対策強化に加え、開発途上国の司法・法執行分野における対処能力向上支援などを通じて、国際社会全体で法の抜け穴をなくす努力が必要です。

青年海外協力隊員が活動するスリランカ唯一の女性専用更正施設。売春、麻薬などの軽犯罪者や浮浪者などが収容され職業訓練を受ける(写真提供:久野真一/JICA)
< 日本の取組 >
●薬物対策
日本は国連麻薬委員会などの国際会議に積極的に参加するとともに、国連薬物犯罪事務所(UNODC)(注49)の国連薬物統制計画(UNDCP)(注50)基金への拠出などを行い、アジア諸国を中心に開発途上国を支援しています。2010年度には、約138万ドルのUNDCP基金への拠出を活用して、ミャンマーにおける「けし(麻薬の一種であるアヘンの材料になる植物)」の不正栽培を監視し、不正な合成薬物製造の調査を行う事業、東南アジアや太平洋地域における薬物統制に関する事業、ラオスにおける薬物統制計画を作成する支援事業などを実施しました。また、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)を通じて、薬物犯罪者処遇についての研修を実施しました。
●人身取引対策と腐敗対策
日本は、2010年度には、UNODCの犯罪防止刑事司法基金(CPCJF)(注51)に対し、9万ドルを拠出しました。さらに2011年8月には、日本が設置を主導した国連人間の安全保障基金を通じて、国際移住機関(IOM)(注52)等が実施する「インドネシアにおける人身取引被害者の保護と能力強化」事業に対し、約236万ドルの支援を決定しました。
人身取引対策については、被害者の緩和ケア(芸術療法等を通じた心理ケア)および社会復帰のための支援に重点的に取り組んでいます。これまでにCPCJFへ拠出することでタイのパタヤにおける人身取引対策プロジェクト(人身取引および性的搾取からの子どもの保護)を実施しました。また、フィリピンの人身取引に関する捜査実務手続の基準を促進するための警察支援を実施します。さらに、今後も東南アジアを中心に支援を行っていくことを検討しています。また、日本で保護された被害者については、IOMを通じて被害者の安全な帰国と本国での社会復帰を支援しています。さらに日本は、不法移民・人身取引および国境を越える犯罪に関するアジア太平洋地域の枠組みである「バリ・プロセス」への支援も行っています。
腐敗対策については、 CPCJFへ拠出することで、これまでにベトナムにおける腐敗防止対策セミナーの開催を支援し、日本のODAの受取国でもある同国において腐敗対策の取組を強化することに貢献しました。今後、他の東南アジアにおいて同様のセミナーを実施するよう、UNODCと協議中です。
UNAFEIを通じて、アジア・太平洋地域を中心とした開発途上国の刑事司法実務家を対象に、様々な研修・セミナーを実施しました。これらの研修・セミナーは、「証人・内部通報者の保護および協力の確保」、「腐敗予防」など国際組織犯罪防止条約および国連腐敗防止条約上の重要論点をテーマとしており、各国における刑事司法の健全な発展と協力関係の強化に貢献しています。
●テロ対策
テロリストにテロの手段や安住の地を与えないようにし、テロに対する弱点を克服するように努めなければなりません。日本は、テロ対処能力が必ずしも十分でない開発途上国に、テロ対策能力向上のための支援をしています。特に2006年以降、テロ対策等治安無償資金協力が創設され、日本は開発途上国でのテロ対策の支援を強化しています。
とりわけ日本と密接な関係にある東南アジア地域におけるテロを防止し、安全を確保することは、日本にとっても重要であり、より力を入れて支援を実施しています。具体的には、出入国管理、航空の保安、港湾・海上の保安、税関での協力、輸出の管理、法執行のための協力、テロ資金対策(テロリストやテロ組織への資金の流れを断つための対策)、テロ防止に関連する諸条約などの各分野において、機材の供与、専門家の派遣、セミナーの開催、研修員の受入れなどを実施しています。
たとえば、日本は1987年度から2010年度まで毎年「出入国管理セミナー」を開催し、東南アジア諸国などの出入国管理行政機関の担当者を招き、情報・意見交換を通じて相互理解を深め、協力関係を強化しました。これは各国の出入国管理業務に携わる職員の能力の向上にもつながっています。
2011年2月には南アジア諸国等からテロ対策の関係者を招き、テロ防止関連条約の理解を深め、条約の締結を促進することを目的としたセミナーを開催しました。さらに、日本は2010年度にUNODCテロ防止部へ約4万8,000ドルの拠出を行い、インドネシアを中心としたASEAN諸国に対しテロ対策法整備のための支援を実施しました。また、2011年1月、アフガニスタン等におけるテロ対策のためにUNODCのテロ防止部へ175万ドルの拠出を実施しました。

タイ「メコン地域における税関リスクマネジメントプロジェクト」メコン側のタイとラオスを結ぶ友好橋のたもとにある通関事務所で通関業務の進め方を確認する日本人専門家とタイ通関職員(写真提供:久野真一/JICA)
●海賊行為への対策
日本は、エネルギーや食料資源の輸入、また、貿易の多くを海上輸送に依存している海洋国家です。テロ・海賊対策といった、海上の船の航行を安全に保つための対策は、日本にとって国家の存立・繁栄に直接結びつく課題です。加えて、海上の安全は、地域の経済発展を図る上でもきわめて重要なものです。近年、アフリカ東部のソマリア沖・アデン湾では、海賊事案が多発しています。国際社会全体による取組は、一定の成果を挙げているものの、海賊による攻撃の発生件数は年間219件(2010年)に達しており、発生海域もソマリア沖・アデン湾からインド洋西部全体に拡大し、船の航行の安全にとって大きな脅威となっています。
こうした脅威に対し、日本は2009年6月に成立した「海賊対処法」に基づき、海上自衛隊の護衛艦2隻およびP-3C哨戒機(しょうかいき)2機をソマリア沖・アデン湾に派遣し、海賊対処行動を実施しています。また、海賊行為があった場合の逮捕、取調べ等の司法警察活動を行なうため、海上保安官が護衛艦に同乗しています。
ソマリア沖の海賊問題を解決するためには、こうした行動に加え、沿岸国の海上取締り能力の向上や、海賊による被害の増加の背景にある不安定なソマリア情勢の安定化を含めた多層的な取組が必要です。これらの取組の一環として日本は、国際海事機関(IMO)(注53)の基金を設立するために中心となって働きかけ、ソマリア周辺地域における海賊対策の訓練センターや情報共有センターを設立するなど、これまで1,460万ドルを拠出しています。
また、海賊に対する訴追を支援するためにUNODCの基金に対し、累計150万ドルを拠出しています。ほかにもJICAと海上保安庁の協力の下で、ソマリア周辺国の海上保安機関職員を招き、「海上犯罪取締り研修」を実施しています。さらに、ソマリアにおいて和平が実現するように2007年以降、ソマリア国内の治安の強化、および人道支援・インフラ整備のために約1億8,400万ドルの支援も実施しました。

海上保安庁の協力を得た「アジア・中東海上犯罪取締り研修」巡視船の操舵室で、日本の海上保安官から研修を受けるアジア・中東の海上保安機関や沿岸警備隊職員(写真提供:JICA)
用語解説
*資金洗浄(マネーロンダリング)
犯罪行為によって資金を得たり、収益をあたかも合法な資産であるかのように装ったり、資金を隠したりすること。例)麻薬の密売人が麻薬密売代金を偽名で開設した銀行口座に隠す行為。
注49 : 国連薬物犯罪事務所 UNODC:United Nations Office on Drugs and Crime
注50 : 国連薬物統制計画 UNDCP:United Nations International Drug Control Programme
注51 : 犯罪防止刑事司法基金 CPCJF:Crime Prevention and Criminal Justice Fund
注52 : 国際移住機関 IOM:International Organization for Migration
注53 : 国際海事機関 IMO:International Maritime Organization
2012年1月1日より、IMO事務局長に関水康司前IMO海上安全部長が就任した
●フィリピン
「フィリピン海上保安教育・人材育成管理システム開発プロジェクト」
技術協力プロジェクト(2008年1月~実施中)
フィリピンは日本と同じく海に囲まれた島嶼(とうしょ)国であり、海上輸送を主要な交通手段の一つとしています。しかし、その周辺海域では天災・人災により海難事故が毎年多発しています。また、海上保安の体制が不十分であることから、死亡者・行方不明者がきわめて多くなっているほか、タンカーの油流出事故による環境汚染、密輸その他の不法行為、テロ・海賊行為などにも十分に対応できていません。こうした背景を受け、日本は海上保安庁の協力の下、これまでフィリピン沿岸警備隊に対して様々な課題に対応するための技術協力を進めてきています。現在は、日本がこれまでに協力してきた内容も含め、フィリピン沿岸警備隊が自ら必要な人材育成を行っていけるようにするための教育・訓練システムの整備を支援する取組を進めています。

消火訓練の実習(写真提供:JICA)
海賊行為が多発している海域