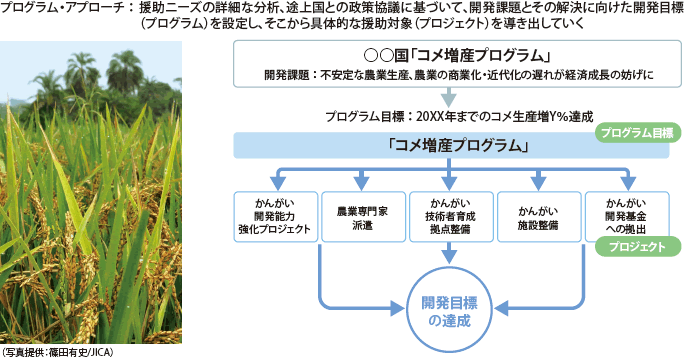第3章 新たな援助の方向性

ボリビア「氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発」ラパス市郊外の観測地点で気象の観測データをパソコンに読み込む日本人専門家とボリビア人技術者(写真提供:久野真一/JICA)
第1節 プログラム・アプローチの強化
日本の経済・財政状況が厳しい中で、国民の幅広い理解を得ながら、限られた予算で最大限の効果を上げるためには、「選択と集中」による戦略的で効果的な援助を行う必要があります。このため「ODAのあり方に関する検討 最終とりまとめ」(2010年6月発表)においてもプログラム・アプローチ(個別プロジェクトを越えて、特定の開発課題に対し援助手法を組み合わせて取り組む)を強化していく方針を打ち出しました。
これまでは、原則として途上国からのプロジェクトごとの要請に基づいて、個別の支援案件の実施を検討してきたため、支援の必要性や成果を判断するのに、どうしても個別案件(プロジェクト)にのみ着目しがちでした。今後は、途上国との政策協議に基づいて、特定の開発課題の解決に向けた目標を設定した上で、その目標達成に必要な具体的案件を導き出していく、プログラム・アプローチに移行していくことになります。
このやり方により、プログラム目標の達成に必要な個別のプロジェクトについて、無償資金協力、有償資金協力または技術協力といった様々な援助手法を有機的に組み合わせることで、プロジェクト間の相乗効果を高め、全体としてより大きな成果を上げることが期待できます。また、プログラム目標の達成に必要な投入要素や規模についてある程度予測ができるようになり、相手国政府や他ドナーにとっても中長期的な開発・援助戦略が立てやすくなります。さらに、日本による支援の政策的意図や援助の効果等についてより筋道だった説明が可能となり、政府としての説明責任を果たすことにもつながります。
プログラム・アプローチに試行的に着手するために、既に下記の試験的プログラムを選定しています。今後こうしたプログラムの増加を図ることで、徐々にプログラム・アプローチの浸透・強化に取り組んでいく予定です。
【試験的プログラム】
(1) インドネシア「ジャカルタ首都圏投資促進のための運輸交通環境整備プログラム」
運輸・交通の容量・能力が飽和状態にあるジャカルタ首都圏において、運輸・交通・物流の関連インフラ整備および効率化を通じて、同地域の投資環境・ビジネス環境の改善を目指すもの。
(2) ガーナ「アッパーウエスト州母子保健システム強化プログラム」
日本が重点的に支援を実施しているアッパーウエスト州における母子保健システム(母子保健についての予防や治療サービスを組織的に提供する仕組み)の改善を目指すもの。
(3) タンザニア「コメ生産能力強化プログラム」
日本も主要援助国として援助協調を進めているタンザニアにおいて、特に不安定な生産能力に悩む農業分野に着目し、コメ生産力の増強を目指すもの。
(4) バングラデシュ「基礎教育内容向上プログラム」
就学率が向上している一方で、修了率の低さ(中途退学率や留年率の高さ)が問題となっているバングラデシュにおいて、教育の質を向上させることによって、初等教育の修了率向上を目指すもの。
(5) ラオス「電力整備プログラム」
水力開発のポテンシャルが高いにもかかわらず国内の電力供給力不足および低い電化率に悩むラオスにおいて、安全かつ安定的な電力供給の拡大を目指すもの。

インドネシアの首都ジャカルタ市内の帰宅時間帯の渋滞。公共交通のインフラ整備が求められている(写真提供:久野真一/JICA)
プログラム・アプローチ(イメージ図)