4. アフリカ(サブ・サハラ)地域
アフリカ、特に、サハラ砂漠より南に位置するサブ・サハラ・アフリカは、依然として深刻な貧困問題に直面しています。サブ・サハラ・アフリカ諸国の大半(48か国中33か国)は後発開発途上国(LDCs)であり、人口の約半分が貧困ライン(1日約1ドル)以下の生活を送っています。また、同地域には、内戦や紛争、難民、干ばつによる飢餓、HIV/エイズをはじめとする感染症のまん延など、発展を阻害する深刻な問題を抱える国も多く、国際社会からの多大な援助を必要としています。国連安保理やG8サミットなどにおける議論を見ても、アフリカのこうした問題は国際社会の重大な関心事となっています。
一方、アフリカは豊富な天然資源や美しい自然環境に恵まれており、貿易・投資や観光の促進による経済成長の大きな可能性を有しています。日本には、アフリカが持続的な経済成長および貧困削減などを実現するため、国際社会の責任ある一員として相応の貢献をしていくことが求められています。

スケレマニ・ボツワナ外務・国際協力大臣と会談する 松本剛明外務副大臣
< 日本の取組 >
日本は、アフリカの自助努力(オーナーシップ)と国際社会による協力(パートナーシップ)を基本原則とするアフリカ開発会議(TICAD)の開催を通じて、アフリカ自身による開発課題への取組に積極的に協力してきました。1993 年に開始されたTICADの15周年にあたる2008年5月には、横浜において第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)を開催し、2010年5月には、タンザニアのアルーシャにおいて第2回TICAD閣僚級フォローアップ会合を開催しました。同会合では、日本がTICAD Ⅳで表明した公約を必ず実行するとの決意を改めて示したことに対し、各国からは公約の履行状況について称賛されました。また、6月のG8ムスコカ・サミットにおいては、フォローアップ会合の成果を紹介しつつ、公約の一つである対アフリカODAの倍増とともに、アフリカにとって重要なMDGs達成のための支援を強化していることを伝えました。
●TICADプロセスを通じたアフリカ支援については、第I部・第3章・TICADプロセスを通じた取組も参照してください
また、日本はアフリカ地域における平和と安定の実現に向けた取組にも貢献しています。たとえば、スーダンへの支援は、TICAD Ⅳの重点分野の一つに掲げられているとともに、日本が対アフリカ政策の重要な柱として強調する「平和の定着」に向けた支援の一例となっています(注61)。2008 年にオスロで開かれた第3回スーダン・コンソーシアム会合では、<1>南北スーダンのバランス、<2>対南部スーダン支援における人道支援から復興・開発支援への移行、<3>地域格差の是正を念頭に置きつつ、これまでの支援に加え、当面約2億ドルの支援を表明し、2010年8月までに約2億2,000万ドルの支援を実施しました。特に、2011年1月に予定されている南部スーダンの独立などを問う住民投票は、南北包括和平合意(CPA)履行プロセスの集大成であることを勘案し、日本は住民投票に対する約800万ドルの緊急無償資金協力を国際社会に先駆けて実施しており、同国の平和の定着を支援しています。また、国際機関や日本のNGOと積極的に連携しながら、難民の帰還・再統合支援、地雷・不発弾の除去活動や回避教育、小児感染症対策などの医療支援、食糧支援などを行っています。
注61 : スーダンでは、1983年以降継続していた南北内戦が、2005 年1月に南北包括和平合意(CPA)により終結し、暫定憲法が公布されるなど、和平に向けた本格的なプロセスが進められている。しかし、約500万人にものぼる国内避難民、経済・社会基盤の破壊、武器拡散や地雷、多数の元兵士の存在など、内戦の傷跡が残っており、また、西部ダルフール地域では、反政府武装勢力の活動が継続しており、政府の鎮圧活動と併せ、地域の開発と安定の阻害要因となっている。
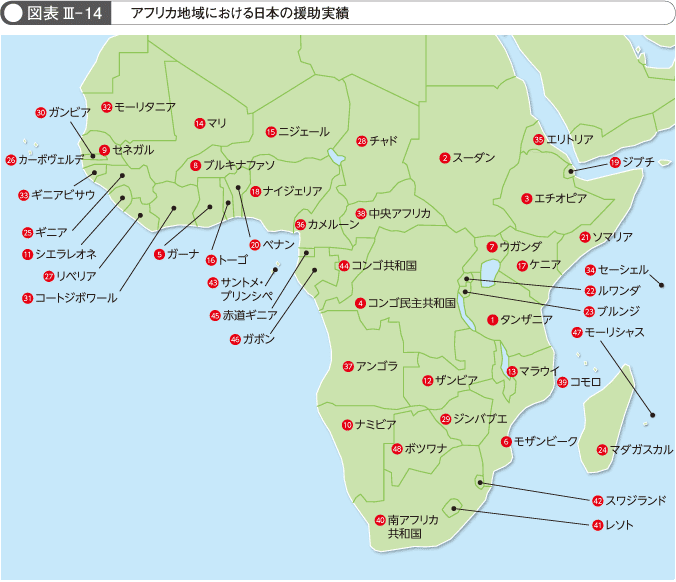
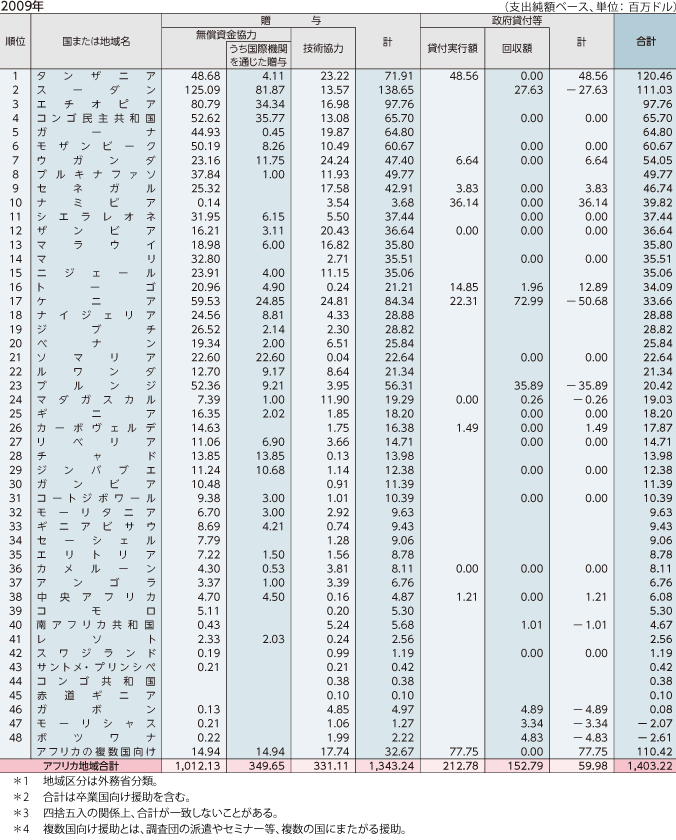
●エチオピア「アファール州給水計画」
エチオピアの首都アディスアベバから北東へ約250kmに位置するアファール州は、全域が土漠地帯で、水資源が乏しい地域です。2007年に日本が協力を決定したとき、エチオピア全体の給水率は約31%でしたが、アファール州ではわずか17%に過ぎませんでした。州内のどの地域でも、水の確保のために女性や子どもが多大な労力を費やしており、不衛生な水による健康被害が発生していました。日本は、アファール州内の9つの町で井戸を掘削・改修し、送・配水管を敷設し、合計28基の公共の水道を設置しました。これにより、女性や子どもによる水汲み労働の負担が軽減され、住民が衛生的な飲料水により容易にアクセスできるようになりました。

設置された公共の水道を利用するアファール州の人々