2. 教育分野の新政策
教育は人々の社会参加を実現する基礎を形成します。日本は、人間の安全保障を推進するために不可欠な分野の1つとして、教育分野における支援を重視してきました。2002年には「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN(注5))」を発表し、教育の機会の確保や質の向上、マネジメントの改善を重点項目に、学校建設や教員養成などハードとソフトの両面を組み合わせた支援を行ってきました。
MDGsおよび「万人のための教育(EFA(注6))」の達成期限である2015年まで残すところ5年となった2010年、開発途上国の多様なニーズや、教育支援に関する国際的な議論の潮流も踏まえつつ、日本は新たに「日本の教育協力政策2011-2015」を策定し、MDGs国連首脳会合の機会に発表しました。菅総理大臣は、この政策に基づき、疎外された子どもや紛争国を含む世界中の子どもたちが教育を受けられるよう、2011年からの5年間で35億ドルを支援することを表明しました。この政策により、日本は少なくとも700 万人(延べ2,500 万人)の子どもたちに質の高い教育環境を提供します。
新政策は、<1>基礎教育支援、<2>ポスト基礎教育(初等教育修了後の中等教育、職業訓練、高等教育)への支援、<3>紛争や災害の影響を受けた脆弱国における教育の支援、を3つの柱とし、教育セクター全体を対象とした包括的な政策です。日本はこの政策の下、教育関連のMDGsおよびEFAの達成に貢献するとともに、2015年以降も見据えて協力を実施し、人間の安全保障の実現に努めていきます。
MDGsの目標2(普遍的初等教育の達成)の達成に直結する基礎教育の支援については、支援モデル「スクール・フォー・オール」に基づき、学校・コミュニティ・行政が一体となった包括的な学習環境の改善を行います。具体的には、相互に関連する5つの項目、<1>質の高い教育(教師の質など)、<2>安全な学習環境(栄養・衛生面など)、<3>学校運営改善、<4>地域に開かれた学校、<5>インクルーシブ教育(貧困層、紛争、障がい者など就学が困難な状況下の子どもへの対応)を重視し、各国のニーズに応じて適切な支援を実施していきます。また、初等教育の普及を加速化させるための国際的な枠組みである「ファスト・トラック・イニシアティブ」(FTI(注7))に対しても、その改革プロセスにかかわる議論と改革への実際の取組に積極的に参画するとともに、FTI が設置している基金への拠出を増額することで支援を強化していきます。
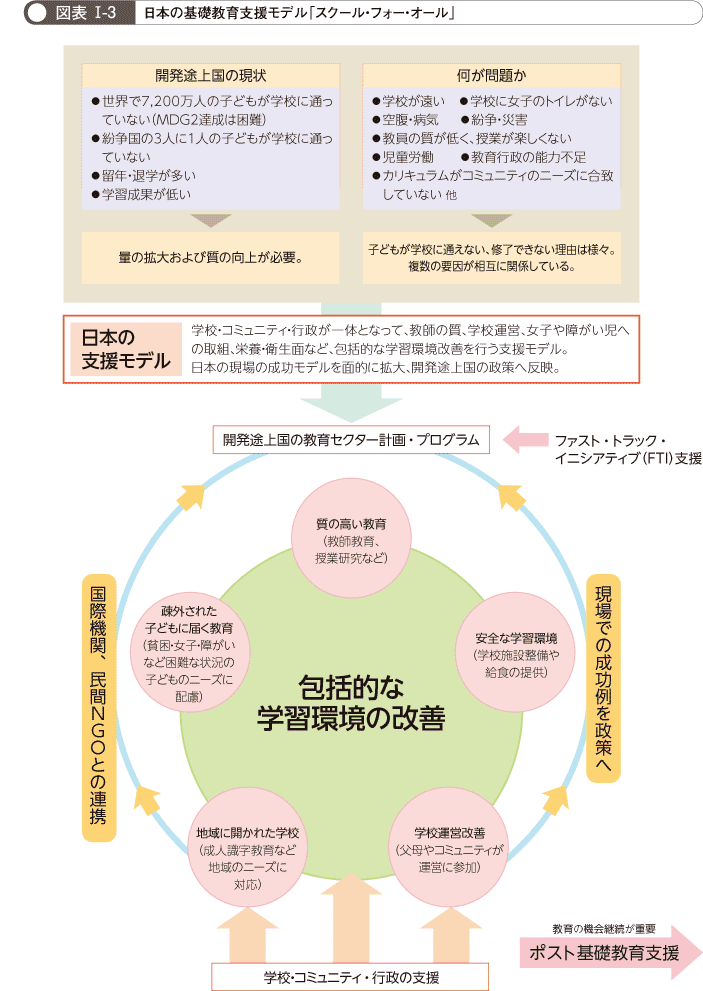
グローバルな知識基盤社会においては、経済成長や国際競争力を向上し、貧困を削減していく上で、ポスト基礎教育の重要性がますます高まっています。日本は、初等教育の普及に伴い、ポスト基礎教育への需要が高まっている現状も踏まえ、拠点となる職業訓練校の強化、高等教育ネットワークの構築促進、留学生の受入れや交流の促進に特に取り組んでいきます。
また、就学していない児童の約35%を占める2,500 万人の子どもたちが紛争の影響下にある低所得国で生活していることなどを踏まえ、紛争や災害の影響を受けた脆弱国における教育の支援にも力を入れます。

小学校の授業風景(ウガンダ)(写真提供 : 佐藤浩治/JICA)
注5 BEGIN : Basic Education for Growth Initiative
注6 EFA : Education for All。 1990年にタイのジョムティエンで開催された「万人のための教育世界会議」において、基礎教育(生きるために必要な知識・技能を獲得するための教育および基礎的学習のニーズを満たすための教育)がすべての子ども、青年、成人に提供されねばならないことが確認された。
注7 FTI : Fast Track Initiative。EFAダカール行動の枠組みやMDGsに含まれている「2015年までの初等教育の完全普及」の達成促進を目指す国際的な支援の枠組みで、2002年4月に設立。