第2節 MDGs達成に向けた日本の貢献
日本はMDGs達成に向け、問題を抱える国々が自立できるよう、保健や教育といった分野で、国際機関への拠出や相手国への直接的な支援を行っていきます。
1. 国際保健分野の新政策
日本は従来から、人間の安全保障に直結する地球規模課題として保健医療分野での取組を重視し、保健システムの強化などに関する国際社会の議論をリードしてきました。2005年に発表した「『保健と開発』に関するイニシアティブ(HDI)」は、5年間で50億ドルという包括的な協力を行うという目標を達成し、2009年度末で終了しました。日本はMDGsの達成期限まで5年という節目の年に「国際保健政策2011-2015」を策定し、MDGs国連首脳会合の機会に発表しました。菅総理大臣は、この政策に基づき、保健関連MDGsの達成に貢献するため、この分野において2011年からの5年間で50億ドルの支援を行うことを表明しました。
この新政策は、<1>母子保健、<2>三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)対策、<3>公衆衛生上の緊急事態への対応、を3つの柱とする保健分野の支援に関する包括的なものです。日本はこの新政策の下で、保健関連のMDGsを達成していく上での課題(ボトルネック)解決に焦点を当て、効果的で、効率的な支援を実践していきます。
MDGsの達成に向けた進ちょくが特に遅れている母子保健については、日本が国際社会に対して提案した支援モデルである“EMBRACE(エンブレイス)”(注4)に基づき、産前から産後まで切れ目のない手当てを確保するための支援を強化します。具体的には、妊産婦の定期健診や、機材と人材の整った病院での新生児の手当て、病院へのアクセス改善、ワクチン接種などがパッケージで行われるよう国際社会と協力して支援を行います。日本はこの政策をもとに、支援の実施国において、国際機関などのほかの開発パートナーとともに、68万人の妊産婦と、296 万人の新生児の命を含む1,130万人の乳幼児の命を救うことを目指します。三大感染症対策については、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(世界基金)を通じた支援を特に強化します。日本は、2010年9月のMDGs国連首脳会合および10月の世界基金第3次増資会合において、世界基金に対して当面最大8億ドルの拠出を行うことを表明しました。こうした資金面でのさらなる貢献のみならず、世界基金を通じた支援と二国間支援との補完性の強化にも取り組んでいきます。日本はこの政策をもとに、その支援実施国において、ほかの開発パートナーとともに、エイズ死亡者を47 万人、結核死亡者を99 万人、マラリア死亡者を330 万人削減することを目指します。
新型インフルエンザやポリオなどの国際的な公衆衛生上の緊急事態や、自然災害、紛争などによる健康被害に対しても積極的な支援を行っていきます。これらを通じ、コミュニティの安定と平和構築に貢献していきます。
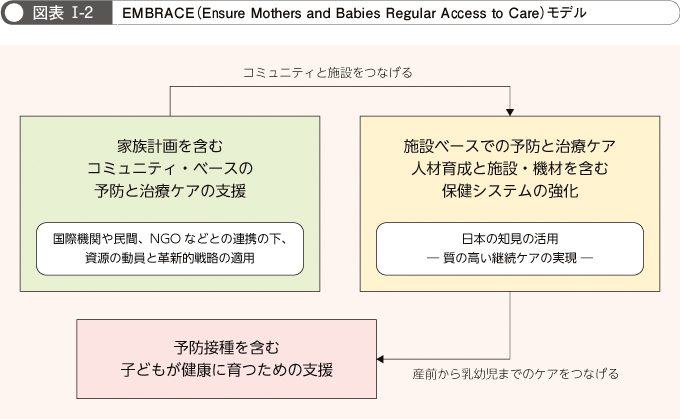
注4 EMBRACE:"Ensure Mothers and Babies Regular Access to Care"の頭文字を取ったもの。